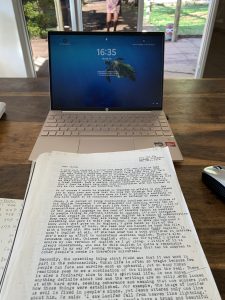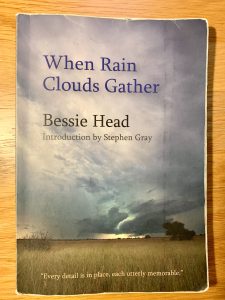11月11日(ポッキーの日)、かねてより見物したいと思っていた「文学フリマ」に参加した。おのぼりさん感覚、文化祭感覚、そしてかつて開いていた僕の本屋「フィクショネス」感覚を、存分に味わうことができた。誘っていただいた破船房の仲俣暁生さん(当「マガジン航」の編集発行人)に、まずは感謝する。現場でも仲俣さんは大奮闘なさって、おかげで僕は楽ができた。
開場は12時の予定で、準備は10時からということだったが、僕たちが到着した時(つまり開場2時間前!)には、すでに来場者が行列を作っていた。東京流通センターをフルに使った会場は広かったが、個々のブースは狭かった。破船房もひとつのテーブルを半分だけ使うことができて、そこに仲俣さんや僕の本を、なるたけ見栄えよく並べて客を待った。
テーブルの残り半分を占める隣のブースは、11時を過ぎても人が来なかった。大きな段ボールがいくつも積んであるばかりで、他人事ながら大丈夫なのかと心配になったが、開場20分くらい前にようやく段ボールが開かれた。中からは表紙に可愛い男女の描かれた、B5サイズの300頁くらいある本がどかどかと出てきた。
寒風の中で待ち続ける来場者たちを慮ってか、開場を10分早めるというアナウンスがあった。僕たちのブースはすっかり準備が整っていたが、となりは段ボールを開くので精一杯の様子である。間もなく開場となった。すると来場者たちは、はっきりとなりのブースを目指して集まり、そのぶ厚い本を中心に次々と買いあさっていくのである。たちまち行列になり、僕たちのブースの前を覆い始めた。仲俣さんは行列に向かって、通路の中央に並んでくださいと何度も声を上げたが、行列は伸びる一方、ついには文フリのスタッフが人員整理をしなければならない仕儀となった。
僕も驚いたが、そのブースの人たちにもこの人気は意想外だったらしい。印刷所から届いた本の帯封を切るのさえもどかしげに、ばんばん本を売っていった。千円札や一万円札が飛び交い、空になった段ボール箱を片づけることすらできず、開始10分で売れ切れた本もあったようだ。
そのブースの人たちはとても礼儀正しく、僕たちに御迷惑をおかけして申し訳ありませんと、何度も言ってくれた。中の一人は僕のことを知っていたばかりか、数年前にご挨拶もしてくれていたという。文芸畑の人なのだった。他の方々も僕たちに終始気をつかってくれた。その間も本は売れ続け、金庫代わりにしているクリアファイルは紙幣で膨れ上がり、ラグビーボールみたいになっていた。
そうなると僕としてはもはや羨ましくすらない。そういう現象を目の当たりにしたという、お祭り見物みたいな愉快な気持ちであった。そしてもちろん、彼らの売りまくっている本の内容が気になる。覗いてみるとどうやらそれは、ビジュアルノベルの批評集なのだった。
少し客足が落ちついてきたころに、僕は訊いてみた。
「ビジュアルノベルっていうのは何ですか? ラノベみたいなもんですか?」
「むしろゲームですね。コンピューターゲームなんだけど、小説として楽しめるというか」
「ああ」僕は必死に貧弱な知識を動員して理解しようとした。「つまり『ポートピア連続殺人事件』みたいな?」
「あのへんが起源ですね」
のちに知ったのだが、僕の出した例も完全なトンチンカンでもなかったにしろ、むしろ『ときめきメモリアル』と言ったほうがよかったようだ。恋愛シミュレーションゲームである。
なるほど、と僕は思った。彼らはあれを「ノベル」=「小説」と見なしているわけか。
論争のない世界
破船房のブースの売り上げが悪かったとは思わない。仲俣さんがさかんに声を出してくれたおかげもあって、破船房から出してもらった『新刊小説の滅亡』は50冊近くも売れたし、仲俣さんの本には完売も出た。知り合いにばかり売れたのでもなかった。我々は我々なりに奮闘し、成果を上げたと言える。
僕たちが売った本には写真集もあるが、大半が「純然たる小説」とそれに関わるものだった。「純文学」のことではない。「ビジュアルノベル」に較べれば純然、という意味である。ビジュアルもなければ音も出てこない、文章だけで出来ている小説を僕たちは売っていた。
水と油である。ビジュアルノベルから見たら僕たちのやっていることなどは、殆ど遺跡の発掘も同然だろう。一方で僕から見ればビジュアルノベルは果たして「ノベル」なのか、と問いたくなる。
だが僕は問わなかったし、彼らも僕らを嗤わなかった。それどころか彼らは僕らに気を配ってくれたし、僕も彼らに好感を持った。僕たちはお互いに笑みを交わし、気持ちよく別れた。
それはこの「文学フリマ」全体を象徴する光景に、僕には思える。店番の合間に会場を回ることもできたが、そこには多種多様な、あまりにも多種多様な「文学」があった。詩集あり海外文学あり、ラノベあり二次創作ありフォトエッセイあり、マイナーな趣味のエッセイあり政治的提言あり短歌あり旅行記ありエロあり創作文藝ありと、細分化していけばまだまだいくらでも広がるジャンルの「文学」が、幾千の著者によって書かれていた。ブースからブースへ渡り歩く人たちはそれらの小冊子や本でエコバッグをぱんぱんにしていた。つまりここで売られている「文学」はただ幾千の著者が書いているだけでなく、幾万の読者に読まれているのである。ちなみに著者と読者が重複するのは当たり前のことで、今に始まったことでも、論じて何かになることでもない。
そんな、収拾のつけようもない「文学」の乱切りポトフが「文学フリマ」であり、「文学」なのだと、僕はその巨大な空間を呆気にとられながら思い知った。
かつて文学には論争があった。お前の文学は間違っているとか、こんなものは文学じゃないとか、そんな言葉が真剣に応酬されていた。そこでは恐らく、弁証法が信じられていたのだろう。相容れない二項を対立させれば、そこに止揚が、アウフヘーベンが現われるという希望があったに違いない。
だがもはやそんなことは希望すべくもない。なぜなら対立するのは二項ではなく、百項、千項であり、これをアウフヘーベンするなんて芸当は非現実的だからだ。これら「文フリ」に広がる百項を統合し、二項か三項くらいにまとめあげようとすれば、そこにはどこか権力志向を思わせる雑駁さ、図々しさが露呈するだけではなかろうか。
人はもはや「文学とは何か」を共有しようとはしていない。『新刊小説の滅亡』と「ヴィジュアルノベル」は水と油なのかもしれないが、この二項が対立するには、まずお互いへの基本的な理解が必要になる。そしてその「基本的な理解」に至る道は、なんと遼遠なことだろう。私たちは勉強をしなければならない。その勉強の先に、もしあるとすれば「対立」は生まれるかもしれないが、対立するためにする勉強など、どこが面白いのか。そもそもそんな対立は生じることなんかなくて、互いへの理解を深める可能性だって小さくはない。水と油は、どちらも液体という共通項を持っている。それで充分という結論に達する可能性だってある。
だったら最初から相手に深入りしなければいいのだ、というのが「文フリ」なのかもしれない。実際、ヴィジュアルノベルの人たちに限らず、言葉をかけあったどのサークルの人とも、私たちは礼儀正しく振る舞うことができたし、人々も礼儀正しかった。そしてお互いのやっていることや目指していることにはほぼ抵触せず、ポッキーの話や来場者の多さを語り合って別れたのである。それは居心地のいい空間であり、居心地がいいのは悪いことでは決してない。それに私たちは、自分らの本を買ってくれる、自分らに関心を持ってくれる人たちとは、短いながらもしっかりと対話をすることができたのだ。
「判る人だけ判ればいい」と「仲良きことは美しき哉」。これが「文フリ」の空間を支えている不文律だった。表現芸術全般にとって「判る人だけ判ればいい」は、今に始まったことではない。僕が現代性を感じたのは「仲良きことは美しき哉」の方である。実際それは美しい。機会があればまた訪れたい。「文フリ」は魅力的で祝祭的な場所である。
だがその「美しさ」は、何かを隠蔽してはいないだろうか。その何かを突き止めるのは、批評の重大な役割ではないだろうか。