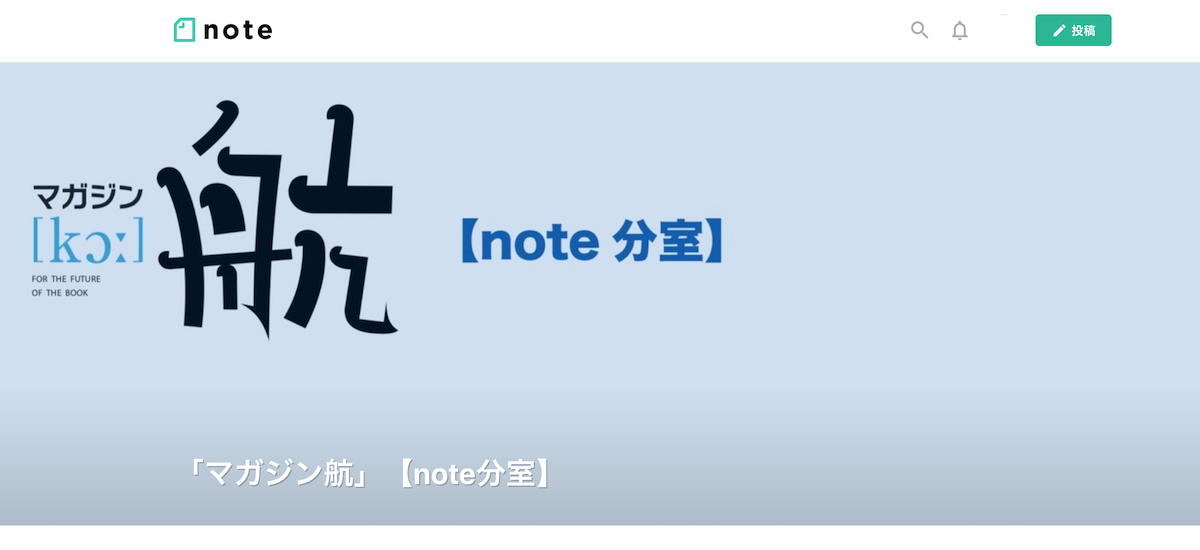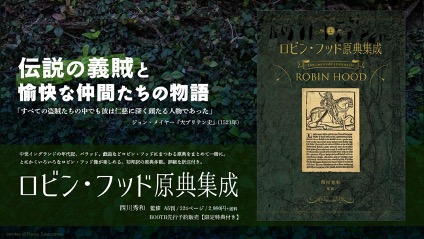デビュー前の僕は、前衛だった。マルセル・デュシャンとジョン・ケージが守護神で、文学のアイドルは、ヌーボーロマンの作家たちだった。自分で撮影した写真にキャプションをつけて小説と称していた。
しかし地方の若者には、孤独な作業である。理解者が欲しかった。当時、吉本隆明氏が発行していた『試行』という雑誌の愛読者だったので、吉本氏に電話をかけた。
僕は小説を書いているのですが、普通の出版社には受け入れられそうにないので、そちらに掲載していただきたいのですが……
吉本氏は、そうですか、うちは何でも大丈夫ですから、送ってください、と実に親切に対応してくれた。
僕は高揚した気分で、自分の撮影した写真を大きく引き伸ばして額に入れ、タイポグラフィーで打ったキャプションをつけた。そして、うちの近くの宅配便の取扱所まで抱えていって、送った。しかし、吉本氏からの音沙汰はなかった。
考えてみれば、大きな額に入ったキャプション入りの写真を小説として掲載するのは、いくら『試行』でも難しかったのだろう。僕が編集者であっても、いまになってみると、その気持ちは分かる。
横書き小説がめずらしかった時代
その後、文学的な事情によって、僕は前衛を卒業した。そして、彼らが廃棄した19世紀のリアリズム小説を拾ってきて、リサイクルし、カスタマイズし、自分の新しい小説を書き始めた。
ある大手出版社の新人賞をもらったのは、それから3年後だった。同時受賞者がいて、吉本氏の娘の吉本ばななさんだった。僕は不思議な縁を感じたが、『試行』に投稿したことは言いそびれてしまった。
デビューして、ある雑誌に短篇の連作をした。そのなかに、パソコン通信のスタイルを取った作品があった。まだ、インターネットの草創期で、リアルタイムで映像のやりとりをするのは難しいころだったと思う。
しかし、リアルタイムで文字のやりとりをするのも、十分に面白かった。僕は、その原稿をパソコン通信のスタイルそのままに、横書きで出稿した。担当者は面白いと言ってくれたが、編集長が渋った。
ヨコのものをタテにするのが、日本文学だろう――これはそのときの編集長の名台詞である。結局、今回限りということで、その雑誌の歴史始まって以来、横書きの小説が掲載されることになった。
当時、ほかにも何人かの作家が横書きで発表したので、新聞の文芸欄から取材を受けた。これは当時のパソコンでは縦書きができなかったことに原因があると思う。パソコン通信などのやりとりをリアルに再現しようとすると、横書きにするしかなかったのだ。
時代は進んで、多くの人がスマホを手にするようになった。10年ほど前、電車に乗って車内を見ると、一列の座席に座っている人の何人かが文庫や新聞や単行本を読んでいた。
5年ほど前から、みながスマホを見ているようになった。そのころには、すでに活字文化の終焉が語られて久しかった。しかし人々が見ているスマホの画面に映っているのは、活字ではないが、文字だった。僕は、彼らのスマホに何とか自分の小説を送り込みたいと願った。
新しい読書人階級に届けたい
20年ほど前だったろうか。電子本が登場したとき、紙本は、やがてなくなる、と予想された。しかし、その後の進展は、予想に反し、電子本と紙本が共存しているような状態になった。
漫画は別にして、文字の電子本はそれほど売れない。紙本も、文字ものは、やはりそれほど売れない。読書をする人々が相対的に減少しつつある。しかし、まったく読書をする人がいなくなかったのかと言うと、そうではない。
昔、中国には読書人階級があった。知識層のことだ。庶民は文字の読み書きができない。読書は知識人のものだった。いま日本には、新しい読書人階級が生まれつつある。彼らは、専門的な知識人というわけではない。しかし、本を求めて、読書を欲している。
今後、読書をする人々としない人々のあいだには、大きな知識の格差が生じていくことだろう。
僕は、読書をする人にはもちろん、スマホでゲームをしている人々のなかにも、できれば読者を求めたい。そのためには、まず、作品を彼らのスマホに送り込まなければならない。繰り返しになるが、そう思った。
『マガジン航』の仲俣暁生氏と出会ったのは、そんなことをぐるぐる考えているときだった。そのうち原稿を書かせてください、と言うと、仲俣氏は笑いながら、小説でもいいですよ、と言った。僕のなかで、何かが反応した。
『マガジン航』はWEBメディアである。これは、僕が、ここしばらく考えていたことを実現するチャンスではないか。そうだ。小説を書こう。WEBメディアでしか読めない小説を。
そういうことで、僕は、WEBメディアになじむ短篇小説を書き始めた。1章は短く。そして、写真を入れる。それは挿絵のようなものではいけない。作品と有機的に繋がっている必要がある。
1カ月ほどで1作の短篇小説を仕上げて、仲俣氏に送った。面白い、と言ってくれた。そして、発表するにあたって、いろいろとアイデアを出してくれた。『マガジン航』のnote分室に掲載されることになった。それが『ニキ・サントス・クルーズ』という作品だ。
なぜアジアを主題に書くのか
僕は、紙本から電子本に乗り換える気はない。つい先日も、『台湾聖母』(コールサック社)という紙本を出したばかりだ。これは台湾の日本統治の時代に教育を受けた台湾の俳人が主人公の小説である。
20年ほど前からアメリカ発のグローバリゼーションにどう対応するかというのが、僕の文学的な問題意識の一つだった。対応の仕方は3種類ある。①グローバリゼーションに乗る(開く)=村上春樹。②グローバリゼーションとは別の極を作る(閉じる)=三島由紀夫。③自分たちの伝統的な文化を見直し、グローバリゼーションを利用しつつ、それを新しく変えて、広げていく(閉じながら開く)。そして、アメリカ発のグローバリゼーションそのものを変質させる。
日本を含むアジアには長い伝統文化の蓄積がある。まず、アジアとは何かを問うことで伝統の内実を探り、そしてグローバリゼーションの鑿で、それを新しく加工して、世界に広げていく。僕は、この第三の道を選んだ。そして、いまアジアを主題にした小説を書いている。
最初から読書をするつもりで、書店に行って紙本を買う読者ばかりでなく、ゲームのあいまにたまたま短篇小説を見つけて、読んでみたら面白かった、という読者を見つけたい。
これから電子本と紙本がどうなっていくのか、僕には予想ができない。しかし、メディアはメッセージであるという考えに従えば、電子媒体は小説そのものを変容させていくことだろう。
僕は、それを愉しみながら、電子本の世界へ乗り出していく。
【お知らせ】「マガジン航」はnote上で【note分室】の活動を開始しました。その第一弾として、村上政彦さんのフォトノベル、『ニキ・サントス・クルーズ』を公開しました。今後もさまざまな作家やクリエイターとコラボレーションしていく予定です。[編集部]