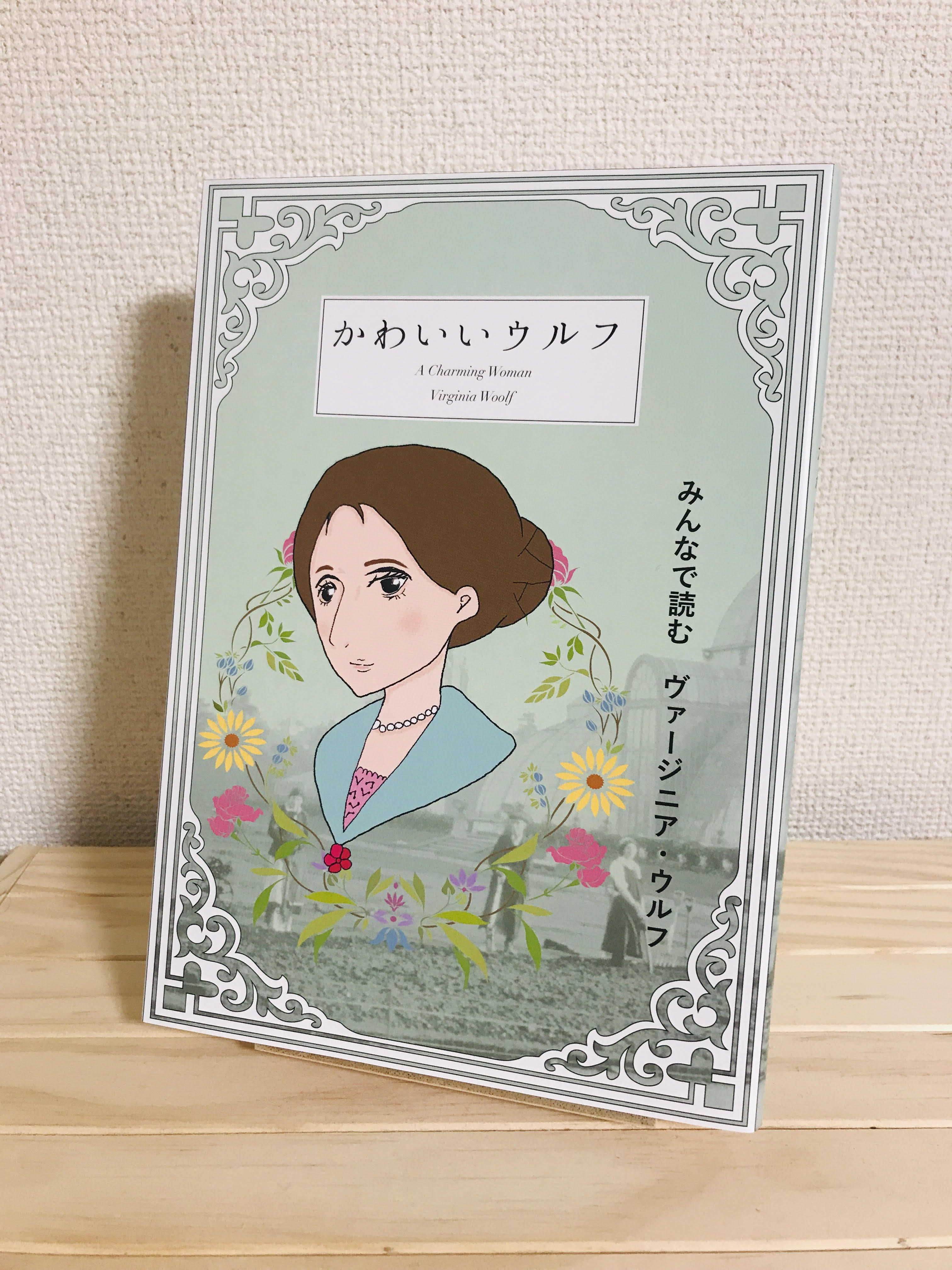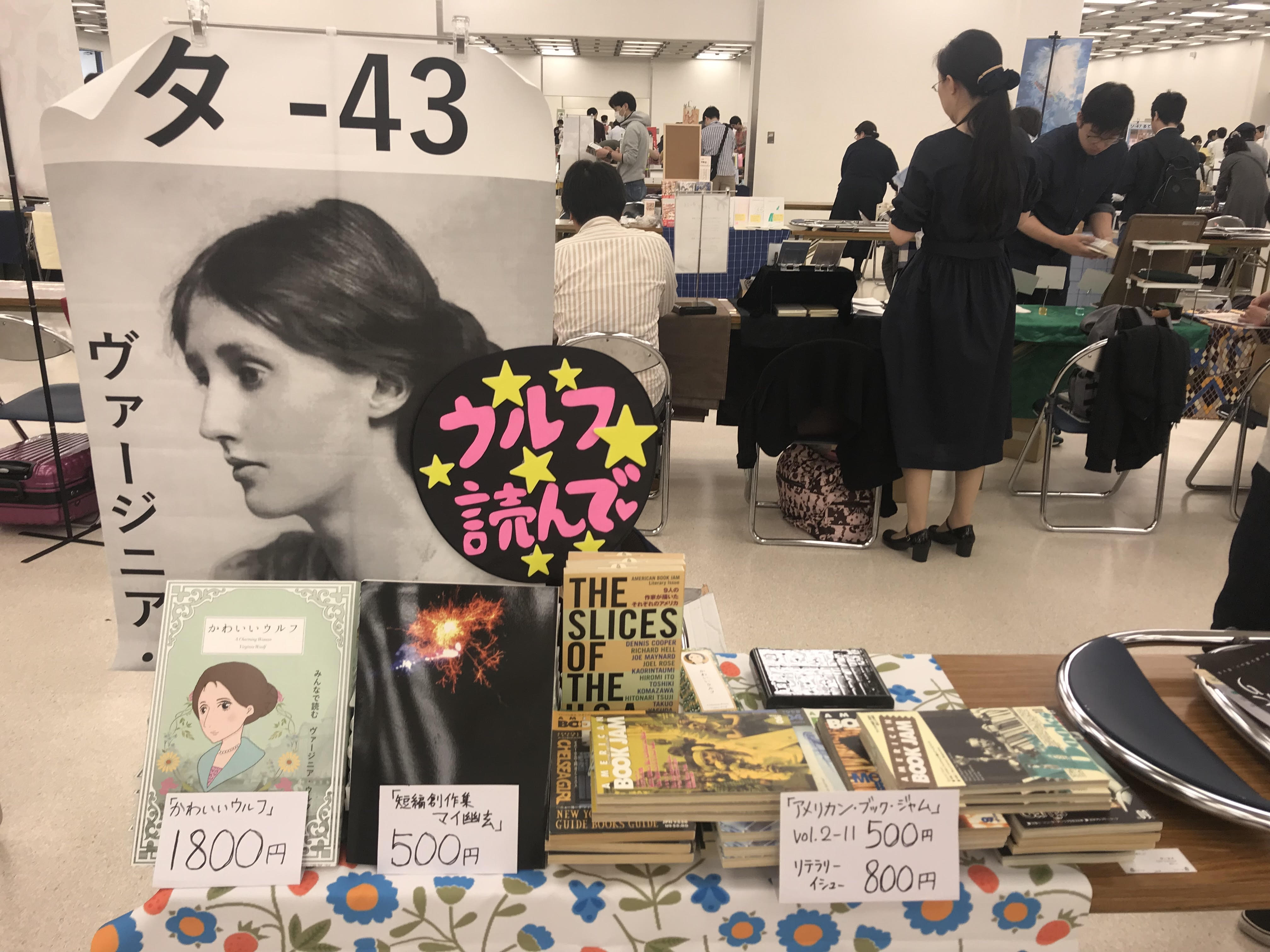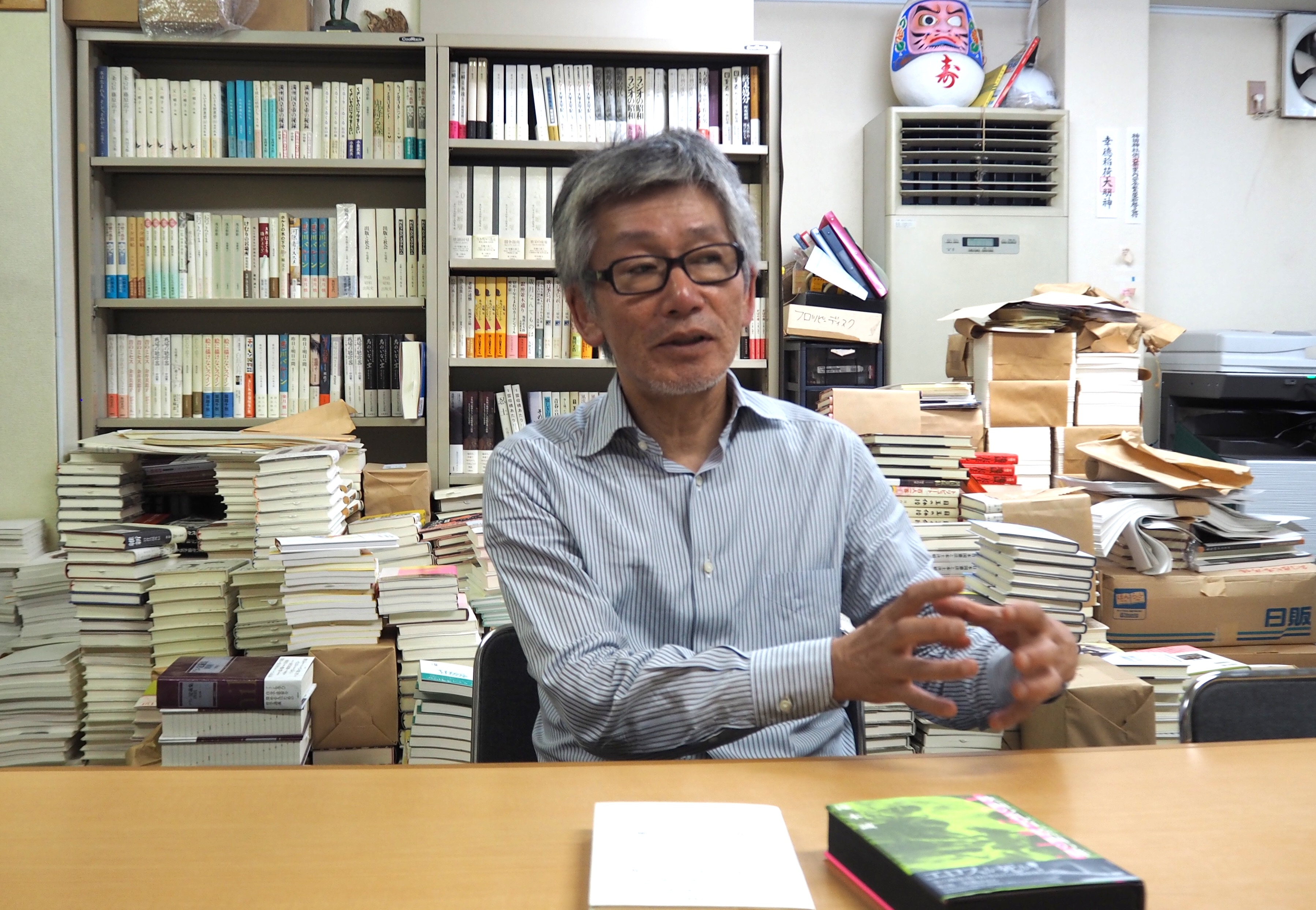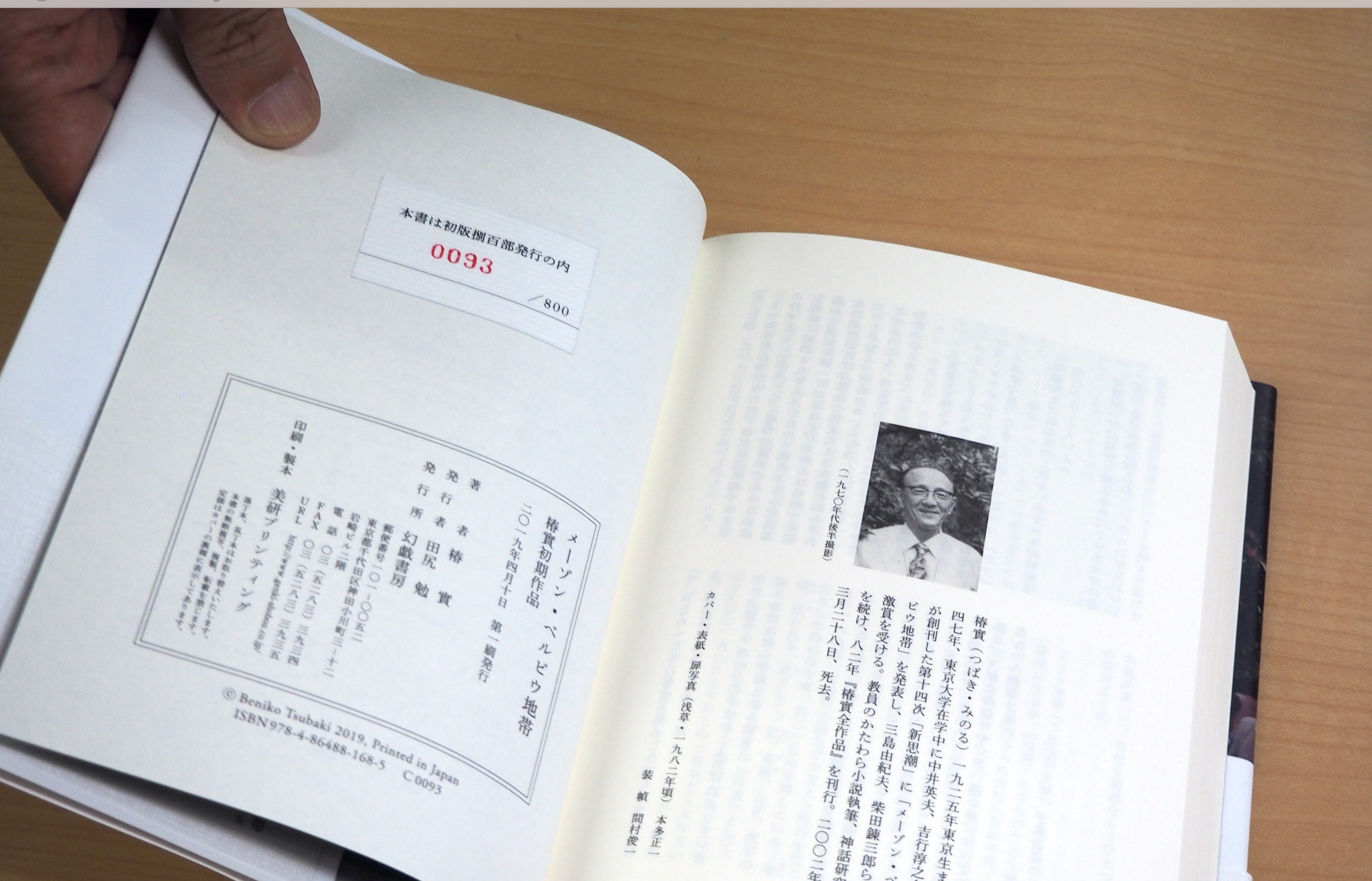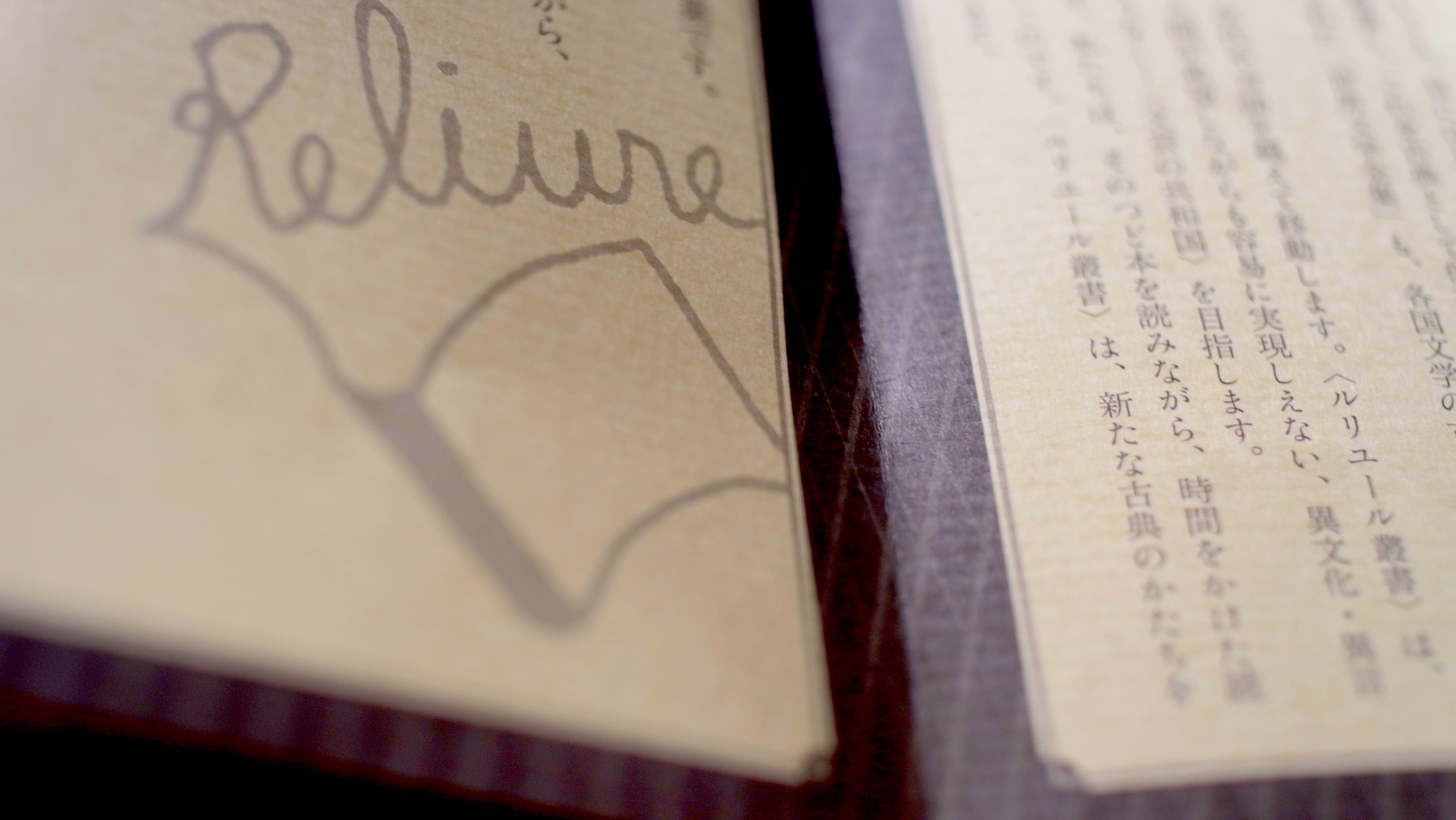8月1日に開幕した国際芸術祭「あいちトリエンナーレ2019」の企画展の一つとして、メイン会場の愛知芸術文化センターで開催されていた「表現の不自由展・その後」の展示が3日いっぱいをもって中止された。
この企画展の趣旨は上記のページで以下のように説明されていた。
「表現の不自由展」は、日本における「言論と表現の自由」が脅かされているのではないかという強い危機意識から、組織的検閲や忖度によって表現の機会を奪われてしまった作品を集め、2015年に開催された展覧会。「慰安婦」問題、天皇と戦争、植民地支配、憲法9条、政権批判など、近年公共の文化施設で「タブー」とされがちなテーマの作品が、当時いかにして「排除」されたのか、実際に展示不許可になった理由とともに展示した。今回は、「表現の不自由展」で扱った作品の「その後」に加え、2015年以降、新たに公立美術館などで展示不許可になった作品を、同様に不許可になった理由とともに展示する。
皮肉なことに、この企画展自体が開催3日で「展示不許可」に追い込まれたことになる。中止の決定に至る経緯として、同トリエンナーレの芸術監督である津田大介氏は記者会見でこう語った(発言の引用は朝日新聞より)。
「安全管理上の問題が大きくなったのがほぼ唯一の理由。想定以上のことが、とりわけ電話で行われた。回線がパンクし、受付の人も抗議に対応することになった。対策はあったかもしれないが、抗議の過熱がそれを超えていった」
また同日に記者会見を行った愛知県の大村秀章知事も以下のように、展示中止の理由を語っている(同じく朝日新聞より)。
「これ以上エスカレートすると、安心して楽しくご覧になることが難しいと危惧している。テロ予告や脅迫の電話等もあり、総合的に判断した。撤去をしなければガソリン携行缶を持ってお邪魔するというファクスもあった」
一方、こうした判断を事前に伝えられていなかった参加作家の「表現の不自由展・その後」実行委員会は、中止の決定を受けて抗議文を公表し、そのなかで以下のように述べている(抗議文全文は朝日新聞のこの記事で参照できる)。
何より、圧力によって人々の目の前から消された表現を集めて現代日本の表現の不自由状況を考えるという企画を、その主催者が自ら弾圧するということは、歴史的暴挙と言わざるを得ません。戦後日本最大の検閲事件となるでしょう。
この中止決定に先立ち、あいちトリエンナーレの開催地である名古屋市の河村たかし市長が2日、大村知事に「表現の不自由展・その後」の展示を中止するよう求めたという報道もされていた。また河村市長は3日の中止の決定を受けてさらに、関係者への「謝罪」を求めたとも報じられた。同トリエンナーレの開催地首長としてこのような発言がなされたのが事実とすれば信じがたい。
今回の中止決定はこうした政治的な圧力が原因ではなく、「卑劣な非人道的なファクス、メール、恫喝(どうかつ)脅迫の電話等で、事務局がまひ」(大村知事)しているためであり、「安全管理上の問題が大きくなったのがほぼ唯一の理由」(津田芸術監督)だというが、もしそうであればなおのこと、中止の決定が展示内容とは無関係であることをトリエンナーレとして明確にすべきではないか(大村知事は「行政が展覧会の中身にコミットすることは控える」とのみ発言している)。その上で安全管理態勢を万全にし、出展作家とも協議して開催期間中の展示再開に向けて努力してほしい。
それにしても、公共の美術館等で開催されている国際芸術祭の展示、しかも「表現の自由」そのものを題材にした展示が暴力と恫喝によって中止に追い込まれたことには、深い憂慮の念を抱かざるを得ない。これは美術館だけの問題ではない。たとえば公共図書館やそれに準ずる公共施設、あるいは大学等においても、市民の間で賛否や議論が分かれるテーマについて、講演やシンポジウム、企画展示等がなされる機会は多い。
美術館(今回のような国際美術展も含む)や図書館が担うべき公共性のひとつとして、かならずしも全員一致の結論を得られないテーマやアジェンダに対し、安全な環境のもとで公的な議論を喚起するということが挙げられると思う。今回のトリエンナーレの場合、安全な環境が担保できないということが展示中止の最大の理由とされたが、それは担われるべき公共性の一面でしかない。
これまであまりにも政治的な文脈でばかり議論されてきた「平和の少女像」が訴えかけていることの意味を、「美術」という新たな文脈のなかで問いかけた今回の「表現の不自由展・その後」の試みは、美術館のような場が担うべき公共性の一つの現れだったと私は考えている。実際、来場者のなかでもこの企画展に対する関心は高く、多くの人が長い列をなして入場を待っていたという報道もある。そのような機会が暴力と恫喝によって失われたことに対して、あらためて怒りを表明したい。
ところで、以前のエディターズノートで話題にしたフレデリック・ワイズマン監督の映画『ニューヨーク公共図書館〜エクス・リブリス』が日本でも思いがけないヒットとなり、いまも全国で公開が続いている。あの映画を見て公共の施設が担うべき「公共性」について少しでも考えた方は、もしもあの映画が図書館ではなく美術館あるいは美術展を舞台にした作品だったら、と思って考えてみるとよいと思う。図書館が民主主義を支える場であるのと同様に、美術館も民主主義と切り離せない場だと私は考える。
MLAKという、ミュージアム、ライブラリー、アーカイブ(公文書館)、公民館の頭文字をとった言葉がある。心あるMLAK関係者は今回の国際芸術祭への不当な攻撃に抗議し、あいちトリエンナーレが無事に会期末を迎えることと、中止とされた企画展のなんらかの形での再開に向けて、どのようなかたちでもよいので援助と協力をしてほしい。