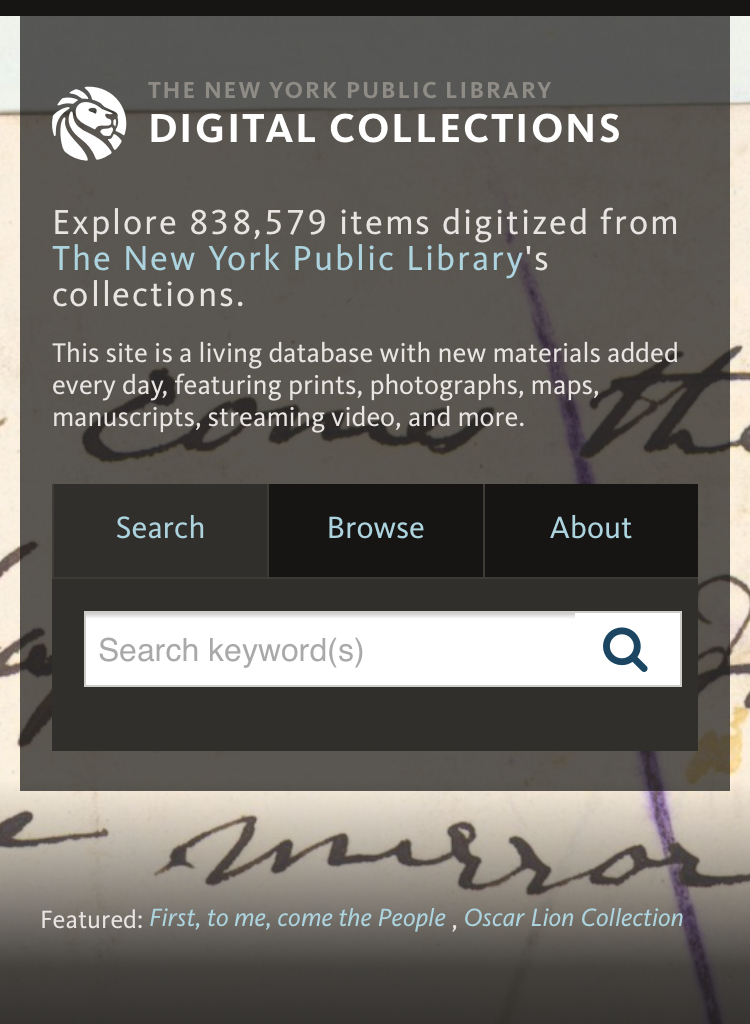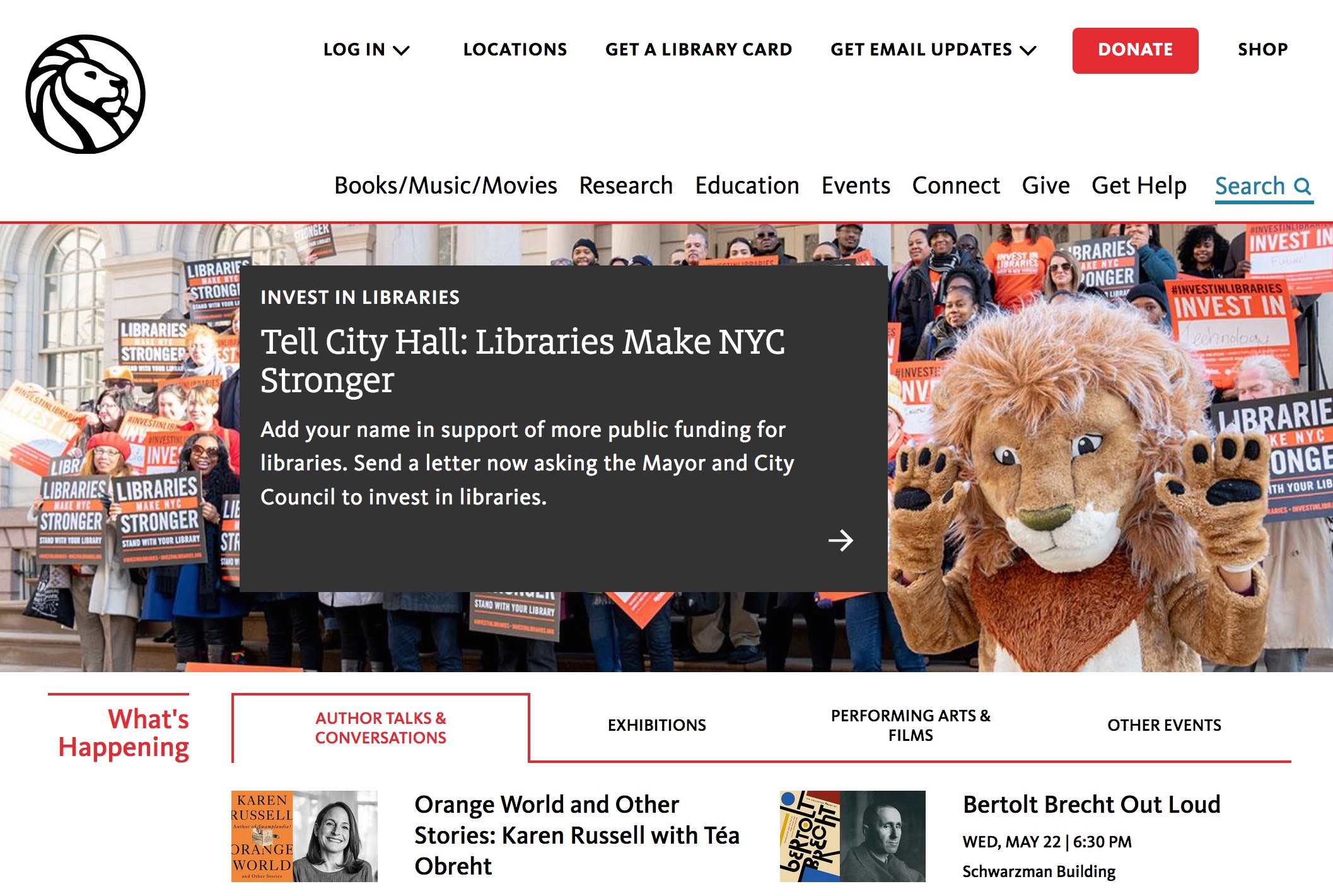「図書館」という言葉から最初に連想するものはなんですかと問われたなら、本の貸出、新聞や雑誌の閲覧、調べもの、受験勉強……といったあたりを思い浮かべる人が多いのではないか。もしそこに「民主主義」という言葉が加わったら、はたして違和感はあるだろうか。
図書館を舞台にしたドキュメンタリー
フレデリック・ワイズマン監督の映画『ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス』を、先月の終わりに試写会で観た(5月18日より東京・岩波ホールほか全国で順次公開)。約3時間半にわたる超長尺のドキュメンタリー作品であるにもかかわらず、不思議なことにいつまでも観つづけていたい気持ちにさせられた。その理由はこの映画のテーマと深く関わっている。

『ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス』劇場公開用パンフレット(4月9日に開催された日比谷図書文化館でのイベント風景より)。
『ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス』の主題は、図書館を題材にしていることから想像されがちな「本」や「読書」ではない。あえてキーワードを挙げるとすれば、「コミュニティ」「文化」「デジタル」の三つが思い浮かぶ。公共図書館がこれらと深い関係を切り結ぶことで、アメリカ合衆国では――少なくともニューヨーク市では――民主主義をしっかりと支える土台になっている。そのことを痛感させられたので、私はこの映画をもっと見続けていたい気持ちになったのだった。
私がニューヨーク公共図書館に興味をもったきっかけは――おそらく多くの人と同様――、若い頃に読んだ吉田秋生の『BANANA FISH』でこの場所が描かれていたことだ。この図書館はイタリアン・マフィアの支配下から脱しようとする不良少年アッシュが独力で知性を育んだ場であり、彼がもっともやすらぎを感じられる場でもあった――そう受け取れるラストシーンがとても印象的で、いつかこの場所のことを詳しく知りたいと思っていた。
2003年に岩波新書の一冊として刊行された菅谷明子さんの『未来をつくる図書館 ニューヨークからの報告』は、この図書館の歴史と(当時の)最新の取り組みについて、基本的な知識と知見を与えてくれるすぐれた本だ。シブル(SIBL)の愛称で呼ばれる科学産業ビジネス図書館が積極的に市民の起業支援をしている話や、図書以外のさまざまな資料をアーティストが芸術活動のために積極的に活用している話はとりわけ印象的で、自分の中での先入観が取り払われ、公共図書館に対するイメージが一新された。
現在は四つの専門的な研究図書館(人文社会科学図書館、科学産業ビジネス図書館、舞台芸術図書館、黒人文化研究図書館)と88の地域分館からなるニューヨーク公共図書館は、インターネット上でのコレクションの公開に積極的であることでも知られている。デジタル・ネットワーク社会における図書館の役割という観点からも、彼らの活動はつねに目が離せない(「マガジン航」でもそうした取り組みについてはなんどか紹介してきた)。だからこの図書館を題材にフレデリック・ワイズマンがドキュメンタリー映画を撮ったと知ったとき以来、日本での公開をなにより心待ちにしていた。
人々の表情や声、身振りから浮かび上がる図書館の役割
映画『ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス』の予告編はYouTubeでも公開されている。冒頭の場面で、子供からの問い合わせに対してだろうか、「じつはユニコーンは想像上の動物なんですよ」と答える司書の対応はじつに丁寧だ(予告編の日本語版は編集が若干異なり、この場面が出てこないのが残念である)。「アンディ・ウォーホルは私たちからたくさんのものを盗んだ」と語る写真コレクションの担当者や、「図書館は人のことなんです」と語る新館を設計した建築家も予告編に登場する。これらの言葉は本編の文脈のなかに置かれると、さらに印象的なものとなる。
ワイズマンはこのドキュメンタリー映画で、ニューヨーク公共図書館の多岐にわたる活動をできうる限りディテールまで伝えようとしている。市民に向けて行われる公開レクチャーやコンサートなどの様子は、プロモーションビデオのような断片的なエピソードとしてではなく、その活動の実質が十分に把握できるよう、一つ一つがしっかりと長いカットで紹介される(これほどの超長尺になったのはそのためだ)。日本でもよく知られているリチャード・ドーキンスやエルヴィス・コステロ、パティ・スミスといった有名人が登場する場面も楽しいが、私にとってはまったく未知の作家やパフォーマーが聴衆に向けて訴えかける姿に強く心を打たれた。
日本ではいつの時代にも「図書館=無料貸本屋」という批判がなされるが、ニューヨーク公共図書館は市民が本や雑誌を「消費」する場所ではない。ハイレベルの研究図書館として学術研究に取り組む者や、意欲的な文化芸術の創造者にも大きな助けとなるが、前述の菅谷明子さんの本で詳しく紹介されているとおり、ここはニューヨーク市民に対する起業やビジネス支援の場でもある。市内各地の分館はそれぞれのコミュニティに深く関わっており、ライブラリアンは各地域が抱える現実的な課題の解決に献身している。
学術研究の支援、文化芸術創造の支援、ビジネス支援、地域コミュニティの課題解決の支援……このような多岐にわたる活動を支える人々の表情や声、身振りを『ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス』という映画は、長い時間をかけてじっくりと映し出す。そうした明確な理念と目的意識のもとで、ニューヨーク公共図書館はインターネットや電子書籍といったデジタル技術の採用や普及にも積極的だ。冒頭で述べた「コミュニティ」「文化」「デジタル」という三つのキーワードは、この映画が教えてくれるニューヨーク公共図書館の活動を特徴づけるものだ。そこから思わず浮かび上がる言葉が、冒頭で挙げた「民主主義」なのである。
公民連携の理想的モデルとしての「パブリック・ライブラリー」
この映画の試写と並行して、4月9日には東京の日比谷図書文化館で、この映画にも登場するニューヨーク公共図書館の渉外担当役員キャリー・ウェルチさん、先述の菅谷明子さんを迎えたトーク&パネルディスカッションが行われた。

中央がウェルチさん、右が菅谷明子さん。
ところでニューヨーク公共図書館は「パブリック・ライブラリー(public library)」ではあるものの、日本の図書館法が定めるような「公立図書館」ではない。その運営は非営利組織(NPO)が担っており、活動資金はニューヨーク市や州からだけでなく、個人や企業からの様々な規模の民間寄付によってもまかなわれている。
19世紀半ばにニューヨークにあった二つの個人図書館、アスター図書館とレノックス図書館をその前身とするニューヨーク公共図書館は、日本でいう公立図書館よりはむしろ私立図書館に近い。だが日本の図書館法は第26条で「国及び地方公共団体は、私立図書館の事業に干渉を加え、又は図書館を設置する法人に対し、補助金を交付してはならない」としており、活動資金の多くをニューヨーク市から得ている彼らのあり方は、そこからも外れている。ニューヨーク公共図書館は「公立図書館」でもなければ「私立図書館」でもなく、まさに「公共図書館」と呼ぶしかない存在なのだ。
日本でも最近はくっきりとした「公(官)」と「私」の分離が見直され、「公民連携」や「官民パートナーシップ」(PPP、Public and Private Partnership)と呼ばれる取り組みが注目されるようになった。その先駆的なモデルとして、ニューヨーク公共図書館の活動に関心が集まるのは当然だろう。この日のパネルディスカッションでも、彼らの事業モデルが中心的な話題となった(年間3億7000万ドルにものぼる運営費のうち、ニューヨーク市からの支援は全体の約半分だという)。実際、ワイズマンの映画でも幹部たちの経営をめぐる会議風景がなんども挟まれる。地に足がついた活動と、それを支える両輪としての理念と財源。このいずれもに均等に光をあてていることが、『ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス』という映画を魅力的なものにしている。
〈パブリック〉とは〈私たち〉のこと
ニューヨーク公共図書館は「公」と「私」の間に橋をかけているだけではない。高度な学術研究や芸術文化の創造を支援する研究図書館(リサーチ・ライブラリー)としての役割と、その地域に暮らすすべての人に開かれた公共の場としての役割との間にも、なだらかなつながりを築こうとしているように思える。日本においては国立国会図書館から都道府県立図書館、市町村立図書館の中央館とその分館まで、国公立図書館はわかりやすいピラミッド構造をなしている。だがニューヨーク公共図書館は、市立図書館の分館レベルの活動と、国の中央図書館に匹敵する高度な活動とが、相互に関わり合いをもちながら進められているのだ。
ウェルチさんの言葉で印象的だったのは、アメリカでは図書館とは「普通の人々のための宮殿(Palace)」である、という部分だ。彼女は第二部のパネルディスカッションでも「〈パブリック〉とはニューヨークで暮らす〈私たち〉のことだ」と語っていた。ワイズマン監督のドキュメンタリー映画から「民主主義」という言葉を私が連想したのは、ウェルチさんのこうした言葉をあらかじめ耳にしていたからかもしれない。

第二部のパネルディスカッションには田中久徳さん(国立国会図書館)、越塚美加さん(学習院女子大学)、野末俊比古さん(青山学院大学)も参加した(画面左側、中央から順に)。
日本でもこの十数年、図書館をめぐる話題がようやくさかんになってきた。広く「本と人が出会う場所」として書店までを含めるならば、図書館論や書店論はいま空前の賑わいをみせているといってもいい。しかし、その多くはいまだに「本」や「読書」に軸足を置いているように私には思えてならない。本(に象徴される知識や情報)を必要とし、そのことで自分の暮らしを変えていこうとする「人」の具体的な姿があまり見えてこないのだ。
ワイズマン監督の映画では、本そのもの(それはそれできわめて魅力的な被写体のはずだが)は中心的な役割を演じない。あくまでも主役は人、人、人である。図書館(や書店)がもし民主主義の土台になりうるとすれば、それは本の力だけでなく、その場に関わるすべての人の力によるものだ。そのことをあらためて教えてくれたこの映画を、私は一人でも多くの人に見てもらいたい。
『ニューヨーク公共図書館 エクス・リブリス』

© 2017 EX LIBRIS Films LLC – All Rights Reserved
監督・録音・編集・製作:フレデリック・ワイズマン
原題:Ex Libris – The New York Public Library|2017|アメリカ|3時間25分|DCP|カラー
字幕:武田理子 字幕協力:日本図書館協会国際交流事業委員会
配給:ミモザフィルムズ/ムヴィオラ
*5月18日(土)より岩波ホールほかで全国順次ロードショー
執筆者紹介
- フリー編集者、文筆家。「シティロード」「ワイアード日本版(1994年創刊の第一期)」「季刊・本とコンピュータ」などの編集部を経て、2009年にボイジャーと「本と出版の未来」を取材し報告するウェブ雑誌「マガジン航」を創刊。2015年より編集発行人となる。著書『再起動せよと雑誌はいう』(京阪神エルマガジン社)、共編著『ブックビジネス2.0』(実業之日本社)、『編集進化論』(フィルムアート社)ほか。
最近投稿された記事
- 2023.10.22Editor's Note軽出版者宣言
- 2023.06.02往復書簡:創作と批評と編集のあいだで暗闇のなかの小さな希望
- 2023.04.06往復書簡:創作と批評と編集のあいだで魂のことをする
- 2022.09.24往復書簡:創作と批評と編集のあいだで様式によって動き出すものがある