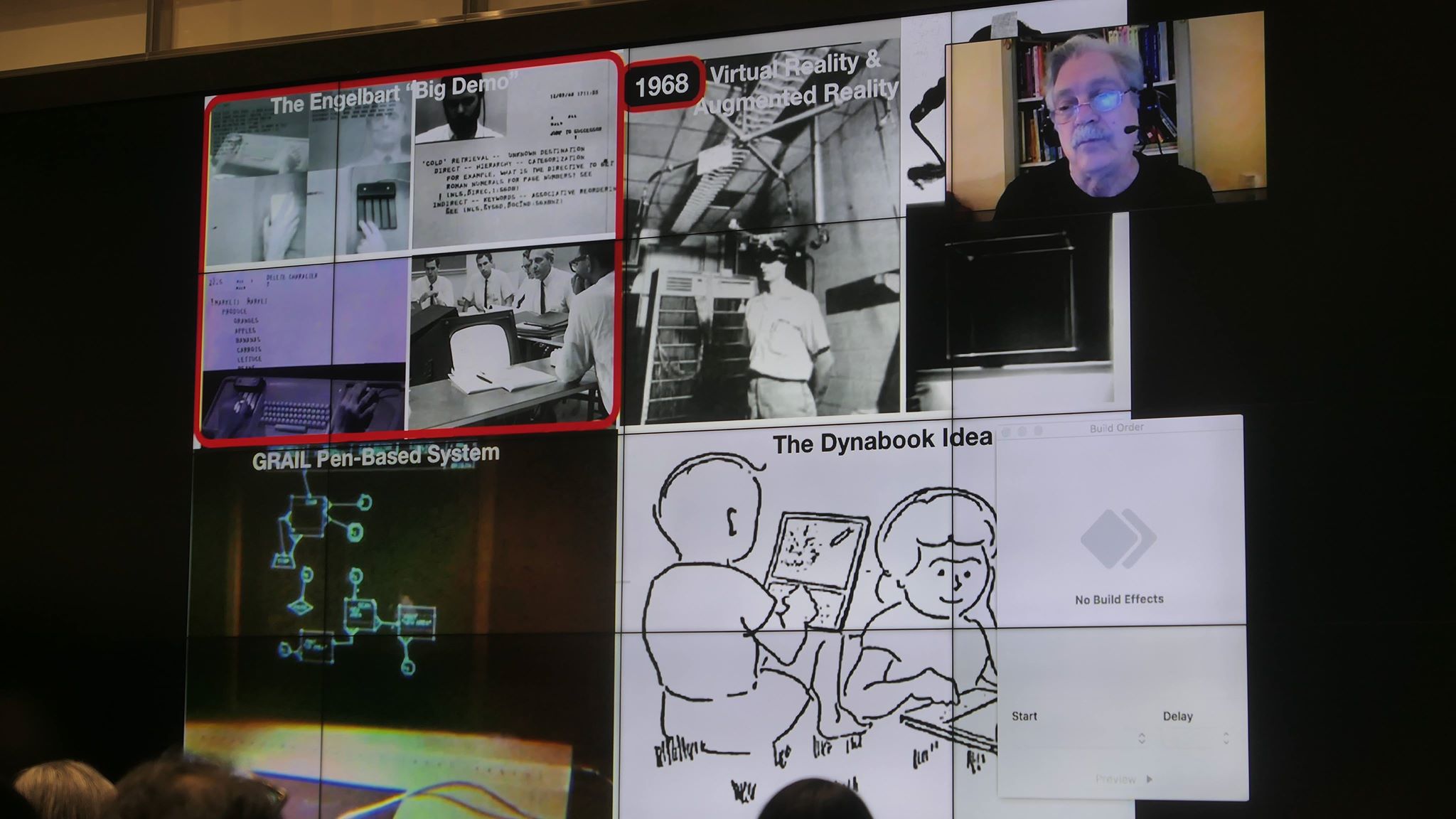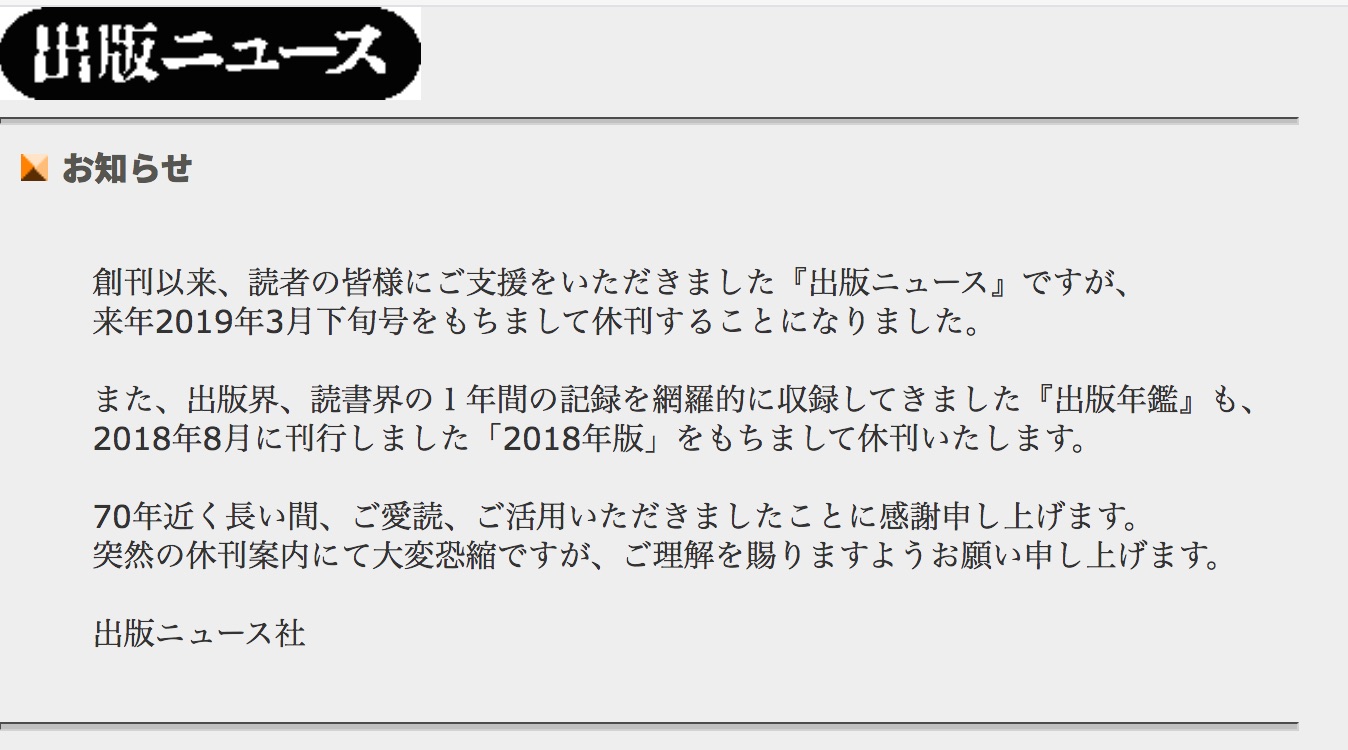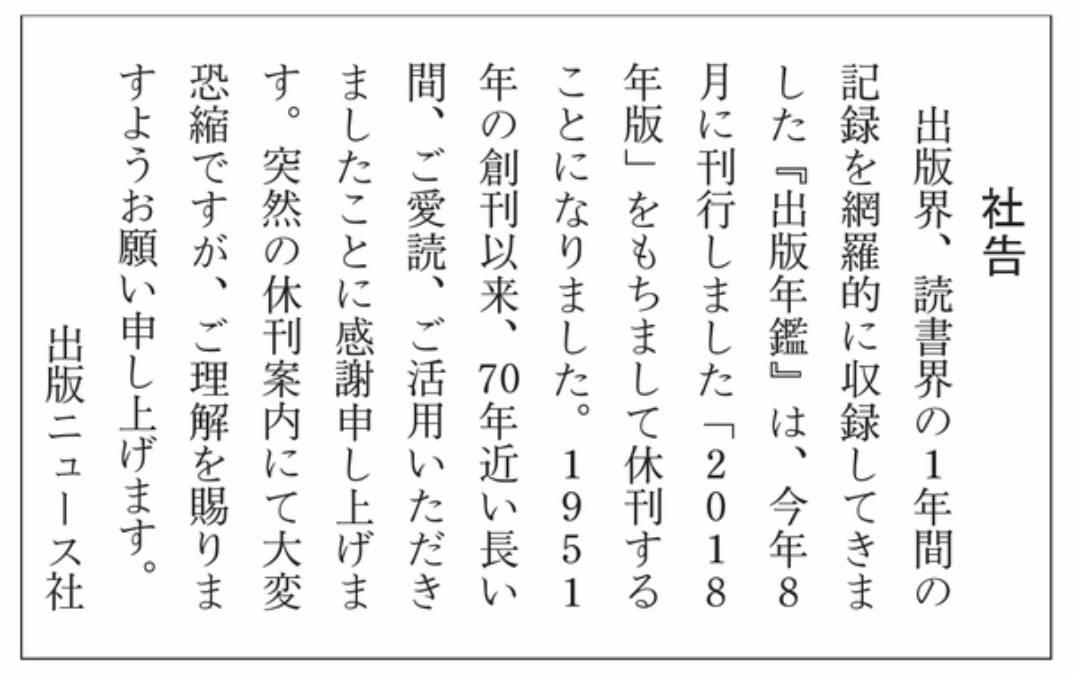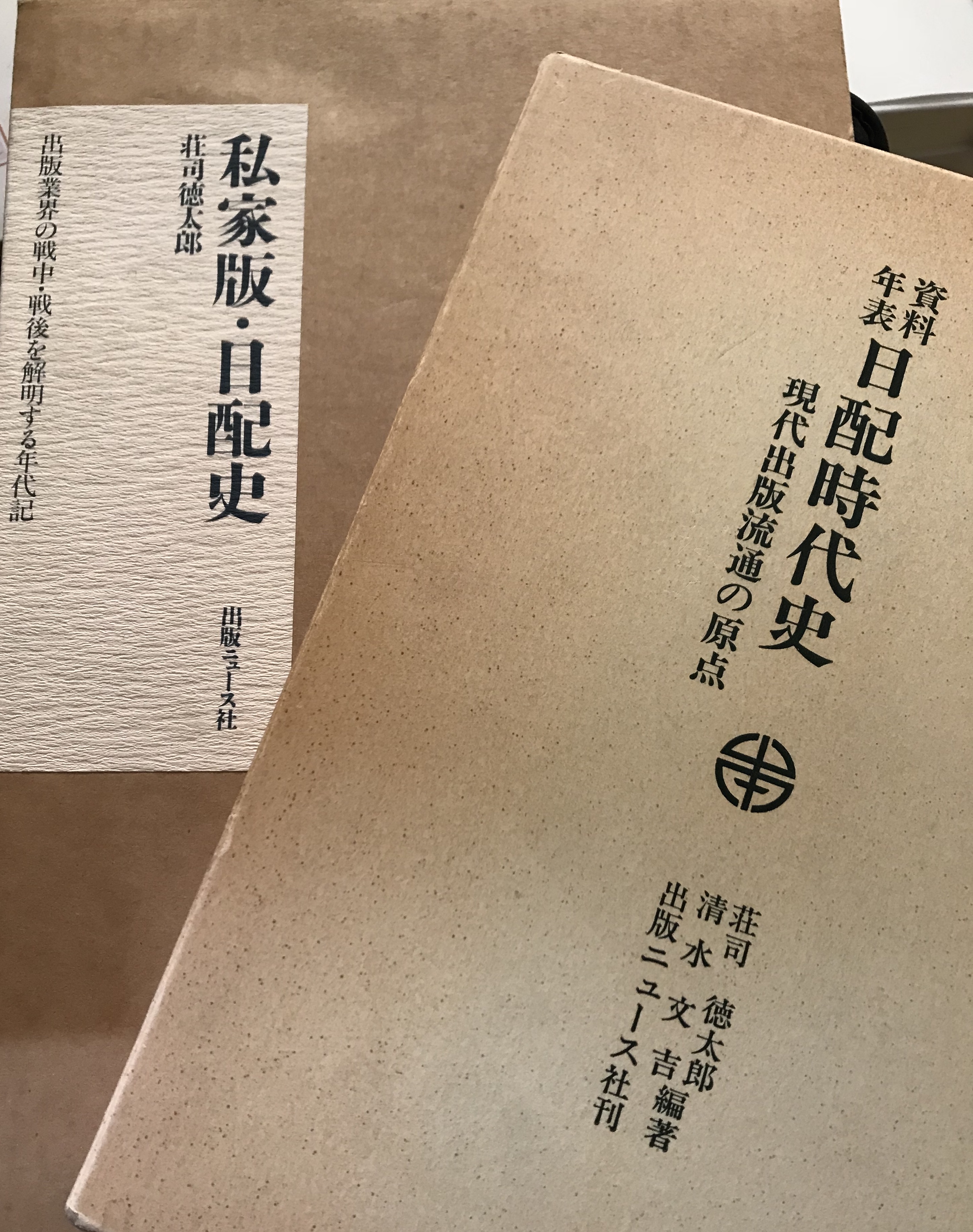第10信(藤谷治から仲俣暁生へ)
仲俣暁生様
頭の中で果てしなく連想ゲームを膨らませてしまう僕は、人と話していてもいつの間にか、目の前の話題からかけ離れたことを考えたり言ったりしてしまうという、失礼な癖があります。仲俣さんの手紙にあった、出版不況と電子書籍と雑誌という話を読んで、僕は「だくだく」という落語を思い出してしまいました。
「だくだく」は、一文無しの家に泥棒が入る話です。その家には家財道具が一切なく、タンスも掛け軸も壁に描かれた絵なのです。これに呆れた泥棒が、しかしせっかく入ったところで何も盗らないのは沽券にかかわると、「タンスを開けたつもり。風呂敷を広げたつもり。品物を風呂敷に集めたつもり」と、すべて「つもり」で泥棒を演じます。声に目覚めた家の主が、泥棒の「つもり」に乗っかって、「泥棒を退治するつもり。槍をつかんだつもり。槍で泥棒を突き刺したつもり」と相手をすると、泥棒が倒れて「うーぬ、血がだくだくと出たつもり」というオチ。
僕が小説家になる以前から、出版不況や雑誌が売れないという話はありました。しかし「フィクショネス」立ち上げ当初(1998年)には、それは「雑誌に広告収入が足りない」ということだったと思います。店によく来ていたフリーの編集者がその話をしながら、この「だくだく」の話をしたのでした。
「だからね、雑誌なんか本当に出す必要はないんですよ」とその編集者は言いました。「出版社は作家の原稿を集めて、作家は原稿料を貰う、そのために雑誌があるんですから、それだけをやればいいわけです。版元は印刷したつもり、売ったつもりで毎月締め切りを設けて、本物の雑誌をつくる経費は浮かしていいんですよ」
もちろんその編集者はふざけてそう言ったのですし、僕もその時は笑っただけでしたが、その後にこの話を思い出すことがありました。電子書籍の台頭したころです。
確かに僕は電子書籍が出版界を席巻するとか、紙の書物は漸次駆逐されるといった議論には、当時も今も浮薄なものを感じています。現在に至るも僕が使っている電子書籍に類するものは「青空文庫」だけですが、あれを使うたびに僕は、そこに書かれたものに対する自分の冷たさ、残酷さを思わずにはいられません。
それは無料だからでもなく、読みたいところだけを抜き読みするからでもありません。僕が電子書籍を読むことに感じる冷たさは、ひとえに「そこにない」ことに理由があります。情報端末のディスプレイに浮かぶテキスト情報は、ただいっとき僕の目の前に浮かぶだけで、存在ではありません。存在しないからこちらの思い付きで朝でも夜中でも、どんな場所にも呼び出すことができます。どんな犬より忠実で、どんな娼婦より安価で、どんな友人より捨てやすい。これは同じテキスト情報用のツールでありながら、存在を主張する紙の本とは真逆の特徴です。存在しないものには温度もなく、したがって冷たい、ということでもあります。
しかしこれらの特徴は、雑誌としてならすべてが長所となりうるのではないか。僕はそう考えています。電子書籍の雑誌を作るのに予算がどれくらい必要なのかは知らないのですが、紙媒体よりも安価にできるとすれば、それは笑い話だった「だくだく」方式に、とても近いものになるはずです。在庫や返品に悩まされることもないでしょうし、雑誌の電子化に出版社が本腰を入れれば、こんにち課題とされているらしいネット上での課金への抵抗感や集客についても、大きな改善が期待できると思います。
どうやら現状では、紙媒体よりもネットの雑誌は、商業としてはまだまだ難しいようです。そして紙の雑誌も売れないという話しか聞きませんから、ネットの不振と出版不況は、どこかでつながっているのでしょう。
僕は思うのですが、今年を最後に出版人は、落ち込んだり萎縮したり、どうすれば売れるんだろうと頭をかかえたりするのを、一切やめたらどうでしょう。僕自身のことでもありますが、不景気の波に吞まれて暗い顔をするのは、もううんざりです。そしてどんな人でも陰気な顔をするときは、常にちょっと、馬鹿みたいです。
不況の時に必要なのは背中を丸めて神に祈ることではなく、諸行無常を嘆く諦念でもなく、闘争心です。仲俣さんの言う「運動」とも、それは通じるのではないかと思います。
運動とか闘争とか言うと、まるで古い左翼活動のようなイメージが出てきてしまいますが、僕の考える運動、そして闘争心は、それとは恐らく異なるものです。それは「書字」のようなものです。
これは、ひところ石川九楊氏の本を好んで読んでいた時に学んだことです。長いこと僕は、書というのはなんか知らんがそれっぽい字が和紙の上に書かれていて、床の間に麗々しく飾られている、それを茶人がありがたがる、そんなものだと思っていました。でもそんなものではないのでした。書を見るというのは、起筆がどこからどのように始まり、どこで力が抜かれ、また力が籠められ、どこで筆が浮いてどこに再びおろされるか、という、運動を見るということだったのです。運動の軌跡ではありません。書は、書き終えられたものであっても、今そこで運動しているのです。書は、それを見ることによって動く。実際に書をそのように、「どう書かれているか」を見ていけば、誰にでもそれが判りま す。
僕が考える闘争心とは、そのような運動をみずからに促す力であり、運動とはまったく即物的な、動きそのものです。私たちにはそれがどうしても必要です。動く、ということは、芸術の根本だからです。美術であれ文学であれ、運動のない芸術がどこにあるでしょう。芸術の優劣を定めるのは、哲学的な価値基準でもなく政治的な党派性でもない。そこに運動が見いだせるかどうかです。そして芸術とは、つまり人間の営みのすべてのことです。
運動の反対は萎縮であり、出版界が不況によって萎縮しているとすれば、それは僕に言わせれば、出版界の人間がみずから自分の運動を放棄しているのと同じです。
「フィクショネス」を開く直前、僕はサンフランシスコに行きました。1998年のことです。それ以来僕は渡米していません。
本屋を開いて一人で切り盛りするとなれば、旅になど当分出られなくなる、と思っての一人旅でしたが、目的地はひとつしかありませんでした。サンフランシスコ名物である坂の途中にある、黒い塀の本屋でした。
16年間、誰にも気づかれたことはありませんが、「フィクショネス」のレジ裏の壁には、「シティ・ライツ・ブックストア」の紙袋が、画鋲で貼ってありました。当時からシティ・ライツは、半分観光名所になっていて、お土産用の布バッグやマグカップも売っていたのですが、そんなものを買ったら「フィクショネス」がこの店のようにはならなくなる、と意地を張って、本を買った紙袋だけを持って帰ったのでした。
シティ・ライツの創立者であり、詩人でもあるローレンス・ファーレンゲッティは、あれでなかなかの商売人ですから、とてもあのような経営を僕が日本ですることは適いませんでしたが、ああいう書店でありたい、ありたかったという憧憬は、今でさえあります。
そしてそのような可能性をはらんだ書店は、実は今、増えているのではないでしょうか。「シティ・ライツ」がビートニクのたまり場だった頃、アメリカは決して黄金時代ではなかった。むしろ惨憺たるありさまだった。とりわけ文学者の境遇はひどかった。不遇が優れた芸術を生む、というのはステレオタイプかもしれず、当事者たる私たちにはたまったものではありませんが、世間の冷たい風と無関心こそが、出版新時代の吉兆である可能性は、小さくないのではないかと思っています。
こちらも長い手紙になりました。良いお年をお迎えください。