今年の2月、アメリカのOR Booksを立ちあげた編集者ジョン・オークスからメールがあった。ジョン・オークスとは数年来の知り合いで、僕は彼を題材にアメリカ出版界についての本を書こうと何度か彼にインタビューをしていた。
そのメールは1950〜70年代にかけて、グローブ・プレスが出していた伝説的な文芸誌「エヴァグリーン・レビュー」がウェブマガジンとして再び出版されることになり、それを祝うパーティがブルックリンのバーで開かれるという知らせだった。
「Invitation to the re-launch of the Evergreen Review」とメールには書かれていた。そして「返事は無用、ただ来ればいい(no rsvp necessary; just show up)」とも。公式なパーティの招待状は普通「RSVP(出席か欠席の返事をお願いいたします)」の文字がついているものだが、この「そんな返事はいらないからただ来ればいい」という少々荒っぽい文章にニヤリとした。
僕はこの2月の夜のパーティに出かけてみた。マンハッタンから地下鉄を二度も乗り間違えて、到着するのに1時間もかかってしまった。なかなか目的地の駅につかない地下鉄の中で僕はジョンが以前「文芸誌を始めようというのは、どんな時にもよいアイデアではない」と冗談っぽく言っていたことを思い出した。
今回、「エヴァグリーン・レビュー」はどんな体制で再始動したのだろう。彼らはそれを通して何をしようとしているのか、そしてどう存続させていくつもりなのだろうか。また、そもそも何故、この媒体を再始動させようとしているのか。メールをくれたジョン・オークスは「エヴァグリーン・レビュー」のCEOともなっている人物だ。編集長となった作家デール・ペックとも連絡が取れる。さっそく、二人から話を聞いてみることにした。
伝説の編集者バーニー・ロセットが創刊した雑誌
新しい「エヴァグリーン・レビュー」の話の前に、そもそもこの雑誌がどんな媒体だったかという話をしなければいけないと思う。
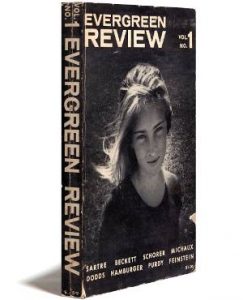
フォックスロックから出版された「エヴァグリーン・レビュー」の復刻版1号。PDFは無償でダウンロードできる。
「エヴァグリーン・レビュー」の創刊は1957年。そのときどきで季刊誌だったり月刊誌だったりしたが、紙媒体として1973年まで発行されていた。その後、1998年にもウェブマガジンとして復活させる試みがあったが、うまくいかなかったようだ。そして、実は昨年も「エヴァグリーン・レビュー」は再始動パーティをおこなっている。僕も今回同様そのパーティに出かけて行った。それから約1年間、「エヴァグリーン・レビュー」は何も動かなかった。その理由は、資金不足だったことが今回の話でわかった。
サミュエル・ベケット、ウィリアム・バロウズ、ジャン=ポール・サルトル、ヘンリー・ミラー、ローレンス・ファーレンゲッティ、アルベール・カミュ、大江健三郎、スーザン・ソンタグ、アレン・ギンズバーグなどがこの雑誌に寄稿した。当時はまだ彼らの多くが無名、あるいは新進作家だった。
僕はもちろん当時の「エヴァグリーン・レビュー」を読んでいた訳ではない。僕にとっては何といってもグローブ・プレスの発行人だったバーニー・ロセットが創刊した文芸誌というかサブカルチャー誌だったことに大きな意味があった。バーニー・ロセットは彼のグローブ・プレスを通して大江健三郎、ジャン・ジュネそしてベケットをアメリカに紹介した出版人/編集者だ。
招待のメールをくれたジョン・オークスは、バーニー・ロセットがいた時のグローブ・プレスの編集者でもあったので当時の彼の話を聞くことができた。
バーニー・ロセットは、グローブ・プレスでD.H.ロレンスの『チャタレイ夫人の恋人』、ヘンリー・ミラーの『北回帰線』、ウィリアム・バロウズの『裸のランチ』といった作品を発行した際、政府のとった出版禁止措置にそれぞれ反対して裁判で争い、いずれも勝訴した。
この一連の裁判でロセットが最も狙っていたのはヘンリー・ミラーの『北回帰線』の出版だった。しかし、いきなりあまりにきわどい『北回帰線』では冒険過ぎると思い、最初に文学的に受け入れられやすい『チャタレイ』で戦うことにした。
アイリッシュの血を受け継ぐロセットは、D.H.ロレンスのイギリス的感覚を最後まで好きになれなかったと言っている。
「1番ロレンス、2番ミラー、3番バロウズという感じ」と彼はこの裁判を野球の打順に喩えている。
ジョン・オークスによると、グローブ・プレスでは編集会議のようなものはなく、ロセットにこの作品を出版したいと相談し、了承を受けるという形を取っていたという。
ロセットが型破りな人物であることは彼のヘンリー・ミラーとの出版交渉のやり方にも現れている。彼は『北回帰線』のアメリカでの出版権を得るために当時ミラーが住んでいたカリフォルニア州ビッグサーまで出向いていった。その時、ロセットはミラーとピンポンの試合をやりながらこの交渉をしている。また、彼は映画の配給も行ったが、自分が配給しようとする映画の内容が猥褻で過激すぎてアメリカのどの映画館でも上映されないと分かると、映画館を買収してしまった。また、自分でバーを開いて大赤字を出したこともある。
そのバーニー・ロセットが「エヴァグリーン・レビュー」を創刊した理由は「なんとなく必要なもののような気がしたから(There just seemed to be a need for it.)」というものだった。まあ、彼らしい理由だ。
非営利組織によるリスタート
話を今回の「エヴァグリーン・レビュー」再始動に戻そう。
僕は先ほど述べたブルックリンでのパーティの後、マンハッタンのチェルシー地区にあるジョンの自宅まで出かけていって、今回の再創刊をめぐる話を聞いてみた。
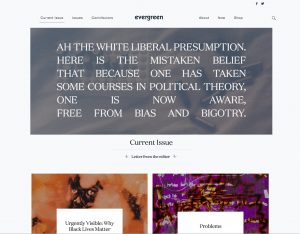
再始動した「エヴァグリーン・レビュー」のウェブサイト。
分かったことはまず、「エヴァグリーン・レビュー」は非利益組織となっていること。資金は大きな財団の基金と、裕福な個人的な寄付から出ているが、これからもさらに資金集めもしていくということ。そして、CEOとなっているジョン・オークス、編集長のデール・ペック、エグゼクティブ・エディターのカルヴィン・ベイカー、インターナショナル・エディターのジア・ジャフリーにはお金が出ていないこと。「エヴァグリーン・レビュー」とは別に、フォックスロック・ブックスという書籍のインプリント(別ブランド)を抱えている、ことなどだった。
「私、編集長のデール・ペック、またそのほかの編集者にはお金が出ません。著者、アーティスト、デザイナーなどにはお金が出ます。将来的にはこの状況が変わるといいのですが、いまはとにかく「エヴァグリーン・レビュー」を始動させ軌道に乗せることを考えています」とジョン・オークスは言っていた。
そして、いまは人々に読んでもらうために「エヴァグリーン・レビュー」は購読無料だが、この後2年間ほどで有料購読になるかもしれないという。
では、どんな作家の作品を載せていくのだろう。
その決定をするのはジョンではなく編集長のデール・ペックだ。僕はデールにも連絡を取り、ウェストビレッジのバーで酒を飲みながら話をした。
デール・ペックは自身も作家であり、ニューヨークのニュースクール大学で教鞭も執っている。『Hatchet Jobs』という本と作家についての評論の著作もある。この本でデールはデヴィッド・フォスター・ウォレス、リック・ムーディなどの今の作家についての非常に辛口な評を書いた。
『Hatchet Jobs』でデール・ペックは、「デヴィッド・フォスター・ウォレスはトマス・ピンチョンの作品の焼き直しをしただけで、何も新たなことを語っていない」としている。そして、トマス・ピンチョンについても、「思考の前菜的なものは数多く登場するが、メインコースとなるものはみられない」としている。リック・ムーディについてはさらに酷評で「彼は彼の世代の作家で最も酷い作家だ」という文章から始まっている。
これに対し、文芸誌『Believer』の編集者で作家のハイディ・ジュラヴィッツは、最近の書評は「人の注目を得るようなアプローチの仕方で、書評自体をエンターテインメントとして扱っている」と反論している。つまり、世間の注目を浴びるために、その題材を酷評する手法を使っているというのだ。
『Believer』といえばゼイディ・スミス(『ホワイト・ティース』)、デイヴ・エガーズ(『驚くべき天才の胸もはりさけんばかりの奮闘記』)、ベン・マーカス(『沈黙主義の女たち』)などの若手中堅作家と結びつきが強く、彼らを敵に回した感がある。
『Hatchet Jobs』の論争はアメリカ文学界の大きな話題となったので、僕はそのことをデールに聞いてみた。
「デヴィッド・フォスター・ウォレスを読んで僕が感じたことは、これはポストモダンの焼き直しで、1970年代がまたやってきたみたいだと思った。僕は彼の書いたような本は何百回と読んできた。デヴィッド・フォスター・ウォレスは何も新しいことを語っていないと思った。僕はそれを言いたかったんだ」とデールは言った。
こちらの話も興味深いが、僕は話題をエヴァグリーン・レビューに戻した。
彼はエヴァグリーン・レビューのサイトで「Letter from the editor」を書いている。この文章は一読の価値があると思う。
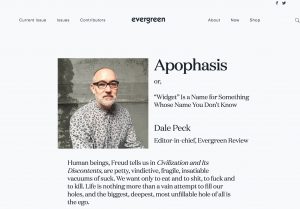
デール・ペックによる「Letter from the editor」。
話はちょっと難しくなってしまうが、彼がここで書いていることを少し紹介してみよう。
デールはこの文章の中ではスーザン・ソンタグの有名な言葉である「解釈は知識人の芸術に対する仕返しだ(interpretation is the revenge of the intellectual upon art)」という言葉を引用している。デールはこの言葉をさらに進め、解釈学は芸術の敵だが、芸術のバイプロダクツ(副産物)の一部であると言っている。そして、それにはシンポジウム、広報、作家の信望者、それに文芸誌も含まれるとしている。つまり、文芸誌もバイプロダクツのひとつだと言っているのだ。
そして、雑誌の目的は芸術をブルジョワ階級の商品に組み込むことだとも言っている。
「使い捨て可能な消費生活製品の広告や、地位を示す製品の広告に挟まれている悲劇的・破局的な物語の意味を真剣に考えることは難しい」
しかし、とデール・ペックは続ける。
「もし芸術が、私たちが入り込んでいる破滅への道へのプロテストだったら、私たちの求める人生が無制限の獣欲主義ではなく、啓発された精神的なものだったら、それはどこかで文学に反映される可能性があるのではないか」
バーのテーブルで彼は「エヴァグリーン・レビュー」にどんな作品を載せたいかも語ってくれた。
「カタルシス(浄化)や情報ではなく、怒りとアクションや社会・道徳的に不適切な作品(これは山ほどあるとデールは言う)でもなく、その表現が特異で一度きりしか表現できない詩。人に見せるのが恥ずかしくなるような、自分のつまらなさ、失敗、裏切りを露呈させる物語。そのおかしな形態や攻撃性により物語にもなっていないような物語ではなく、自意識の甲羅を超えて私たちを人間とさせている核に迫る作品です」
とデールは言う。
「文学も文化の中にあるのですが、それはいつも戦いです。文化の中にあってもその文化からどれだけ離れているか、文化とその距離の引っ張り合いの中で成立しているような作品を載せていきたいんです」
彼の言う「文化」とは社会的な生活や精神活動を指していると僕は思った。つまり、社会や人に受け入れられる、納得を得られる枠と、それを外れ受け入れられない作品とのせめぎ合いだ。バーニー・ロセットがやってきたことでもある。
そして、「エヴァグリーン・レビュー」ではこれから英語が母国語でない作家の作品も載せていきたいと言う。
「いまアフリカ、アジア、スペインなど五つの違った言語圏の作家が英語で書いた作品を読んでいます。ネイティブスピーカーが書いたものではないことは読めばすぐわかります。彼らの作品は保守的なセンシビリティ(感覚)、つまり英語はこう使われるべきだという考え方を脅かすものとなるはずです」
僕はデールの他の編集者のことも聞いた。
「エグゼクティブ・エディターのカルヴィン・ベイカーとはもう16年の付き合いで、いつか一緒に雑誌をやろうと話していました。インターナショナル・エディターのジア・ジャフリーとも15年の付き合いで、彼女は海外の作家と強い結びつきがあります」
つまり、デールを中心に昔からの仲間がエヴァグリーン・レビューを作っていくことになるのだ。
最後に「エヴァグリーン・レビュー」の更新方法を聞いた。
「いまのところ年3回、4カ月に一度に新たな号を出していきます。まずは毎号8本から10本の作品を載せて、さらに毎月1本か2本ずつ増やしていければと思っています」
一号あたりの掲載作品を最初の8〜10本から12本、13本、14本と同じ号の中で増やしていくのだ。
ちなみに再創刊の第1号はゲーリー・インディアナ、多和田葉子、バーニー・ロセット(ヘンリー・ミラーとのピンポンの話も載っている)などの作品が掲載されている。
新しい「エヴァグリーン・レビュー」には、かつて同誌に掲載された作品も載せていくことができる。そしてジョンによればサブスクリプション登録をした読者はすでに数千人いるという。これはこの雑誌にとって大きな財産だ。しかし、以前の成功を再現することは無理な注文だろう。
バーニー・ロセットが「エヴァグリーン・レビュー」を創刊したときの理由が「なんとなく必要なもののような気がしたから(There just seemed to be a need for it.)」だったことは先に述べた。
ウェイトレスがテーブルにきてワインのおかわりはいるかと聞いた。もうデールはどこかに行かなくてはいけない。僕はグラスに残ったワインを飲み干し、ところでどうしてまた「エヴァグリーン・レビュー」をやることにしたんだと彼に聞いた。
「I want to beat the odds(勝ちそうもない戦いに勝ちたいんだ)」とデールは笑った。
執筆者紹介
- ブックジャム・ブックス主幹。東京生まれ。記者・編集者を経てニューヨークで独立。アメリカ文学専門誌「アメリカン・ブックジャム」を創刊。ニューヨーク在住。最近の著者に、電子書籍とオンデマンド印刷で本を出版するORブックスの創設者ジョン・オークスを追った『ベスセラーはもういらない』(ボイジャー刊)がある。
最近投稿された記事
- 2021.02.26コラム「月光ソナタ」の楽譜が語ること
- 2017.04.28コラム名門文芸誌エヴァグリーン・レビューの再始動
- 2016.05.13コラムパナマ文書事件が明らかにした「第五階級」とは
- 2015.02.04コラムなぜ「悪いこと」は「良いこと」より強いのか

