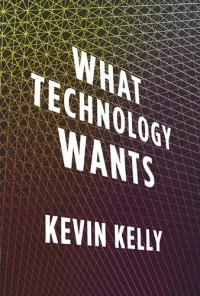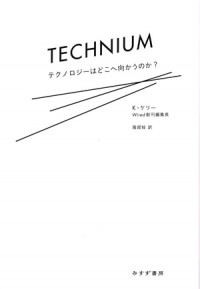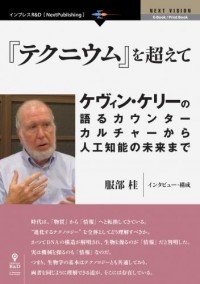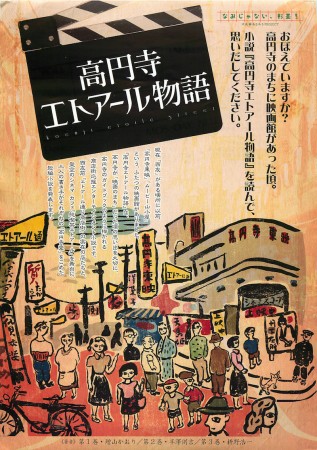ぼくがウィキペディアタウンを知ったのは2012年のことだったと思う。イギリスのモンマス(Monmouth)が世界初のウィキペディアタウンに認定されたというニュースがフェイスブックのタイムラインに流れてきたところ、偶然目にとまったのだった。
参考:Welcome to the world’s first Wikipedia Town(Wikimedia Blog)
モンマスはイギリスのウェールズ南東に位置する人口9千人弱の小さな田舎町で、11世紀初頭にノルマン人の軍事拠点として発祥。モンマス城をはじめ千年近くの歴史を持つ遺産が多く残されているらしい。そんなモンマスで、ある活動が立ち上がった。文化機関のスタッフや市民によるボランティアグループが名所旧跡や博物館の所蔵品など街の観光資源になりそうなあれこれについての記事や写真を次々にウィキペディアにアップロード、そして、ウィキペディアの記事へのリンクURLが仕込まれたQRコードを刻印したタイルを町のあちらこちらに掲出、スマホ等でQRコードを読み込むことで、対応するウィキペディア記事へと直接誘導できるようにしたというものだった。
この、一風変わった田舎町の観光振興施策だが、ぼくにはこの活動が単なる観光振興施策ではない、それ以上の価値を秘めていると思えた。そして、日本でもウィキペディタウンを開催しようと考えた。これが、日本でのウィキペディアタウンの誕生のきっかけだった。
ウィキペディアのルールを知る
ウィキペディアタウンの企画を練っていた当時、ぼくはウィキペディアの編集経験をほとんど持っていなかった。そんな状態でウィキペディアを扱うイベントを開催することが無謀であることはわかっていたので、餅は餅屋ということで「ウィキペディアの中の人」に相談することにした。
幸い、ぼくの周囲にはそういうことを相談できる仲間がいたので、すぐに東京ウィキメディアン会の中心人物を紹介してもらうことができた。日下九八氏との出会いだった。
日下九八氏への協力要請は正解で、すぐに、ウィキペディアを編集するなら基本的な編集ポリシーを知る必要があること、とくに、特筆性といわれる、そのことをウィキペディアに載せる妥当性を客観的に説明できること、ウィキペディアに記す文章では典拠情報を明確にすること、また、典拠として望ましいものはなにかなど、いくつかの重要なポイントを指摘されることとなった。一見煩わしくも思えるようなルールだが、そのルールからはずれると、せっかく書いた記事であっても他のユーザーに修正される(修正されること自体は望ましいことだが)、または、削除すらされることもあるというから大変だ。
改めて思い返してみれば、これまでもウィキペディア上でのトラブルというのはニュースとして見聞きすることはあった。そんな事態も外から傍観しているぶんにはウェブらしい話のネタでしかなかったが、いざ、自分がウィキペディアを編集する立場になった場合には遠慮したいところだ。そして、自分が企画したイベントに参加してくれた人にはなるべくポジティブな印象を持ち帰ってもらいたい。そのためには、このウィキペディアのポリシーを知ることが極めて重要であるということだ。
ウィキペディアの「誰でも編集に参加できるウェブの百科事典」という触れ込みはウソではないが、ウィキペディアがここまで維持発展してきた背景にはそれなりに厳格なルールが存在し、クオリティコントロールがあったということがわかったわけだが、一方で、ウィキペディアのコミュニティはあらたに記事を書いてくれるユーザーを求めているという事実もある。ぼくも会場で聞いていたのだが、東大本郷キャンパスで開催された「Wikimedia Conference Japan2013」でウィキメディア財団のジェイ・ウォルシュ氏はキーノートの中でそうした状況についてデータに基に説明をしていた。
参考:「Wikimedia Conference Japan 2013」リポート毎月5億人が訪れるウィキペディアの舞台裏
ウィキペディアにちょうど良い項目があったので、ウィキペディア自身から引用してみよう。
「1日当たりの記事新設数は日本語版設置後順調に伸び続けたが、2007年3月の469件をピークに減少傾向にあり、2008年5月の1日当たりの記事新設数はピーク時と比較して49%減の240件にとどまった。2009年1月に一時300件台を回復したが再び減少に転じ、2008年5月以降は一部240件台もあるものの、概ね200件台後半で推移していたが、2010年5月以降は再び減少傾向に転じ、2011年5月以降はおおむね150件前後で推移している。2012年8月にはピーク時以降で最小となる131件を記録した。2013年4月現在の日本語版の記事新設数は143件であり、内部リンク数上位10言語版(英語版、ドイツ語版、日本語版、スペイン語版、フランス語版、ポーランド語版、イタリア語版、ロシア語版、ポルトガル語版、オランダ語版)の中で内部リンク数ではドイツ語版に次ぐ! 3位につけているものの、記事新設数では10位である。」
出典:「ウィキペディア日本語版」(2015/03/02時点)
典拠を見ると、主に、「ウィキペディア 多言語統計」のデータの解釈であることがわかるが、たしかに、記事新設数はピーク時よりは低い水準で推移している。ウィキペディアの価値について多少乱暴な言い方をさせてもらうと、それは、圧倒的な項目数とピアレビューによる信頼性であると言える。その価値を高めていくためにはユーザーの獲得、それも、単なるユーザー利用者ではなく、項目を新設してくれて、また、間違いを正してくれる、編集者としてのユーザーの獲得が不可欠なのである。
ウィキペディアタウンの仕掛けでは、まちに暮らす一般の人々を対象とするが、その多くはウィキペディアを編集することについてはまったくの素人だ。素人ゆえに前述のような基本的なルールを十分に理解しないまま投稿してくるケースもでてくるかもしれない。しかし、ウィキペディアタウンはウィキペディアに対し、コミュニティの裾野を広げ、コンテンツの拡充という面でメリットを提供できる。さらに、詳しくは後述するが、まちの既存のコミュニティとの連携により見いだされる新たな価値も提供することができる。
コミュニティのガバナンスという視点からはコミュニティの拡大とクオリティコントロールの両立という難しい課題もあるだろう。ウィキペディアタウンの活動をポジティブなものにするために、活動に賛同してくれている「中の人」には、企画時からいろいろとトラブル予防的観点でのアドバイスももらっているし、トラブルに発展しそうな場合にはいわゆる調停役も担ってもらうこともある。
新たに参加するメンバーはこれから書こうとする記事の質を高める努力は惜しむべきではないとは思うが、萎縮して書き込むことを止める必要もない。
従来からのコミュニティメンバーとウィキペディアタウンをきっかけに新たに入ってくるメンバーとの関わりの中でさらにウィキペディアを発展させて行く良い方法を模索することもぼくらに課された課題の1つなのかもしれない。
ウィキペディアタウンの価値
ウィキペディアタウンにはじつに多様な価値があると思うが、ここでは、学びの機会としての価値に注目してみよう。
ウィキペディアタウンは図書館や博物館といった文化機関、または、まちを舞台としたインフォーマルな学びのプログラムとして成立している。そして、一言で「学び」と言っても大きく2つの側面があると思っている。
まず、核となるのはウィキペディアタウンが対象とするテーマについての学びということになる。ウィキペディアタウンでは調査対象を地域の歴史的、文化的、地理的、社会的な特徴としており、参加者は記事を書くために現地調査を行ったり、関連する文献を調べたりする。そして、ときには文化機関の職員による、専門的な知識を活かした講座に参加する機会も提供される。ぼくが過去に企画したウィキペディアタウンでは音楽ホールや美術館のバックヤードツアーを、博物館では展示をみながら学芸員に横浜の歴史を教わる講座なども実施した。参加者はこうした体験を通じて地域のさまざまな事柄について学ぶことができる。
また、最終的にウィキペディアにアウトプットすることを目標とするので、学びの効果も高いように思う。また、ウィキペディアに足跡を残せるという点でワークショップに対する満足度や達成感も大きいようだ。
つぎに、情報そのものについての学びについて考えてみたい。ウィキペディアの編集をはじめると、情報を扱うということがどういうことなのか、根本から考えるようになる。ご存知のとおり、ウィキペディアの記事はすべてユーザーによって書かれており、その確からしさはどこまでいっても不明としか言いようがない。もちろん、コミュニティとしては前述のように強いガバナンスが働いており、全体として必要十分な質は担保できているのだと思うが、個々の記事を取り出したときにそれが正しいかどうかは誰も保証してくれない。
先日、横浜開港資料館でウィキペディアタウンのワークショップを実施したときに、同館の副館長である西川武臣氏が講義の中であるエピソードを紹介してくれた。それは、横浜開港当時、生糸貿易で成功した豪商、中居屋重兵衛についての都市伝説と言えるものであった。中居屋について書かれた資料は明治から現代に至るまで多く発行されているが、多くの嘘が含まれるというのだ。中居屋はペリーを追って下田まで出向き、ペリー艦隊の乗組員に生糸を売ったとか、井伊直弼暗殺に使われた拳銃は中居屋から尊皇派の志士に提供されたとか、いずれのエピソードもそれを裏付ける資料は残されていないのだそうだ。今風に言えば「盛りすぎ」ということか。
参考:「開港のひろば」第50号(平成7年11月1日発行)
ようするに、ウィキペディアに限らず、書籍であろうと、研究論文であろうと、人による情報には不確かなものやいくらかの虚偽が混じり込むことは、むしろ、普通であって、そうした中で、自分が情報と対峙した際、なにをどの程度信用するか判断する能力が情報リテラシーであるということだ。
ちなみに、西川氏は生糸貿易に関する歴史を専門として調査に基づく数多くの著書を持つ。おそらく、西川氏の知ることが真実であろうと、ぼくは思うが、それを確かめるには自ら調査するしかないわけだ。
ウィキペディアタウンにはここで紹介した学びの機会としての価値以外にも、地域にとっては地域の情報をより広範に対して発信できる機会でもあるし、また、アーカイブとしての価値もある。文化機関にとってはコミュニティとの協働の新たな機会となるし、所蔵品の活用の機会ともなるかもしれない。ウィキペディアのライセンスはオープンライセンスであり、そこに蓄積されるコンテンツやデータはオープンデータとして活用されているという価値もある。これらについては、別の機会にそれぞれ掘り下げて紹介してみたいと思う。



(写真は2015年2月15日に行われた第5回ウィキペディアタウン横浜(IODD2015横浜分科会)の様子。撮影は筆者)
ウィキペディアタウンの今後
最初のウィキペディアタウンから3年が経ち、横浜ではこれまで6回のワークショップを実施している。実はその間にも、二子玉川や京都にはじまり、この活動は全国に波及しはじめている。そうした盛り上がりを受けて、先日、ぼくも活動に参加している任意団体、オープングラムジャパンの主催によりウィキペディアタウンファシリテーター養成講座が日本におけるウィキペディタウン発祥の地である横浜で開催された。北は北海道から南は佐賀まで日本中から40人以上があつまり、たいへん盛況であった。その準備にあたってコアメンバーを中心にさまざまな議論を交わす機会を得て、また、講座の参加者の方々との交流をもって、ぼくは、あらためてウィキペディタウンのもつ大きな可能性を感じることができた。
ウィキペディアタウンは図書館や博物館、美術館、といった地域の文化資本や地域コミュニティといった社会関係資本を活かし、そこに、ウィキペディア、オープンストリートマップ、ローカルウィキといったウェブ上のオープンな技術資本を掛け合わせながら、学びやアーカイブ、情報発信といった活動をレバレッジしていく。今後、ウィキペディアタウンといったときには、単にウィキペディアを編集するにとどまらない、まちをフィールドにウェブを通じて情報発信する総合的な学習プログラムのことを指すようになるのではないか。ウィキペディアタウンの益々の発展に期待をしている。
※この記事はACADEMIC RESOURCE GUIDE(ARG)メールマガジン2015年4月6日配信号に掲載された記事「ウィキペディアタウン-ウィキペディアを通じてわがまちを知る」を、著者の承諾を得て改題のうえ転載したものです。
■関連記事
・ウィキメディア・カンファレンス・ジャパン2010報告
・Wikimedia Conference Japan 2009への誘い