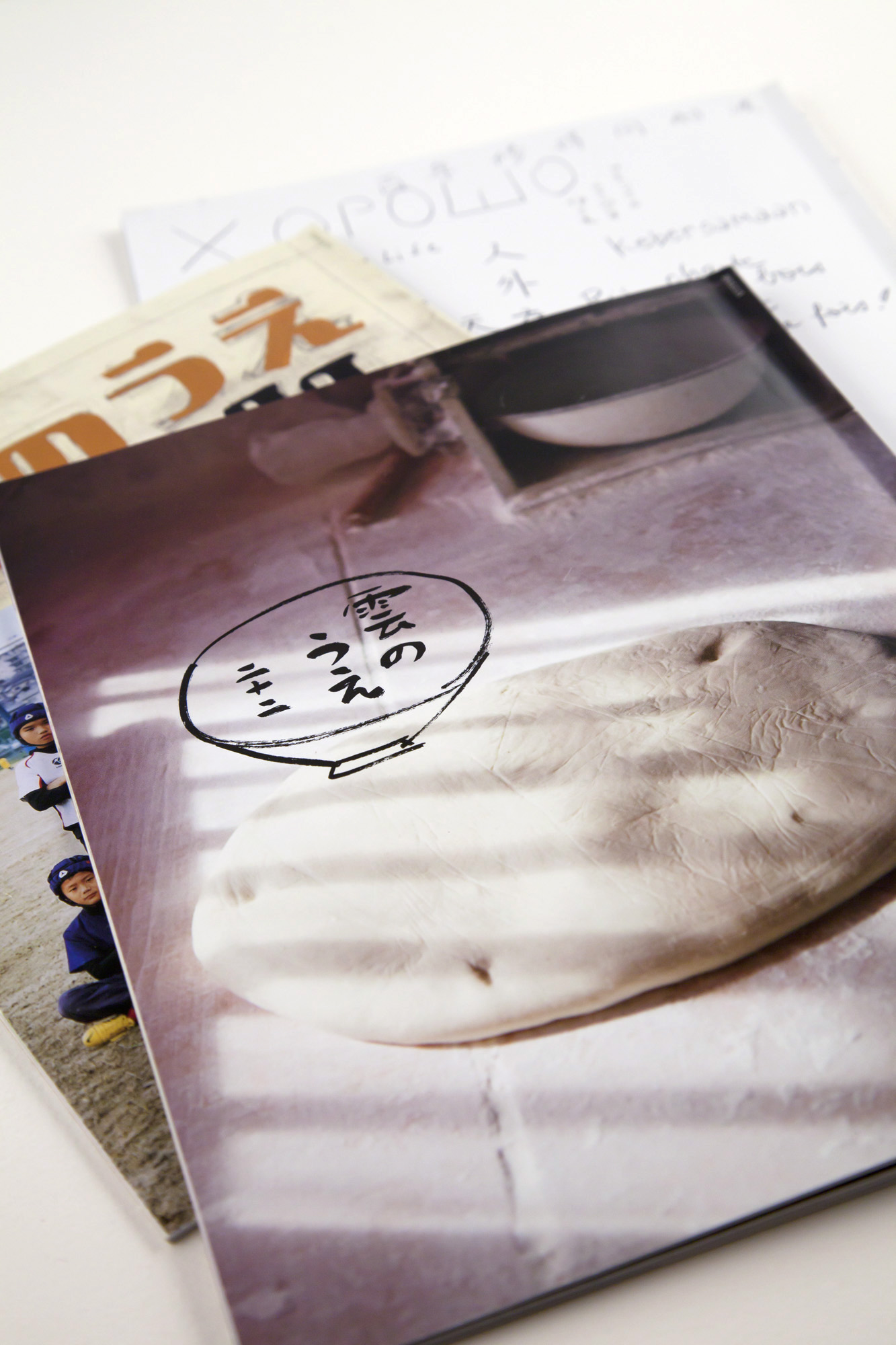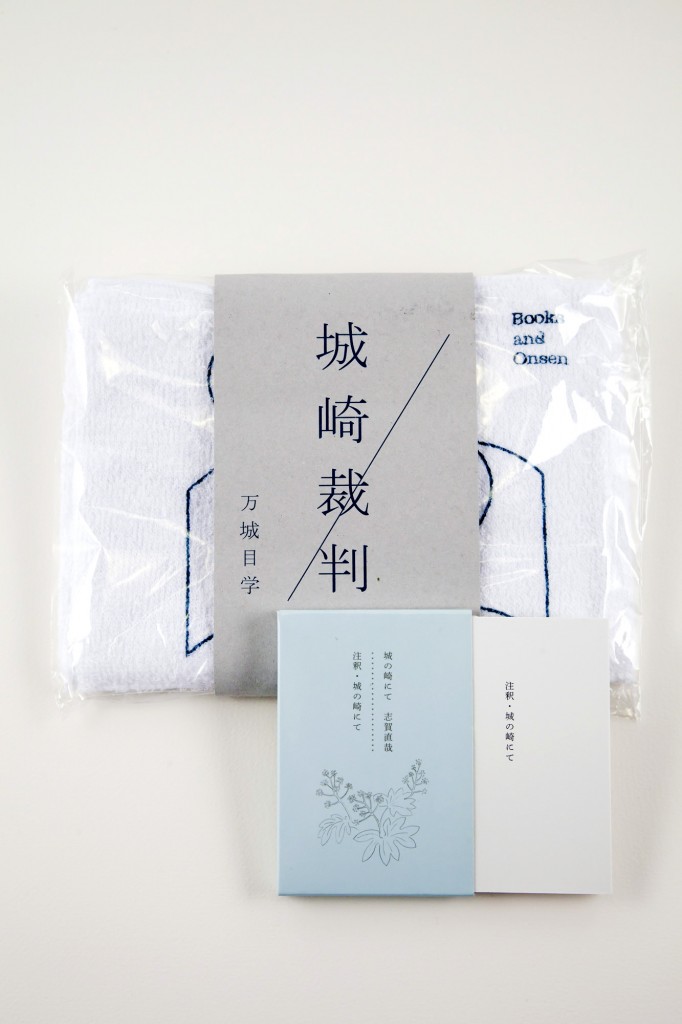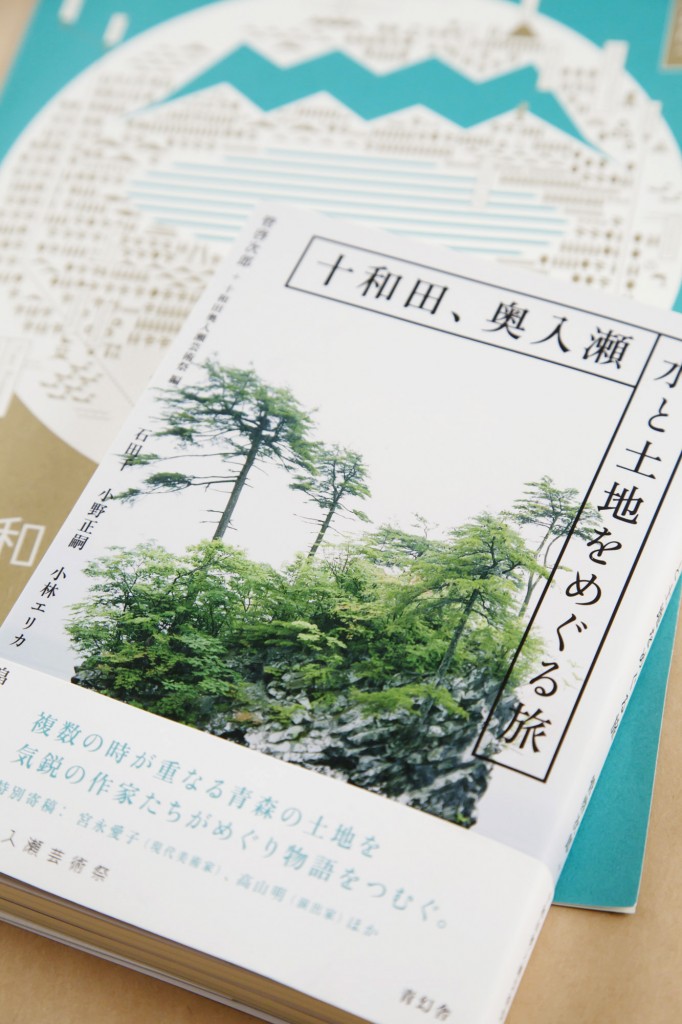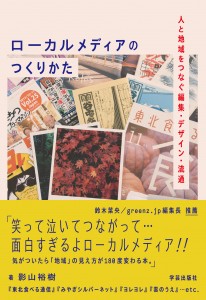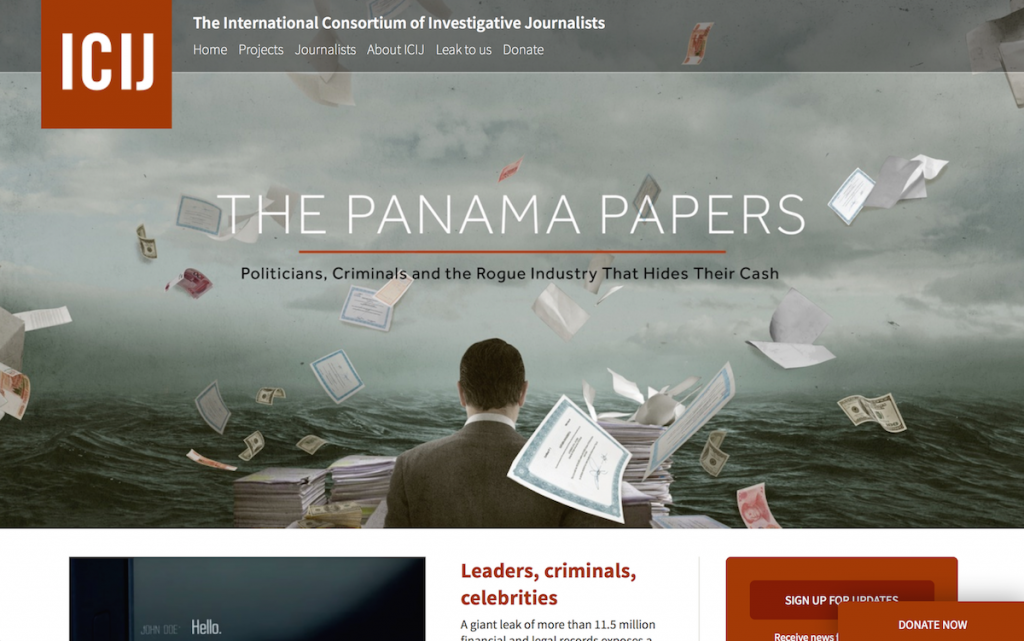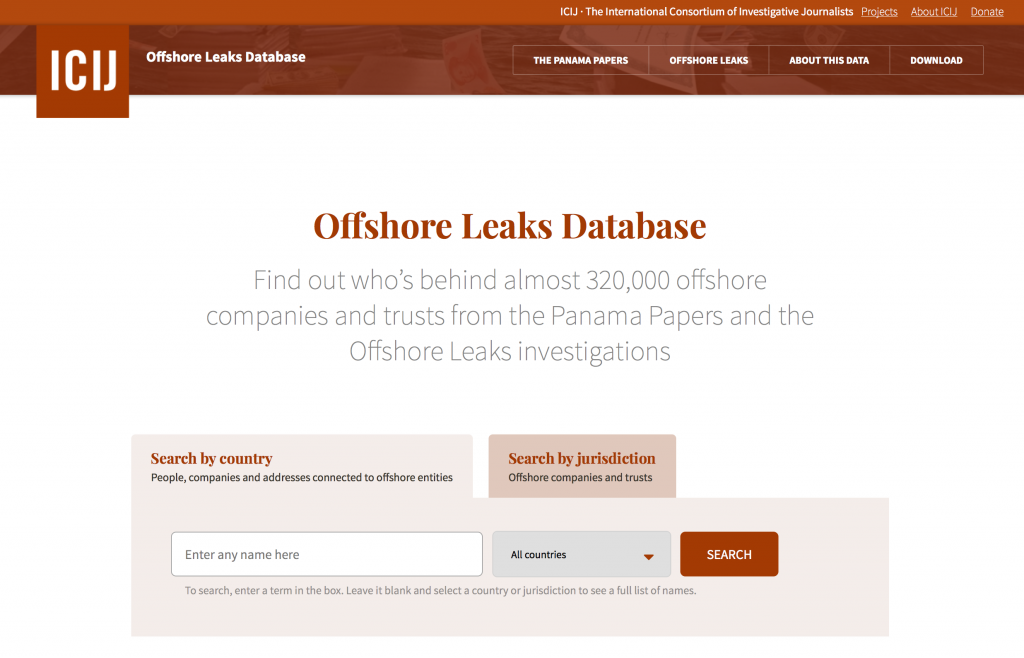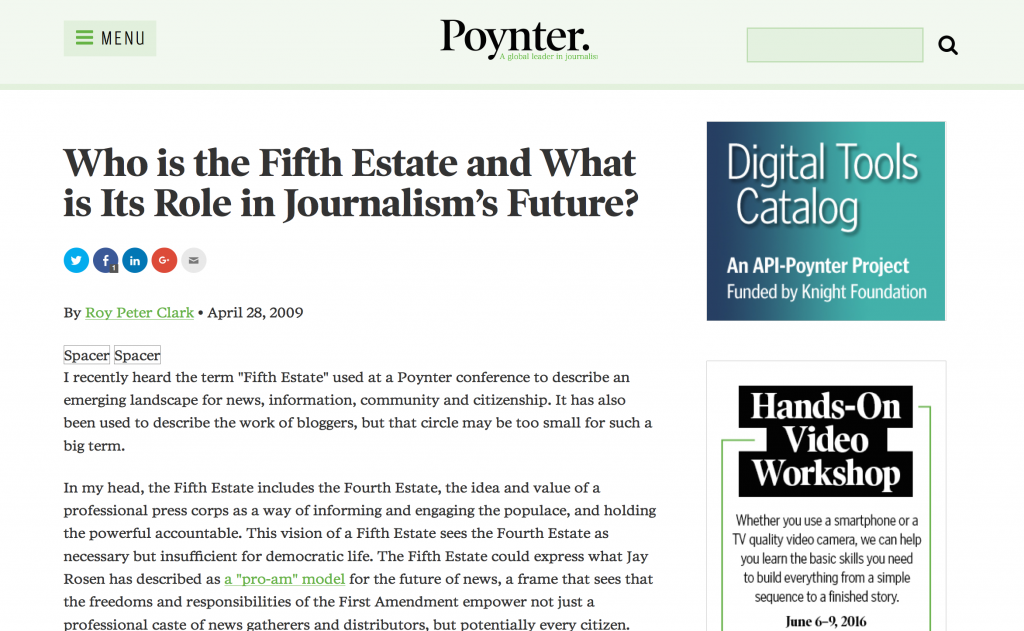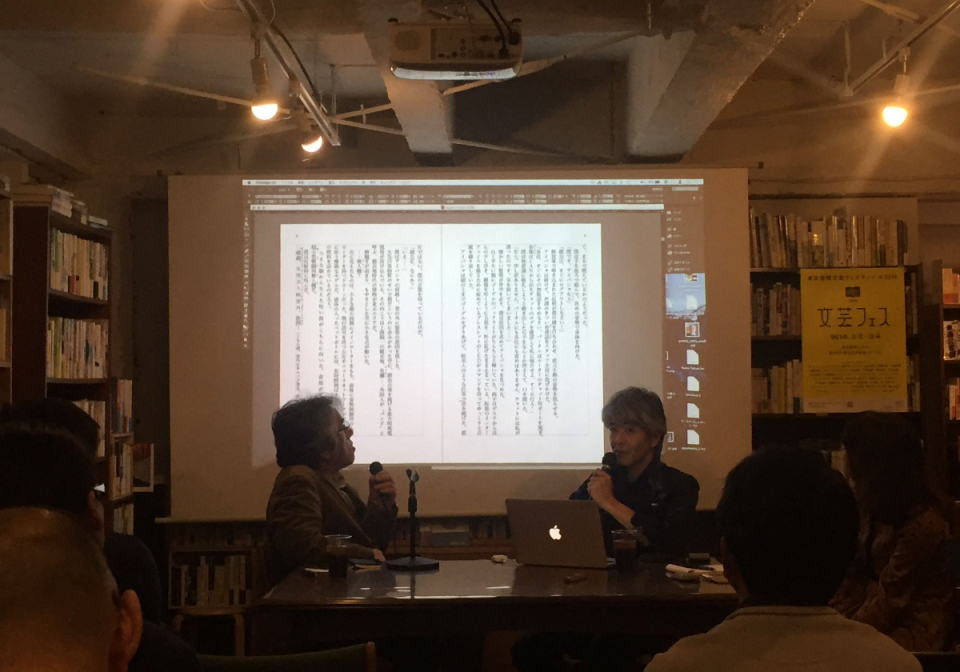2016年3月5日、小説投稿サイトE★エブリスタ主催のイベント「2066年の文芸 第二夜」が、下北沢の本屋B&Bで行われました。「東京国際文芸フェスティバル」の一環として行われた同イベントでは、作家の藤井太洋さんと藤谷治さんをゲストにお招きし、「50年後の文芸はどうなっているのか?」という大きなテーマについてお話いただきました。今回はマガジン航の読者の皆さまに、その一部を抄録でお届けします。
(司会・構成:有田真代)
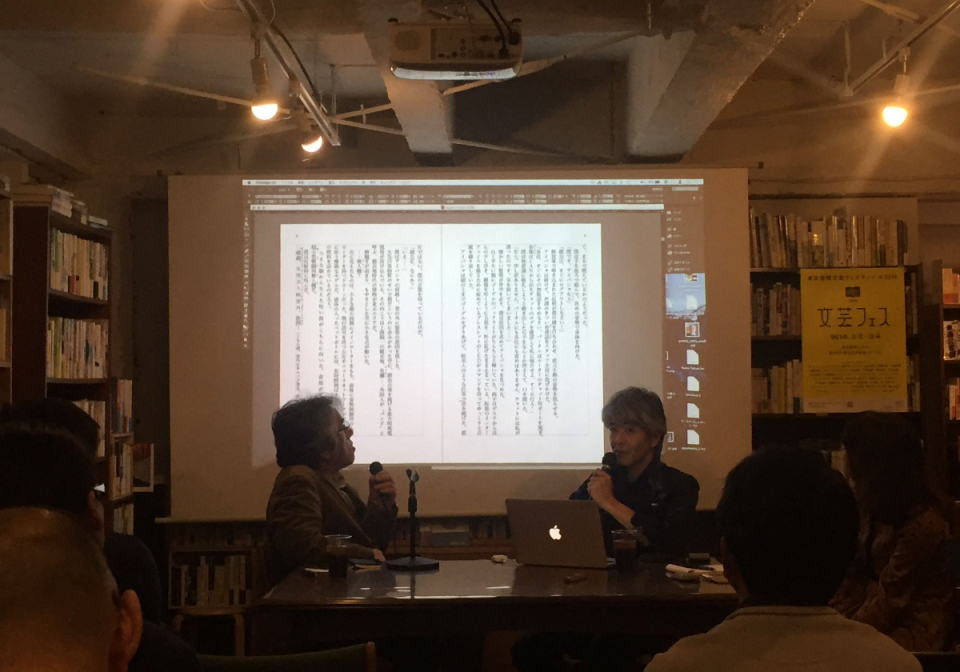
このイベントは東京国際文芸フェスティバルの一環として下北沢の本屋B&Bにて行われた。
文学とテクノロジーの関係
藤谷 藤井さんのお仕事を拝見していると、「小松左京が現役だったら、きっとこういうことを率先してやっているだろうな」と思うことがあるんです。小松左京は当時、「一桁1万円」のキャッチフレーズで売りだされた12桁の卓上計算機をいちはやく購入したり、執筆にワープロを導入するのも早かった。最先端のテクノロジーをとにかくまず使ってみて面白がった人です。文学とテクノロジーのあいだには本当は密接な関係があるはずなんですが、僕にはまだ掴みきれていないところがあります。それが藤井さんにはどう見えているのか聞きたいです。
藤井 紙の上でやっていたことをデジタルに移行することで、恐ろしく消えている部分がいくつもあると思っています。たとえば、コンピュータって画面上で文章を消してしまうと、原稿の見た目、姿が変わってしまうじゃないですか? 冴えているときに書いたものを間違えて消してしまったとき、紙だと残りますけど、コンピュータだと取り返しがつかない。それを補うために、過去の履歴を細かく残せるScrivenerを執筆に使用したり、校正にInDesignを使用したり、いろいろなツールを使っています。
藤谷 僕の場合、「こう書けばスマートだ」と思いついたことも、ご飯を食べたら忘れちゃう(笑)。けど、それは永遠に忘れたままにしますね。僕自身はこれほど細かい内容を残したことはないので比較はできませんが、旧式の文学に対する考え方から言えば、「失われたものは永久に失われたと思ってやるべき」というところに、書いていくという営為、行いは鍛えられたと思っているんです。失ったものを拾うくらいだったら、必死こいて思い出すか、新たにそこにふさわしい一語を生み出すほかないと思うんだけど、もしかしたらそれは昔の体育で「水を飲むと弱くなる」と教えていたように、時代錯誤な考え方なんじゃないかと思うこともあります。本当はどちらなのかな。
藤井 私の場合、4年前まで小説を書いたことが一回もなくて、促成栽培のように長編を書いているので(笑)、経験が浅いゆえにいろいろな方法を試しているというのもあります。実際に書く経験を積んでいくにしたがって、過去から拾うことは少なくなってきましたね。書きはじめたときに書こうとしたことが間違って消えてしまってないか確認する作業は毎回欠かさずやっていますが、ようやく、昔のものを掘るよりもいま書いたほうがよくなるケースが増えてきてはいます。
藤谷 実際にこの書き方で、藤井さんは評価の高いものを出しているんですもんね。物書きって基本的に、「勝手にやっている」ものなんですよ。でも「勝手にやる」ことには終わりがあって、それは本が出たときです。本が出たあとは、世間がそれをどう見るかがとても気になる。なぜなら、自分がやったことが、時代や社会とどう切り結ぶかがわかってくるから。そう思うと、藤井さんの執筆方法の方が社会と触れていると思うんだけど、いま初めて見たばっかりだから、どう捉えていいかまだ分からない。
エゴイズムがあれば、文体は変わらない
――逆に藤谷さんが細かく変更履歴を残しながら執筆した場合、いま書かれているものとは様子の違う小説ができあがるのか、それとも最終的なアウトプットは変わらないのか、興味があります。
藤谷 でも、根本的な発想は作業には左右されないでしょ?「こういうものを書きたい」とか、「こういうものがテーマだ」ということについて、ツールが書き手に向かって要請してくることはありますか?
藤井 ないとは言えませんね。私が使っているScrivenerというツールでは章や節、シーンがしっかり分かれているものを書きたくなりがちだとは思います。細かい断章で完結していくような形にはなりますね。
藤谷 僕の文体が変わるとしたら、それは内容が違うからですよ。普段は手帳とかメモに一度手書きで書いたものをワープロで清書していくんですが、連載などで執筆が間に合わなくなってくると、清書しながら途中から続きを直接ワープロで書いていくんです。そうしても、手書きで書いた箇所とワープロで書いた箇所とで、内容や文体が変わったりはしないですね。
藤井 素晴らしい。
藤谷 それはもちろん僕が素晴らしいからなんだけど(笑)、それ以上に、小説ってエゴイズムで書くじゃないですか? エゴイズムがあれば、文体は変わらないのでは?
――それはエゴイズムなんですかね? 藤谷さんの中にあるエゴイズムというよりは、作品自体が持つ文体や世界観にドライブされて出てくるものなのでは?
藤谷 そうです、それと「エゴイズム」は同じ意味です。藤井さんだってそうなんじゃないの? 一つの小説が要請する文体というのがあって、それにしたがって書くわけだから、ツールで変わるわけではないんじゃないの?
藤井 当然、小説に要請される文章を書き出すようにはしていますが、私の場合は推敲の結果ですね。最後に出ていくときには、要請される文体になっている確信はありますが、その途中経過で片手で打ったり、音声入力したりしているときは、ツールごとの「揺れ」は確実にあります。
藤谷 二葉亭四迷の『浮雲』は、最初と最後で文体がまったく違っていて、未完なんですね。文体が変わってしまったから、どうしていいかわからなくなって未完なんだろうという説もあるんだけど、読んでいて統一感がないわけですよ。ところがその「統一感のなさ」が、物を書いている自分から見ればうらやましい魅力を持ってるんです。「統一」「全体のバランス」を考えていると、小説は生き生きしないんじゃないかという気が最近はすごくしていて。たとえば編集者や校閲から表記ゆれを指摘されても、漢字を統一することにできるだけ抵抗しています。「怖い」と「恐い」と「こわい」とか。藤井さんみたいにツールでがっしり作って考えていくと、「統一性による殺風景」みたいなものは生まれてこない?
藤井 あるでしょうね。出ると思います。
藤谷 そこをワイルドにいってみようとは思わないんですか? 推敲しないでみるとか。
藤井 あんまりそれはしないですね……最終的に、作品が出ていくときに生き生きしていればいいと思っています。
電子書籍の提案する読み方
藤井 漢字を統一することに抵抗するというお話がありましたが、電子書籍の時代になって、これからは読者が文章を読むスピードにあわせて、ソフトが漢字をひらいたりひらかなかったりするようになるかもしれないと思っています。
藤谷 そうなったら怒らない? 何のために漢字にしたの!? って。読む人のことなんか考えたら、読む人のためのものができないと思っちゃう。読む人は、見たことも聞いたこともないものに触れるつもりで、びっくりしてほしい。だからそこにソフトが出てきて、「今日はご精が出ますねー、この漢字はひらいてあげましょう」……冗談じゃないよ~! でもそうなりそうなんですか?
藤井 Kindleの英語版にはいま「Word Wise」という機能がありまして、難しい言い回しの上に、簡単な英語のルビがつくんです。英語読者はこれにより初めて「ルビ」というものを見て「何じゃこりゃ!」と、結構みんな驚いてるんですけど(笑)。実際使ってみるとよくできていて、スイスイ読んでるとWord Wiseが減って、モタモタ読んでるとまた増えてくる。難しい単語だけでなく、熟語や言い回しにも言い換えがつくので、結構ためになるんですよ。いま『アンクル・トムの小屋』を読んでいるんですが、時代も時代だし、聖書の引用なども山のように入っているので、さすがに難しくて、Word Wiseを拾いながら読んでます。たかだか百数十年前の小説でもこういった機能が必要になっちゃうんだなと思うと、これからはルビが増えたりはすると思いますね。
藤谷 でもそれは注釈ですもんね。辞書を引くのと同じことをKindleがしてくれているということですね。
藤井 現時点ではそうです。導入としてはおもしろいと思うんですけど、これが行き着く果てはどうなるんだろう? と。10年20年で大きく変わるとは思いませんが、50年後はかなり変わっていくと思う。
――一部のスマホ小説ではLINEのチャット画面のように、登場人物の顔のアイコンとふきだしで会話文が表現されます。これもある種の「読みやすさ」を追求した結果ですね。
藤谷 じゃあ読んでいる人は、登場人物をイラストでイメージするんだ。ラノベなんかはすでにそうだもんね。でも、みんなはあれでいいの? 自分の頭の中で、登場人物を近所の可愛い子に当てはめたりはしないの?(笑)
藤井 ふきだしを使うオンライン小説では、会話文から役割語が追い出されているものを見ることがあるんですよ。会話が平板でもイラストのアイコンでキャラ分けができちゃうからなのですが、現実の会話にものすごく近い。たとえば男女の役割言葉がなくても、女性男性どちらが話しているかはっきりわかる。それは評価したいな。ふきだしは嫌ですが。
藤谷 根本的に、文章がビジュアル的なイメージに依存するのはどう思う?
藤井 私はあんまり好きじゃないですけどね。
藤谷 小説を読んでる人間にとって、アンナ・カレーニナという人は、誰にとっても存在しないわけですよ。そこがいいんじゃない!
Web小説は現代の『三銃士』?
藤谷 「2066年の文芸」という話でいくと、今後はあまり頭を使わないで読んでいけちゃう小説が求められるようになるのか、昔ながらの古色蒼然とした、イメージは読者が作っていく小説が残っていくのか、どうなると思いますか? テクノロジーの進化の観点から。
藤井 読まれ方の違いで一番大きく変わるのは、終わらない作品が、より増えることだと思います。デビュー作が代表作で100巻以上あるというようなもの。そんな作品と「ここからここまでですよ」とパッケージで完結する作品で分かれていくと思いますね。読む側も、映画とテレビドラマのようにそれぞれ分けて消費するんじゃないかなと。
藤谷 でもそれって、19世紀の小説と同じですよね。ざっくりとした小説の歴史でいうと、ユーゴーやデュマが19世紀にグツグツグツグツ『レ・ミゼラブル』や『三銃士』を、もういつまで経っても『三銃士』! みたいに書いているのに対抗して、フローベールらが簡潔な小説を書くようになった。それに影響を受けて、1920年代から30年代にかけて、ヘミングウェイとかアメリカのハードボイルド作家が出てきて……と、小説は長くなったり短くなったりしている。その繰り返しの中で、また『三銃士』に戻るということ?
藤井 そういう作家がこれからまた生まれてくると思います。スマートフォンで読まれる、横書きで吹き出しがつくスタイルの小説では、そういう終わらない話が「小説」として認識されていくのではないかと。
藤谷 でもそれはやっぱり『三銃士』と一緒ですよね。そこまで新しい感じはしない。「Kindleじゃないとできない話」とか、「スマホとか電子書籍の上でだけ起こっていること」があれば面白いと思うんですが、僕が岡目八目で見るかぎり、まだあまりない気がしていて。携帯小説から『三銃士』くらい面白いものが出てきたらいいですけど、その辺りはどうですかね?
――Webでの連載小説が紙と一番違うのは、公開したらすぐにコメントがつくことですかね。週刊漫画誌の連載のように、読者の反応に合わせて展開を微調整していく人もいます。
藤谷 藤井さんにもそういう経験があるんですか?
藤井 私はまだ連載の経験が少ないのですが、反応を見て内容を変えるということはないですね。何を書くか決めてから書くので。
藤谷 藤井さんがやったセルフパブリッシングと、小説投稿サイトとはまた違いますよね。そこが藤井さんに「勝手にやる」という、小説家としての資質があったところだと思う。小説投稿サイトにいる人に僕がちょっと首を傾げちゃうのは、小説の基本は「勝手にやる」ことなのに、何で群れるの? という点なんです。もちろん、書いている人たちに群れているつもりはないと思います。自分の作品を書いて、反応が良ければ嬉しいと原理的には思うんだけど、絶対そこには何らかの「空気」があるはずだとも思うんです。たとえば僕が「小説家になろう」に匿名で投稿したら、「なろう系」の小説じゃないし、どう受け取られるかはわからない。けど、僕は自分が書いてきたものが間違っているとは思わない。
「幸運」は優れた作品の必須条件
――小説投稿サイトの作家は、必ずしも全員がプロ志向ではないところが面白い点だと思います。エブリスタの場合は作品の販売もできるので、会社員や主婦の方が月に数万円だけ稼いだり、プチ作家、日曜作家的な人がいっぱいいるんですね。
藤谷 ディレッタントが生まれる土壌が日本の文学史にはなかったので、それができたのはいいことですね。ジュリアン・グラックが書いた『シルトの岸辺』という、本当に素晴らしい小説があるんですが、もしグラックが日本の出版状況にいたら、これは読者に届いてないと思う。フランスには、ディレッタントが小さな出版社から1,000部の本を出して、本屋もその1,000部をいつまでも売ってくれるというシステムがあるから、この小説は僕の手にも届いたわけです。そういうことをネットが担っているとしたら素晴らしい。ジュリアン・グラックがネットから現れるには、まだ時間がかかると思いますけどね。
藤井 小説投稿サイトの場合、参加している人が多いので、名作があっても埋もれてしまうのが一番つらいところですね。「カクヨム」がオープンしたときに40本くらい読んでみて、なかには面白い作品もあったんですが、ランキングから見るに読んだ人は私を含めて5人くらいじゃないかと。数が増えてくると、今度は見つからなくなる問題がある。
藤谷 藤井さんはなぜ何万人もいるネット上の小説家の中から、プロになれたんだと思いますか?
藤井 私が小説を書こうと思ったのが2011年の冬、『Gene Mapper -core-』が書き上がったのが2012年の春。たまたまKoboが日本にきたのが2012年7月、Kindleが10月だったんです。当時電子書籍で売られていたSF作品はほぼ全部旧作で、そこにピカピカの新作をねじ込めたのが大きかったですね。これがもう一年早くても、もう一年遅くてもデビューできたか分かりませんし、仮にデビューできていたとしても、時期はもう少し遅れていたかもしれません。
藤谷 作品が優れていたことは前提として、それを拾い上げるツールとして電子書籍のプラットフォームが機能したという良いケースですね。
藤井 それは本当にたくさんの幸運をもらったと思いますね。
藤谷 商業出版の世界でも、小説の数が増えて埋もれてしまう現象はありますが、僕は自分自身の境遇も含めて同情しません。「優れた作品である」ことの指標のひとつとして、もちろん「良い作品である」というのとは別の次元で、「運がいい」というのがあるんです。小説家になるにも幸運は必要だし、書いたものが読まれるのにも幸運が必要で、それは作品の内容とは一切関係がない。だって『シルトの岸辺』、みんな知らないでしょ? けれどナボコフの『ロリータ』はみんなが知っている。それは『ロリータ』という小説が幸運だったからです。
藤井 いま「エブリスタ」や「なろう」や「カクヨム」で書いている人の中から、デュマみたいに立ち上がってくる人がいないと私は思わないので、面白い作品を見つけたら広めたいなと思っています。やはり誰かが褒めて、拾い上げないと作品は浮き上がってこない。レビューをするスタイルが生まれると、日本の文学界も変わっていくと思います。
AIが書いた小説は運を掴めるか?
藤井 星新一さんの小説のプロットを分解して、人工知能(AI)に星さんのような小説を書かせるプロジェクトがいま行われています。AI作家は幸運をつかめるでしょうか? 執筆の途中経過にはまだまだプロの手がかかっているので、大変そうなんですが。
藤谷 それはコンピュータが書いた小説に、人間が赤字を入れるということですか?
藤井 その逆ですね。筋立てや、「登場人物は二人の場合と三人の場合がある」「二人の場合はこういう関係性のバリエーションがある」「こういう発明品がある」「こういう発明品だと結末はこういうパターンになる」……というパラメータを与えて、コンピュータが文章を出力するんです。
藤谷 もうコンピュータが小説を書いてるわけですね。その小説、面白かったですか?
藤井 星新一さんの1,000編の中に混ぜられると、私は気付かないでしょうね。いまはショートショートですが、今後長くなる可能性も十分あるのではないでしょうか。開発者は必死で頑張っていると思う。はたして、そうやって書かれたものは運をつかめるのか? と考えると、面白い問いだと思います。
藤谷 そのとき、人間のエゴイズムが問われますね。でもそうなってくると、さっきおっしゃった「終わらない小説」のほうがAI作家には向いてそうですね。
藤井 ショートショートのほうが難しいんじゃないかという気はします。いくらつけたしても構わないし、いままで書いたことを捨ててもいい、終わらないスタイルの小説が「エブリスタ」「なろう」「カクヨム」などのプラットフォームに上げられ、読者のフィードバックを受けながらひたすら続いていくというのはあり得ますね。
藤谷 正直に言うと、自分の本を買ってくれる人の割合は少しでも上がってほしいので、ネットや、ましてAIから優れた作家が現れたらどうしようという気持ちもあるんですが。
藤井 でも小説ってそこまで食い合いにならないですよ。私は小説家になる前はソフトウェアを売っていたんですが、ソフトってひとつ売れちゃうと、ほかのソフトは売れないんですよ。アンチウィルスソフトってひとつしか要らないじゃないですか? でも小説はテーマが被っていても、同じ人が何作も買ってくれますよね。たとえば維新ものだと、登場人物がほぼ100%同じなのにも関わらず、維新ものだけを何十冊も読む人がいる。
藤谷 それでいうと、「SF」とか「時代小説」はジャンルの中に入るでしょ? 自分はジャンルに入る小説をめったに書かないから、「このジャンルを読もう」という人が買ってくれないんです。ガチガチの密室ものでも書こうかな……(笑)。でも僕はそこも、骨の髄までエゴイストなの。「ジャンル」っていうもの自体に、もう抵抗を感じてしまう。
藤井 ジャンルはたしかに強いですよ。ジャンルはいいです(笑)。
2066年の文芸
藤井 あと、小説書く人って読むんですよね。私も経験上、書くようになってから読む量が桁違いに増えました。昨年、『NOVA+ 屍者たちの帝国』という、『屍者の帝国』の二次創作をプロがやる大森望さん企画のアンソロジーに参加したんですが、感想を検索していたら、Webで作品を書いている人が結構読んでいて。書く人って絶対に本気で読む人にも転換していくので、どんどん皆さん書き始めてほしいです。
藤谷 じゃあ藤井さんは、これからの小説、文芸のありかたについてはあまり悲観していない?
藤井 全然ないですね。ただ、人口が減っていくと読者は減ってしまうので、英語版をどんどん出していきたいというのはあります。
藤谷 去年、「新刊小説の滅亡」という小説を書きました。主要な商業出版社が軒並み新刊小説を一切出さなくなるというスペキュレイティブ・フィクションで、それを書いてからいろいろ気持ちも変転したんだけど、「書いていく」こと自体に大きな変化はないだろうと思うんです。変わるのは「書かせる環境」ですよね。「商業的な文芸出版は残るだろうか」という意味での50年後はどう思いますか?
藤井 「新刊の刷り部数がかなり減っている」という話はずっとありますが、インクジェットを使ったオンデマンド本になると500部くらいからできるので、そうなったら商業的に今の文芸を支えているボリュームが残るかは心配ですね。ただ、全体のボリュームは下がっても、トップセラーが売る数は変わらないじゃないかなと思います。ロングテールの傾きがもっと急になると思う。
藤谷 流通形態そのものの変化についてはどう思いますか? 出版社→取次→書店という流通の流れや、再販制度が変わると、本が本屋や読者に届くまでに、予想がつかない変化が起こりそうですが。
藤井 日本に限って言えば、50年経つと地方自治体の三割は人口減でなくなるはずなので、逆に書店が残るくらいの都市部じゃないと暮らしていけないと思います。かつて奄美大島には12軒の書店があったんですが、今は4軒で、その内のひとつがTSUTAYAです。残りの3軒は学校の教科書を卸すような本屋さんで、皆さんTSUTAYAでしか本は買わない。県庁所在地から離れた場所から次第にそうなっていくと思います。逆に、人が住んでいる場所には必ず本屋があるという現象が起こるのではないかと。
藤谷 東京や大阪の大都市か、マッドマックスかみたいな世界になるわけだ(笑)。そうなると、文芸出版の世界の規模が適正になるかもしれないですね。本当なら文芸出版なんて5、6人いればできるはずなので、今はどう考えても出版社がでかすぎる。雑誌が出版を支えていた時代もありましたが、今は逆転しつつあるので、大変革は起きる。そうすると、文芸の世界はやりやすくなるかもしれません。

左が藤谷治さん、右が藤井太洋さん。
【登壇者プロフィール】
藤井 太洋
小説家。表紙のデザインから広告まで自身で手掛けた電子書籍『Gene Mapper -core-』が、2012年Kindle本年間ランキングで文芸部門1位にランクイン。翌年、同作を改訂した『Gene Mapper -full build-』(早川書房)でデビュー。2014年『オービタル・クラウド』(早川書房)で日本SF大賞、星雲賞を受賞。
→藤井太洋さんの小説「不滅のコイル」の試し読みはこちら
藤谷 治
小説家。1998年にオープンした下北沢の書店「フィクショネス」経営のかたわら創作を続け、2003年『アンダンテ・モッツァレラ・チーズ』(小学館)でデビュー。2013年『船に乗れ!』(ポプラ社)がアトリエ・ダンカンプロデュースで舞台化。2014年『世界でいちばん美しい』で織田作之助賞受賞。
→藤谷治さんの小説『おがたQ、という女』の試し読みはこちら