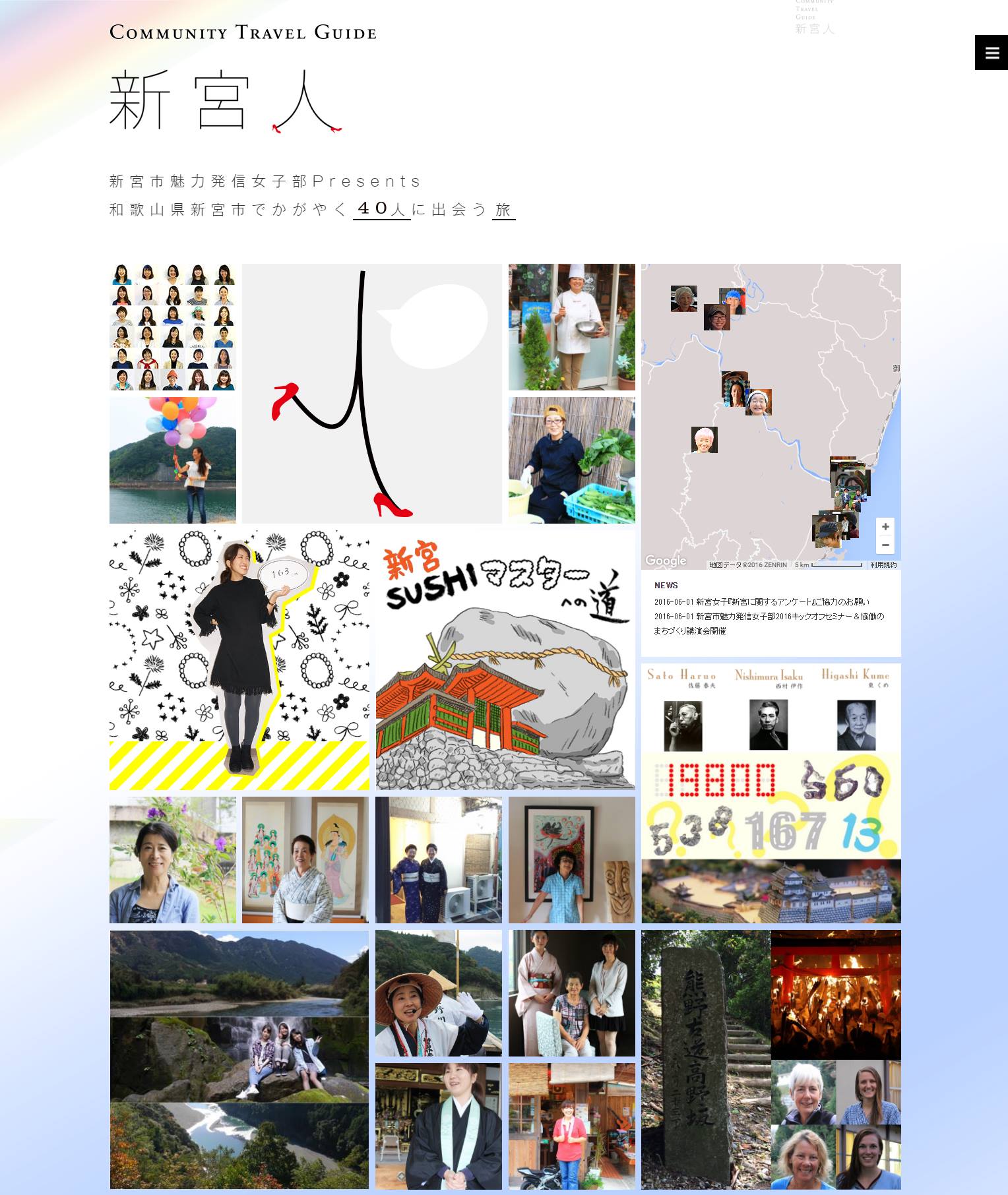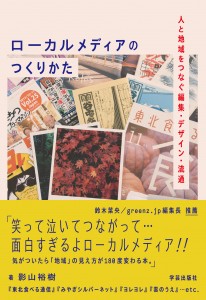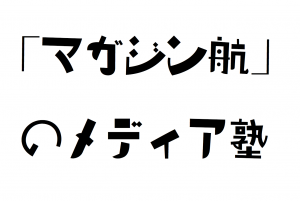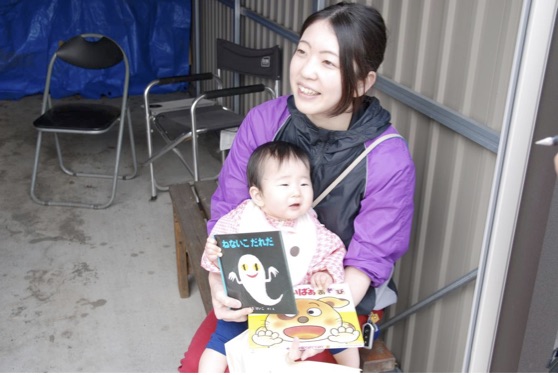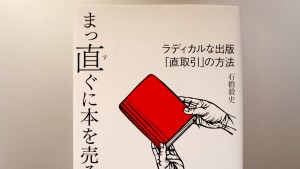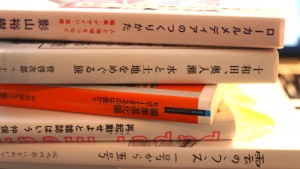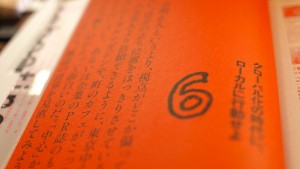2013年6月、CIAに勤務していたエドワード・スノーデンは、アメリカ合衆国の国家安全保障局(NSA)が日本を含む世界の38ヵ国の大使館に対して盗聴を行っていたことを暴露した。ワシントンのEU代表部に対しては、職員のパソコンの作業ログをのぞき見ることも行っていた。また、英国の政府通信本部(GCHQ)はネット上の通信記録から個人を特定することを行っていた。
このように、現代のウェブでは利用者のプライバシーが国家によってないがしろにされている。このことに多くの知識人は危機感を抱いている。
非集中型ウェブ・サミット:ウェブをオープンにしよう
World Wide Web(ウェブ)の発明者でW3Cの創設者であるティム・バーナーズ=リー、TCP/IPプロトコルの共同開発者でインターネットの父と呼ばれるヴィント・サーフ、そしてインターネット・アーカイブの創設者で所長であるブリュースター・ケールが一堂に集まるとそれだけでニュースになる。
2016年6月8日〜9日にサンフランシスコのインターネット・アーカイブの本部で開かれた「非集中型ウェブ・サミット: ウェブをオープンにしよう」(Decentralized Web Summit: Locking the Web Open)はニューヨーク・タイムズ、フォーチュン、ニューズウィーク、インクワイアラ―などの紙面を飾った(下はサンフランシスコのインターネット・アーカイブ本部[元教会の建物] の前で撮った集合写真)。
Okay who's hosting the next #DwebSummit? There's so much more to talk about… pic.twitter.com/eH2lwy9P6u
— Internet Archive (@internetarchive) June 12, 2016
これを報じた各メディアの見出しは次のとおりである。
ニューヨーク・タイムズ
「ウェブの創設者たちは作り直しを目指している」(The Web’s Creator Looks to Reinvent It. The New York Times. 2016/6/7)フォーチュン
「二人の預言者が壊れたインターネットの修復を求める」(Here’s How Two Visionaries Want to Fix a Broken Internet. Fortune. 2016/6/8)ニューズ・ウィーク
「ウェブの修正第一条とインターネットの未来への希望」(Building the First Amendment into the Web and Other Hopes for the Internet’s Future.)インクワイアラ―
「バーナーズ=リー卿語る、インターネットは世界最大の監視装置となってしまった」(Sir Tim Berners-Lee: Internet has become ‘world’s largest surveillance network’. The Inquirer. 2016/6/8)
ネットの「預言者」たちはかく語れり
これらの記事に紹介された、「預言者」たちのことばを具体的に紹介しよう。
ティム・バーナーズ=リーの発言。
photo by Brad Shirakawa
ウェブは人々を監視し、何を読んでいるかスパイし、国によってはサイトをブロックし、利用者を誤ったサイトに誘導している。問題なのは巨大な検索エンジン、大規模なソーシャル・ネットワーク、そしてツイッターである。これを克服するには、非集中型のウェブが必要である。(上記「インクワイアラー」より)
ヴィント・サーフの発言。
photo by Brad Shirakawa
いまや歴史はウェブの上で起きている。したがってウェブの永続性が必要である。非集中型には必ずしも賛成しないが、ウェブが自分で版を管理しアーカイブを保存するような仕組みが必要だと考えている(上記「ニューズ・ウィーク」より)。
ブリュースター・ケールの発言。
photo by Brad Shirakawa
インターネットは ①信頼性があり、② プライバシーが守られ、③そして楽しいものでなくてはならない。今は ①②が実現していない。これを変えるには非集中型ウェブが必要である(上記「ニューズ・ウィーク」より)。
「非集中型ウェブ」構想の詳細については、この会議を招集したインターネット・アーカイブのブリュースター・ケールが自分のブログで次のように説明している(Locking the Web Open: A Call for a Distributed Web. 2015/8/11.)。
1)インターネット (コンピュータ通信のハードとソフト) は分散型で共同運用されているにもかかわらず、その上で動くウェブ (ブラウザを通じて情報を流す仕組み) は集中管理されている。ウェブには持続性がなく、またプライバシーがない。これを非集中型のものとして再構築すべきである。
2)エドワード・スノーデンが暴露したように、世界の国家はインターネットを通じて自国民、他国民を監視している。また中華人民共和国はニューヨーク・タイムズもインターネット・アーカイブもブロックしている。
3)非集中型ウェブを実現するための既存の技術としては、JavaScript、公開鍵暗号、発信者への支払いシステムとしてのBitCoin、分散システムを実現する技術としてBitCoinをサポートする技術であるBlock Chainなどが考えられる。分散型CMSであるWordPressを使って多数の利用者がデータを互いに持ち合うことも考えられる。それを可能にするモデルとしてはピア・ツー・ピア技術を用いたファイルの配布システムBitTorrentがある。これを用いればあるファイルを請求した場合、複数のコンピュータからすでにダウンロードされたファイルから断片が送られてくる。ダウンロードした利用者自身がファイル提供サーバーとなっているのだ。このようにしてデータの所在や発信源を分散すれば、個人の閲覧履歴を国家が窃視したり情報をブロックすることが困難になる。

左上から右に「Blockchain」「BitCoin」「JavaScript」のロゴと「公開鍵暗号」のイメージ。
当然のことながら、ケールが紹介した技術がすべてではなく、またこれらは要素技術としては存在するが、いまだ組み合わされて新しいウェブとして実現しているわけではない。今回の会議では、これらの技術やその他の可能性について議論されたと思われる。
この会議に集まった人々は、開かれた、検閲のない、分散化されたネットワークを目指している。会議の様子をとらえた写真を見ると、上記のような大物は一部で、多くの参加者は第一線で活躍している若い技術者たちのようである。

photo by Brad Shirakawa
非集中型ウェブを構築しようという試みは始まったばかりだが、Google、Facebookといった現在の巨大IT企業も、もともとは小さなスタートアップだった。若い技術者たちの大胆なアイデアがこれまでネット社会を牽引してきた歴史を顧みれば、非集中型ウェブという夢もまったく無謀な計画ではないと思われる。なおこの会議にはGoogle, mozillaなどもスポンサーになっていることも最後に記しておく。

このサミットをスポンサーしている企業の一覧。