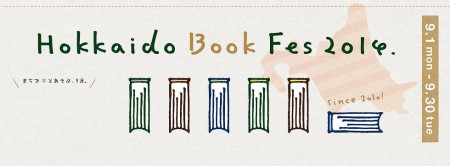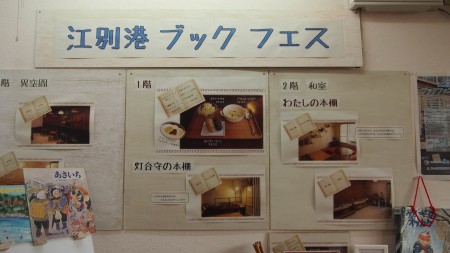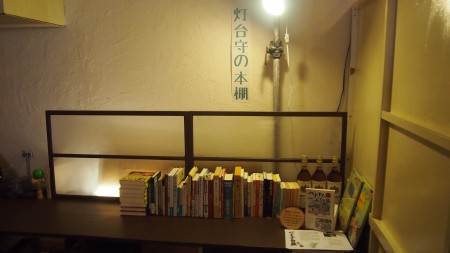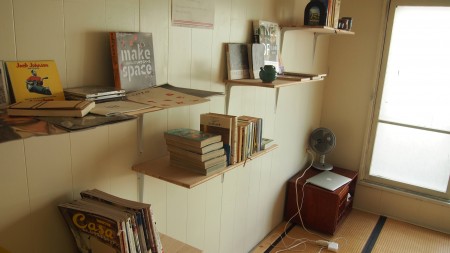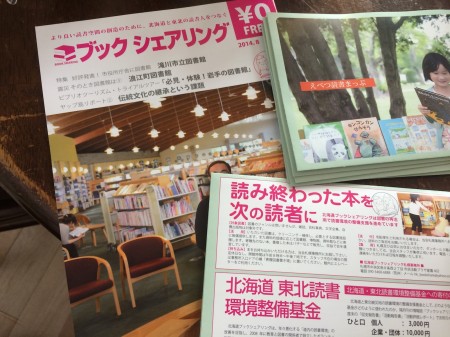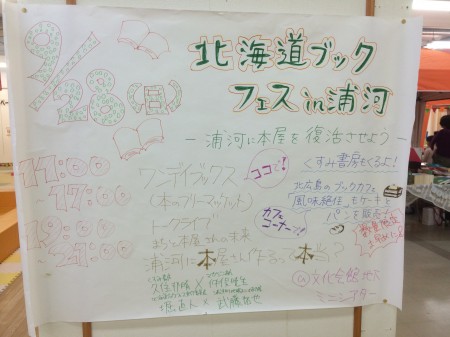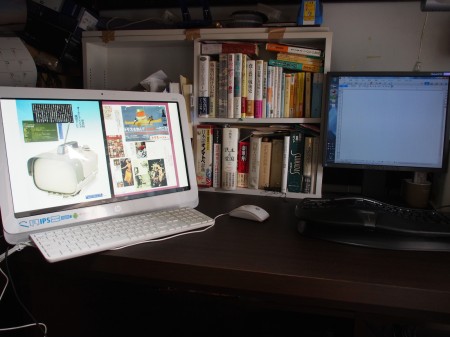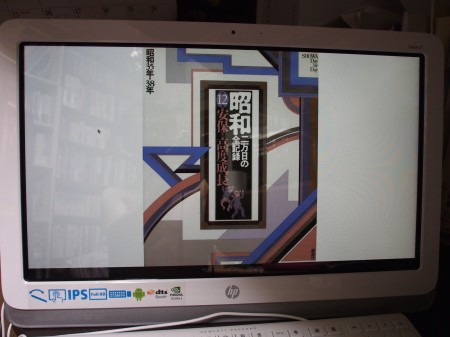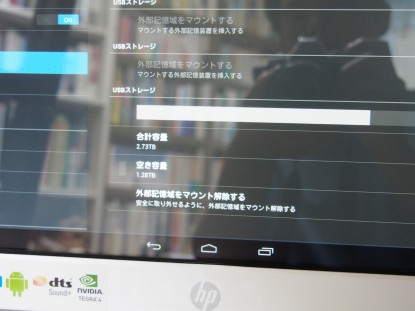リスペクトがインスパイアでオマージュする
これから話すのは私が久しぶりに本を書こうと思った日々の話だ。
ロビン・スローン著『ペナンブラ氏の24時間書店』(東京創元社刊)については、前回お話した通りだが、かいつまんで言うと、現代アメリカの失業青年がひょんなことから奇妙な24時間営業の古書店の店員となって、奇妙な店主であるペナンブラ氏と出会い最新デジタル技術を用いて伝統的西洋式活版印刷技術で組み上げられた奇妙な謎を解き明かす、という物語である。
この連載をお読みの方は、もちろん、このひと月の間に、すでに、原書をお読みに、なっている、と思うので詳細については割愛させていただく。なお、前回は「ですます調」であったが、今回は「である調」のほうが都合がいいのでこのようにした。文字数も減らせるし。
話を先に進めよう。読者諸兄と同じく、私もこの本を読み、ドキドキしワクワクしハラハラし、感動してエンディングを迎えた。そして、私もみなさんと同じように思ったのである。
「江戸の出版だって負けちゃいませんよ。」
と。……思ったよね?
『ペナンブラ氏〜』では「活版印刷」が重要なキーワードであり、最新のデジタル&出版事情と中世の出版技術の融合が実に面白かったのだが、それだったらわが国の近世印刷技術だって決してひけを取るものではない。当時世界最大の都市であった江戸で発達した印刷・出版技術は、掛け値なしで世界最高峰であり、印刷物の大衆化は西洋のはるか先を行っていたのである。
一応、活字の技術も中国から伝わってはいたのだが、江戸出版の主流は木版印刷だった。これは、英語のような文字数の少ないアルファベットだけで済む言語とは違い、日本語は漢字からひらがな、さらにカタカナまであるため、もうそのまま彫ったほうが早いぜてやんでぃ、ということだったのだろう。江戸時代には多くの出版物が、手彫りで印刷され、あらゆる身分の人々に売りさばかれていたのだ。
また、浮世絵などでも知られる多色印刷の技術力も特筆すべきものがある。当時、これらの絢爛豪華な印刷物は倹約を推奨する幕府によって禁制品とされたので、行商書店の訪問販売を隠れ蓑にした地下流通があったと伝えられている。そのような政府からの抑圧が、かえって印刷技術の発達を促進させたというのも、また興味深い話ではないか。たくさんの本を背負って得意先を回る「貸本屋」も、全盛期には江戸全体で800軒もあったそうだ。
江戸の出版はちょっと小ネタを並べただけでも、こんなに面白い。私は、ロビン・スローンへの感謝と敬意を示すためにも、近世日本の印刷・出版事情をテーマに『和製ペナンブラ』を書いてみたくなったわけだ。
というわけで、今回は小説の執筆に関してのお話である。
タイムスリップするのしないの
まずは、どんな物語にするかを考えてみた。
江戸時代が舞台となるのであればそれは時代小説だ。時代小説は藤沢周平や池波正太郎、隆慶一郎など大家が大勢いるし、最近では冲方丁著『天地明察』の大ヒットもある。小説に限らず漫画や映画などでも幅広く根強い人気のジャンルなのだ。山東京伝や蔦屋重三郎を主人公にして、禁書の規制を強化してくる幕府と対決させるというのも、ドラマチックで面白いだろう。しかし、私は充分な時代考証ができるほどの予備知識があるわけではなく、丸腰で江戸時代人の話を書くのはあまりにハードルが高い。
児童文学やジュブナイル小説の分野では、現代っ子が突然タイムスリップして江戸時代を冒険するというストーリーが少なくない。シリーズ自体はいつも現代劇でも、エピソードによってタイムスリップさせるというようなものもあり、読者を日常から非日常に一気に吹き飛ばすには、使い勝手のよい小道具であるといえるだろう。
最近ハリウッド映画にもなった桜坂洋著『オール・ユー・ニード・イズ・キル』は、同じ時間を何度も繰り返す「タイムリープ」という仕掛けを基軸にしているし、三部けいの『僕だけがいない街』というコミックもタイムリープがテーマになっている。少し前でも『涼宮ハルヒ』シリーズにタイムリープをネタにしたエピソードがあったのは、知られた話だ。
タイムスリップやタイムリープは、『ドラえもん』の昔から多くのストーリーテラーによって、手を替え、品を替え演じられてきたギミックである。これを使わない手はないと思いもしたが、登場人物をタイムスリップさせたら結局舞台が江戸時代になり、あとで描写に苦労することになってしまう。
どうしたものかと思って元の『ペナンブラ氏〜』に立ち返ってみると、そもそも主人公たちは現代人で、現代の世界で物語は終始し、タイムスリップなどしてはいない。私はすっかり思い違いをしていたのだ。昔を語るには、その時代に行かなければならない、と。しかし、小説の世界ではそんなことをする必要はない。時間旅行をするのは読者だけでよかったのだ。本書では登場人物は誰もタイムスリップをさせないことに決めた。登場人物は、ね。
あんたが大将堂:タイムトラベルに関する参考本棚
ひとりブレストで江戸をぐるぐるする
いよいよ、物語のプロットに思いを巡らせる時間だ。
小説を子どもに例えるなら、これはさしずめ仕込みの夜のようだ。作家にとっては一番のお楽しみの時間帯であるといえるだろう。この作品では、私の他には特に誰もスタッフがいないので、作家としての自分と、編集者としての自分が脳内でガチンコ対決をするということになる。
まず、江戸時代の出版物についてだが、大きく分けて評論や学術本のような黒本、子ども向けの赤本、大人向けの娯楽本の青本がある。江戸期の出版は青本が一般大衆にまで大いに広まったのが特徴的なのだが、これが日に焼けて黄色に退色したものを後に黄表紙と呼ぶようになり、娯楽出版物の総称にもなった。
黄表紙作家として最も知られているのは山東京伝だろう。他にも大勢いるが、最も有名な版元・蔦屋重三郎とのタッグは、江戸出版界の黄金時代を築き上げた。この2人は外せない。調子に乗りすぎたこのコンビは、宿敵・松平定信の「寛政の改革」で弾圧を受け、京伝は手錠をかけたまま自宅謹慎を強いられる手鎖五十日の刑に、蔦重は財産の半分を没収というたいへん重い処分を受けることになった。
幕府は以前からも禁書目録を作り、幕府や諸大名にとって都合の悪い内容の出版物や、公序良俗を乱す出版物を取り締まってきた。これは主に宗教的な理由で禁書取締を行った欧州とは少々事情が異なる。絵師の鈴木春信は、美しい多色刷りである錦絵の技術を完成させたが、倹約の世にそのような派手な出版物はけしからんということでこれも禁書目録に加えられた。錦絵の完成は、かの平賀源内も一役買ったと伝えられるが、彼は男色家としても知られているので、歴史の裏で春信と何かあったのではないかという邪推も面白いだろう。
幕府に禁じられた本、とくに艶本などと呼ばれる春画本は、貸本屋が行李の底にこっそり持ち歩き、得意先で売り貸ししていたようだ。これらの本は幕府に知られない裏の流通であるため、絵師達が存分に腕を奮って仕上げ、一般に流通する本より遥かに豪奢な作りだったという説も残っている。また、蔦重は吉原の生まれで、元は吉原大門前の書店で『吉原細見』を売っていた。黄表紙には吉原での出来事を題材にしたものも多く、色街吉原と江戸の出版は切っても切れない関係にあったのだ。
江戸期に隆盛を極めた木版印刷だが、明治に入り本木昌造らが活版印刷を普及させると急激に廃れていった。同時に江戸の貸本屋も消えてゆき、いま貸本屋といえば戦後流行った少年漫画誌を貸してくれるあれのことを指すように変容していったのである。
もしも、江戸の貸本屋が現代でも営業を続けているとしたら、どんな世の中になっていただろうか。ということで、ようやく小説のメインテーマが決まった。「禁書目録を巡っての現代の貸本屋と幕府の末裔の奮闘記」である。
タンターターター、タンタンタン
テーマの方向性が決まり、プロットの輪郭が見えてきたところで、そろそろ決めておきたいのはタイトルである。
近年の流行は、やたら長い文章のようなタイトル。最初のうちは『○○と××と△△』みたいなものだったのが、今では『××が△△だったら○○はどうする?』だの『△△が○○で××している』だのという文章系タイトルが百花繚乱となっている。わざわざ長くしておいて、それから『はがない』などと略すのも最近の流行のようだ。しかし、そのラインを狙っても、いまさら感満点なのでやめておく。
流行には関係ないかもしれないが、英語だけのタイトルもちょっといいかなと思っている。先ほど紹介した『オール・ユー・ニード・イズ・キル』もそうだが、サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』を村上春樹がカナ表記で『キャッチャー・イン・ザ・ライ』と改めたのを思い出した。むしろこれは007のサブタイトルの感覚かもしれない。『ネバー・セイ・ネバー・アゲイン』に『ダイ・アナザー・デイ』などなど。
カナ表記に併せて、言葉のリズム感も大事な要素だ。とりわけ黄表紙のタイトルには秀逸なものがいくつもある。『東海道中膝栗毛』、『金々先生栄花夢』、『南総里見八犬伝』などなどなど。長く愛される古典は、タイトルの語呂、語感も素晴らしいのだ。声に出して読むと、「トーカイドーチュー、ヒザクリゲ」、「キンキンセンセー、エイガノユメ」、「ナンソーサトミ、ハッケンデン」である。私はこれらのタイトルを夜中に繰り返し発声することで、基本リズムが「タンターターター、タンタンタン」で共通していることを発見した。
つまり、英語カナ表記でこのリズムのタイトルなら、多くの人々の目と耳から浸透し、大ヒット間違いなしということになるではないか。ということで、タイトルは『ストラタジェム;ニードレスリーフ』に決まった。この言葉の意味については、またいずれしかるべきときに。みなさんも今すぐ3回ずつ繰り返し声に出して、リズム感を楽しんでいただければ幸いである。
あんたが大将堂:タイトルに関する参考本棚
執筆ツール選びで試行錯誤
そして、いよいよ本文に着手していくわけだが、書くためのツール選びには悩んだ。私の場合、普段はノマドワーカー的な動き方になるので、一ヶ所で腰を落ち着けて執筆するということはできない。メインマシンはMacBook Airだが、自宅ではMac miniを使っている。軽装備で出るときはiPad miniで書くこともあり得る。
まず、GoogleDocを使ってみた。番号付きでアウトラインを書き進めていけるので、初期段階ではうまく機能したが、個人的な環境の問題でChromeの動作が鈍くなるという症状に悩まされ、全体のアウトラインまで作成したところで断念した。仕方ないのでデータを.docxで書き出し、MS Wordに移行することにした。
Wordでは第1章を書き上げるところまで試してみた。書くこと自体は特に問題なかったのだが、実は私はWordについてはあまり習熟しておらず、いじればいじるほどストレスが溜まるのだ。その後いろいろ試した結果、長年使い慣れたmiというエディタソフトに落ち着いた。
とりあえず第1章が書けたところで、Adobe InDesignでレイアウトイメージを組んでみた。私は根が読者なので、実際に読むのを想定するとおかしなところがよく見えてくる。説明の過不足もよくわかるし、重複やくどいところも浮き彫りになってくる。InDesign上で三周ほど推敲したらまずまずの仕上がりになってきた。二割ぐらいはInDesignで加筆したかもしれない。
ただ、InDesignは紙やPDFでリリースするのであればそのまま出せるので便がいいのだが、EPUBでリリースするにはひと手間ふた手間余分にかかる。一度textに書き出して、EPUBのオーサリングツールに流し込むのだが、InDesignから直接EPUB形式で書き出すこと自体は現時点でも可能なので、この機能がどこまで実用性があるのか次回までにテストしたいと思っている。
『和製ペナンブラ』のキャラクターたち
物語のアウトライン作成と平行して、キャラクターシートも作成した。
現代パートの主人公は「三重田辰野」。ミエダタツヤは、字面をご覧の通り蔦屋重三郎のモジリだ。物語が始まる直前の段階では、両国駅前の書店のアルバイトをしている。彼は素人童貞でシェアハウスの住人でSNSやMMORPGのプレイヤーで、筋力には少し自信がある日本の平均的な若者だ。思想的にはニュートラルで、一応主人公ではあるが、実際にはこの物語の狂言回し的存在である。『ペナンブラ氏〜』の主人公クレイ・ジャノンがモデルなのだが、アメリカの青年と日本の青年で行動指針に若干の違いはある。
ヒロインは「千束小町・恋川」こと「松葉しずく」さんだ。彼女についてはここでは多くは語れないが、元のキャット・ポテンテよりももっと「猫っぽさ」を強調した設定にした。恋川の名前は、江戸時代の戯作者・恋川春町から頂戴した。
エイジャックス・ペナンブラに相当するのは「神田カンジ」という中年。ペナンブラよりももう少し若い設定になる。日本橋の「本屋横丁」内にある組合事務局を拠点に「貸本屋四六」を1人で運営していて、「本屋仲間」という同業者ギルド(日本貸本屋組合)に所属している。
マーカス・コルヴィナにそのまま該当するキャラクターはおらず、代わりに幕府禁書取締方の末裔で「水野」という人物が登場する。序盤で姿を消す「伊豆宮」もコルヴィナの機能の一部を担当している。
江戸時代パートは、まず平賀源内と鈴木春信が登場。非常に重要なキーパーソンである彼らは後半にも再登場の予定だ。続いて山東京伝と蔦屋重三郎が秘密会合を開くが、この酒宴には、幕府の要人が来訪する。一方その頃、若き日の松平定信は怒り心頭、復讐を誓う。
後半に登場するのは、江戸時代後期浮世絵の大家・渓斎英泉、そして曲亭馬琴。「三代豊国」として知られるベロ藍使いの技巧派・歌川国貞、江戸のポップアーチスト歌川国芳、そして潔癖性の老中・水野忠邦、その配下の渋川六蔵を予定している。北斎、歌麿、写楽も一応出る。これだけのビッグネームをずらっと並べれば、「大江戸オールスターズ」を名乗っても納得していただけるだろう。
江戸出版の参考文献をかき集める
編プロ時代に春画のガイドブックを手掛けた経験から、江戸の出版物についてはある程度の予備知識があったものの、それはあくまで裏流通のものに限った話であり、『ストラタジェム;ニードレスリーフ』のためにはそれだけでは足りない。ひとまず、みんなのWikipediaさんで大まかな予備知識を拾って、Amazonで書名を探して、図書館で借りることにする。ここの図書館はWebで予約して近所の館に取り寄せてくれるので便利だ。
かつてに比べるとだいぶ楽に文献が探せる時代になったが、ネットで横断全文検索までできたら、もっと早く確実に探せるのに、というもどかしさは残った。横断検索自体は仕組みとしてはSideBooksクラウドで出来上がっているので、こいつがもっと普及してくれたら実現は可能なのだが、現在のようなプラットフォーム分断の状況からそこまでたどり着くのはなかなか難しいだろう。
今回集めた大量の参考文献から、代表的なものをいくつか紹介しよう。
内田啓一著『江戸の出版事情』(青幻社刊)は大判カラーで物の本から絵草紙まで幅広く紹介していて、総合的な知識を得ることができた。最初に読むべき本だろう。中野三敏編著『江戸の出版』(ぺりかん社刊)も江戸出版の全容を知るには良い文献だった。これは2010年に休刊になったぺりかん社の専門誌『江戸文学』の記事で構成したもので、さらに江戸出版の深みを知りたいのであれば、この雑誌のバックナンバーを集めるといいかもしれない。鈴木俊幸著『江戸の本づくし』(平凡社刊)も黄表紙を中心におおまかなことがわかる。
禁書目録は『ストラタジェム〜』の大きなテーマなので、重点的に調べる必要があるが、井上泰至著『江戸の発禁本』(KADOKAWA刊)、今田洋三著『江戸の禁書』(吉川弘文館刊)を主たる資料とした。ほかに、江戸パート主要登場人物の山東京伝については棚橋正博著『山東京伝の黄表紙を読む』(ぺりかん社刊)が非常に詳しく、京伝の思考シミュレーションに役立った。
春画に関する知識の補強には白倉敬彦著『春画と人びと 描いた人・観た人・広めた人』(青土社)と同氏監修『春画の楽しみ方完全ガイド』(池田書店刊)がある。江戸期の生活習慣などの一般情報の参考文献としては、石川英輔著『大江戸生活事情』(講談社刊)をKindleで購入した。
江戸出版に関する本以外にもう1冊付け加えておきたいのは、筒井康隆著『創作の極意と掟』(講談社刊)だ。小説を書く人、書きたい人、書いた人は本棚の常備本にぜひお持ちいただきたい。必ず役に立つと断言できる。実はこの本は、今回の企画が生まれる前に手に入れており、第1章まで書いたところで、ふと本棚を見たら目に入ったので手にしてみたらまさに今読むべき本だったのだ。メーテルリンクの『青い鳥』のように、探していたら近くにあったわけである。
あんたが大将堂:ストラタジェム参考文献本棚
魅惑のミュージアムめぐり
書籍資料を漁る以外に、博物館や資料館などにも出向いた。私は調べ物をWebで終始させたりはしないのである。フィールドワーク重視のアウトドア派で現場主義なのだ。
まず向かったのは、物語のスタート地点でもある両国だ。ここにはご存知、江戸東京博物館がある。実に無駄な設計の建物だが、展示物は素晴らしかった。出版に関する資料も豊富で、町民の暮らしぶりもよくわかった。吉原の展示が少ないのが残念だ。今回は関係ないが明治〜昭和の展示もなかなか充実している。そのあと散歩がてら浅草まで回り、帰りにカキモリで専用ノートを拵えた。
清澄白河からすぐの深川江戸資料館も素晴らしかった。内部には江戸の街並が再現されていて、町民気分がリアルに味わえる。今回は運良く松平定信の特別展示があり、たいへん良い取材になった。深川資料館通りには個性的な古書店(しまぶっくなど)がいくつかあり、ぶらぶら歩くにはいいだろう。そのまま抜ければ東京都現代美術館(MOT)まですぐに着く。ちょっと上質な休日を過ごしたい向きにはオススメのコースだ。
浮世絵の取材もしておこうということで、原宿の太田記念美術館にも行った。このときは特別展が「江戸妖怪大図鑑」で、大量の北斎、国貞(三代豊国)、国芳が見放題であった。妖怪画は、春画や美人画とはまた異なる緻密なディテールのおどろおどろしさがたまらない。10月から国貞の特別展があるのでまた足を運びたいと思う。ベロ藍の美しさを直に見られるのは本当に喜ばしいことだ。
浮世絵に関しては、長野県松本市の日本浮世絵博物館にも足をのばした。ここでは摺り師による摺り作業の実演も行われており、摺りシーンのディテールアップにたいへん参考になった。あんまり参考になったので、第7章をまるごと松本編に変更したぐらいだ。やはり、実物が見られるのであれば、どんどん出かけたほうがいいのである。家族サービスも兼ねれば一石二鳥ではないか。
求め、探せ、門を叩け。さらば道は開かれん
世の中には、偶然で片付けられないことがたまに起こる。
とある飲み会に参加したときのことだ。江戸の出版をテーマに小説を書こうと思っているという話をしたら、他の参加者の方が最近和書についての本を手掛けたそうで、橋口候之介氏の著書を薦めてくださった。その会話の中で、神保町の一誠堂書店という古典籍を扱う書店のことが挙がり、不思議と印象に残った。
翌日、黄表紙の実物を手に入れてみたくなり、古典籍を扱う古書店を検索したところ、トップに出てきたのは偶然にも一誠堂書店だった。Webサイトで店の場所を確認したら実は何度も行ったことのある店だった。神保町は10年ほど通勤したし、今でもよく行くのだが、恥ずかしながら古書店それぞれの店名までははっきりと知らなかったのだ。
さらに翌日。ひと月以上前から図書館で予約していた本が用意できたと連絡があり、さっそく借りてきた。いま話題の森岡督行著『荒野の古本屋〈就職しないで生きるには21〉』(晶文社刊)である。予約10人待ちからやっとのことで手にしたので、さっそく読んでみたのだが、これはさすがに驚いた。なんとこの著者が過去に一誠堂書店に勤めていたとあるではないか! 初めて耳にした古書店の名前が立て続けに飛び込んでくるという連日のこの偶然は、果たして本当に偶然なのだろうか?
そして数日後、ついに一誠堂書店で本物の黄表紙を目にすることができた。実物を知ることは、小説のディテールの強化にはとても有効である。私は一連の偶然の連続に感謝した。もっとも、一番安い『吉原細見』ですら数万円と高すぎて、買い上げるのは無理だったけれど。もし『ストラタジェム〜』で少し稼げたら、また行ってみよう。
後日、この現象に名前があることを知った。先述の筒井康隆の指南本に「セレンディピティ」という言葉があるが、それがまさにこの偶然の連続のことだったのである。何かに悩み、何かを追い求めているのならば、自ずと答えやヒントは次々に飛び込んでくるものだ。例えば、今これを読んでいるあなたが、ここまでの私の文章から偶然の出会いにより何かをつかんだのなら、それがまさにセレンディピティなのである。
さらなる仕込み。ピントを合わせる作業
第1章を書き上げたところで、いくつかの課題が浮き彫りになった。いわゆる「人称問題」である。原典の『ペナンブラ氏〜』は主人公クレイの視点による一人称小説である。一方、私の『和製ペナンブラ』のほうは、主人公の機能の一部をヒロインが分担してしまったために、三人称視点で書かざるを得なかった。もっと原典の雰囲気に近づけるには、やはりどうしても一人称に直さなければならない。しかし、後々のクライマックスで、どうしても主人公が知り得ないことを地の文で記述しなければならないことがわかっているので、一人称の採用に踏み切れないでいたのだ。
煮詰めて行くと、主人公とヒロインの関係性を物語の中でどこまで高めることができるかが焦点となっていることがわかった。出会ってからどのようなプロセスをたどれば、タツヤは恋川からの決定的な信頼を得ることができるのか? 読者が腑に落ちる理屈を組み上げることができなければ、この小説は失敗である。逆の見方をするのであれば、もし主人公とヒロインの関係性をそこまで書き上げることができれば、本作は青春小説としては成功である。私は一か八か、第1章をすべて一人称で書き直した。
第2章の仮記述が済んだところで、また悩んだ。アウトラインにあらすじや、主なセリフをだいたい書き込んで、ざっと読んでみたのだ。この段階では、ストーリーが主人公たちの行動と会話を時系列のまま順に追っていくだけで、これがなんだか単調でありきたりでつまらない。それと、二人の密室の出来事をそのまま書くのはあまりに下衆いではないか。私は、さて、どうしたものかと筆を休めた。
数日後、きっかけはうっかりすっかり忘れてしまったのだが、私は以前見た映画『メメント』を思い出していた。それをヒントに第2章の構成を改めた。まず、主人公の起床時を基準とし、それ以降を現在進行時間として書き、起床より前すなわち昨夜の出来事を発作的に思い出される回想としてかつ時間軸を逆行する形で挿入する構成に変更した。これにより、朝からの日常風景を淡々と語って読者を焦らしつつ主人公の日常を示し、同時に都合の良い密度で昨夜の出来事(非日常)を、遅延工作を行いながら読者に徐々に刷り込むという機能を得たわけである。実際にどんな感じになったかは、本編リリースをお待ちいただきたい。
江戸パートの記述方法も再考した。当初は江戸出版物を再現した戯作調で書いていたのだが、バンクハウスの仮設本棚で実験公開したところ、どうもこのパートが終わる辺りで閉じている人が多い。なるほど読みにくいページが続くので、この辺で面倒になるに違いない。しばらく悩んでいたが、こうも脱落者が多いのでは、ちっとも本編を読んでもらえないではないか。現代パート同様に平文で書き直し、ただし、こちらは三人称での文体にすることとした。江戸パートの挿絵をどうするかの悩みも無くなったので、これは一石二鳥である。
* * *
さて、最後に今後の予定をお知らせしておき「ます」。
第3回はいよいよ、この本のリリースに関しての話。最終回の予定です。小説の内容についての話題は今回まで。次は電子書籍の体裁を整える技術的な話題に終始するつもりであります。書き上げた原稿をどのような工程でリリースまで持ち込むのか、また、どのように広めるのか、同志諸君の参考になるような体験談をお送りできればと思っています。
今のところの計画ですが、この連載の最終回の公開と同日に、和製ペナンブラ『ストラタジェム;ニードレスリーフ』の「第1巻(仮称)」を皆さんにご覧いただこうと考えています。全8章のうちの第2章まで入れられるのではないかと思いますが、その辺りはこの第2回の反響次第、かもしれません。提供するプラットフォームは現時点ではお知らせできませんが、少なくともリフロー形式でのご用意まではしたいと思っています。もちろんこのあたりの工程も次回詳しくレポートいたします。
それから、第3回の公開と同時に、連載完結と小説リリースの記念を兼ねて『SideBooksユーザーミーティング』を開催します。開催要項は以下の通りなので、近郊お手隙の方はお立ち寄りいただければ幸いであります。
SideBooksユーザーミーティング #01
2014年10月31日(金)20:00〜 途中参加歓迎
会場:Bar『ネッスンドルマ』(新宿ゴールデン街)
http://www.goldengai.net/shop/c/17/
参加費:¥2,000(チャージ料+ワンドリンク込み)
内容:SideBooksおよび本屋横丁デモ
小説またはアプリに関する質疑応答
(内容は追加または変更になる可能性があります)
特典:『ストラタジェム;ニードレスリーフ』PDF版直接配布
※ AirDropで配布しますが、非対応の方には他の方法もご用意しています。
備考:SideBooksをインストールしてご参加下さい。
店内スペースに限りがございます。万が一満席の場合は、しばらくお待ちいただくこともあります(まあ、それはないと思いますが一応)
問い合わせ:info@honyoko.com
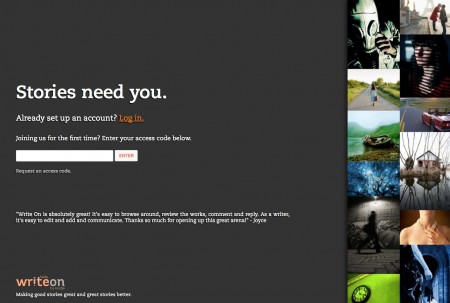
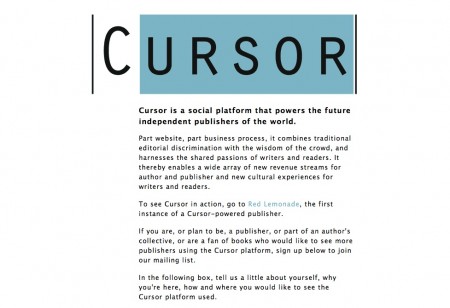


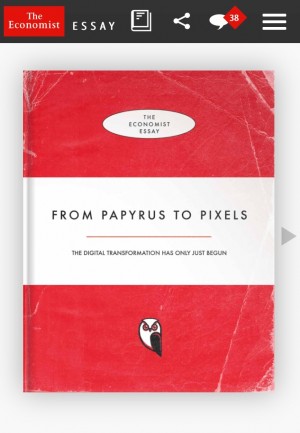
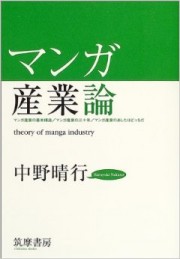 まず描き手は、デジタルという新しいおもちゃで何ができるのか? 何をしたいのか? を考えてみることだ。いや、考えなくてもいい、試してみることだ。失敗したらまたやり直せばいい。エンタテインメントはみんなそうやって形を成してきたのだ。運がよければなんとかなる。
まず描き手は、デジタルという新しいおもちゃで何ができるのか? 何をしたいのか? を考えてみることだ。いや、考えなくてもいい、試してみることだ。失敗したらまたやり直せばいい。エンタテインメントはみんなそうやって形を成してきたのだ。運がよければなんとかなる。