今年は6月に講談社の月刊マンガ誌「少年ライバル」、秋田書店の老舗青年コミック誌「プレイコミック」が休刊。9月には小学館の月刊マンガ誌「IKKI」、集英社の同じく「ジャンプ改」と大手出版社のマンガ誌で休刊が相次いでいる。いずれも販売部数的には苦戦してきたが、個性的な作品を数多く連載し、それらの単行本の売上で雑誌の赤字をカバーしてきた雑誌だ。単行本が雑誌の赤字をカバーしきれなくなった、とすれば、マンガ不況を象徴するような事態である。
2014年は紙から電子への転換点
紙のマンガ出版が苦しんでいる一方で、勢いがあるのが電子コミックだ。
2014年8月、NHN PlayArtが運営するスマートフォン向け無料コミック配信サービス「comico」の人気作品『ReLIFE』(作画・宵待草)の単行本がアース・スター エンタテイメントから発売され、たちまち10万部を超えて話題になった。電子コミックといえば、電子書籍端末やタブレット端末で読むことが一般に想定されているが、2013年秋にスタートした「comico」はスマートフォンに特化したサービスでオールカラー。小さな画面でも読みやすいように縦スクロールで読むスタイルになっているのが特長だ。作品はプロ契約をしたアマチュア作家による公式作品のほかに、読者投稿によるチャレンジ作品、ベストチャレンジ作品があって、『ReLIFE』は公式作品のひとつ。何をやってもダメな27歳の男が、1年間だけ高校生に戻るというファンタジック・コメディである。
これまでのマンガ作品は、人気雑誌に連載されたものが単行本化されるというパターンでないとなかなか売れない、とされてきた。雑誌で周知されることが前宣伝になっているわけだ。「comico」はアプリのダウンロード数300万(2014年6月現在)とは言いながら、紙とは全く別の世界で読まれている電子雑誌だ。その読者が、果たして紙の単行本を買うのかどうか? 7月に単行本発売のニュースを聞いたときから、私としては「あまり期待できないのではないか」と想像していたのだが、見事に杞憂に終わってしまったのである。
マンガ作品の供給源が、これまでの紙のマンガ雑誌から、電子雑誌に移っていく、ひとつの転換点になるのかもしれない。そんなことさえ考えさせられたのだ。
今後は、大手出版社も本気で電子コミックをどう展開していくのかを考えなくてはならなくなるだろう。もちろん各社とも取り組んで入るのだろうが、そのスピードを上げなければ生き残れない。まさに正念場なのである。
携帯コミックから離陸した電子コミック
「携帯電子端末でダウンロードしたマンガを読む」というスタイルの電子コミックが登場したのは、2003年11月。当時、凸版印刷の事業部門だったビットウェイ(現在の出版デジタル機構)がKDDI(au)の第3世代携帯電話向けにコミック配信をしたことにはじまる。フィーチャー・フォンの小さな液晶モニターに対応させるために、マンガのコマを切り分けて読ませるというビュワーも開発して、これが携帯コミックと呼ばれる新しい電子コミックのスタイルを生み出した。
2004年8月にはNTT西日本系のコンテンツ配信会社・NTTソルマーレが「コミックi」のサービスを、翌05年5月には「コミック・シーモア」のサービスを開始して、携帯電話で読む電子コミック、つまり携帯コミックが定着する。
携帯コミックは第3世代(3G)機の普及とパケット定額制によって読者を増やした。また、電話の利用料に乗せてコンテンツの利用料を徴収するキャリア課金は、配信元にとっての利便性を上げた。カード決済やプリペイドカードによる決済よりも、簡便で確実な売上回収ができたのである。
当時の携帯電話がほとんどの国民が持っている電子端末だったことも幸いした。わざわざ専用の端末を買わなくても、いつも使っているケータイでマンガが読めるのだから。
一般に、「日本の電子書籍はアメリカに比べて10年遅れている」と言われてきたが、コミックに関して言えば、アメリカに先んじていたことになる。
携帯コミックはマンガを読むスタイルも変えた。よく読まれているのはお馴染みの少年マンガや青年マンガ、少女マンガではなく、男同士の性愛を描くB.L.(ボーイズラブ)や少年少女の性愛を描くT.L.(ティーンズラブ)と呼ばれる作品。描き手は同人誌作家と呼ばれる人たち。読者は女性が多く、ダウンロードが集中するのは深夜12時から2時。書店に行かなくてもダウンロードして読める、ということが新たな読書スタイルにつながったのだ。
2005年に46億円だった携帯コミックの市場は2009年には513億円を突破する。
実を言うとこの頃、日本のメディアや研究者、評論家たちはこの現象に冷ややかだった。「これは電子書籍ではない」というのである。マンガに対して「文字よりも一段下のもの」という捉え方をするのは、知識層の伝統なのかもしれないが、それなりにマンガに理解を示している人たちも、読まれているのがB.L.やT.L.というジャンルの作品であることをあげて、アメリカの電子書籍市場とは別物である、としてきたのだ。
私もこの時期、イーブック・ジャパンのメルマガに連載しているコラム『まんがの「しくみ」』などで「B.L.やT.L.ばかりでは市場は頭打ちになる。ここからごく普通の人たちが読みたくなる作品を充実させることが必要になる」と書いている。「ほらごらんよ、同じ穴のムジナじゃないか」という声も聞こえそうだが、私は、携帯コミックを否定したのではない。ユーザーを広げよう。市場に普遍性を持たせる工夫をしよう、と言いたかっただけだ。
新メディアはスケベとともに
これは単なる俗説だが、日本でテレビが普及した最初のきっかけはマリリン・モンローが来日したから、という説がある。ジョー・ディマジオとともに日本にやってきた彼女が、記者会見のときにふと足を組みかえた。そのとき、スカートの中がテレビに映った、というのだ。それで世の男たちがあわててテレビを買いに走った、というのだが、どうだろう。一般に言われる皇太子御成婚と東京オリンピックがテレビの普及をうながしたというのが本当のところだろうが、モンロー説もなんとなく捨てがたい。
家庭用のビデオデッキの普及にはアダルトビデオが寄与したという話もある。販売店がお父さんのために1本プレゼントするサービスを始めたところ売れ行きが伸びたというのだが、その結果何台売れたのかというデータは残っていない。アメリカのCES(コンシューマー・エレクトリック・ショー)のお隣の会場では、アメリカ最大のポルノコンテンツの見本市(AVN)があるという話もある。行ったことはないが、これは本当らしい。
とどのつまり、スケベな衝動は人を新しいメディアに向かわせる力を持つということだろう。B.L.やT.L.がその役目を果たしたのであれば、そこをとっかかりにしてメディアをさらに普及させればいい。そのときには、エッチなコンテンツだけではだめで、エッチはエッチとして置いておいて、子どもたちや家族が楽しめるコンテンツを増やすことが大切だ。これがうまく行けば、メディアはテレビやビデオのように生活の一部となることができる。
何もアメリカの電子書籍市場ばかりがスタンダードというわけでもあるまいし、このままコンテンツの幅を広げながら日本独自の電子書籍市場が生まれればいい。マンガがその牽引車になればいい。あとにも書くが、マンガは文字と比較してデジタルとの親和性が高い。マンガで市場を拡大しておいて、文字もデジタルにふさわしいものは電子書籍で読むというのが自然な流れだと考えたのだ。
しかし、この目論見は、2011年度(2012年3月末)に崩れる。電子コミック市場が頭打ちになったのだ。ユーザーの携帯電話(フィーチャーフォン)からスマートフォンへのシフトが予想以上に早かったことが原因である。先にも書いたように、携帯電話は当時誰もが持っている携帯端末だった。小さなモニター画面だが本を読むことにも使える。コマ単位で切り分けられるマンガにはちょうど良い電子書籍端末だった。
紙と電子は10年以内に逆転
アップルの社の多機能のスマートフォン、iPhone 3Gが日本国内で発売されたのは、2008年6月である。しかし、キャリアがソフトバンク1社だったこともあって、それまでの携帯電話の市場は当面安泰だと考えられていた。携帯配信各社もスマートフォン向けを意識しながらも、携帯コミックが中心という姿勢を崩さなかった。携帯コミックは利益を生んでいたのだから、あえて乗り換えることはない。むしろ、積極的にiPhone向けのマンガ配信を進めたのは、イーブック・ジャパンなど、PC向けにマンガを配信してきた電子書店各社や既存の出版社だった。
携帯コミックの配信元の対応が遅れたのにはもう一つ理由がある。
携帯電話を動かしているOSはトロンプロジェクトから生まれた国産OS「ITRON」「μITRON」だ。ビュワーもデータもこれに合わせてつくられている。iPhoneでマンガを読むためには、iOSで動く新しいビュワーを開発し、データを加工しなくてはならない。それには人手と時間ががかかる。当時、日本の携帯コミックのデータづくりは中国と台湾の企業が請け負っていたが、ここが新しいデータの注文でパンクしてしまった。いきなり携帯コミックからスマホコミックに転換するなんてできない相談だったのだ。
こうして、津々浦々にまで普及していた携帯電話が、コミックを読むための電子書籍端末になっていたことが逆に足を引っ張る形になった。ユーザーの携帯からスマホへのシフトは配信元の予想を超える速さで進み、対応の遅れた電子コミックは一時売上を落とすことになった。
仕切り直しして、2012年度から再び電子コミック市場は拡大を始めた。携帯コミックは縮小したが、スマートフォンやタブレット端末向けの配信がそれ以上に拡大したからである。
インプレス総合研究所の「電子書籍ビジネス調査報告書2014」によれば、日本国内の電子書籍と電子雑誌をあわせた2013年度(2014年3月末まで)の市場規模は1000億円を超えた。そして、電子書籍市場のおよそ8割を占めているのが、電子コミック、つまりマンガである。
インプレス総研の報告書によれば、5年後の2018年には電子書籍の国内市場は3000億円に達するという。このままの比率でいくなら電子コミックは2400億円。現在のマンガ雑誌と単行本を合わせた市場規模、3669億円のおよそ3分の2にまで拡大する。マンガ雑誌、単行本(コミックス)の市場は毎年110億円程度の減少を続けているので、10年以内には紙と電子の逆転劇が起きる。
「まさかそんなバカなことが起きるはずがない」と現役のマンガ家やマンガ編集者、マンガファンは考えているかもしれない。が、「起きるかもしれない」という前提で対応を考えないと手遅れになる。
電子コミックの現状と課題
もちろん、新しい動きはいくつも出ている。その中には、成功しているものも多い。
2008年にスクエアエニックスが創刊した電子雑誌「ガンガンONLINE」は同社紙媒体からの移籍組やオリジナル作品を無料配信するWEBマガジンの先行組だが、『男子高校生の日常』(山内泰延)、『私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い!』(谷川ニコ)、『帰宅部活記録』(くろは)などがアニメ化されるなどしてヒット。単行本も売れている。
集英社の「となりのヤングジャンプ」、小学館の「裏サンデー」など、大手出版社もWEBマガジンを展開しており、「となりのヤングジャンプ」からは『ワンパンマン』(ONE・原作、村田雄介・画)のようなヒット作も出ているが、「となり」「裏」というタイトルからもわかるように、正面切って展開するまでには至っていない。
むしろ熱心なのは最初に紹介した「comico」のようなコンテンツ配信のITベンチャー企業だ。
通販やソーシャルゲーム「モバゲー」で知られるIT大手のDeNAは、2013年8月に小学館系の小学館クリエイティブと提携してマンガアプリ雑誌「少年エッジスタ」の有料配信を開始した。これは、2010年にNTTドコモとの合弁でスタートさせた小説、コミックの投稿サイト「E★エブリスタ」の人気ライトノベルをコミカライズして配信するもの。また、12月には、人気マンガ家の新作を無料アプリで読める「マンガボックス」をスタートさせて、年末には大々的なTVコマーシャルも行った。
「comico」や「少年エッジスタ」は無名の描き手を積極的に採用していて、マンガ家を目指す若い人達にとっては、チャンスが増えることが期待できるなど、楽しみな動きではある。『ReLIFE』の宵待草のような新しい才能も生まれるかも知れない。
しかし、これらの無料配信型で気になるのは、マネタイズの段階では従来の出版市場に頼らざるを得ない、という点だ。有料配信の「少年エッジスタ」も含めて、いずれも単行本化で資金が回収される仕組みになっている。せっかく新しい媒体を利用するのに、紙に印刷される場合の制約に縛られてはおもしろくない。
電子コミックとして完結する方法はないのだろうか? きっとあるはずだ。
一方で、マンガ家の中にも積極的に電子にコミットして、シュリンクする紙の出版からの脱却を図ろうという動きがある。
ひとつは、アマゾンが提供するKindle Direct Publishing(KDP)というセルフパブリッシング・サービスを利用して、自ら出版を行うタイプ。出版社の中抜きをなくすことが可能になるこの仕組みでは、鈴木みそが成功例だ。新作、旧作を含めて積極的にKDPでの電子化を行った鈴木は、2013年だけで1000万円を稼いだことをブログに公表している。
赤松健は、絶版マンガを広告とバンドルして無料配信する「Jコミ」(現在は「絶版マンガ図書館」と改称)の正式版を2011年4月にスタートしている。
ただ、ビジネスセンスを持ったマンガ家がそうそういるわけではあるまい。むしろ、「お金のことはわからない。そんな時間があれば作品を描きたい」というマンガ家が多いのではないか。全員が、鈴木や赤松のように成功するという保証はない。
また、紙のマンガをデジタル化して配信するというスタイルでは、やはり紙の制約に縛られることになる。
次のステップへの進化を阻む大きな壁
そもそも、今のように紙のマンガ雑誌やコミックをデジタル化して配信するというスタイルに依拠している限り、決してバラ色の未来が待っているわけではない。紙のマンガ市場が滅んでしまえば、配信するべきコンテンツがなくなってしまうからだ。
先にも書いたように「comico」のようなオリジナルの電子コミックも増えているが、これらの多くは無料で配信したものを紙の単行本にまとめて、これを販売して利益を上げる仕組みになっている。つまり、このまま紙のマンガが滅んでしまえば、電子コミックだって共倒れになる可能性が高い。
ここまではまあまあ順調だったが、次のステップに進むにはひとつ大きな壁を乗り越えなくてはならない。2015年は、未来のマンガを真面目に考える年になる。いや、考えなければならない年になるはずだ。
さて、ここでどうしても言いたいことが二つある。ひとつは「電子コミックで儲ける」のを目的にするのはやめましょう、ということだ。「儲けるな」というのではない。儲けるのは大いに結構。儲からないとビジネスが長続きしない。
だが、儲けるのが目的であっては困る。KDPをつかったセルフパブリッシングで何百万儲けたとか、出版の市場規模が減った分を電子書籍で埋めるためにはどうすればいいか、といった議論ばかりでは未来は拓けない。
もうひとつは、既存の本やマンガのイメージをとりあえず忘れよう、ということだ。
「本というのはめくるものである。だからめくりがない電子コミックはダメ」とか「今あるマンガ表現から外れるとマンガがマンガでなくなる」と言われたのでは、新しいものは生まれない。結果として、今の本やマンガの姿に還ってくるのは別に問題ないのだけど、そこに縛られたくはない。
本もマンガも長い歴史の中で、生まれ、洗練されてきたものだ。縛られないようにするのは難しい。が、長い歴史の中では何度も変革を経験して今日に至っている。既成概念をやぶって新しいものをつくるのは難しい。手塚治虫だって、戦後まもない出版界に「漫画でも小説でもない」ストーリーマンガを持ち込んだときには、ずいぶん非難を受けている。それを乗り越えたから手塚のマンガは今なお、日本マンガに大きな影響を残している。
「劇画」もそうだった。1950年代半ばに登場した頃は、「残酷だ」「絵が汚い」「荒唐無稽」とさんざん叩かれたものだ。しかし、マンガの多様性を生み出す基盤を作ったのが劇画だ。そして現在、劇画の名付け親でもある辰巳ヨシヒロは、世界から最も注目されるマンガ家のひとりになった。
手塚たちの成功は、既成概念にとらわれずに、逆にそれを壊そうとしたところから生まれている。
マンガとデジタルの親和性
では、電子コミックという新しい表現の確立に向けて、私たちはどうすればいいのか。
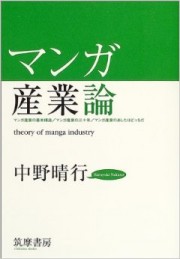 まず描き手は、デジタルという新しいおもちゃで何ができるのか? 何をしたいのか? を考えてみることだ。いや、考えなくてもいい、試してみることだ。失敗したらまたやり直せばいい。エンタテインメントはみんなそうやって形を成してきたのだ。運がよければなんとかなる。『マンガ産業論』の著者がこんなことを言うのはまずいのかもしれないが、一発で成功する方程式などない。
まず描き手は、デジタルという新しいおもちゃで何ができるのか? 何をしたいのか? を考えてみることだ。いや、考えなくてもいい、試してみることだ。失敗したらまたやり直せばいい。エンタテインメントはみんなそうやって形を成してきたのだ。運がよければなんとかなる。『マンガ産業論』の著者がこんなことを言うのはまずいのかもしれないが、一発で成功する方程式などない。
次はそれをみんなで楽しむ。マンガ家も楽しい。彼をサポートする人たちも楽しい。もちろん読み手も楽しい。
そこから生まれるものは、もはや文学だとか、マンガだとか、映像だとか、ゲームだとか、そういうものをひっくるめたものになるのかもしれない。手塚治虫が「小説でも漫画でもない」ものからストーリーマンガを生み出したように。
それは鵺(ぬえ)のようなものかもしれない。でも、いずれははっきりした形になるはずだ。そもそも、先にも書いたように、絵で読ませる表現手法はモニターで読むという今の電子端末にぴったりの表現手法なのだ。どんな端末を使うにしても文字を読む場合にはストレスが大きい。文字を読むために、本という形は究極の進化だったろう。モニターで読むならコンテンツ側が環境に合わせて進化しなくてはおかしい。見ただけである程度の意味が伝わるマンガは、モニターでも読みやすい。電子書籍の8割をマンガが占めているのは、活字の作家やライターたちが消極的だからではない。マンガとデジタルに親和性があるからだ。
一方で、絵で表現するマンガは2次元に閉じ込められることで大変な不自由を味わっている。動けない。音を出せない。そして、これは日本だけかもしれないが、色がない。集中線やオノマトペはこの不自由を凌ぐために開発された苦肉の表現だ。
つくり手が表現したいものを自由に表現できること。それが喜びになること。そして、できあがったものが読者(そのときには読者とは呼ばないかもしれないが)が喜ぶ。感動し、励まされたりもする。そういうものがこの鵺(ぬえ)の正体になる。
この話をすると、結構な数の人が「それはマンガじゃなくて、アニメかゲームじゃないですか」と言う。そうではない、これは「未来のマンガ」だ。
未来のマンガは当然のことながら電子書籍端末でなければ読めない。紙の本にして収益を上げることはできなくなるかもしれないが、電子コミックに素晴らしい作品があれば、読むためには端末を手に入れるしかない。昭和30年代、わたしが小学生だった頃に、オリンピックを見るためにテレビを買ったようなものである。こうなればしめたもの。電子コミックがビジネスとして成り立つのか、という心配もなくなる。消費者がほしいものを売ってお金を得ていく、という最も基本的なビジネスが成立する基盤ができているのだから。
実を言えば、携帯コミックが成功したのも、「欲しいものを消費者に」ができていたからなのだ。
表現と技術の革新が黒船を破るとき
表現の革新からは、技術の革新も生まれる。つくり手や読者から「こういうことをしたい」「こういうものを読みたい」という声が出れば、端末やソフトウェア(アプリ)はそれに応えるように、創意工夫されて改良されていく。携帯端末やデジタルカメラの進化を見ればよくわかる。
いま日本の電子書籍市場はアマゾンのキンドルストアや、アップルストアのような黒船に覇権を奪われようとしている。しかし、日本の電子コミック表現が進化して、技術も進化した段階で、キンドルは古びた電子書籍になってしまう。紙の本の版面をデジタル化しただけの電子書籍なんて、もはや過去のものになってしまうのだ。
物量作戦で来る相手に正面から向かっていくのは日本の戦い方ではない。相手にはできないことを積み重ねて、最後に勝利を得るのが日本らしいやりかただ。それは、アメリカ大リーグに革命を起こした、イチローの戦法でもある。バットコントロールで野手のいない場所にボールを運び、足で塁を稼いでいくイチローは、パワーヒッターぞろいのアメリカの野球を変えた。
私たちが目指す電子コミックもイチローのように小ワザを積み上げることで、黒船を破ることができる。
もちろん、紙の本も残る。文字ものもそうだろうし、マンガも紙の方が読みやすい作品はたくさんある。「紙の本はレガシーなものになる」という人もいるが、紙と電子がそれぞれ別の媒体になっていくからには、補完関係になるのが自然だ。
これは夢物語なのだろうか。私は夢だとは考えていない。それよりも、ここに書いたような未来が現実にならないのであれば、電子コミックも時代の徒花に終わる、と危惧するのである。
■関連記事
・「日の丸プラットフォーム」の本質を見誤るな
・マンガの「館」を訪ねる[後編]
・マンガの「館」を訪ねる[前編]
・日本漫画の国際化を翻訳家の立場から考える
・日本産アニメ・マンガの違法流通について考える
執筆者紹介
- マンガ研究者。和歌山大学経済学部卒業後、銀行勤務を経て編集プロダクションを設立。1993年に『手塚治虫と路地裏のマンガたち』(筑摩書房)で単行本デビュー。『マンガ産業論』(同)で日本出版学会賞奨励賞、日本児童文学学会奨励賞を受賞。『謎のマンガ家・酒井七馬伝』(同)で日本漫画家協会特別賞を受賞。2014年、日本漫画家協会参与に着任。
最近投稿された記事
- 2019.04.16ネオ・マンガ産業論第8回 中国に見る新しいマンガ・コンテンツの波
- 2018.02.23ネオ・マンガ産業論第7回 「紙vs電子」はWin, Lose or Draw
- 2017.11.21ネオ・マンガ産業論第6回 電子コミック時代はマンガ・エージェントが活躍する!?
- 2017.10.11ネオ・マンガ産業論第5回 デジタルで変わるマンガ家の仕事

