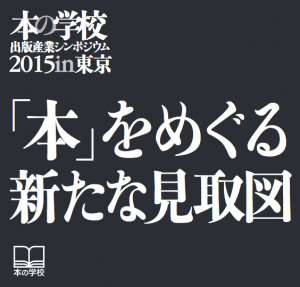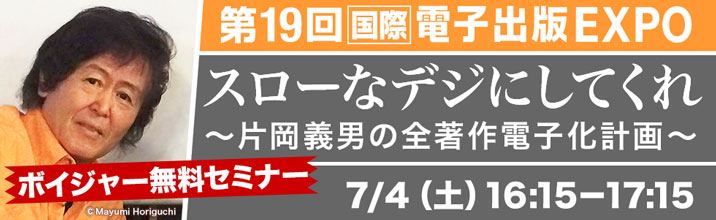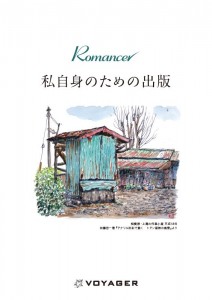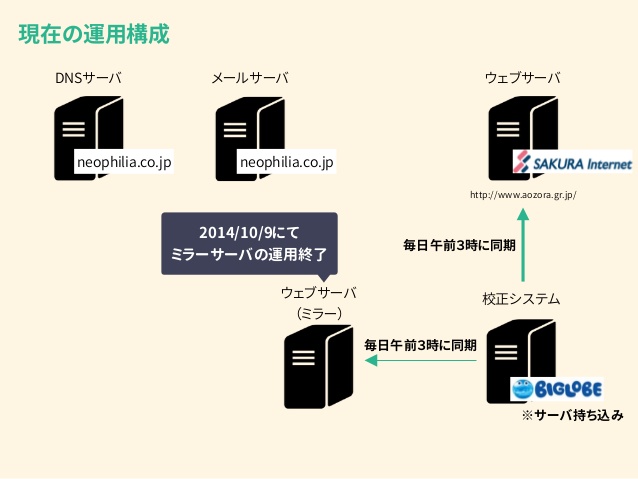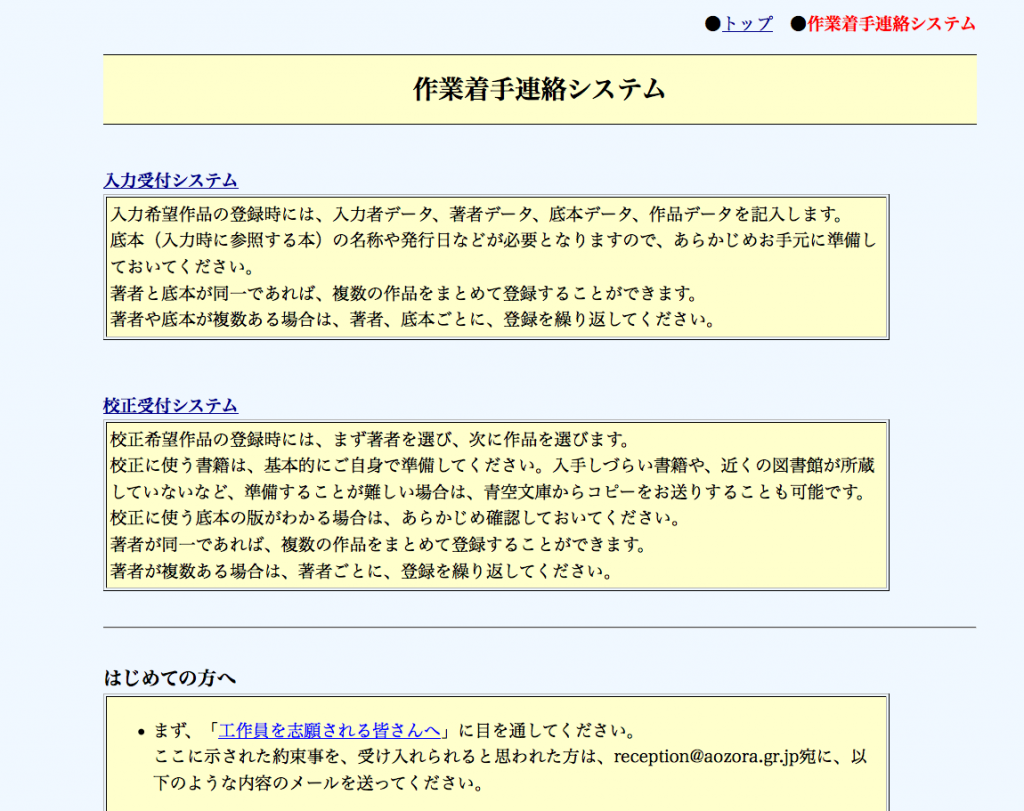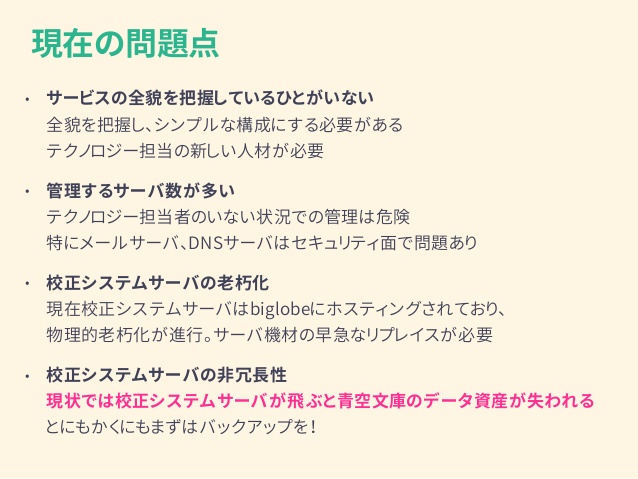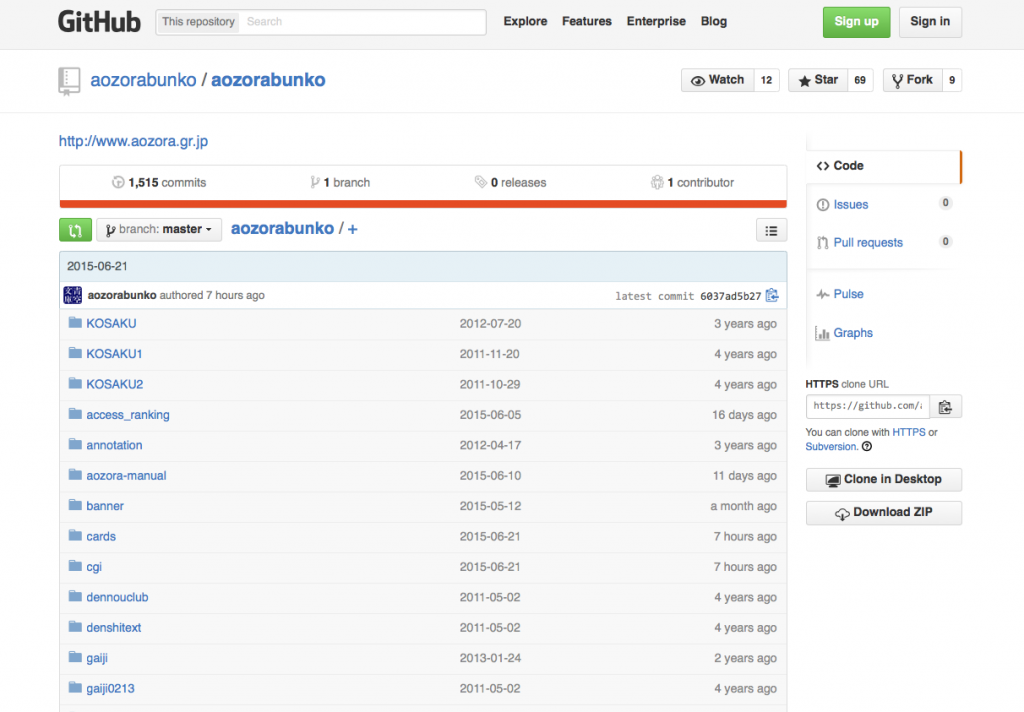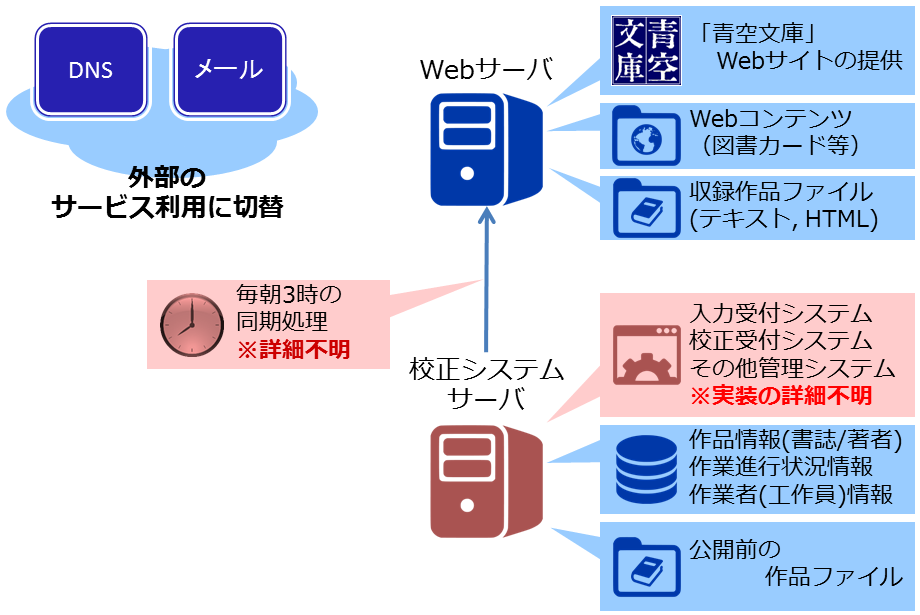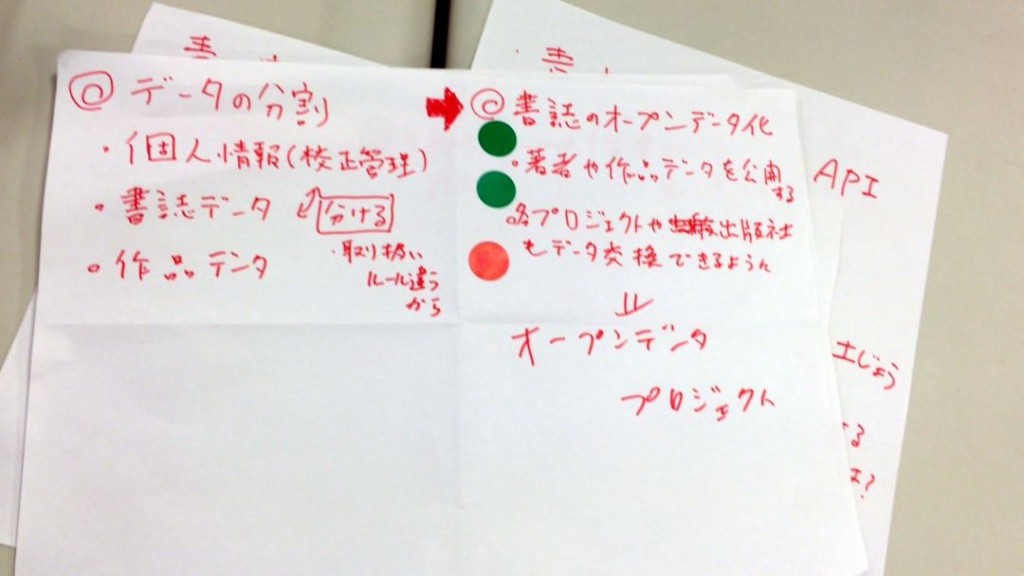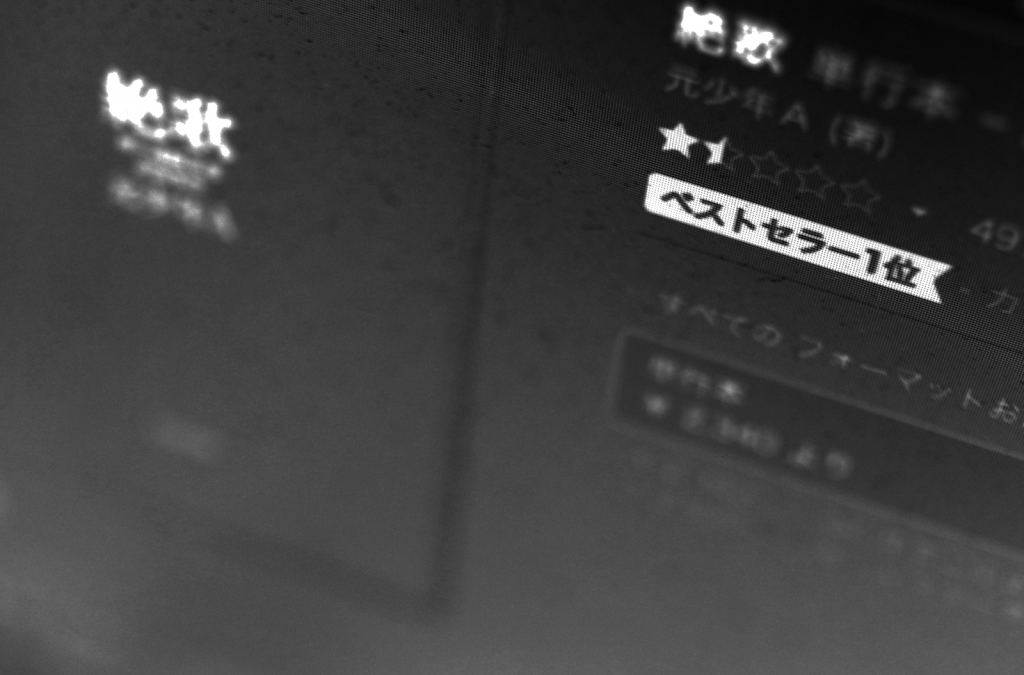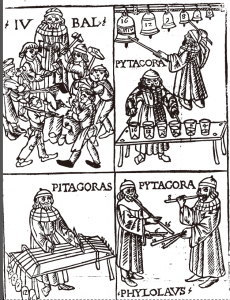※本記事は公益社団法人日本文藝家協会が発行する「文藝家協会ニュース」特別号(2015年4月30日発行)に掲載された、今年2月2日に紀伊国屋サザンシアターで行われた「シンポジウム〈公共図書館はほんとうに図書館の敵?〉」の記録を転載したものです。(編集部)
シンポジウム〈公共図書館はほんとうに本の敵?〉
公共図書館・書店・作家・出版社が共生する「活字文化」の未来を考える

日時=2015年2月2日(月) 18時30分〜20時30分
会場=紀伊國屋サザンシアター〈シンポジウム〉
協力=「21世紀の出版契約を考える会」有志
登壇者:
佐藤 優〈作家・元外務省主任分析官〉
林 真理子〈作家・日本文藝家協会常務理事〉
根本 彰〈東京大学大学院教育学研究科教授〉
猪谷千香 〈ジャーナリスト〉
菊池明郎〈筑摩書房相談役〉
石井 昂〈新潮社常務取締役〉
進行=植村八潮〈専修大学文学部教授〉
写真:高橋祐功
◆ ◆ ◆
現在、日本の出版産業と紙の本、それを書く作家たちは完全に未知の領域に入っております。この19年間でほぼ1兆円の売り上げが削り取られて消滅し、電子書籍は、われわれが当初想定した3分の1程度の伸びしか見せません。世界で最も長い歴史を誇る、寛政年間から続く日本の出版産業は、いま非常な危機に陥っています。
以前は、「図書館は版元の敵ではないか」という議論がなされたこともありました。だがすでにそういう状況ではなく、図書館も苦しい。この20年で図書館の資料費は約7割5分くらいに落ち、専門職としての図書館員は7割程度に減っています。図書館も同様に危機にあると私たちは考えます。
確かに地域の結節点たろうとする新しい図書館も各地にできてはおりますが、まだ全体の1%程度にしか達していない。その根本原因は社会のネット化にあると考えられます。情報はタダである。文学も情報だとすると、タダでないと誰も読まない。さらに安倍首相がいうような経済成長は現実として見込めない中で、青年たちの貧乏が後押ししています。
斜陽産業の出版とその書き手たちは新たなフェーズに入りながら、共に途方にくれています。そのような時代の空気があって、図書館と版元と書き手はどう共存できるか、あるいは理想の図書館とはどのようなものか、それを考え議論する機会をここにつくりました。
◆ ◆ ◆
植村 最初に私から事実確認ということで話したいと思います。
まず出版市場の推移。一般に出版産業というと売り上げだけを見ますが、雑誌広告の収入減少も厳しいです。雑誌の販売部数の減少は顕著です。書籍も微減ですが、何とかなるかというと、決してそうではありません。
もう一つ。書籍の販売冊数と図書館の貸出し冊数。2009年ころに図書館の貸出し冊数がうなぎ上りになり販売冊数を超えてしまったと、よく言われますが、80年代に図書館数が増えて、貸出し件数が3、4倍になったのです。実は読書離れはどこにも起こってない。これに新古書店の販売冊数を足すと、本はますます読まれている。これは知っておきたい。
大学生協が調べた第49回学生生活実態調査によると、なんと1日の読書時間がゼロ、1か月に1冊も本を読まない人が半数近くになりつつある。ただ、学生の勉強時間は増えている。どういうことかというと、一つには大学に於いて、Eラーンニングやデジタル教材が確実に増え、デジタルで学ぶ時間が増えている。
雑誌と書籍の関係を言いました。日本の出版界は非常に特徴があります。海外ではブックストアは書籍しか売らない。雑誌や漫画を書店で売るのが日本型書店の特徴です。雑誌や漫画の利益が書店経営を支え、取次流通のトラックを動かしている。日本の本がこれだけ安いのは漫画と雑誌のおかげだった。漫画と雑誌が売れないことが、書籍に危機をもたらしている。
文化産業に共通することは文化事業体と営利事業体の二重構造をもつことです。流行作家もかつては新人だった。なかなか本が売れない新人たちが流行作家になるまでのプロセスを支えているのは大ベストセラー、中ベストセラーです。漫画においては「メジャーな漫画雑誌」とそのマンガの「二次創作のあるコミケ」が共存しています。寡作な作家が大学で教えたり、講演したりしながら、書いている。対談やエッセイを手掛ける一方で、「ライフワーク」に取り組み、誰でもが感動するような作品を書くには長い年月がかかる。出版社は、文庫にして売っているが、赤字の文芸雑誌も続けています。文化産業にかかわるすべての分野に二重構造があります。それを巧みに作り上げたのが日本の出版産業です。世界で最も素晴らしい産業システムだと思っています。それが破綻しそうになっているのではないでしょうか。
国会図書館に年間に納品される約11万冊本のうちの8万冊は出版社により産み出され、残り3万冊は自費出版と行政資料です。私たちが本を買うことだけで、大半の本は産みだされ、出版社と書店は経営されています。取次流通は、この8万冊の本と雑誌を運ぶ売上げでもっています。そのお金の中のいくばくかが、作家、ライターたちに印税や原稿料という形で回っています。国家のお金は入ってない。これは大事なことです。私たちが本を買って支えなければ、言論表現活動は成り立たないのです。言語表現はただ書くだけ言うだけでは読み手に届きません。流通のプロセスをすべて保障することでしか言語表現の自由は成り立たない。それは私たちが、買う本でしか成立しない。そこに国家のお金を入れたらどうなるか。かつての中国では、国営新華書店電子書籍化本は手に入らず、国営放送局はどこでも国家のプロパガンダ機関となっています。
では図書館は何だろうか。それは憲法によって守られている私たちの言論表現の自由の中に含まれている知る権利。知る権利は国家の義務として国家が提供しなければいけない。私たちが誰でも平等にあらゆる知識にたどり着く機関が図書館です。
この両輪が成立していたのが今までで、それがどうやら破綻しつつある。
皆さん、初めて自分のお金で自分の意志で買った本を覚えていらっしゃいますか。私はよく覚えています、ヘミングウエイの『老人と海』です、中学一年の時でした。新潮文庫で90円。なぜ言えるかというと、今でも持っているからです。父がとても本好きで、家に本はいっぱいあるけれど明治期以降の日本文学しかない。全集もあるけれど、海外文学がなかった。中学で国語の先生が海外文学の面白さを教えてくれた最初が『老人と海』でした。読みたくなって帰りに書店によったら置いてある。手にして悩んだけど買った。そしたらすごく面白い。なぜ悩んだか。ひょっとすると父にとって、海外文学は決して家に置いてはいけない、とてつもないトラウマとか、何かがあるんじゃないかと。しかしすごく面白い本だから父に話したくて、ちょっとドキドキしながら、こわごわと「僕これ買ったんだ」と話した。すると、父が本当に思いもかけずに喜んで、「昔は文学とか芸術は貴族とか特権的な階級の上の人たちのもので、彼らによって支えられていた。でも今は、われわれ全員が支える時代だ。本を買うだけでいい。この本を買うことで印税が作家に回り、みんなが少しずつ払うことで作家が新しい作品を生み出す。つまり我々みんなが芸術のパトロンの時代になった。いい時代だろう。だから、八潮ね、お前は今日から作家のパトロンになったんだよ」と本当に嬉しそうに言ってくれました。その誇らしい想いは今でも覚えています。そういうシステムが連綿と続いています。それを今もう一回皆さん方と考えたい。
私と図書館
石井 図書館の敵のように言われていますが、私は図書館を敵と思ったことは一回もありません。2003年に「公共図書館の貸出し調査」をしました。運動自体はあまり進んでおらず、今に至るという感じです。2011年に作家の樋口毅宏さんが『雑司ヶ谷R.I.P.』の奥付に「貸出しを6か月待ってください」と書きました。高崎市立図書館はとても反応してくださいましたが、結局、一石を投じたということで終わってしまいました。
本が売れないのは図書館のせいだなどとは思っていません。本が増刷できないのが困るという話です。増刷ができないと出版社は潰れてしまうメカニズムを、ご説明したいと思います。
根本 図書館にかかわって40年です。今は教育学研究科に所属しています。その前には大学院終了後、国立図書館情報大学の助手になり、その後、東京大学で図書館情報学を担当しています。
どちらかというと、公共図書館に対しては貸出し路線を非難してきた立場ですが、文芸家、出版社の方からすれば図書館の味方と見えるでしょう。ちょうど中間にいるので、どちらの側も見える位置にいると自認しています。本日は、最終的にはその二つは必ずしも矛盾しないという問題提起をさせていただきたいと思っています。
林 私は最近、こういうシンポジウムや対談にお呼びいただくことが多いです。今日は佐藤さんもいらっしゃいますが、作家は内心出たくないと思います。非常に売れている作家の方は、「お前ら、さんざんいい思いをしてきて、もっと、これ以上金が欲しいのか」と言われることが目に見えているからです。そして売れない作家の方々は、割と消極的で売れないことがわかっていますから、なんとなくおとなしくなってしまうのが現状ではないかと思います。私は田舎の小さな本屋の娘です。そこで育って食べさせてもらって大学を出してもらい、自分の職業と出版文化に本当に恩義があって、どんなところにでも馳せ参じようと思っております。
私も図書館を敵とは本当に思ったことはなく、若い時には豊島区立図書館に日参いたしました。子どもが生まれてから、地域の図書館で2人で有意義な時間を過ごしたことは大切な思い出となっておりますし、今日も話に出ると思いますが、武雄市図書館も、私はいい記憶がいっぱいあります。私は本屋の娘として、そして今、これで食べさせてもらっている作家のひとりとして、お互いに今、乗っている難破船の中でいがみ合うのではなく、もう少しいい潮に船が乗るように、皆で手を携えて頑張りたいと思います。
佐藤 「公共図書館はほんとうに本の敵?」という質問に対する私の答えは、「そうではない、味方だ」になります。我々がいま対立しているのは疑似問題にとらわれているからだと思います。本当の敵は、この20年間世界を席巻している自由主義、最近顕著になった反知性主義です。要するに、客観性、実証性を軽視もしくは無視して、自分が理解したいように世の中を理解するという態度から、自分の首を絞めるようなことをしている。
公共図書館に関しては、大学図書館を含めて本当にお世話になりました。まず同志社大学神学部図書館、ソビエト社会連邦共和国国立レーニン図書館、国立国会図書館そして外務省図書館、これらなくしては、今の私はなかったです。ちなみに私はこの12年、図書館には一歩も足を踏み入れておりません。一番行き慣れている国会図書館に行った場合、外務省の元同僚、会いたくない国会議員に会う可能性が高いのでいかない。その代わり国会図書館のデジタルライブラリーを見ない日は1日もありません。ですから図書館との付き合いは、バーチャルなところで、現在でも、深いです。
猪谷 私は図書館の専門家でも司書の資格があるわけでもありませんが、去年の1月にちくま新書で『つながる図書館』という本を出させていただきました。取り上げたのは公共図書館が主ですが、この10年間で全国に貸出し中心の図書館ではなく違った機能を持つ図書館が増えてきたということをレポートしました。元々新聞記者で、国立国会図書館、都立中央図書館などを仕事で使ってきたユーザーでしたので、そういった立場から図書館を取材しています。この本を書いたきっかけは、東日本大震災で多くの方の命が奪われたと同時に、被災地の図書館もかなりの被害があったことでした。職員の方が全員落命し図書館が壊滅したところもありました。自分が日常的に使っている図書館が、あんなふうに災害で失われるというのを報道で見てショックを受けまして、自分と図書館、皆にとっての図書館とはなんだろうかと考えたいと思っていました。図書館の方に伺うと、自治体の予算が減るなど、図書館はいま厳しい状況に置かれています。ですので、やはり出版業界や書店の方々と手を取り合って、地域に本の文化を根付かせていこうという図書館も増えてきている感じがいたします。
菊池 私はだいたい25年間、日本書籍出版協会図書館委員会委員として日本図書館協会の方と交流してきました。全国各地の図書館を見てきて、20数年前と比べると、ある程度は図書館と出版社との相互理解が進んできていると認識しています。図書館にも、もちろん本を買ってもらっている出版社ですが、言うべきことは出版社の立場として言わなくてはいけない。矢面に立つのは嫌だなと思いながらも、再販制度についても委員をしておりましたので、図書館の皆さんとよく議論して、図書館は必ずしも定価では納入されてはいないのだけれど、あまり書店さんが困るような割引は求めないでほしい、また再販制度によって日本の出版文化は守られているのだという話もしました。出版流通に図書館の方がどういう不満を持っていらっしゃるのか、その説明をして、これからどう改善しようとしているのかという話をしてきました。出版社としては、新潮社は文芸を主体とする大きな出版社ですが、筑摩書房は専門書の出版社と大手出版社のちょうど真ん中で両方の話を聞かされてきました。
図書館との交流の経験と、出版社としてのそういう立場で話題を提供して本日の議論に多少の足しになればと思います。
なぜ重版が必要か
植村 菊池さんが言われたように本は大変多様で、専門書のように図書館があったからこそ支えられている分野と、エンターテインメント、文芸の分野がある。そこを整理して進めなくてはならないと思います。冒頭で石井さんがおっしゃった、なぜ重版が必要かを切り口にして始めたいと思います。
石井 敵だとは思っていませんが、どうしても分かっていただきたいことがあります。この10年間で図書館数は423館増えて全国で3248館に、貸出し数も7億1149万冊になりました。すでに書籍の販売部数を超えている中で、何が問題かというと、最初の頃はベストセラーの複本が多いことでした。たしかNHKテレビの「クローズアップ現代」で、図書館が『ハリー・ポッター』を100冊入れていることが問題になり、そのあとすぐに、町田図書館が「それは事実と違う。上巻が50冊、下巻が50冊である」とお書きになった。その時代から見ると、複本の数は減りました。実は、いわゆるベストセラーの複本だけが問題なのではない。
出版社がどうやって生きているのかを、意外にご存じない方が多いような気がします。本に定価を付ける時は9割売れてトントンにします。今は単行本の返本率が40%を超えていますから、ほとんどの本が赤字です。初版は書店さんに見本を配っているようなものです。新潮社の校閲は伝統もあり、20年で一人前という本当のプロの校閲者が50人以上、もちろんほかにも大勢の社外校正者がいます。校閲の経費で年間8億以上です。それだけ高品質の本を出さなければいけない。文芸雑誌「小説新潮」「新潮」は、もちろん新しい書き手を発掘する重要な畑ですが、それぞれ数億ずつの赤字が出ている。単行本も赤字がほとんどです。ではなぜ経営できているのでしょう。私も不思議な感じがしますが、なぜかというと唯一、増刷できる本があるからです。出版社の存立が増刷ではかられている。いわゆるベストセラーで爆発的に売れる本よりも、中堅の作家、失礼な言い方かもしれませんが、そこそこ増刷をしてくれる本で新潮社のような文芸出版社は成り立っています。発売から8か月間の出庫と返本のデータがあります。直木賞をとって今人気の女流作家の方の初版は2万5000部です。今、2万5000部の初版は大変な数字です。それが1か月でほぼ2万部売れて、そのあと、パタッと止まってしまう。2か月目が約2000部ちょっと。そのあとは700台、4か月目からは返本が増えてマイナスになります。結局増刷はかからない。2、3年前では考えられなかった状況です。行き着くのは図書館でベストリーダー上位の本が図書館で貸し出され、今、例に挙げた方の本は2700冊くらいが図書館に入っていて、もちろん推定ですが、フル回転すると8か月で4万2000部以上が読まれている。なおかつ貸出し数の見込みは一館で800〜900が予約に入っている。増刷できるはずの本が増刷できないのは、やはり図書館の無料貸出しに問題があるのではないかと思っています。
もう一つ頭の痛いのは、びっくりするくらいのサービスです。民営化した図書館では長い時間開いている。ここ10年くらいで、文庫、新書を含めて本はタダで読むものという認識がかなり進んできたように思います。「とても立派な着物を着た銀座の老舗の奥様がパーティの席で、先生の本は全部読んでいる、と言われたので、それはどうもありがとうございます、と頭を下げたら、でも待ち時間が長くて、とおっしゃる。お金持ちの方でも、本はタダで読むのだとびっくりした」とある女性作家が言ってました。
後はネットで海賊版を読む。村上春樹の『1Q84』は、アップストアで230円で売られている。タダではないけれど、ほとんどタダ同然。本はお金を出して買うものではないという常識になっている。ネットの中で「ええっ、本ってお金出して買うの?」というような書き込みがあるのを見ると、やはり何とかしなければと思います。
これを言ったら、図書館東京大会で私は非難されましたが、お願いが二つあります。せめて、増刷になりそうな本は貸出しを6か月間猶予してほしい。増刷を何とか考えていただきたい。本は書店に行ってお金を出して買っていただきたい。
貸出しをするなとは言いませんが、あまりにも便利になって、スマホで図書館の本が借りられる。猪谷さんの本にもある「お客様目線」に寄りすぎて利用者の利便性がちょっと行き過ぎてはいないか。林さんが言われたように、相当水が入って沈没しそうになっている状況の中で、図書館は敵ではなく味方になっていただきたいので、他にもブックオフとかアマゾンなどの問題はいろいろありますが、せめて図書館だけは船を沈めないように、協力してなんとか知恵を出していただきたいと思います。
植村 新潮社の出版しているような文芸エンターテインメント領域に関しては、ある種限定的に貸出し猶予をしてほしいという提案だったと思います。出版社にはいろいろある。教養、専門書、書籍出版社の筑摩書房の菊池さん、お願いします。
菊池 複本問題は未解決ですが、ひと頃と比べたら図書館が出版社の事情あるいは作家の抱えている問題を理解してくださったのかなと思えます。
文京区立図書館ベストリーダー、ベストオーダーの資料があります。オーダーの資料では一館あたりでは2、3冊です。複本数33冊ですが、本館と分館11館を合わせた冊数です。貸出し期間は一回につき2週間ですが、必ずしもフル回転するわけではないと図書館の方は言われます。そのことも勘案しながら、今の本の買われ方、置かれ方、利用のされ方をいろいろ検討する必要があると思います。
貸出し猶予期間の問題では、そういう事情を抱えているということが本によってはあるでしょう。著者と出版社が合意して提案した問題を図書館がどう受け止めるかという問題があります。発行部数の少ない専門書、ひと頃は初刷り3000部だった本がもはや2000部しか刷れない。2000部の教養書を定価3800円で作ると、4割から5割は大学図書館と公共図書館の購入によって支えられている。そして購入された書籍は利用者がすぐに読みたいと思うはずで、図書館で購入した本を館内で閲覧しようと借り出そうと一向に構わない。その中で、「やっぱりこの本は手元に置きたい」と買ってくれる人がときどきいる。そういう効果が図書館にはあるので、中小の出版社はあえて6か月間の貸出し猶予を求めることはしないでしょう。むしろ図書館でも読んでもらったほうがいいと思う著者や出版社が多いと思います。したがって石井さんのおっしゃる6か月間の貸出し猶予については、そのことを理解した図書館が、対応していただければいいのかなと思います。
ともかく図書館とどう付き合うかというときに、新古書店では直近で1年間に3億冊近く売れている実情も合わせて考える必要があると思います。読書環境を考えると、本にお金を出せる人が少し減ってきているのかなという気がします。新古書店なら買う、あるいは活字はスマホで読めばいいと多くの若者は考えているように見えます。そういうもろもろのことに対して、出版物を提供している出版社と著者がだんだん細って行ったらどうなるのかを考えていただきたいと、同じ出版社としては強く思っているので、そのあたりを丹念に見ていただきたいのです。
筑摩書房でも重版がなかなかできずに苦労していますが、新古書店にすらなかなか置いてもらえないのが実態です。中小出版社は非常に苦しい所に追い込まれています。出版文化をこれから、どう守っていくのかという観点から会場の皆様にはお考えいただきたいと思っています。
石井 複本は今でももちろん問題ではありますよ。実際に林さんと取材に行った町田図書館で「複本は20冊入れ、売れ行きがよければ、さらに20冊入れる」と伺い仰天しました。
植村 文芸の作家は著述業で書くことで生活している。一方、大学の先生や企業の研究者は本職の支えがあって、知識や教養を本として外に出している。これは分けて議論しなければいけないと思います。今の石井さんの切実な声は「作家が、文芸出版社が」ということであると考えたうえで、お話をお聞きください。
林 石井さんと町田図書館に伺いびっくりしたことがございました。図書館にガードマンが立っている。なぜかと言いますと、図書館利用者に定年退職した方がとても多く、朝、日経新聞を誰が読むのかで小競り合いがあるので、と言う。ベストリーダーの借りているリストを見ると497回、397回とかでびっくりします。私も1冊入れていただいていますが、だいたい東野さん、池井戸さん、宮部さんです。もっとびっくりするのは今売れている『その女アレックス』(文春文庫)が入っている。複本の問題もありますが、新書や文庫を図書館に置かれることに違和感があります。
石井さんのお話を聞いていて、冷や汗がたらたら流れました。作家が聞いていてあのくらい辛いことはありません。「もっと売れる本を書きゃあいいんだ」という責めのようです。私がこの間、新潮社から出した本は初版もかなり刷っていただき、海外取材もしてお金がかかっているのですが、増刷がない。今、私は自分が責められているように聞いていました〈会場爆笑〉。
根本 複本に関して現時点での調査はしていないのですが、これまでの経験から言えることは、複本については大げさに伝わっているようです。たとえば文京区のベストリーダーですが、11館で427回貸し出されているということは、この本について一館が40回貸し出している計算になります。1回の貸出期間が2週間なので、1冊は半年で平均12回転します。40を12で割って、1館当たり持っている複本数は3冊ちょっとということになります。このように計算するとそれほど多い印象はありませんが、それがフル回転するとこのくらいになる。文京区は11館が3冊ずつ買っていることをどう考えるかです。町田の例についても、分館を合わせると10館以上あるので全体を合わせるとかなりの数になります。
しかし、それが可能なのは財政的に余裕のある一部の自治体にすぎません。複本に関しては、全体に購入予算が減り、出版界、著作者からの多すぎるという意見があり、図書館界でも、もう一度図書館の役割を考え直すことが進んでいます。それによってだいぶ減っているのではないかと考えています。
ただ、やはり若干問題はあります。
一つは行政評価です。いったい図書館の目的はなんであって、どのように評価するかというときに「何人来館者があり、何冊本が借りられたか」という非常に単純なもので評価することが一般的です。それは図書館界が作ってきたもので、貸出しを中心にサービスが成り立っているという考え方を採用してきました。数値の出しやすいもので評価することをしてきたわけです。しかし実際の図書館の役割は極めて多様です。文芸書だけではなく、知識、教養、情報全体について様々なものを提供しているので、そうした全体を評価するような視点を作り、自治体の行政や住民の間で共有することが必要です。
もう一点、司書という専門資格です。私も教育にかかわっているので、養成の問題を感じます。たとえばアメリカではMLIS(図書館情報学修士)というマスターのレベルで、1年間フルタイムでみっちりと授業を受けて初めて資格になります。が、日本では、大学の授業で片手間に単位を積み重ねれば、資格が取れてしまうわけです。司書という資格で、本を選んで評価する視点はどこまで作れるか。結構大きな問題が内包されていると思います。
行政の非常に単純な評価の体質と司書の養成状況が今のような問題を許す体制を作ってきたと思います。欧米ではもう少しきちんと出来ていて、本の専門家としての司書を養成し、それによって、図書館が全体的な知識の領域をカバーする体制になっています。
植村 図書館の図書購入費は減っています。その中で首長などに予算を求めていくときにも、「図書館は本来どうあるべきか」は知っていながら、入館者数、貸出し冊数というわかりやすい数字を出すのではないかと思います。
図書館の役割は何か、図書館の公共性とは何か

植村 公共図書館の中で論争された武雄市図書館があります。指定管理者制度などを含め様々な問題が取り上げられました。実際に行かれて、お書きになった林さん、いかがでしょう。
林 行く前は、いい感情を持っていませんでした。ほんとうに商業主義に徹して、出たがり屋の市長がTSUTAYAと組んでと。
でも実際に行ってみると、とてもいい雰囲気でした。皆さんがとても楽しげにスターバックスのコーヒーを飲みながら本を読んでいる。
正直に申し上げて、私が行ったときには何回も何回も叩かれて想定問答集が出来ていた。「複本は2冊です」「上位の貸出しの本と売り上げはこのようにリンクしています。借りに来て、予約がずっと先だと購入されます。見てください、このリスト」。私はあれが本当ならちゃんと考え抜かれていると思います。
なぜ、武雄に行ったか。無報酬で3人組で中学に出張授業に行く文化団体に入っています。武雄市の中学校で授業をした時に「図書館に行ったことのある人、手を挙げて」と言いましたら、全員が手を挙げた。「じゃ本が好きな人手を挙げて」と言いましたら、これまた全員が手を挙げた。これを渋谷区でやったらどういうことになるか。1割も図書館に行ったことのある子はいないし、本が好きな子は半分くらいかな。それを思うにつけて、まだいろいろ課題はあるにしても、一石を投じて、ここから本当に本好きが育っていくとしたら素晴らしいことではないかと思い、市長にもエールを送ってきました。かつて「樋渡さんはこれで名前を売って、いずれ国政に出るおつもりなんじゃないですか。そのために全国的にこの図書館をアピールしているんじゃないですか」ときつい質問をしましたら、「そんなことは絶対ない。一生武雄の市長として、この図書館を守り抜く」とおっしゃった。知事選に出られて、唖然としました。あの図書館が、あのまま運営され、残るならいいと思っています。
植村 公共図書館が首長により、ころころ変わっていいのかという問題があります。図書館の役割は何か、図書館の公共性は何かという問いが立つと思います。武雄の時によく聞かれた障害者サービス、地域資料が乏しくなってきているのではないかということでした。
佐藤 図書館をどういうふうに使うかを、私は同志社の神学部の先生たちに教えられました。中世において、2冊目の本を借りる時には1冊目を全部理解しているかの口頭試問があり、通らないと2冊目は貸してくれない。
神学部である時、フリードリヒ・シュライエルマッヘルの『宗教論』(岩波文庫)が教科書に指定になったので、「『宗教論』をもっと入れてくれ。なぜ、神学部の図書館に1冊しかないんだ」と言ったら、「それはお前たちが買うんだ。親にねだって、あるいはバイトをして買うんだ。そういう本を入れるのは神学部の図書館の仕事ではない。他の学部の教授たちは研究費で買った本を持って退官する。神学部の図書館は明治時代から全部集中管理している。その代わり世界の神学書は全部集める意気構えでやっている」と。ある時、『死海文書のレプリカ』を数百万円も出して買ったので、私は学生自治会の活動家でしたから「これは無駄遣いだ」と文句を言いました。後の同志社の理事長、当時の旧約聖書神学担当の野本真也教授が、「佐藤君。君のその考えは間違っている。こういう本は図書館じゃないと買えないの。死海文書を羊皮紙のレプリカで触ってみることで感じて、旧約を専攻するという意欲が出る神学生が10人でも20人でも出れば、これくらいのカネは全然無駄ではない」と言われました。
逆に私がお願いして買ってもらった本があります。ソ連で久しぶりに聖書が出たが、発行部数が少ないので日本には1部しか入ってこない。ソ連には著作権がないので現代ロシア語社という小さい本屋がリプリントして1万7000円くらいで売った。アメリカで刷られて、ソ連にプロパガンダ用に送る聖書は500円でナウカで買える。ただロシア正教の聖書だから配列が違うし、旧約聖書続編が入っているので少し厚い。それからお祭りの日が書いてある。「先生、この聖書、欲しいんですけど」と言ったら、その時点で「神学部でロシア語を読めるのは、お前しかいない。今後ロシア語を勉強する神学生が出てくるかどうか分からないけれど、これは買おう。将来、読む人がいるかもしれない」。その時気づいたのですが、ロシア語を誰も読まないのに、「モスクワ総司教庁雑誌」が創刊号から揃っている。いつか誰かが読むかもしれない。極端な例ですが、2000年続いている神学では、そういうふうに図書館の使い方を教育されます。
逆に最近ショックを受けるのは、図書館に本がないことです。「資本論に関する講座をする」というと、「参考資料は何を読んだらいいですか?」「それは筑摩の宇野弘蔵の資本論研究全5巻だ。あれは世界最高水準だ。その図書館にもあるよ」「図書館にないです」。あるいは「新潮社の『マルクス・エンゲルス全集』はすごくいい。共産党系とは違う林健太郎さんなんかの訳だ。どこの図書館だってあるよ。たくさん出てるから」。それが廃棄されていて図書館にはない。古本屋には図書館からの廃棄本が入りますが、古本屋でも全巻は手に入らない。私がわずか80人の講座で褒めたら争って買うので、インターネットショップ「日本の古本屋」で、ある時4、5万円まで上がり、売切れたら、ない。もし図書館に入っていれば、あの優れた『マルクス・エンゲルス全集』に皆がアクセスできる。
最近ではイスラム国などが出てくるけれど、そもそも戦争に関して何を読めばいいかというときに、「戦後の本はダメです。戦争をしないことを前提にしているから。戦時国際法がほとんどない。戦前の岩波全書の横田喜三郎の国際法を読めばいい。どこの図書館にでもある」と答える。私が学生の時はありましたから。今はない。スペースは限られているから、新本を入れると、古い本は捨てなければならない。定量的にやっていると、たぶん貸出し件数の少ないものから捨てることになる。廃棄される形で知の相当の遺産が国立国会図書館、日比谷図書館、東京大学図書館等限られた図書館にしかないことになっている。
ピケティの講演で配った袋に東大が寄付のお願いを入れていた。東大の中央図書館を、300万円払ったら一生、30万円なら3年間使える。そうなるとアカデミーヒルズの上の会員制図書館と東大の図書館はどう違うのか。図書館の在り方がわからないです。
植村 図書館の人と話していると、大学図書館と公共図書館はまったく別の世界として感じますが、図書館としてとらえなければいけない。お互いが本を考えなければいけないのに行政的な図書館法という区分けをしすぎているような気が私はします。
根本 大学図書館と公共図書館の違いは、どこの国でもあります。それぞれを設置しているアカデミズムのコミュニティーと一般の市民社会のコミュニティーは役割が違います。だから、私は、コレクションをどう作っていくかの違いについての違和感はありません。
今の公共図書館の選書に関して、公共性の基準をどこに作っていくかですが、基本的に自治体において、教育委員会が管轄し、図書館長がいて、司書の集団がいて、そこで作っていくことになります。指定管理になると、管理を任されている民間の経営体の考えが強く出る可能性があります。司書が選書の考え方を一貫させていかなければならないのですが、それを無視して素人がかかわってくる問題点があります。ただ他方で、市民の考え方を広く取り入れていくべきだという考え方もあり、予約制度、リクエストの考え方などを総合的に取り入れながら、司書の集団が蔵書を作るわけです。
その時に予約をどう扱うか。予約したものはすべて提供しなければならないのか。先ほど待ち時間の話がありましたが、待ち時間を少なくするために複本をどんどん多くするという考え方があります。そういうことを考え合わせながら、どういうポリシーで作っていくかを考えなくてはいけない。全体としてはマネジメントを自律的に行えないことを危惧しています。司書の集団の危うさともかかわっていますが、自治体としてどうしていくかが問われていると思います。
植村 選書などは司書が作っていくものですが、首長の圧力よりも市民の圧力を感じます。たとえば武雄のように市民が気持ちいいのがいい図書館なのか。自治体として、たぶん市民の2割しか借りに来ていないのではないか。スーパーリピーターのヘビーユーザーがいるけれど、8割の人は来ていない。
この8割の人が来る図書館を考えるべきでしょう。ごくごく少数の、あるいは定年退職の日経新聞を読みたいおじさんたちのような人たちだけを満足させて、市民の声に応えているというのは間違いではないか。520件のベストオーダーの圧力、結局何百件のベストセラーを借りたがる市民が、公共図書館の在り方を作ってしまうのではないか。司書が、その図書館をどう作るべきかを言うことが難しいのではないかと思います。
注目されている国内の図書館と海外の図書館事情
猪谷 最近、注目されている図書館の事例をご紹介します。
東京都武蔵野市の武蔵野プレイスは、ツイッター、フェイスブックを見ると、ユーザーの間でかなり評判のいい図書館です。「おしゃれ」「素敵」、中には「住みたい」と言う人もいます。ここは図書館だけではなく、武蔵野市がもともと持っていた行政課題を解決するために作られた複合施設です。図書館は4層のフロアに分散していまして、1階には雑誌や新聞のコーナーがあり、カフェに持ち込んで読めます。ユニークなのは地下の青少年活動支援のフロアです。中央にテーブルやイスがあり、放課後には小中高生が勉強したり、打ち合わせをしたり、おしゃべりしたりしています。フロアには、子供たち向けの本のライブラリーがあり、バンド、ダンスができるスタジオも備えています。実はここは20歳以上の人は使ってはいけない、子供たちの天国みたいな場所で、中高生は午後10時までいられる。地域で子どもを守るということからいうと、今は共働きが多いのでご両親が帰ってくるまでここで過ごせますので、大人の目の届く安全な場所として機能しています。館全体でイベントをするときは、職員の区分けを取り払い、図書館や地域市民活動、青少年活動支援などそれぞれの担当者が一緒に企画し、市民の方たちが、武蔵野プレイスを交流スペースとして利用できるようにしています。今、全国で、公共施設が非常に老朽化し、かつ地方自治体の財政はシュリンクしています。大きな公共施設をそのまま再建するのは難しいので、駅前の便利で人が集まりやすい場所に複合施設を建てて運営していくという流れの参考事例として注目を集めています。
また、長野県「小布施町立図書館まちとしょテラソ」という図書館があります。小布施町は人口は1万1000人ですが、年間観光客は100万人です。新図書館建設については、町長、行政がトップダウンで決めるのではなく、町民100人が集まり徹底的な議論をしました。反対もありましたが、結論としては建築が決まり、町民50人を公募し図書館建設運営委員会を作りました。自分たちの町にふさわしい図書館はどういうものかを、図書館専門の先生方を呼んで勉強し、図書館リテラシーを町民の方たちで高めて、「自分たちの理想の図書館はこれだ」というコンセプトを作り実現した図書館です。館長も公募です。非常に面白いことをしています。私が行ったときは午後二時くらいでしたが、いきなりスタッフが机の上にのぼりマイクで何か話し始めました。それだけでもびっくりしますが、「皆さん、そろそろ勉強とか本を読まれるのに疲れたと思いますので、簡単なストレッチをやりましょう」とイスを使ってその場でできるストレッチを始めました。「ストレッチなんて、やるのかなあ」と思っていましたら、皆さん普通に始めたのにまた驚きました。私が知っている図書館では見られない光景なので、当時の館長に「これ、苦情は出ないんですか。静かに本を読みたいと思っているのに、とか」と伺いましたら「うちの図書館は常に何かが起きているわくわくする図書館ということを、皆さんよくご存じなので別に驚かれません」と。また、小布施町には有名なパン屋さんがあって、小布施の方ならどなたでも知っているけれど、まだメディアには情報はないわけです。そこで、図書館がその方をインタビューして動画やテキストを図書館にアーカイブするといったこともされていました。それは町の歴史にもなります。50年先、100年先を考えた時に街づくりの歴史を見るうえで大事な資料になると思います。
それから、地方創生の先駆例として、今、一番注目を集めているのは岩手県紫波町の図書館です。紫波町の駅前に、ずっと塩漬けになっていた10.7ヘクタールの町有地がありました。紫波町はここに補助金に一切頼らず、公民連携事業で建物や広場を作り開発をしました。「オーガルプロジェクト」と呼ばれています。2012年に図書館が入居する最初の中核施設ができ、年間80万人から90万人の方が来るようになりました。どんな施設かと言うと、図書館だけではなく、産直マルシェ、居酒屋、カフェ、クリニック等民間のテナントが入り、そのテナント代から図書館の光熱費が賄われているそうです。図書館は原則無料の施設ですので、理解のない行政から見れば金食い虫という一面もあります。この図書館は建築前の段階で非常に計画が練られています。建設費を抑えるために、天井は配管がむき出し、でもとてもおしゃれに作っているので全然貧乏くささがない図書館です。図書館自体は農業支援サービスを主軸にしています。紫波町は農作物がたくさん採れる、農家の多い町です。一方で、少子高齢化で若手の農家がなかなか育たない現状があります。町としてはここを何とか解決したい。この図書館を舞台に若手の農家さんのコミュニティーを作ろうとされています。
次に、図書館と書店の関係で注目している例をご紹介します。
東京都千代田区千代田図書館は九段下、本の町神保町に近いということで、書店や出版業界との関係を何とかして構築していこうと努力しています。コンシェルジュがいて、様々な案内をしてくれます。たとえば、「神保町でおいしいカレー屋さんはどこですか?」と聞くとお勧めを教えてくれたり、急ぎで借りたいけれど貸出しされていて図書館にない本を、神保町の書店、古書店のデータベースをその場で検索して在庫を調べてくれて「こちらに行けば、すぐ手に入ります」と教えてくれます。千代田図書館はビジネス支援にも力を入れているので、仕事で使われる方には、本当にありがたく、私もよく使っています。
鳥取県は図書館と書店の関係が非常にいいと言われています。実際に鳥取県内の書店を取材すると「図書館なしではうちはやっていけません」とおっしゃいます。それがよく表れているのが鳥取県書店商業組合の『マイ・メモリアルブックキャンペーン』です。「人生の記念日、『結婚しました』『孫が生まれました』といった日に、あなたの人生の記念日に書店商業組合を通じて本を買って県内の図書館に寄贈しませんか」というものです。本好きの方は自分が寄贈した本が図書館で皆に読んでもらえて嬉しい、書店商業組合は本が売れて嬉しい、図書館は本が増えて嬉しい。これは全国に広まってほしい動きです。
今日のテーマは公立図書館ですが、実は公共図書館は公立図書館だけではありません。全国で「まちライブラリー」という小さな図書館が増えています。ワーキングスペース、カフェ、お寺にもあります。人が集まるパブリックスペースに本を置き、貸出しをしています。宮崎県都城市にある書店の都城金海堂本店は、入口に自前でこの「まちライブラリー」を作りました。なぜ書店がわざわざそんなことをするのか、電話で伺ったところ、「商店街自体が地盤沈下を起こしていて地域の話題作りをしたい、皆に本を読んでもらいたいという思いでやっています」ということでした。特に地方の小さな書店は逼迫して減っています。地域の書店と図書館がいがみ合うより、一緒に地域の本の文化を絶やさないように頑張っていこうということだと思います。
地域で本好きのコミュニティーといえば、東京の谷中、根津、千駄木の地域で、2005年から始まった「一箱古本市」という取り組みがあります。本好きの人たちが自分の好きな本を一箱詰めて持ち寄り、フリーマーケット形式で売るイベントです。これが全国に広がり、80か所以上で開催されているそうです。地域によっては書店や古書店が中心になったり、図書館が参加していることもあります。
地域、地方で細かく見れば、書店と図書館が、本の文化を守って、地域の本好きのコミュニティーを作っていこうという運動があるように思います。
植村 千代田図書館の、「その本は貸出し中ですが、この書店さんに売っています」というコンシェルジュの案内は素直に受け入れられるのでしょうか。
猪谷 千代田図書館は仕事で使われる方が多いので、そういう事情があると思います。図書館の性質にもよると思います。
植村 山梨県立図書館で、阿刀田館長は「本をすぐ読みたいのなら、やはり買ってもらうように言いなさい」と指導していると聞きました。自らが言うのはいいけれど、たぶんフロントの人が利用者に言うのはむずかしい。なぜかというと、私の学生が、図書館でアルバイトをしていて、予約が200番だと「私、税金を払っているんだから、200冊買いなさいよ」と罵声を浴びせられたという。猪谷さんが紹介された「いい図書館」は、結局、市民性の反映かなと感じました。ちょっと言い過ぎかもしれませんが。
猪谷 やはり図書館リテラシーが高い利用者が多いのではないかと思います。
根本 千代田図書館には私もかかわっていたので申し上げます。今の件については、まず図書館のポリシーとして複本は買わないことになっています。最初の柳館長の基本的な方針があったからです。様々な案内業務を行うコンシェルジュも司書ではない。資格を持っている方も、もちろんいると思いますが。違う論理で本を扱う仕事です。神田の書店街を背景にした千代田区で、書店、古書店で買っていただくことも想定し、マーケットの論理を導入した、新しいタイプの仕事です。
ここで外国と日本において図書館と出版がどのような関係になるかを考えてみます。たとえば、ハワイには本屋さんがほとんどない。アラモワナ・ショッピング・センターに有名書店バーンズ・アンド・ノーブルが1軒あることはありますが、そんなに大きくはない。紀伊國屋書店新宿南口店のワンフロアくらいしかない。ハワイ大学にブックストアはありますが、教科書と最近のペーパーバックスを置いてある程度です。それ以外は個人商店とセカンドハンドの本屋で、合わせて25軒くらい。それに対して、ハワイの図書館の数は公共図書館50館、大学図書館20館、公立学校図書館261館、専門図書館47館です。専門職員の数は合計で345名と学校図書館では職員の8割が専門職でした。公的な図書館をきちんと位置付けて、商業的に弱い面を補いながらインフラとしているのです。
人口がハワイとほとんど同じ沖縄県では、書店が155店、そのうち100坪以上の店は31店あります。全然ハワイとは違いますね。沖縄で出版された本も多く、出版文化を大事にされています。出版市場がきちんと作られているわけです。それに対し、沖縄の図書館は公共図書館38館、大学図書館10館、公立学校図書館471館、専門図書館9館、専任職員は合計で181名でした。図書館の事情は日本の平均だと思います。
一般に、北と南では読書に対する態度に格差がはっきりとあるということです。本を買って読む習慣がなければ公共的にそれを確保することが行われています。
デンマークでは、最高レベルの図書館サービスが行われています。フィンランドも図書館サービスが非常にしっかりしています。スウェーデンでは19世紀的な構造の図書館も現存していて、電子書籍ではなく、手に取って触れて読む図書館となっています。イギリスは福祉国家の時代には図書館大国だったのですが、新自由主義経済で図書館予算が非常に削られていると聞いていました。しかし最近できたバーミンガムの新中央図書館を見ると、建築にも提供するサービスにも大変お金をかけた、1日いて楽しめる新しいタイプの図書館が作られていました。図書館が単に、読み物を貸出しする場所ではなく、市民レベルの知の形成に欠くことができない機関であるという考えが共有されているのでしょう。
石井 外国の図書館でも無料貸出しがどんどん行われていますか。
根本 ヨーロッパでは無料が一般的ですが、オランダ、ドイツそしてフランスの一部では、大人が貸出し登録をするには有料となっています。20世紀後半に財政危機から導入された制度で、毎年数十ドルの登録料金がかかります。また、新刊書の予約は、大した金額ではないですが、お金を取るのが一般的です。公共貸与権の制度がヨーロッパにはあって、図書館での貸出しについては国家的な規模で著作者に還元することが行われています。このように、商業的な出版制度と公共的な図書館との役割の違いを制度に反映させているところが日本とは違います。ただ、日本でも、今ここで行われているような議論があるわけで、時間をかけてそれぞれの国に合った制度の導入をはかることになるのでしょう。
植村 貸出し猶予にしても猪谷さんの紹介してくれた館でも、市民の読書リテラシーが重要ではないかという気がしてきました。
石井 なかなかいい図書館があることは分かります。しかし悪い図書館も実はあります。
今、寄贈を呼びかけている図書館がある。横浜市中央図書館は「新しい図書、予約が多い図書、特に文庫本を寄贈してください」、岸和田市立図書館では「出版がおよそ五年以内の図書、予約が多い図書、人気のある図書、特に新書本、文庫本を寄贈してください」と堂々と言われています。そういうところで図書館が足を引っ張っている。
佐藤 究極の寄贈図書館は意外なところにあります。私が512日間ほどお世話になった東京拘置所。受刑者が図書係をしていて、未決拘留者が差し入れや購入でとった本で廃棄された中から、皆の希望に即した形で、究極の寄贈文庫ができている。図書の全体のだいたい半分が犯罪小説、4分の1がヤクザのしきたりの本、残りはエロ小説が多かった〈会場爆笑〉。私は取り調べの特捜検事に言いました。「これでは矯正効果がないじゃないか」と。検事は「無罪推定が働いているので、刑務所と違って、ここはお客さんの需要に合った形で書籍を揃えている」と。
私は聖書を持たないで入りました。「教誨」があるから、聖書、仏典は入っていると思ったら、まったくなかったです。ちなみに検事にこう言われました。「そのこと手紙に書いたらダメだよ。あんたの手紙は拘置所が注意して検閲しているから、過剰反応して皆の楽しみを奪うことになる」。雑居房では、犯罪小説をまわし読みしては、「この犯罪、できるわけないだろう」と皆の話題になり、ヤクザの盃の儀式は東京拘置所で覚えていく。需要だけで備えていくと、お客さんの水準、リテラシーによっては、東京拘置所に類する水準になっていくということではないでしょうか。
私にとっての理想の図書館
植村 マイ図書館としての理想の図書館を、一言ずつお願いします。
菊池 以前からいいなと思っているのは伊万里市民図書館です。20年前に、当時のふるさと創生資金を上手く使い、市民が図書館の方々と伊万里塾という市民参加型の学習活動を8回して、アメリカの公共図書館を見学し、いいところを取り入れながら自分たちの図書館を作りました。去年、東京国際ブックフェアで伊万里市民図書館館長が話されましたが、図書館をリニューアルした当時の市長が「図書館の役割がひいては地域のまちづくりに影響を与える」と言ったことを現市長も受け継ぎ、そのことに対して図書館の友の会が、大変協力をしてきました。20年前に100人規模で始めたこの会は今は4倍くらいになりましたが、図書館に対してもいろいろと意見をしてきた結果、伊万里市民図書館は先ほどから話題になっている複本もかなり抑制した幅広い蔵書の構成になっています。
開館直後に行って、「なるほど。こういう小さい町で、これだけたくさんの基本図書、専門書を幅広く揃えているのか」と感心しました。最近ではビジネス支援に力を入れています。伊万里は、焼き物の町ですから焼き物の資料をたくさん集めていますが、それを使い、焼き物をベースにした万華鏡と万年筆を作り、ビジネスを立ち上げた人がいます。水力発電や風力発電の小型化で、四つの特許を取り、風力発電の注文を取りそこから起業した人も出ました。利用者の非常にユニークな活動に図書館資料が結びついていると言えます。大事なことは図書館の収書方針です。伊万里市民図書館では、どういうふうに自分たちの町おこしと結びつけるかという観点が入っています。こういうやり方が公共図書館の一つのありようとして、地方の図書館から発信されていることに意味があると思います。
猪谷 長い目で見て、本の文化を盛り上げていくための活動が実現できる図書館が、私にとっての理想です。今、気になっているのは、去年、日本の子どもの貧困率が過去最高の16.3%になったことです。
昨夏、中公新書の『地方消滅』が非常に話題になり、地方自治体の方に大変な衝撃を与えました。2040年までに少子高齢化が進み、900くらいの自治体が消滅してしまう、というレポートです。日本の公共図書館の多くが地方自治体、市町村立図書館です。一方で子どもの貧困率が上がると学力格差が広がる懸念があります。塾に行けない、家庭教師が付けられない子どもたちは、図書館で勉強します。その予算を削られて、活動の幅を狭められてしまうと、ますます子どもにとっての学びの場がなくなり、私たちの社会全体がシュリンクしていくことにつながるのではないでしょうか。そんなことのない図書館を求めたいです。
佐藤 私は沖縄県久米島町久米島高校の学校図書館です。久米島町には図書館がない。沖縄県立図書館が巡回したことが2回しかない。本屋もない。コンビニが二つあるだけ。半嶺通男校長がすごく頑張っている。子どもたちが本を読むことによって大学への進学など現実に影響を与えている、あの図書館には未来があると思います。
林 私の理想の図書館は、まず家から近い、ごちゃごちゃ人がいない、まず願望は喧騒がないことを言いたいです。私が理想とするのは私が昔通っていた豊島区立図書館の、あの静謐さをもう一回どこかで取り戻したい。
根本 私は学校図書館の重要性を感じています。というのは、学校は3万校以上あって、すべての学校に図書館が設置されているからです。しかしながら職員もいないような学校図書館もあり、中途半端に位置づけられています。この学校図書館を整備し、学校図書館専門家を養成し配置することが課題です。読書の重要性に反対する人はいません。赤ちゃんから小学生くらいまでは読書習慣の形成を重視して、子どもに本を読ませようとするけれど、そこから先に受験を意識したとたんに、読書から離れてしまうことになりがちです。中高で総合学習など資料を使って自分で考えて発表するタイプの学習は存在していると思いますが、現実にそれほど重視されていない。諸外国の学習を見ると図書館がなければ学習は成り立ちません。自分で調べて学び、その結果を外に向かって発表するタイプの学習が真の学習なのです。日本では学習指導要領の中で学習範囲が決められ、それをもとにした狭い範囲の知識を学んで受験でいい点数を取ることが目標になりがちです。こういう中では、ネット世代の人たちが大人になって、本を読むようになるとは思えないのです。とくに十代の子どもたちを対象に読書市民を形成することが重要です。
石井 私の理想の図書館は出版社が潰れるのを助けてくれる図書館です。正確に言うと、著者と版元がお願いした書籍の六か月間の貸出し猶予をぜひ理解をもって応じてくださる図書館が私の理想の図書館です。
植村 最後に、理想の図書館を実現するのは行政、図書館だけの仕事ではなく、市民、図書館を支える人々によって支えられるのだということが見えてきたと思います。
〈文責=日本文藝家協会 長尾玲子〉
公共図書館への提言
日本文藝家協会は、「21世紀の出版契約を考える会」有志の協力を得て、本年2月2日、東京・新宿の紀伊國屋サザンシアターで、「公共図書館はほんとうに本の敵?」と題したシンポジウムを開催しました。
パネラーは、石井 昴(新潮社常務)、根本 彰(東京大学教授・教育学)、林 真理子(作家)、佐藤 優(作家)、猪谷千香(ジャーナリスト)、菊池明郎(筑摩書房相談役)の6氏、司会進行は植村八潮氏(専修大学教授・コミュニケーション学)でした。聴衆450名、満席となったのは主題への注目度の高さゆえでしょう。公共図書館が日本の出版文化に大きな影響を及ぼしていることの証しでもありましょう。
パネラーは一致して、「公共図書館は、もちろん本の敵ではない」と確認しました。
しかし議論を深める中、作家や出版者にとって現状の公共図書館のありかたは「理想」とは程遠いのではないか、という意見も出されました。
公共図書館に、「レファレンス」系を中心とする専門的書籍、あるいは個人購入がためらわれる高価な本を備えて欲しいと望むのは当然で、それが本来の公共図書館のつとめでしょう。さらに、本以外の情報、地域資料、音楽・映像等の提供、博物館・史料館との連携、地域文化活動の支援等々、欧米の先進的公共図書館の多様な活動に比べると、日本では本の貸出し冊数が評価基準となり過ぎている傾向は否定できません。
たしかに日本でも地域密着型の新しいタイプの図書館が出現しつつあります。しかしその数はいまだ全体の1パーセントに満たず、「住民ニーズに応える」というエクスキューズのもとにベストセラー貸出サービスから脱皮できない図書館が大半です。複本問題が話題となった10年前と実情はほとんど変わっていないといえます。
いや、事態はより深刻かもしれません。過酷な予算削減を要求され、資料購入費の減額を余儀なくされている公共図書館では、購入する書籍が、単行本から安価な文庫版、新書にシフトしています。はなはだしくは文庫版の寄贈まで呼びかける状態に立ち至っているのは、図書館の「モラルハザード」といわざるを得ないという見方も、議論中にしめされました。
そのような現状を見かね、石井氏からは、図書館での大量貸出し予約が予想される一部ベストセラーについて、あくまでも著者からの要望がある場合という条件付きで、発行後6か月間の貸出し猶予を図書館に望みたい、との意見が出されました。一方、菊池氏からは、ベストセラーに偏らず、多様な作家活動・出版活動を支えるためには公共図書館の資料購入費の増額がどうしても必要だという声が上がりました。
公共図書館は、民主主義社会には絶対不可欠の存在です。しかし、作家の表現活動の継続を支え、新たな作家の登場を促し、出版物の品質を高度な校閲などによって保証しているのは出版社と出版産業です。公共図書館は作家・出版社・出版産業を苦境に追い込むことなく、むしろこれらと協力しなければならない存在、ともに戦う友軍だと考えます。
図書館人には、出版界の声に真摯に耳を傾けていただきたい、また予算削減のみを要求する運営自治体に、自らの理想とする図書館サービスのあり方と意義を説いていただきたい。そういう痛切な願いを、私はこのシンポジウムを通じて抱きました。
公共図書館が果たすべき役割は大きいのです。出版界と協調しつつ次世代の読者と作家を育て、日本の出版文化、日本語文化の未来に貢献されることを期待します。
平成27年4月2日
関川夏央〈日本文藝家協会 常務理事・事業委員長〉