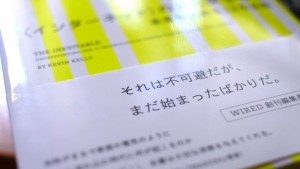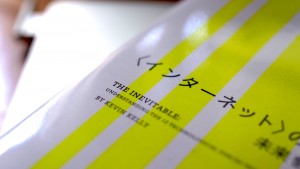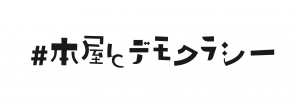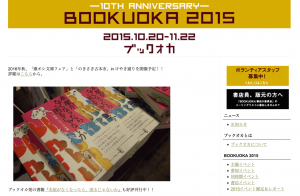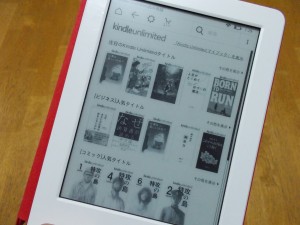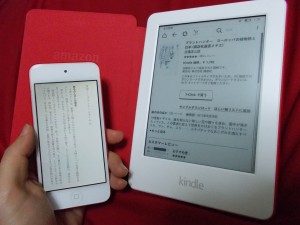谷本真由美さま
なんだかんだでオリンピックも終わって、ロンドンどころか、あのリオでさえなんとか盛大なイベントを開催できたのを見て、少し安堵していいのか、さらに4年後のことを心配していいのかわからない今日この頃です。
さて、日本では誰よりも先にミーハー丸出しで飛びついておいて、もう飽きたなどと、通のゲーマーぶってみせる輩も見受けられる「ポケモンGO」ですが、ニューヨークでもものすごいことになっています。
ポケモンはなぜアメリカでも成功できたか
もともとニューヨーカーといえば、あの小さいマンハッタン島の中を「この私を轢けるものなら轢いてみろ」とクルマにガンを飛ばしながら歩きまわっているので、うってつけのゲームだったと言えるでしょう。いまだに誰もポケモン捕獲中にタクシーにはねられて死亡していないのは、普段から歩きスマホも、ジェイウォーク(横断歩道じゃないところを斜めに渡ること。一応ニューヨークの条例では違法となっているが、誰も守っていない)もお手の物だからかと思っております。
「ポケモンGO」をめぐる騒動で思い出すのは、やはり最初にアメリカで、「ゲームとアニメと映画がマルチメディアでシナジーを起こす」などと言われていた頃のことですね。もう20年近くも前の話です。あの頃、アッシュ・ケッチャム(サトシの英語名)がリビングルーム(お茶の間ではなく)に登場して、ニンテンドーのゲームにはまったアメリカンな小学生たちが、オタク感溢れる大学生・社会人になって「ミュウツー」だの、「ギャラドス」だの言いながらボールを投げているかと思うと、感無量です。
なにしろ、インスタント冷凍ワッフルがポケモンバージョンを出したり、ラジオシティー・ミュージックホールでポケモンショーをやっていたり、プロモーションと称して、フォルクスワーゲンの黄色いビートルを改造したピカチュー車が何台も子供の多い街に出没してゲームをやらせていたぐらいなんですから。
何がきっかけでアメリカでポケモンがブレイクしたかといえば、ニンテンドーがアジア圏以外でのアニメとマーチャンダイスのライセンスを売り飛ばしたからなんですよね。買ったのは、アル・カーンという人物で、それまでにアメリカで「キャベツ畑人形(Cabbage Patch Kids)」という、お世辞にも可愛いとは言えない人形を流行らせたこともある人です。
ちなみに、アメリカ人にとってCabbage Patch Kidsといえば、なんでクリスマスにあんなものを欲しいと思ったのか、本気でサンタさんにお願いしてしまったのか、過去の自分を殴りたいぐらいの黒歴史になっているおもちゃなのであります。そもそもなんでキャベツ畑で子どもが生まれる設定なんだよ? と突っ込んであげると面白いかと思います。
郷に入りては郷に従え
ポケモンのランセンスを根こそぎ買って大儲けした4Kids Entertainmentという会社は、ポケモンのアニメをアメリカ風にかなり勝手にアレンジしたと、いまではオタク系の米アニメファンに責められる存在ですが、「遊戯王」を扱った時のトラブルが元でその後に破産宣告しました。インターネットも一般に普及していないその頃は、サトシがアニメで「おにぎり」を食べていても「あの黒いボールはなんなのだ? ポケモンを捕まえるための道具ではないのか?」というトラブルを避けるために、サンドイッチの絵を代わりに挿入した、などの逸話が残っています。
ブームの頂点ではアメリカで年商30億ドル近いとされていたので、アル・カーン氏はこれで億万長者となりました。その後、ロングアイランドの母校に何億円ものお金を寄付したり、投資を装ったネズミ講で逮捕されたバーニー・メイドフの五番街のお屋敷を破格の安値で買ったときにも、ニュースで名前を見かけました。
もちろん任天堂としては、実は日本のことなどちっとも理解しているわけではなかったこの人物が、濡れ手に粟のごとく、しこたま儲けたのは面白くないでしょう。でももし、任天堂の日本人駐在員が乗り込んでいったところで、ポケモンがアメリカであれほど売れたかというと、私は違うと思います。
郷に入りては郷に従え、ということわざじゃないですが、現地の子ども向け番組のバイヤーと親しいとか、おもちゃ業界のR&Dの人とコネがあるとか、ワッフルやパスタのような異業種商品の流通に詳しいとか、そういう人材がいなければ、いきなり異文化のマーケットに「これ、日本で流行ってるんですけど〜」という理由だけで食い込むのは難しいからです。
そもそも、アメリカ人の子どもたちが何を「クール(カッコいい)」と感じるのかがわからないと、ダメですよね。日本政府側が「クールジャパン」と称して推してくるものが、大抵ハズれているのはそのためです。可愛くないキャベツ畑人形もこうすれば売れるとか、忍者のコスプレと思われるイタリア名の突然変異した亀がヒーローのコミック(ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートル)がなぜか人気があるとか、どうすればアメリカ人がお金を出すのか、こうしたことがわからなければなりません。安倍首相がいくらオリンピックの閉会式でマリオになりきろうが、一国の首相があんなことしてるよ、という笑いをとって終わりです。
これはコンテンツ輸出を目論む出版社にも言えることですが、版権は、それを売るノウハウを持ち合わせていなければ、宝のもちぐされであって、いくら自分たちで守っていても一文にもならないことになります。
4年後をみすえて何をすべきか
日本人的な感覚だと、ポケモンがイケるんだから「妖怪ウォッチ」だっていいだろう、と思いがちですが、日本的な「妖怪」という感覚が海外でどう受け取られるかは未知数です。十分に子供たちにフォーカスグループで実験し(そもそも、「フォーカスグループ」に相当する日本語が思いつかないあたり、マーケティングのコンセプトとして浸透していないものと思われますが)、その上で、ランセンシングに詳しい現地の人たちを雇うのが、成功のカギを握るように思います。
「ポケモンGO」の人気を、相も変わらず「日本すげー!」の一例として捉えたい人がネット上には多いようですが、これはグーグルマップという大容量のデータと、ナイアンティックが「イングレス」に続く新しいARゲームとして英知を結集させたものであって、未だに萌え少女のRPGのレアアイテム狙いで課金させている日本のゲーム界には、逆立ちしても作れなかったろうな、と感じてしまうのであります。
同じ感覚で、4年後に日本側が「おもてなし」と思っていることと、東京にオリンピックを見るために乗り込んでくる外国の人たちが準備しておいて欲しいことはだいぶ違うのではないか、と危惧されます。
残念ながら、政官主体の「クールジャパン」では思いっきりハズれたおもてなしになるのが目に見えるようなので、ここは素直に若い人に任せるとか、海外の人たちの声を素直に聞くとか、「ジジ抜き」を心がけてほしいものであります。たとえば、ハズレは「成田空港に着物を纏ったお姉さんが立っていて、冷たい手ぬぐいを渡してくれる」で、アタリは「成田に着いた途端、ワンクリックで高速の無料無登録Wi-Fiがサクサクと動き、SIMカードが海外登録のクレカでサクッと買える」ということなのですが、これをITには不案内そうな五輪担当大臣に説明するだけでもハードルはかなり高い気がします。
この往復書簡は今回の往復で最終回ということですので、私からはこれが最後のお便りになります。4年後の東京オリンピックをみすえて、日本人は何をすべきか、谷本さんはいかがお考えでしょうか?
※この投稿への返信は、WirelessWire Newsに掲載されます
この連載企画「往復書簡・クールジャパンを超えて」は、「マガジン航」とWirelessWire Newsの共同企画です。「マガジン航」側では大原ケイさんが、WirelessWire News側では谷本真由美さんが執筆し、月に数回のペースで往復書簡を交わします。[編集部より]