地下鉄東西線の大谷地駅を降りると幹線道路沿いに大型電気店とパチンコ店、ショッピングモールが見える。どこにでもある何の変哲もない郊外だ。強いて言えば6月末でも夕方になると肌寒い点が札幌らしさかもしれない。そのショッピングモールの一角に次々と斬新で画期的な企画で成功を収め、メディアを通じて全国からも注目を集める「町の本屋さん」、くすみ書房は店をかまえている。
地域と本のことを考え続けるくすみ書房の経営者、久住邦晴氏(以下久住氏)は、柔和な表情で筆者を出迎えてくれた。
戦後間もない1946年、札幌の中心部から離れた琴似の商店街でくすみ書房は開店した。どこにでもあるような町の本屋さん、つまり地域に根づいた書店であった。地元の学校の教科書も取り扱った。順調に営業していたくすみ書房だったが、それまでその終着駅だった地下鉄東西線が琴似から延長された。1999年だった。売上が激減した。
しかし、それは何も札幌の終着駅に限った話ではなかった。その頃から雑誌やマンガも取り扱うコンビニ、ナショナルチェーンの大規模書店、Amazonや楽天を中心としたネットショッピング、ブックオフをはじめとする古本屋、このような新たな書籍の流通形態が一挙に出現し始めていた。全国各地で町の本屋さんが消え始めた。こうした状況下で、くすみ書房はたまたま地下鉄延長が契機となったに過ぎない。
危機感を覚えた久住氏は中小書店ならではのあり方を模索した。今ではよく知られる「なぜだ!? 売れない文庫フェア」をはじめて手がけたのは2003年のことだった。その後も本屋のオヤジのおせっかいと称した「中学生はこれを読め!」や北海道大学の教員を招いたトークイベント「大学カフェ」といった企画を成功させてきた。ともに書籍化もされている。ここ10年で実現してきた企画は筆者が数える限り約20である。
突然の危機と「友の会」をつうじた支援活動
ここまでは読者も知っているくすみ書房のサクセスストーリーかもしれない。だが、先述のような状況に加えて書籍全般の売上も減る中で運営を続けるのは、くすみ書房といえども困難だった。出店攻勢を続ける大型書店には規模経済で勝てない。そこで店舗面積の広い大谷地へと移転し、「町の小さな本屋さん」から「郊外の中くらいの書店」へとその姿を変えることとなった。企画棚の常態化やトークイベントのスペースもできた。地下鉄駅直結も幸いして売上は上がり、経営は順調だった。
そんな中突然「くすみ書房がなくなる!?」というニュースがウェブ上で駆け巡った。リンク先は、久住氏の娘であり、フォトグラファーであるクスミエリカ氏のホームページ上にたち上げられた特設サイトである。そこには今月(2013年6月)中に一定額の資金を用意できなければ閉店する可能性が濃厚であると父から聞いたこと、現状ではそれを免れる手段としては「くすくす」の会員を増やすことくらいしか思いつかないこと、そしてそれを個人的にお願いしたい旨が書かれている。
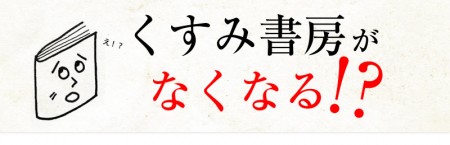
「くすくす」というのは2012年にはじめたくすみ書房の会員制度であり、入会費(年間)1万円を支払って入会すると久住氏自身がセレクトする書籍が年間四冊(7000円相当)が送られてくるものである。驚きとともにそのニュースは全国に拡散された。

くすみ書房の友の会、「くすくす」の入会案内。
駅前に8店舗あった地元書店はゼロに
本当にこのままではくすみ書房はなくなってしまうのだろうか。筆者自身、自宅が近かった琴似時代に一般書も教科書もお世話になった書店の危機について話を伺わないわけにはいかなかった。
「北海道はもちろんのこと全国のマスコミから取材申し込みがきているが、現時点ではまだお話できる状況にはないため丁重にお断りしている」と久住氏は前置きした。なお、筆者はこの一件の仔細についてというよりもむしろこの一件を通じて、危機的な状況に置かれている全国の地域の書店の現状が広く共有されるべきという考えを前提にお話を伺ったことを書き添えておく。以下、北海道書店商業組合の理事長でもある久住氏の考えと、それを踏まえた筆者の意見を述べたい。
くすみ書房が閉店の危機にあるのは確かである。琴似時代の赤字が大きかったのである。先に述べたように、様々な環境要因がある中ではくすみ書房と言えども例外なく中小書店は厳しい。
札幌ひとつとっても駅前通りに8店舗あった地元書店はゼロになり、そこに大手書店が入れ替わった。坪数も品揃えも充実し、読者にとっては非常に豊かな読書環境になっていると言えるだろう。大手にそれが可能なのは小さな書店と違い、取り扱いロットの大きさゆえ取次会社からの掛率(正味)が低く、単純計算でもひと月に百万円近くも粗利が違うと言う。何人分の人件費かと考えると声を失った。
また、全国的に書籍の売上額自体が減少傾向にあるため、取次会社からの締め付けも年々厳しくなっている。もちろん中小書店の厳しさを知る会社から期日を大目にみてもらえることも過去にはあったのだが、それもいまは厳しい。札幌は書店が充実しているだけ読者にとっては良い環境だ。数万人規模の市町村では書店が町から消えている。北海道ではすでに60の市町村に書店がない。これは道内の自治体総数の3分の1にあたる。驚くべき数字だ。だが驚いている間にも次々と書店はなくなっていく。
「本屋のない町で子育てをしたくない」。そんな中で聞いたこの言葉を久住氏は忘れられないと言う。留萌市に最後にあった地元の書店が閉店した際の主婦たちの声である。子どもの頃から自分で数多ある本を手にとって選び、そして将来も自分の手元に置いておく。そんな当たり前のことが不可能になってしまう。その小さな声は一種の市民運動となり、留萌市は書店の誘致活動を行った。そしてその成果が実り現実に三省堂が出店することになったのである。
おそらくこれは全国初の事例ではないかと言う久住氏は、北海道書店商業組合として道内の書店に対する財政支援を行政に求める動きを考えている。また、業界内だけでの取り組みに限界を感じ、業界外部の企業との連携を模索している。たとえば、今のところ中学生へのめぼしい読書推進活動が見当たらないため、メセナ活動との連携や個々の企業とのタイアップの可能性を探っているのである。
書店の役割は「本を売ること」だけではない
このように話を伺っていると書店の役割、そしてその価値はいまや書籍を売るだけではないと感じる。印刷出版は長らく先人の知恵を未来へつなぐ技術として重要な役割を果たしてきた。現代のテクノロジーはその機能をデジタルとネットワークに置き換えることで、より簡易にできるようになった。その劣化しない知恵は複製可能であり、物理的な制約がない。
ところがそのような膨大な知恵の中から自分に最適な知恵をみつける役割はまだ必要であるし、何よりその知恵が必要になるためのきっかけは誰かがつくらなければならない。特に子どもには。そしてまさにそれが、くすみ書房のやってきたことだ。
書店はもはや「本を売る場所」ではなくなっていくのかもしれない。正確に言うならば「本を売るだけの小さな本屋さん」は現代では成立しない。そう言い切ってしまえるのではないか。もしそうであるならばこれからの町の本屋さんはどうなるのだろうか。
そこは子どもが遊びながら本「も」読める場所であったり、紙の本を実際に手にしながら眺めるショールームとなり、もしかすると本は別のところで買うようになるのかもしれない。あるいはそこは、知の広場さながらお茶を飲みながら語らう場かもしれない。いずれにせよ人々が「結果的に」本を買うこともある場。それが図書館の延長なのか、書店の延長なのかはわからない。だがその双方が限りなく近づいていくようなイメージが見えてくる。
そしてそこには行政の支援が必要な理由も納得できる。つまり、児童教育のみならず生涯教育をもその視野に入れた教育機関、またその交流を通じた地域コミュニティ醸成の拠点としてその公共性を訴えることが可能であろう。
もちろんのことだが、久住氏は行政支援や外部協力を求めるだけにとどまらない。ひと目店舗を見渡しただけでも自助努力を日々積み重ねている様子が観察できる。子どものコーナーにはぬいぐるみと低いベンチが用意され、集中力のないこどもでも長時間過ごせるようになっている。これならば親子連れで気軽に来られるだろう。
また壁一面を使って「小学生はこれを読め!」「中学生はこれを読め!」「高校生はこれを読め!」とオヤジのおせっかいが止まらない。しかしそこにはマンガもある。「おせっかいな本屋のオヤジ」が薦めたいマンガを置いているのだ。
店舗が商店街から郊外に越しても変わらない、近所のオヤジの姿がそこにはある。厳しいのを承知で踏ん張っているオヤジの姿だ。そのオヤジの姿にわずか2週間で200名ほどの支援が集まった。みんながオヤジの次の一歩に期待を寄せている。そして(おそらくはあまり良い客ではなかった)筆者もまたそのひとりであり、くすみ書房の存続を願うものである。
くすみ書房への支援に関心のある方はこちらを参照してください
「くすみ書房がなくなる!?」特設サイト
■関連記事
・ワルシャワで、「家みたいな書店」と出会う
・キンドルを伏せて、街へ出よう
・本屋の未来と電子書籍の微妙な関係
・ボーダーズはなぜダメになったのか?






