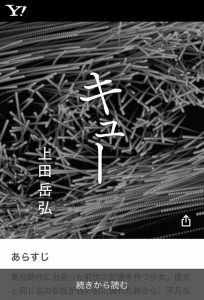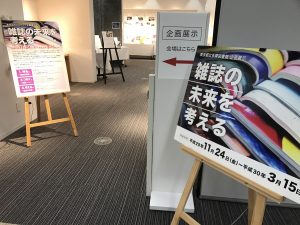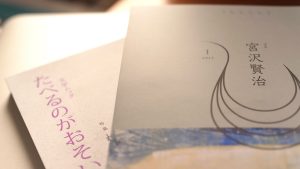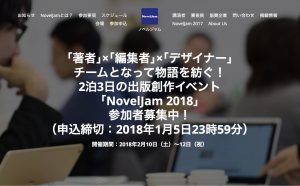以前のエディターズ・ノートでも紹介したように、文芸誌「新潮」2017年10月号から連載が開始された上田岳弘さんの長編小説『キュー』が、Yahoo! Japanの特設モバイルサイトにて並行して無料公開されている。しかもテーマは「シンギュラリティ(技術的特異点)」を通過した後の世界という、純文学としてはかなり突飛な設定だ。
従来の文芸誌とはことなる新しいチャネルで読者に作品を届けようとする姿勢に共感し、上田さんにはいつかお話をうかがいたいと思っていたところ、昨年の10月下旬に虎ノ門ヒルズで開催されたTORANOMON BOOK PARADISEという本のイベントにお招きすることができた。以下は、このイベントの際に「文学✕テクノロジー✕シンギュラリティ」という題名で行った公開インタビューを再構成したものである。

公開インタビューを行った「TORANOMON BOOK PARADISE」の会場
強度をもったテキストが未知の読者に「誤配」される
——「新潮」とYahoo! Japan、タクラムというデザイン会社の三者のコラボレーションとして『キュー』のネット無料配信プロジェクトが始まった経緯を教えてください。
上田 そもそものきっかけは、2015年に『私の恋人』で三島由紀夫賞をいただいたあたりで、Yahoo! Japanの岡田さん、西村さんと飲んでものすごく盛り上がったことです。Yahoo! Japanとしても創業20周年を迎える節目の年なので、ページビューやクリック率に還元できない価値を提供していかなければならない。お二人は僕の小説をとても気に入ってくれていて、その一つとして「小説もいいんじゃないか」という話になった。僕のほうではデビュー前から『キュー』というタイトルの長編を書きたいと思っていて、だったらこういう小説を書きたい、と提案しました。
そのときすでに「新潮」とも長編を書くという話をしていたので、ざっくりした方向感が出来あがってから「新潮」編集部に伝えました。彼らの指針は明確でしたね。第一に「それは文学のためになるか」を考える。その次に「作家のためになるか」、最後に「新潮」という雑誌や新潮社という会社のためになるかを考える。この順番で考えた結果、いずれも大丈夫なので乗りましょう、というのが「新潮」編集長・矢野さんの返答でした。
——開始後の反響はどうでしたか。
上田 このプロジェクトが開始した9月7日にYahoo!ニュースのトップ下に特設ページへのリンクが載り、数百万の露出がありました。10月現在で、十万単位のユーザーが小説に目を通したと聞いています。「誤配」という言い方がありますが、本来届くはずじゃなかった読者にも届いた。数字を例に出しましたが、しかし本質的なことは規模ではありません。バナーをクリックした先のサイトで、たまたま僕の小説を読んでみたら面白かった、という体験をした人がいたのであれば、このプロジェクトをやった価値があります。
インターネットで配信することを目的に、その読者層に寄ったものではなく、文芸誌に載るだけの「強度」をもった純文学のテキストが、このプロジェクトでなければ届かなかった人々に届いたときになにが起こるか。僕にとってはそれがこのプロジェクトの楽しみです。副次的な効果として、『キュー』の初回が載った「新潮」2017年9月号の売上も一割ほど増えたと聞きました。連載開始の発表会ではNHKや新聞各社、テック系のニュースサイトなど50社ほどに足をお運びいただきましたが、いろんなメディアでこのプロジェクトが話題になったことが、「新潮」という雑誌にとっても告知効果につながったのかもしれません。
そもそも「あまり小説を読まない人」にも二種類いると思うんですよね。一つは何をどうやっても読まない人。でも面白ければ読むという人や、「昔は小説も読んでいたけれど、いまはノンフィクションしか読まない」という人もいる。そういう人たちが今回の実験を面白がってくれて、一つでも二つでもその人たちの心に残る文章があればいいなと思います。
——純文学作品が電子テキストとして流通し、読まれていくことについては率直にどう思いますか。
上田 僕が大学生だった十数年前、電車に乗ってる大人はだいたい日経新聞を、学生はマンガや文庫本を読んでいました。でもいまはほぼ100パーセント、スマホですよね。これだけスマホの利用率が高まっているなか、純文学も当然そこに流れていくべきだろうと思っていました。
そうしたなかで今回の試みの特徴は、スマホでもあえて「ブラウザで読む」ということ。電子書籍のアプリケーションをインストールする必要がなく、URLさえ打てば、読んでほしいフォントで固定されたかたちでテキストが読める。電子テキストの読みやすさはこれからもどんどん進化していくでしょうが、今回は作品へのアクセスが最短距離で可能なところがもっとも斬新だと思います。

上田岳弘さん(写真提供:新潮社)
純文学は「無差別級」である
——作家デビューに至るまでの個人史を少し聞かせてください。
上田 上に兄や姉が3人いる、6人家族で育ちました。本が多い家でしたね。ジャンルもすごく雑多だった。そのうち兄や姉が学校で文字を習い始めて、まだ4〜5歳だった僕にも教えようとする。おかげで就学前からひらがなぐらいは書けるようになり、「これでお金をもらって生きていけるなら、それがいちばんいいじゃないか」と思うようになりました(笑)。そういう原風景的なものがあります。
その後は高校が理系コース、大学は法学部と文学とは逆の方向へと流れていき、大学卒業間際に「本当に作家になるのであれば、そろそろやらなければ」と思って、本格的に書き始めました。それまでも習作は書こうとはしていたけれど、きちんと最後まで書き終えられたのは22歳か23歳のとき。卒業後も2年くらい、「作家志望」ということでぶらぶらしていて、その後にIT系企業の立ち上げにかかわることになったんです。
——上田さんは兵庫県明石市のご出身ですよね。『キュー』では人類にとって戦争とは、原子力とは?という大きな問題が扱われます。これらテーマはご自身の阪神淡路大震災の体験となにか関係がありますか。
上田 原爆のことは誰でも小・中学校で習うと思いますが、僕の育ったあたりは修学旅行も広島・長崎コースなので刷り込みが強いのかもしれません。阪神淡路大震災のときはまだ向こうにいて、淡路島にあった両親の祖父母の家も、片方は大丈夫だったけれど片方は全壊してしまいました。震災のインパクトが大きかったのか、20代前半に小説を書き始めたとき、なぜか「生き埋め」のモチーフが毎回のように出てきた。『塔と重力』にも生き埋めのモチーフがありますが、あれはデビューして少し落ち着いたので、もう一回やってみようという感じで書いたんです。
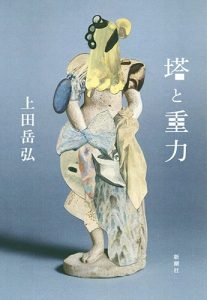
『塔と重力』(新潮社刊)
——「誰にも読まれないテキスト」というモチーフも繰り返し登場します。
上田 多分デビュー前に自分はこのまま誰にも読まれないで終わるのかな、という恐怖心があったんだと思います。デビューするかしないについては、今ではさほど重視すべきではないと思っていますが、当時はその恐怖心を執筆の動機付けにしていたような気がします。「太陽」の登場人物である赤ちゃん工場の工場主、ドンコ・ディオンムが書いていた「誰にも読まれないテキスト」は明確にその思いで書いていましたね(笑)。
——いまは「小説家になろう」という小説投稿ウェブサイトもあり、文芸誌で新人賞をとる以外のデビューへの道筋ができはじめています。また円城塔さんや宮内悠介さんなど、SFと純文学の両方の世界で評価される現代作家もいます。上田さんの場合、文芸誌以外、たとえばSFというジャンルからデビューする、という選択肢はありえましたか?
上田 あまりSFのつもりで書いていなくて、僕が普通に小説を書くとこうなってしまう、というのがいちばん実感に近いんです(笑)。純文学は格闘技でいうと「無差別級」、つまり何でもありの世界であって欲しい。なのでデビューするなら純文学がいいなと思っていました。ジャンル小説だとどうしても過去の作品を参照して書かなければならないと思うんですが、純文学の場合、文学として成り立っているか否かだけが問われるべきです。
よく「器」という言い方をするんですが、同じ料理でも器によって受けとめられ方が違うように、まったく同じ文章でも、SFのレーベルから出るのと純文学のレーベルから出るのとでは受けとめる人の気持ちが違う。「純文学」という器に入ってテキストがやってくると、「これはすごいものかもしれない」と思って受け取る側も読む。要は単に読んでいて楽しいかどうか、と言う尺度では読まない。そうやって読んだもので心が動いたとき、何かが発生する——それがあえて「純文学」をうたった作品群の無視できない重要な機能だと僕は思っているんです。今回のプロジェクトも、その前提がなかったら始まっていないような気がします。
——どういう読書歴から、そうした文学観は培われてきたのでしょうか。
上田 完全に乱読タイプですね。いちばんはじめに読んだ純文学作品も、姉や兄が家で読んでいた村上春樹さんとか吉本ばななさんの本でした。本気で作家になろうと決めたとき、自分が「文学っぽい」と思った本を大量に古本屋で買ったり図書館で借りたりして、一年で200冊くらいをまとめ読みしたことがあるんです。そのときに夏目漱石、フヨードル・ドストエフスキー、ウイリアム・シェイクスピアの全作品を読みました。あの頃の読書体験が、いまの自分にとっても創作のベースになっています。
物語の構造に「手が触れる」瞬間
——上田さんの小説の持ち味となっている、ある意味で「ほら話」とも思えるほど宇宙規模に広がる発想の壮大さや、すべてを見通すかのような視点はどこから生まれてきたのでしょう。
上田 小学校に入る前から、妄想的というか、壮大なことを考える子どもでした。もしかすると、それからずっと成長していないのかもしれません(笑)。さきほどの「無差別級」と同じことですが、せっかく書くならすべてを包含したもの、いちばん「外側」のものを書きたい性格なんです。
いまは偶々こういう形になっているものも、もしかしたら違った形でありえたかもしれない。人間は現在はこういう姿をしているけれども最初はどうだったのか。クロマニヨン人と現生人類とでは、脳の性能はあまり変わらないのに、クロマニヨン人の時代と現代とはまったく違う社会になってしまっている。であれば、十万年先の人類社会も当然、いまとはまったく違っているだろう。そんなふうに「フラットに見るとこうなるんじゃないか」という見方をすることに喜びを覚えるタイプなんです。
たしかミシェル・ウエルベックさんの小説で、いきなり機械の描写を延々と続けることを想像する箇所があります。『地図と領土』だったかな?これを書いて小説になるのか?というような描写なんですが、ウエルベックさん自身が楽しんで書いている。僕もそんなふうに執筆自体を楽しんでいるところがあります。
——今回の『キュー』のようなスケールの大きな作品は、事前にある程度まで構想を固めてから書きはじめるのでしょうか。
上田 作品の細部は、事前にあまり考えないようにしています。『キュー』の場合も、まず「キュー」という音が頭にあって、あとは戦争について書くことになるだろうという直感だけがありました。面白いもので、書いているうちに、読まなくてはいけない本に行き当たるんです。
「太陽」を書いてるときも、最後のほうでゴットフリート・ライプニッツの『単子論』をどうやら読まなければならないとわかった。いま自分が考えていることについて、昔の偉い人も何か言っているに違いないと思って調べていくと、ああライプニッツさんが何か言ってるな、とわかる。『キュー』の作中のキーワードを使うと、《言語の発生》から随分時が経過し、一周目の思弁はやりつくされていますから、いま・ここ・自分を材料に再思弁をおこないオリジナルなものをつくるためには、そうやって時代を逆流し、吸収しながら書いていくほうが効率がいい。逆流することによって差分が明確になり、オリジナリティも担保されるようにも思います。
——シンギュラリティの是非はともかくとしても、ITの発展はここ数十年でいちばん大きく社会を変えた要素です。ITに近いところで仕事をしてきたことは、作品にもなにか影響を与えていますか。
上田 いまから30年前だったらテレビ関係や出版関係などのメディア業界がそうだったのかもしれませんが、僕が大学を卒業した15年ほど前は、IT業界が「とりあえず大学を卒業しました」という僕みたいな人間の受け皿になっていました。IT工学がいまの社会に必要とされていることを仕事のなかで学んでいったので、そこで得たものが小説にも反映していくということはありましたね。
あと、素朴に思うのは現時点が文明開化以後の日本社会において、最大の変革期にあるのは間違いないだろうな、ということです。『異郷の友人』でも扱いましたが、僕は文学の起源を『古事記』などの神話にみています。神話が編纂された当時、原始的な国家が成立していくという社会的な大変動のかげで、集合的無意識が物語を希求した。今書かれるべき文学ももしかしたら、神話的なものに接近していくのかもしれないと感じますね。
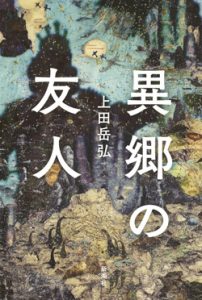
『異郷の友人』(新潮社刊)
——小説はいつ、どのように書いていますか。
上田 出社前に2時間くらい書く。それをシンプルに毎日繰り返してます。そうやってルーチンにして、書くということを今のところはしています。そろそろアレンジを加えようかなとは思っていますが。毎日1500字なり2000字なり、作品によって一日に書く字数を決めて書いていくんですが、ときどき新しい展開が必要になるので、そのときは火事場の馬鹿力でがむしゃらに書く。すると、物語の大きな構造にふと「手が触れる」瞬間があるんです。この感触はなんだろう、と思いながら、それを引き寄せてつつ書いていく感じです。
子どもの頃から、なんとなくこういうふうにやりたいな、と思った感触のまま小説を書いている。だから自分でも、なぜ小説を書いているのかはよくわからないのだけれど、小説を書くことで十分に悩んでいるせいか、生活のほかの部分ではあまり深く悩まず、気楽に生きていけるような気がします(笑)。
——今後、「普通の小説」を書くということもありえますか。
上田 できれば『キュー』が終わったら書いてみたい。というか、『塔と重力』も「普通の小説」のつもりで書き始めたんですけど、なんだかよくわからない要素が入ってきてしまったので、どうなるかはわかりませんが(笑)。
シンギュラリティは意外と「大丈夫」?

「TORANOMON BOOK PARADISE」の会場風景。
——最後に会場からの質問をいくつかお受けします。
(質問1) 『キュー』には「ドナルド・トランプ」のような、雑な固有名が出てきますね。これは同時代の読者には強い引きになる半面、時が経つと色あせ、普遍性から外れてしまう怖れはありませんか。
上田 あえて固有名をテキストに混ぜ込むことで、作品が全体として普遍性をもちえているかどうかの強度チェックをしているんだと思うんですよね。おっしゃるようにドナルド・トランプさんみたいな、雑に見える固有名を出しつつ、それでも文学として読めるかどうか、というような。
(質問2) 同時代の小説家で好きな作家や影響を受けた作家はいますか。
上田 英語の作家だとイアン・マキューアンさんは好きですね。フランス語の作家ならミシェル・ウエルベックさんが好きです。最近ならローラン・ビネさんも良かった。
日本語の作家では町田康さん、保坂和志さん、松浦寿輝さんの作品は、さっき挙げた乱読期に読んで衝撃を受けたのを覚えています。保坂さんの作品で最初に読んだのは『生きる歓び』だったと思います。堂々としたタイトルに惹かれて手に取ったんですが、「そもそも小説とは何か」を考えるにあたり、重要な出会いになりました。表現は難しいですが、それまでの僕に足りていなかった座標軸がすっと加わったような感覚です。
あと、これも同時期に読んだのですが、山田詠美さんのエッセイで「何の取柄もない男に黙ってても女が寄って来る小説に納得がいかない」という趣旨のことが書かれてあって「そうだよな」と肯いてしまって(笑)。僕の小説の語り手像に影響をおよぼしているかもしれません。創作意欲を掻き立てられるという意味では、仲良くさせていただいている俳優や劇作家の仕事から刺激を受けることも多いですね。
(質問3) 紙からデジタルへと出版だけでなくコンテンツ全体のエコシステムが変わっていくなかで、三島賞やGrantaのベスト企画といった顕彰システムはどこまで書き手にとってのモチベーションでありつづけると思われますか。
上田 《インターネットの発生》以後の世界では情報の蓄積性が高い上に、全ての情報が並置されますから、賞の一回ごとの印象はどうしても低下していくんだろうと思います。文学や文学賞に向けられる世の中の関心の総量には限度がありますから、これはどうしようもない部分がある。でも現実問題として、賞でも取らないとそもそも注目を集めにくいので、ほしいと思っている書き手は多いと思います。
(質問4) ウェブコンテンツがPV至上主義になっているなかで、純文学とウェブの組み合わせは今後どうなっていくと思いますか。
上田 音楽の世界ではCDは売れなくなったけれど、人が音楽を聴いている時間や種類は増えたと言われています。どうやってお金を回収するかを脇に置けば、全体の流れとして、文学も音楽と同じ方向に近づいていくだろうと思います。ただ、持ち運びのしやすさを抜きにすれば紙のほうが読みやすいという人は今でも大多数でしょうし、僕も紙の本を読むことが多い。ネットと紙の配分は日々変わっていくだろうけれど、そのなかで純文学がどれだけ尖った存在であり続けられるのか、ということのほうが大事だという気がします。
(質問5) シンギュラリティの文学への影響は?
上田 専門家ではないのであくまで直感でいうと、なにが起こっても意外と大丈夫だと思うんです。ようするに、そのときには「大丈夫」の基準が変わってしまうだろう、と。コンピュータが人間の創造性を超えたとしても、人間の側は大したことが起こっていないように感じるのではないか。いまの視点からは「大丈夫」じゃないように思えても、未来のその時点では、あんがい「大丈夫」なんじゃないかな、と(笑)。
当然、文学の制度はどんどん変わっていくだろうし、作品を波及させていく方法も同時に変わっていくでしょう。でも、「文学」はようするに「書かれた文字」ですから、たとえ出版社がなくなろうと、作家が書きつづけてさえいれば残る。そのとき、どういう残り方があり得るか考えたりもします。
(質問6) 文学とAIの能力がもし対立構造にあるとしたら、それを宥和させる道筋はあるでしょうか。AIと人間が共同制作するアートがすでにありますが、文学もAIと共同で書くとクオリティが向上したりするでしょうか。
上田 AIとの共同制作によって、「人間にはその発想はできなかった!」というものも生まれてくるでしょうね。でも当分は、その表現の主体は人間である時間が長く続くと思います。いずれはその部分も侵食され、人間の側がそこを最終的に譲り渡すかどうか、どちらかと言うと政治的な判断になると思う。その政治判断はおそらく一種の多数決になるでしょうが、その結果がどうなるのかが個人的には楽しみだったりします。ふわっとした回答で申しわけありませんが、ぼんやりと見えているものはあります。まだ言語化できてはいませんが(笑)。
——上田さん、本日はありがとうございました。
(聞き手・仲俣暁生、虎ノ門ヒルズにて)