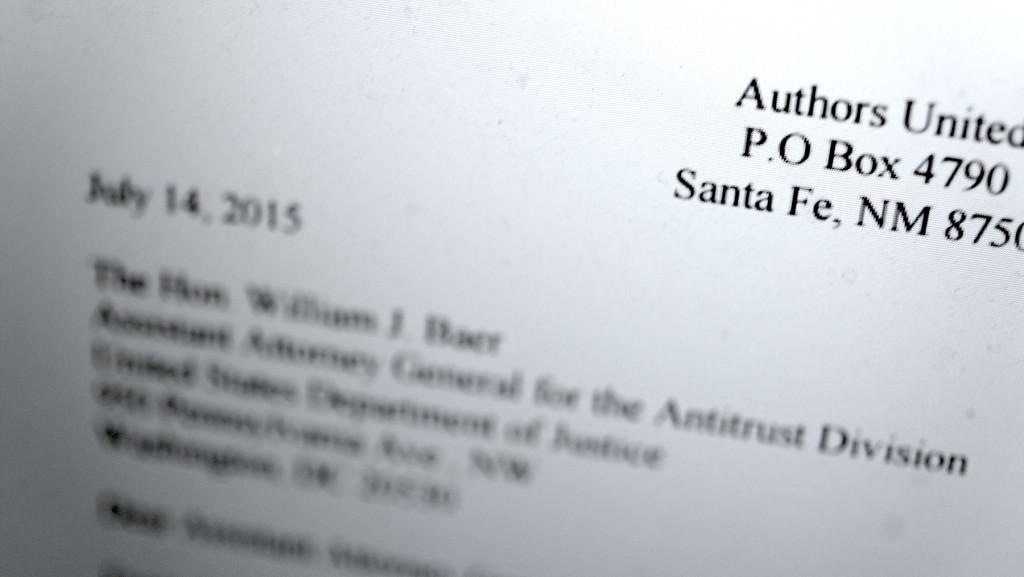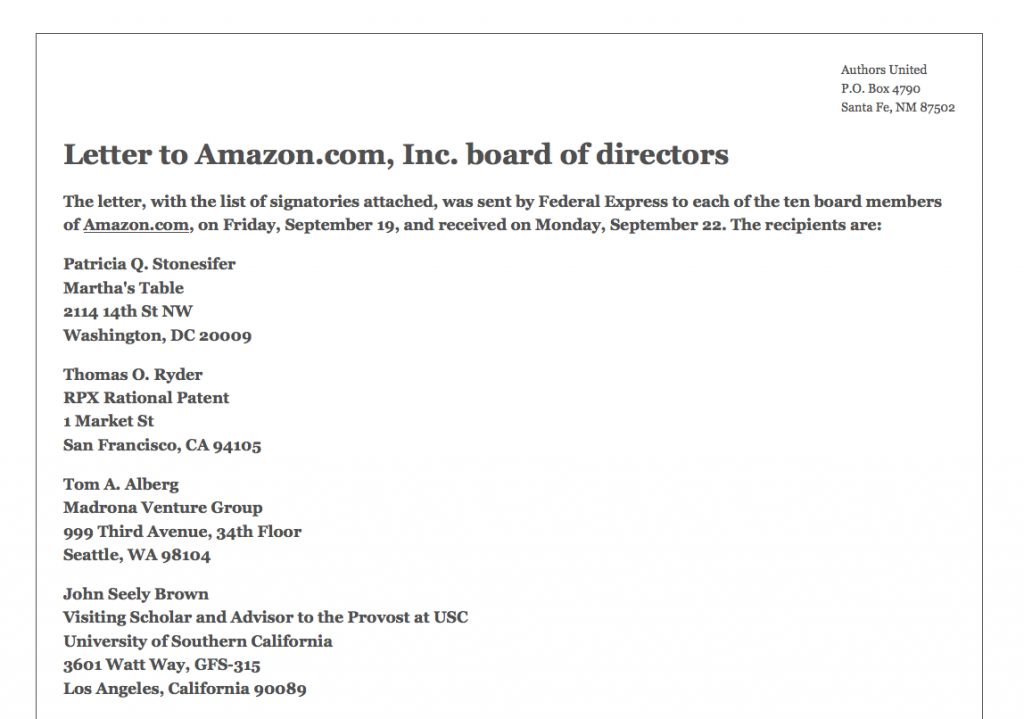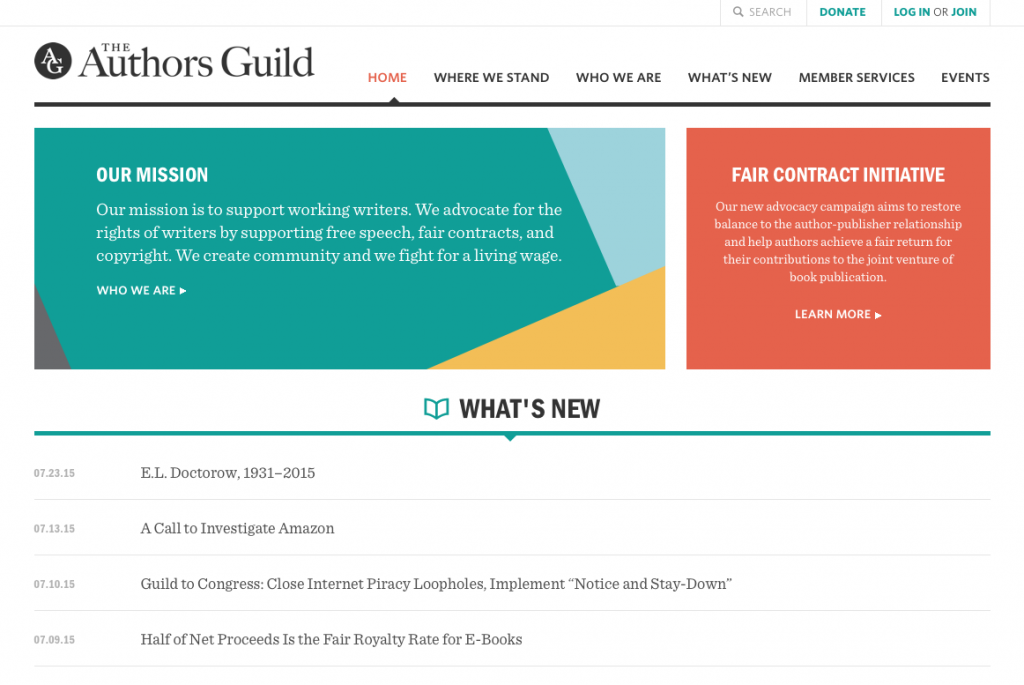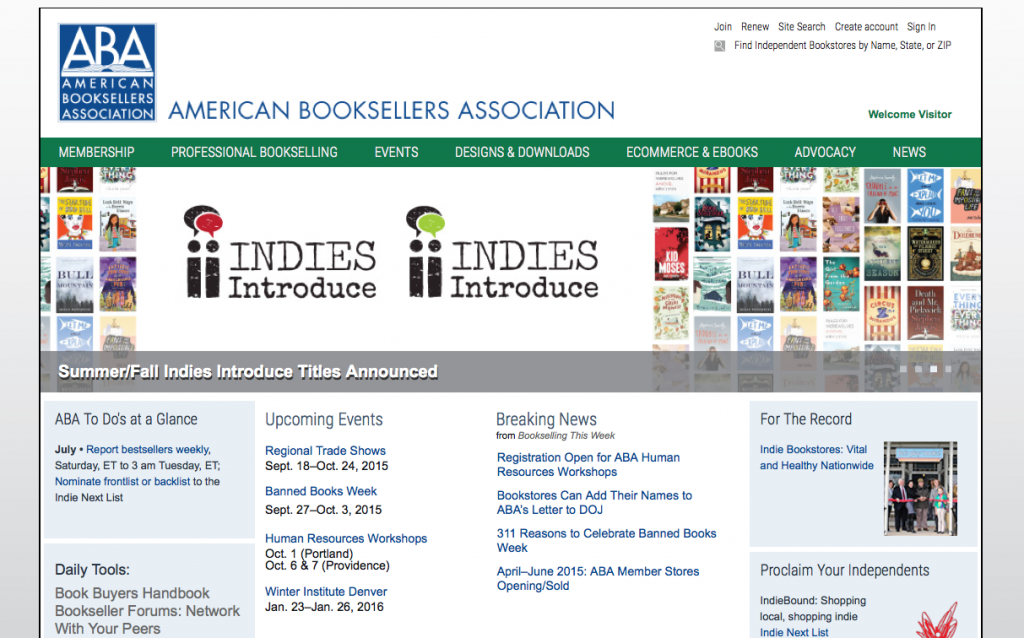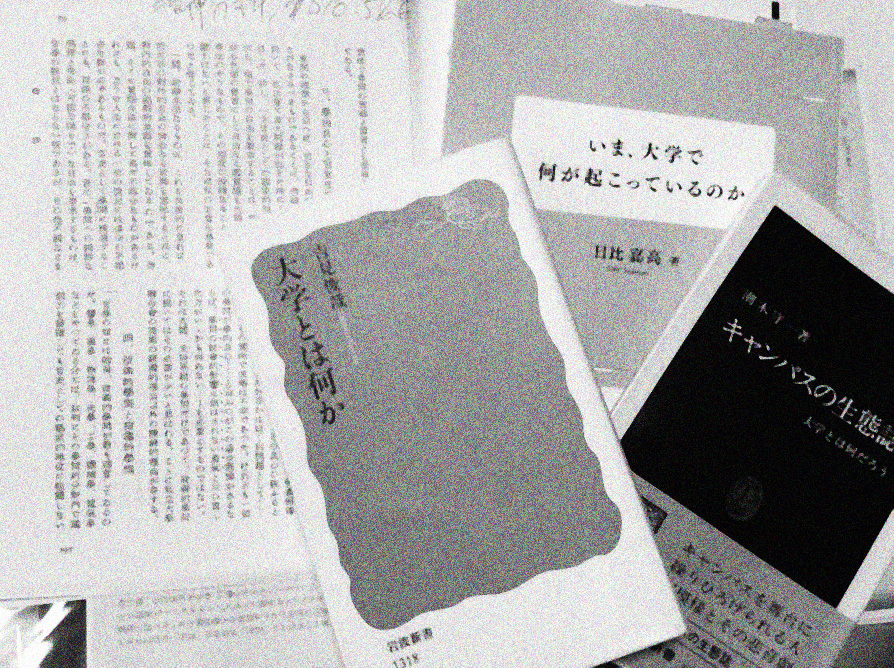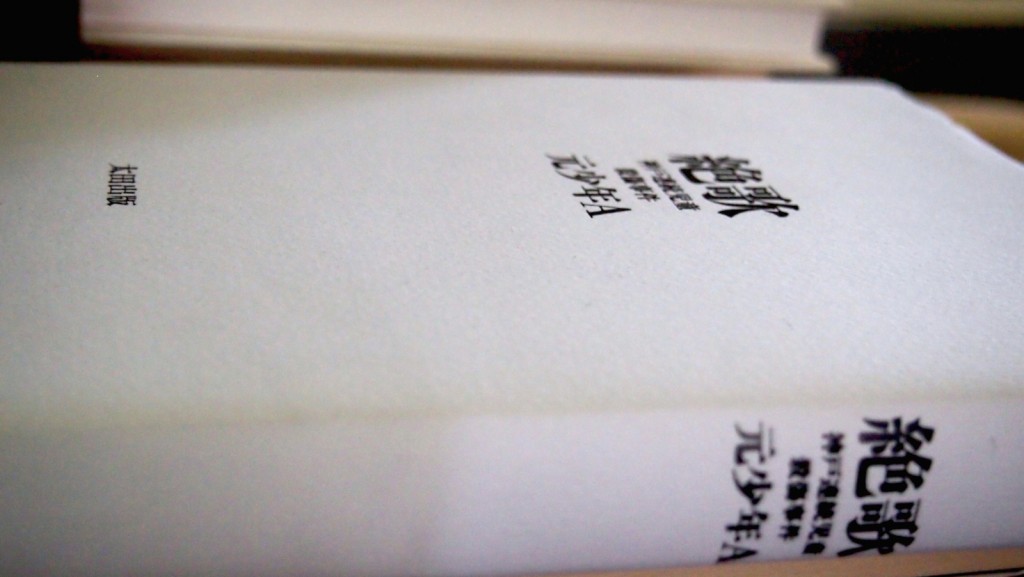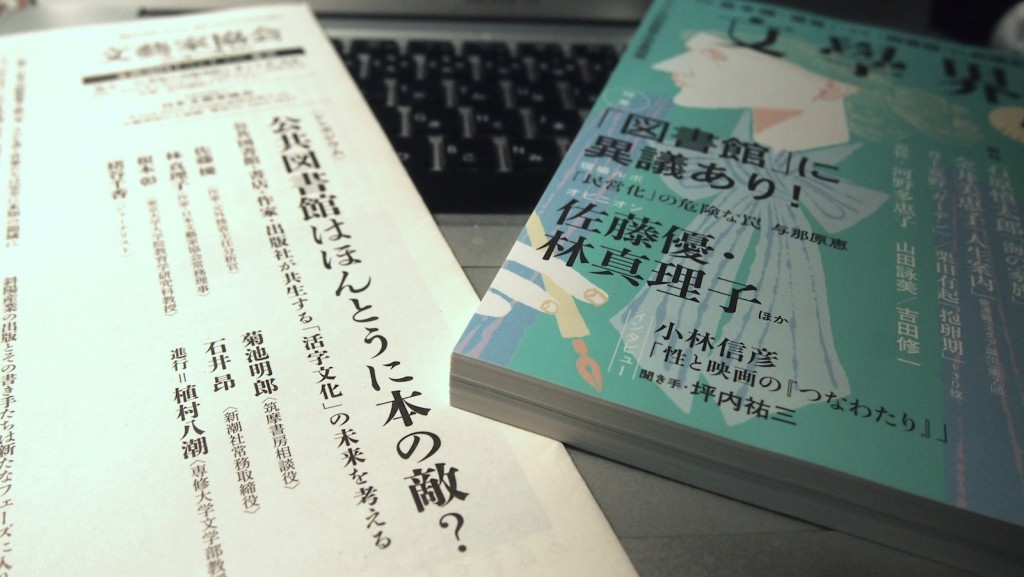私の肩書の一つは、フリーライブラリアンです。「図書館外で図書館司書のようなはたらきをする人」という意味で、数年前から使っています。
きっかけは、二つありました。一つ目は、司書のはたらきは人から必要とされている、けれど届いていない、と感じる出来事があったこと。当時勤めていた大学図書館でのレファレンス(調べものの手伝い)について友人に説明すると「図書館の人にそんな質問してよかったの?」という反応をされることが、たびたびありました。図書館を利用していないわけではない友人たちの反応から、司書にできることが世間で知られていない、知られていないがために活用されていない、と感じました。
「かかりつけの司書」となるまで
そうこうしているうちに、ある年配の社会人大学院生との間で、印象に残るやりとりがありました。社会人入学をされるくらいだから、とても熱心な方です。レファレンスでは、単に質問内容だけを聞くのではなく、基本的な調べ方をとばしていきなり高度な調査方法に入り、結果的に身につかないといったことのないように、あるいはすでに質問者が知っている内容と重複しないように、質問者がどんな調査手段を知っているか、これまでどんなことを調べてきたかを図書館員の側から聞くのですが、この院生さんからは、すでに複数の図書館を回ってかなりの資料に触れてこられたことが、ありありと伝わってきました。
にもかかわらず、会話がかみあいません。おかしいなと感じながらやりとりを続けて、もしかして?と思った私は 「NACSIS Webcat(現CiNii Books。全国の、主に大学図書館などの本や雑誌を横断して検索できる)」は利用されていますか?」と尋ねました。院生さんは、NACSIS Webcat を知らなかった。たくさんの図書館を一括して検索できることを知らず、欲しい資料をもっていそうな図書館に目星をつけては、一館一館検索していたのです。
私がNACSIS Webcat について説明した後、院生さんはしばらく沈黙し「……私は……いままで……いったいどれだけの時間を無駄に……」と言いました。あの声が忘れられなくて、私はいまも、フリーライブラリアンを続けているのだと思います。
厳密に言えば、横断検索サイトではヒットせず各館の検索サイトにのみ出る資料もあるので、完全な無駄ではありません。けれども、資料を集めるための膨大な時間があるなら、資料を読むために使いたいはず。便利に発達した図書館サービスと、そのサービスを必要とする利用者が結びついていないことを感じて、強い違和感が残りました。
これだけであれば、大学図書館で働き続けて利用者と資料をつなぐことに尽力する道もあったのですが、他にも疑問点がありました。出版社に勤めないで編集したり執筆したりする編集者やライターはいるし、フリーランスのキュレーターは数は少ないけれど存在するのに、どうして司書は、常にどこかの建物や組織に所属しているのだろう?という疑問です。
ちょうどこの頃、物理的な資料や物理的な場所としての図書館がなくなった場合に、それでも司書は何をするだろうかということを考えてもいました。つきつめて考えていくと、司書のはたらきとは、ある資料と、それを必要としている人をつなぐことではないか。それができれば、司書はどこにいてもよいのでは。それなら、図書館に所属していなくても、一人でもできると考えました。これが、二つ目のきっかけです。
こうして、大学図書館員時代に勤務と並行してフリーライブラリアン活動を始めました。活動と言っても、私の場合はごくこじんまりと、友人知人に、調べたいことがあったら聞いてほしいと直接会ったときやSNSで伝えておいて質問がきたときに対応するか、SNS上で流れている疑問(場合によっては知らない人に対しても)に勝手に論拠をつけて答えたり、といったことが主です。
たとえば、欲しい本が最寄り図書館で見つからない、ある洋書の入手方法がわからない、ある単位の発音が知りたい、ネット上で読めるこれこれこういうテーマの論文が欲しい……など。高度なものになってくると海外の図書館に質問したりすることもあるので、イメージ的にはかかりつけの医者ならぬ、「かかりつけの司書」。図書館が不要とか図書館員としての司書が不要とかいう話ではもちろんなく、実際には図書館のツールを使う機会も多く、図書館との橋渡しのような存在、図書館も行っているような、さまざまな専門機関との橋渡しのような存在でもあります。
調べ方講座から見えてきたこと
調べものに取り組んでいそうな友人に対して、こちらから提案して調べ方講座を行うこともあります。ゲームクリエイターである友人に対して最近行った調べ方講座では、フリーライブラリアン活動を考える上で参考になる点がありました。
まず、事前に聞き取りを行います。普段の調べ方や、現在調べているテーマについてあらかじめ回答をもらい、それをもとに、調べ方のコツから相手の知っていることを抜いてカスタマイズした入門編と、いまの興味に沿った応用編とを準備します。
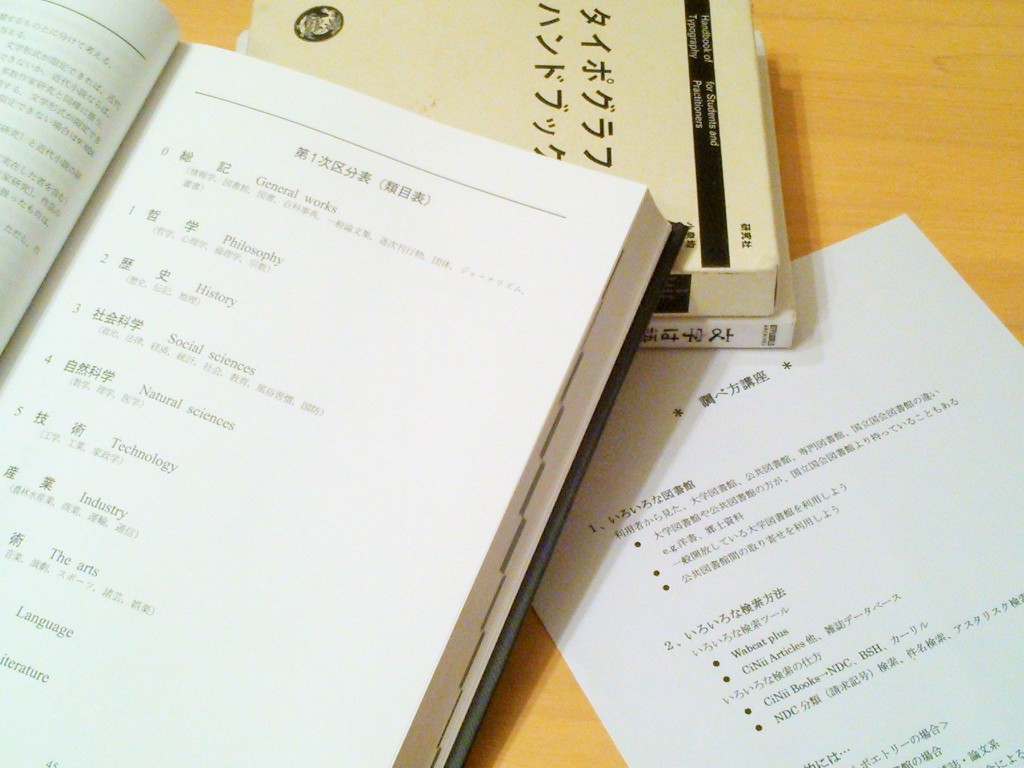
「調べ方講座」を行った際のレジュメと資料。
具体的には、前者はさまざまな図書館の紹介、請求記号(本の背ラベルの記号)の仕組みの説明、請求記号や「件名」というもので検索すると「なんとなくこんな感じのこと」を書いた資料を探すのに便利であること……など。今回の要望は「ゲーム画面作りの参考のためのタイポグラフィやコンクリートポエトリーの資料」と比較的専門的だったので、専門図書館や一般の人でも利用しやすい大学図書館の紹介も行いました。
後者は、前半の実践が中心です。相手がいま知りたい分野に有効な請求記号の書架をざっと見たり手にとったりして、自分の知りたい内容に対して複数の請求記号(書架の配置)がありうることを実感してもらったあと、目的に適したデータベースを使って検索演習を行います。たとえば、コンクリートポエトリー(言葉の内容だけでなく、文字の形や空間配置などにも注目し、視覚的な効果も考えた詩)のようなマイナーなテーマでは丸々一冊本のテーマになっている可能性は低いことから、一般雑誌を含めた記事検索や、検索結果から目当ての記事のコピーを取り寄せる方法などを紹介しました。
この講座から見えてきたり再確認したりしたことは、第一に、調べることがあって図書館に来ていても、本は借りていても、図書館員には質問しない場合があるということ。この友人は学術論文の検索もしたことがあるほどの図書館ユーザーだったにもかかわらず、質問したことはなかったと言います。また、それと関連してか、知りたいことの載った記事だけを取り寄せるという発想はなく、一冊まるごと買っていたので、費用的にも負担だったそう。こうしたことも、利用者と図書館員の間でのやりとりが早くからあれば、違った可能性があったかもしれません。
第二に、当たり前ですが、研究者でなくても、物事をしっかり調べたい人はたくさんいて、しかしその人たちが調べ方を学ぶ機会は少ないということ。もちろん、リサーチャーや記者を筆頭に、調べることに精通した方はどこにでもいるわけですが、学校においても、学校卒業後においても、図書館情報リテラシーに触れる機会はまだ少なく、個々人の努力によるところが大きいのが現状のように思います。
第三に、意外に喜ばれたのが、調べ方云々以前に、専門図書館という存在を知ったことや、普段行くのとは違う大きな図書館に行く経験自体だったということ。この講座は友人の最寄りの図書館ではなく、友人の求めているマイナーな資料をまとまった量、書架で手にとって見ることができ、かつ図書館での並べ方が一通り分かるように、広尾の都立中央図書館で行ったのですが、結果として、図書館は一館一館違い、違う図書館に行けば自分の欲しい資料が思ったよりたくさん存在する可能性もあることを知って、他の図書館に行ってみたくなったそうです(実際にそのあと最寄り以外の図書館に足を運んだそう)。
複数の図書館に足を運ぶことで、入手できる資料はずいぶん変わってくるし、規模も蔵書の傾向も見せ方も活動もさまざまな図書館と出会う楽しさを味わえたり、地元の図書館をよりよくしていく意見が出せるような視点が育ったりもするでしょう。調べ方、と肩ひじ張らなくても、いつもと違う図書館に行ってみるツアーを行うだけでも、図書館や情報収集に対しての意識は変わるのかもしれません。こうした小さなこと一つとっても、まだまだ資料と人をつなぐ余地がありそうです。
「司書」を再定義する必要
ここまで読んで、自分もやっている、自分の方がもっとやっている、少し違うが似たことをしている、という方もおられると思います。そのとおり、私はフリーライブラリアンという名前で呼んでいますが、別の名前をつけて、あるいは名前をつけないまま、あるいは意識しないままフリーライブラリアン的な活動をしている人は、確実にいるはず。
私の周辺でも、大学図書館勤務ののち、別の部署に異動しつつも、司書能力を発揮して講習・講演や論文執筆を行っている人、司書資格を取得後、図書館には就職しなかったが、会社で後輩に資料の作り方を教えることまで含めて司書活動ととらえて行っている人など、自分の持ち味や居場所を活かして活動している人たちがいます。
こうしたフリーライブラリアン活動が増えてほしいし、認知され、利用されてほしい。図書館勤務経験や司書資格が必須というわけではないですが、たとえば元図書館員、あるいは図書館員になる勉強をしたが図書館員にはならなかった人だけでも、潜在的なフリーライブラリアンは大量にいます。
もちろん、どんな資格も、資格取得後にその能力を職業と直接結びつけないことはあるし、そのこと自体が問題なわけではありません。しかし、目的の情報にたどり着くまでの道のりが便利なようで複雑化し、自覚的、無自覚的に情報収集に困っている人がいる中で、司書の素地をもった人には、少なからぬ需要があるのではないでしょうか。
情報を取得し活用することがますます重要になっていく中で、図書館自体もさまざまな要望に応えていくでしょうし、フリーライブラリアンにも幅が生まれ、高度な質問に応えて職業化していく人もいれば、私のように、細く長く身近な場所でやっていく人もいると思います。今回は調べる機能を中心に書きましたが、私の活動で言えば、「知りたいこと」を書かれたものからの知識として提供するのではなく、体験するという形で提供するために、イベント開催も行っています。面白かった本を紹介してほしいという友人の要望で、メルマガを出していたこともあります。世の中にはいろんな図書館があるし、いろんなフリーライブラリアンがいていいと思います。
そもそも司書とは何でしょう(文部科学省のサイトでの説明はこちら。Wikipediaの解説はこちら)。図書館員とは、図書館で働いている人です。しかし、司書であるということは、必ずしもある図書館に勤めているということではなく、問題解決の仕方が司書的であるということではないでしょうか。これは仕事本来のあり方だと思います。世の中に足りないものがあったら、製造者が物を作り、販売者が商品を売るように、足りないことがあれば、サービスが埋め合わせるように、司書はあらゆる場所で、これらのことすべてが起こるのに必要な情報を巡らせ、新たな知識や実践の誕生を活発化させます。
フリーライブラリアンをしようと思ったのは、図書館にいて利用者を待つというスタンスではなくやりたいことがあったから。図書館の中にいてこそできることもあるし、中から外に働きかけることもできる。公共図書館、大学図書館、専門図書館、そしてその中の一つ一つの図書館には、それぞれの役割があり、場をもっている図書館ならではの特性や、周囲と連携した働きがあります。一方で、自分のまわりで情報に困っている人を見つけたほうが、自発的には来なかった人に伝えられる場合もあると思いました。
あるサービスを知らない人は、自分からそのサービスを利用したいとは言いません。けれどそれは、そのサービスを利用したくないとか、必要としていないとかいうことではない。司書には、司書自身が思うよりも、すでに図書館を利用している人が思うよりも、そして図書館を利用していない人が思うよりも、きっとまだまだ、やれることがあります。