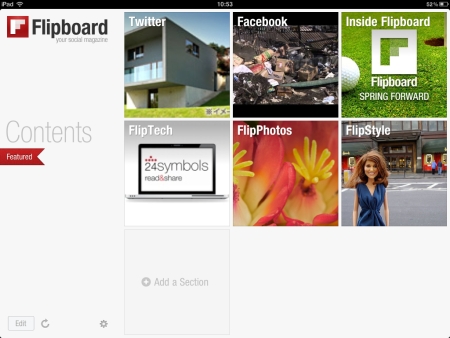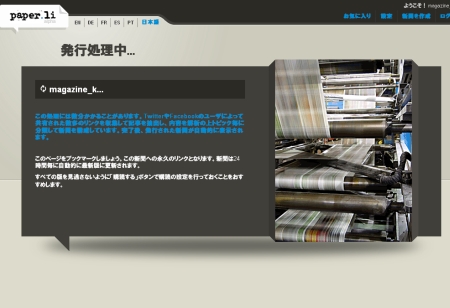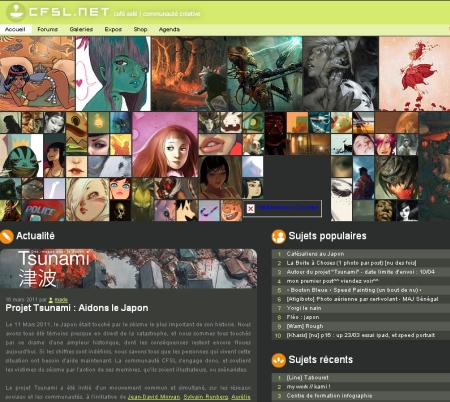日本の電子書籍の問題を考える上で、「青空文庫」の存在と、彼らが培ってきた過去の経験ほど大きな示唆を与えてくれるものはありません。日本でも昨年から、商業的な電子書籍のプラットフォームがいくつも登場していますが、ご存知の方も多いように、青空文庫はこれらとはまったく異なる発想で生まれたものです。
青空文庫は、著作権保護期間がすぎた日本語のテキストを、インターネット上に保存・整理・公開している無償のテキスト・アーカイブです。著作権切れのテキストだけでなく、著者自身がネットでの無償公開を認めたテキストもふくめ、2011年の現時点で9989点の作品が収録されています。1万点の大台まで、あとわずかというところです。[追記:2011年3月15日に1万タイトルを突破しました。]
直接にこのサイトにアクセスしたことがない人でも、iPhone/iPadアプリのさまざまなブックリーダーや、ソニーが発売したReaderなどを通して、青空文庫の本を読んだことがあるかもしれません。青空文庫の存在は知らなくても、紙の本でいまも有料で売られている作品が、電子書籍としてタダで読めるのはなぜだろうと、不思議に思った人は多いと思います。
これら無償のコンテンツが電子書籍の普及に欠かせないことは、アメリカでもグーグルやアップルがパブリックドメインのテキストを、電子書籍サービス立ち上げ時の目玉のひとつに据えていた事実からもわかります。
テキスト・アーカイブは誰がつくっているのか?
青空文庫がモデルとしたアメリカのプロジェクト・グーテンベルクは1971年にイリノイ大学のスーパーコンピュータを使って始められたもので、インターネットをつかって電子書籍/電子図書館の試みとして最も歴史のあるものです(ウィキペディアによる詳細な解説はこちら)。彼らのウェブサイトによると、去る3月1日にこのプロジェクトの内部で制作された電子書籍のコンテンツが4万タイトルを数えたそうで、創設者であるマイケル・ハートがこのことを発表しています。
The Year of the eBook – Project Gutenberg News
プロジェクト・グーテンベルクが40年かけて4万点なのに対し、1997年に開始された日本の青空文庫は15年足らずで約1万点ですから、十分胸を張れる数字です。
ネット上で無償で公開されている電子書籍コンテンツとして、ほかにウィキペディアがよく知られています。底本となる紙の本が存在しないため、ウィキペディアが「電子書籍」と呼ばれることは少ないですが、2001年にスタートしたこのインターネット上の百科事典プロジェクトでは、英語や日本語をはじめ世界中の270以上の言語で、のべ1600万項目以上が記述されています。現実的な利用価値やコンテンツの量を考えると、世界最大の電子著作物といっていいでしょう。
青空文庫やプロジェクト・グーテンベルク、ウィキペディアなどの存在が貴重なのは、たんにコンテンツがタダで読めるからだけではありません。電子書籍のさまざまなアプリケーションやサービスを構築するには、自由につかえるコンテンツがあらかじめ潤沢に用意されていることが、どうしても必要です。
とくに電子書籍ビジネスの立ち上げが遅れた日本の場合、商用の巨大なプラットフォームが登場するはるか以前から、すぐれた日本語ブックリーダーのアプリや、キンドルなどで読みやすいPDFへの変換プログラムが生まれてきたのは、青空文庫によって書誌データ付きの無償のコンテンツがあらかじめ大量に蓄積されていたことと、決して無縁ではありません。
ところで、青空文庫やプロジェクト・グーテンベルクのコンテンツは、誰がどのようにして作っているのでしょうか。これらはいずれもボランタリー・スタッフによって運営されている、非営利のプロジェクトです。だれもが自由かつ無料で利用できるだけでなく、送り手としても貢献できるのが大きな特徴なのです。
青空文庫の場合、底本の選定からコンテンツの入力・校正までを行っているのは、「青空文庫工作員」と呼ばれる人たちです。このメンバーになることによって、誰でも青空文庫のコンテンツの充実に寄与することができるという点で、ウィキペディアとよく似ています。「青空文庫工作員」となるためのマニュアルが青空文庫のサイトで公開されていますので、興味のある方はご覧下さい。
さて、ここからが今日の本題です。
青空文庫工作員の一人で、2007年から『週刊ミルクティー*』という電子出版プロジェクトを行っている、しだひろしさんから「マガジン航」宛てに連絡をいただきました。『週刊ミルクティー*』は青空文庫ですでに公開されている作品や、公開前のテキストを編集して、ボイジャーのT-Timeで読める形式の電子書籍として配信しています。とくに旧字旧かなのオリジナルと、現代表記におきかえたテキストの2パターンでコンテンツを同時収録していることが特徴です。
最新号が出たので「マガジン航」で紹介してほしい、というのがお送りいただいたメールの趣旨だったのですが、こちらで書き起こして記事にするよりも、ご自身の言葉で、これまでの活動について書いていただくのがよいと思い、そのように返事を差し上げたところ、さっそく長い文章をいただきました。この文章を「読み物」コーナーに「週刊ミルクティー*の活動について」という記事として公開しましたので、ぜひご覧下さい。
電子出版の二つのあり方
「週刊ミルクティー*」の活動で驚いたのは、毎号の電子書籍の付録として、本文の解説に役立つ語句をウィキペディアから集め、もうひとつの電子書籍を作っていることです。青空文庫やプロジェクト・グーテンベルクのような文芸作品が中心のテキスト・アーカイブと、ウィキペディアのような客観的な事実を扱ったテキストとを組み合わせた、ハイブリッドな電子出版があり得ることを教えられました。
海外ではすでに、ウィキペディアのコンテンツを自分で編集して、オンデマンド印刷による紙の本やPDFとして手に入れることができる、Pedia Pressというサービスが始まっています。ネット上にパブリックドメインのコンテンツがたくさんあるということは、タダで読めてありがたい、ということにとどまらず、そこから二次的な編集著作物がさまざまに生み出せるということでもあるのです。
この投稿の続きを読む »