今年のゴールデンウィーク、ちょうど瀬戸内国際芸術祭の春会期と夏会期の間の比較的観光客の少ない時期に小豆島を訪れた。目的は主に、小豆島を起点として数日間瀬戸内に滞在し、アート作品を堪能しに行くためだ。

小豆島の名物、ヤシの木。
フェリーで土庄港に着いて海岸沿いへ向かうと、ヤシの木や白い砂浜、瀬戸内海の穏やかな海が迎えてくれた。芸術祭に訪れる観光客が、こうした瀬戸内の自然や時間に癒されるのがよく分かる。到着してからはさっそく、現代芸術活動ユニット「目(め)」の作品や、ワン・ウェンチーの地元産の竹4000本を使った巨大ドーム作品「オリーブの夢」などを見て回った。しかし個人的にいちばん印象的だったのは、ちょうどその時期に開催されていた「肥土山農村歌舞伎」だ。
農村歌舞伎とはその名の通り、地域の住民が毎年手作りで生み出す伝統的な歌舞伎で、歴史も長く、会場となる舞台も趣深く、なにより地元のお年寄りが前方の席に陣取って、化粧をして綺麗な着物を着て台詞回しをする子供たちの演技を食い入るように見入っているのが微笑ましかった。おひねりも飛び交っていた。

肥土山農村歌舞伎の舞台。
現在、全国各地で様々な芸術祭が開催されているが、現代アート作品よりも、地元に根ざした伝統的な祭りに旅行者がふとしたきっかけで出会ってしまう、偶然の回路を作るほうが大事なのではないか、とそのとき感じた。地域振興にアートを用いるという手法がブームとなりつつある昨今、そもそも地元に古くからある、しかも市民たちの手で作られ、楽しまれる伝統的な芸能や文化の価値をこそ現代と接続しなくてはいけないのではないだろうか。そのために、アートやメディアといったものが少しでも役に立てばいいのに、と思う。
オリーブ会社が経営する出版社「瀬戸内人」
小豆島にはまた、『ローカルメディアのつくりかた』(学芸出版社)で取り上げた「せとうち暮らし」を発行する出版社、瀬戸内人(せとうちびと)に100パーセント出資する地元オリーブ会社・小豆島ヘルシーランドがある。この会社は、島内に複数のアートスペース施設を持つ「MeiPAM」をグループとして保有しており、瀬戸内国際芸術祭の会場にもなっている。

「迷路のまち」を感じさせてくれる施設「MeiPAM」の外観。
MeiPAMで作品が展示されている「目(め)」は前回の瀬戸内国際芸術祭の時期からこの小豆島に関わり続けており、地元市民を巻き込んだかたちで継続したプロジェクトを展開している。その成果は二つの作品に結実しており、恒常的な展示として瀬戸内国際芸術祭のお客さんや、地元の人に親しまれている。そして、その活動を全面的にバックアップしているのも小豆島ヘルシーランドなのだ。
『せとうち暮らし』はもともと、香川県でフリーランスで情報誌のデザインなどを行なっていた小西智都子さんが地元の仲間たちと構想した雑誌で、小西さん自ら立ち上げたROOTS BOOKSという個人出版社から発行を続けていた。同誌は全国の一般書店にも卸していたが、なかには瀬戸内海の島々のカフェや美容院などにも置かれており、たまたま小豆島の歯医者で偶然これを見つけ、支援を買って出たのが小豆島ヘルシーランド相談役の柳生好彦さんだった。
その後、神奈川から豊島に移り住み、「一人出版社」として活動していたサウダージ・ブックスの淺野卓夫さんが合流。現在は「瀬戸内人」へと名前を変え、雑誌『せとうち暮らし』以外にも、地元ゆかりの作家・黒島伝治らの書籍を刊行しているほか、小豆島の「迷路のまちの本屋さん」という本棚の企画なども仕掛けている。今後はより小豆島ヘルシーランドの事業と連動した書籍も発行されていくだろう。
最近、企業が出版社を買収したり、自社の内部に出版部門を立ち上げる事例が目につく。たとえば精神障がい者のための自立訓練事業所が行う、メンタルヘルス専門の出版社ラグーナ出版、リアル脱出ゲームの会社が仕掛ける謎専門出版社SCRAP出版などが挙げられる。
他にも大地の芸術祭、瀬戸内国際芸術祭などのアートイベントを手がける北川フラム氏が代表を務める現代企画室や、大手住宅メーカーによるLIXIL出版など、昔から本体の事業と関連した出版社を抱える企業は多くあった。出版不況と言われて久しい現在、出版事業単体で利益を出し続けるのには限界がある。そこで今、本体の収益事業に貢献する専門出版社の存在感が高まりつつあるのだ。
近江八幡に根ざす菓子舗たねやが、地元貢献のために「たねや農藝」という農業のような試みをしたり、ハイクオリティな広報誌『ラ コリーナ』を発行しているように(連載第2回を参照)、小豆島ヘルシーランドのような企業が文化事業を地元で多数仕掛けるうちの一つの枝葉として出版社を立ち上げるのは、とても自然な流れのように感じる。
「出版とはこうあるべき」だとか、「利益率がどう」だとか肩肘張るのではなくて、狭いパーティションに区切られた編集部から外に出て、もっと自然に、風通しのいい地域の景色に身を任せながらメディアや出版を考えることはできないか。それが僕自身がローカルメディアに興味を持った一つの理由でもある。
「本」が起点となり、地域が変わろうとしている
また、これまで取材を重ねてきた全国のローカルメディアの大きな特徴の一つに、大手取次会社を通した出版流通に乗らないということが挙げられる(一部をのぞいて)。全国隅々まで新刊が時差なく届けられる出版流通の仕組みは、大型書店のない地方の住人に本を届けるという重要な意義がある。ただ、昨今のローカルメディアの流行を見るにつけ、従来の出版産業の“リングの外”のほうがより面白いことができるようになっていると感じる。
先日は久しぶりに、地域限定発売「本と温泉」(連載第1回を参照)が話題となっている城崎温泉へと足を運んだ。最近、このプロジェクトの仕掛け人であるBACHの幅允孝さんが地域プロデューサーに就任し、城崎温泉に昔からある城崎文芸館のリニューアルオープンを手がけることになったためだ。
城崎文芸館はJR城崎温泉駅から近いにも関わらず、温泉街のメインストリートから外れたところにあるため、地元の人や観光客の動員に苦戦していた。そこで、全国から注目を集める「本と温泉」プロジェクトと連動したかたちで、新しい客層を開拓するために「KINOBUN」という愛称をつけ、リニューアルの企画が立ち上がった。

城崎文芸館“KINOBUN”企画展。
現在、館長を務める原良式さんは、同館の課題について「これまで文芸館は常設展しかなかったので、地元の人も一度来たらそれで終わりでした。定期的に企画展を開催することで、何度も来てもらえる施設にする必要があったんです」と語る。
記念すべき第一回の企画展は「本と温泉」の第二弾であるタオル表紙の本『城崎裁判』を執筆した万城目学さんを特集したもの。展示内容もちょっと変わっていて、万城目さんが原稿を書くPCの画面写真や、事務所で愛用しているロッキングチェアが置かれていたりと、「地元ゆかりの大作家」という大仰なしつらえを意図的に避けている印象を受けた。
さらに、企画展のチームはアートディレクションをスープデザインが手がけ、特別展示としてライゾマティクスの映像作品も置かれるなど、文学に親しみのない若い層にもうったえかける内容になっている。幅さんはそもそも、志賀直哉来湯100周年をきっかけにこのまちに関わるようになったのだが、「いつまでも昔の文人を推していてもお客さんは来ない。文芸館をやわらかく、幅広い方に来てもらえる施設にしたかった」と語った。
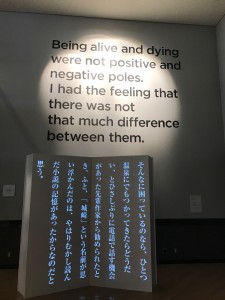
ライゾマティクスによる映像作品
『ローカルメディア〜』で詳しく紹介したとおり城崎温泉には、震災以降、地元の豊岡市にUターンした田口幹也さんが館長を務める城崎国際アートセンターも精力的に活動を続けているし、今回の文芸館のリニューアル、そして湊かなえさん書き下ろしの第三弾が今年の7月に刊行された「本と温泉」と、新しい文化的な取り組みが複合的に絡み合い、点と点が繋がり面へと広がっていると実感した。
「本」というメディアが起点となり、地域が変わろうとしている城崎温泉のここ数年の盛り上がりを見ていると、まるでそれ自体が一冊の本から始まった、一つの(未完の)物語のように見えてくるから不思議だ。

城崎温泉名物のカニをイメージした装幀の、湊かなえ『城崎にかえる』。
「出版」という枯れた技術にも “水平思考” を
大都市に比べて人口の少ない地方で読者や観光客を獲得するためには、独自の流通の仕組みを編み出したり、単体のイベントだけで終わらないよう文化的な拠点を作り出す必要がある。だから今、地方で成功しているローカルメディアの担い手たちは、編集やデザインという制作スキルそのものよりも、特に流通に注力をそそいでいる。
その場所でしか買えない「本と温泉」や、自社のショップのみで配布する『ラ コリーナ』、会員数(読者)を限定し消費者と生産者の結びつきを強める「食べる通信」、取材・執筆、広告営業のみならず配布まで自ら一人で行っている『みやぎシルバーネット』がまさにそうだった。ローカルメディアにとって、流通のあり方は自らのメディアの存在証明であると言っても過言ではない。
また、単に本やメディアを出すことだけが出版社の役割ではない。本やメディアと連動した場づくりやコミュニティの醸成が、メディアづくりと同じか、それ以上に重要だ。だからこそ、企業やNPOなどが手がける、専業ではない出版社というあり方が活きてくる。
任天堂の伝説的な開発者、横井軍平氏は生前、古くなり安価になったテクノロジーを“横にスライド”することで新たな商品を生むという意味の「枯れた技術の水平思考」という名言を遺した。批判を恐れず言えば、DTPや印刷が手軽となった「出版」「メディア」のテクノロジーは今や「枯れた技術」なのかもしれない。
だからこそ、それを“水平思考”し、今までなかった場所に取り入れることで、新たな市場や関係を育む。あるいは、今まで出版社の内部にあった人的資本である編集者のスキルをまちへとインストールすることで、“地域を編集する”という観点も生まれるだろう。
少なくとも、僕が面白いと思うローカルメディアの担い手たちは、自分が手がける本やメディアの売り上げよりも、それが地域にどんな物語を残したか、どのように人と人がつながりあったか、という視点を大事にしながら仕事をしていた。
一冊の本は、単に読まれるためだけに作るものではない。読書体験の先に、どんな物語を編むかが重要なのだ。
* * *
「マガジン航」との協働で今年の7月にスタートしたセミナー「ローカルメディアが〈地域〉を変える」の第3回目は、「地域に根ざした企業メディア」をテーマに今回の記事で紹介した小豆島ヘルシーランドの域事業創造部マネージャー/MeiPAM代表・磯田周佑さん、たねやグループ広報室長の田中朝子さんを講師にお迎えする。ローカルメディアの重要なプレイヤーである地域に根ざした企業の取り組みを詳しく知りたい方はぜひお越しいただきたい。
ローカルメディアで〈地域〉を変える【第3回/最終回】
「メディア+場」が地域を変える:瀬戸内、近江八幡、鎌倉の事例から
第一部では、瀬戸内(小豆島ほか)と近江八幡という二つの地域で、地元企業が「メディア」と「場」を連動させて行っている実践を紹介。小豆島ヘルシーランドの地域事業創造部マネージャーで、『せとうち暮らし』を発行する出版社「瀬戸内人」を経営する磯田周佑氏、滋賀県近江八幡市の「たねやグループ」広報室長で、同社の広報誌「ラ コリーナ」編集長である田中朝子氏に、それぞれの地域での実践についてお話をうかがいます。
日時:2017年2月13日(月)14:00-18:00(開場は13:30)
会場:devcafe@INFOCITY
渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル16F
http://devcafe.org/access/
(最寄り駅:東京メトロ・表参道駅)
定員:30名
受講料:8,000円(交流会込み)
講師:
・磯田周佑(小豆島ヘルシーランド(株)マネージャー/MeiPAM代表 /(株)瀬戸内人会長)
・田中朝子(たねやグループ社会部広報室室長)
・ミネシンゴ(編集者・合同会社アタシ社代表)※講師のプロフィールなど詳しい情報と前売り券はこちらから。
http://peatix.com/event/223768/view
執筆者紹介
- 1982年生まれ。合同会社千十一編集室 代表。アート/カルチャー書のプロデュース・編集、ウェブサイトや広報誌の編集のほか、各地の芸術祭やアートプロジェクトに編集者/ディレクターとして関わる。著書に『大人が作る秘密基地』(DU BOOKS)、『ローカルメディアのつくりかた』(学芸出版社)、編著に『ローカルメディアの仕事術』(学芸出版社)、『あたらしい「路上」のつくり方』(DU BOOKS)など。
千十一編集室:https://sen-to-ichi.com/
最近投稿された記事
- 2019.11.18ローカルメディアというフロンティアへ天気の次の話題を探して――「街の手帖 池上線」
- 2017.10.18ローカルメディアというフロンティアへ第7回 地域のクリエイティブはどこにある?
- 2017.05.09ローカルメディアというフロンティアへ第6回 京都ではじまるローカルメディア・ワークショップ
- 2016.12.26ローカルメディアというフロンティアへ第5回 紙やウェブに捉われない新しいメディアのかたち

