“よそ者”が発見する地元の魅力
『ローカルメディアのつくりかた』(学芸出版社)では、主に三つの論点で取材をしている。「地元の魅力の発見」「発行形態の実験」「よそ者と地元の人との関わりかた」である。前回の連載で取り上げた「本と温泉」は二つめに該当する。
今回は、三つめの“地域の人”と“よそ者”が協働するローカルメディアを紹介したい。
滋賀県近江八幡市に本社のある菓子舗の「たねや」が発行する「La Collina」は、およそ企業の広報誌にありがちな“商品カタログ”的な要素が一切ない。企業が根ざす近江八幡という土地の魅力を最大限に伝えたいという明確なコンセプトがあるので、賞味期限の短いカタログ的な要素を一切排して、川内倫子さんをはじめとした写真家の撮り下ろした人や風景の写真がメインのコンテンツになっている。
だから、まるで写真集を読んでいるような気分になる。さらに、そっと添えられる地元のエピソードが、近江八幡という土地に行きたいという気持ちにさせられる。この冊子は全国の「たねや」のショップで手にいれることができるのだが、このクオリティで無料なのがすごい。

「La Collina」(撮影:喜多村みか)

ラ コリーナ近江八幡「メインショップ」の外観(撮影:著者)。
「La Collina」のディレクションを手がけるのは、東京に事務所を構える信陽堂編集室。遠い滋賀県の企業の広報誌を、東京の人材が手がけるのはスピード感や予算を考えても効率が悪いと一見思える。しかし、たねやグループ広報室の田中朝子さんはこう語る。
「近江にはこんないいところがあるんだ」とか、「どこか懐かしい気持ちになるなぁ」とか、地元の再発見につながるものにしたいというのがまずありました。そして、県外の人には、近江はこんなにいい場所なんだよって知ってもらう。そのためには、外の人の視点でこの町の魅力を発見してもらう必要がありました。
ローカルに根ざしたメディアだからといって、地元だけで流通するわけではない。いや、前回紹介した「みやぎシルバーネット」のように、地元で完結するという“潔さ”も大事なのだが、ローカルなコンテンツを都市部の人々の届けたい場合は、外から見てユニークかどうかという視点は確保する必要があるだろう。そこで、「La Collina」のように都会のクリエイティブ人材を協働のパートナーとして選ぶローカルメディアが増えている。
“よそ者”と“地元の人”が一緒になって“まち”を編集する
『ローカルメディア〜』の中で紹介した媒体はどれも、外部のクリエイティブチームとタッグを組む際、彼らに仕事を投げっぱなしにしないよう気をつけていた。地元と外部の制作者が共に考え、同じ立場で作り上げるという姿勢が大切なのだ。クライアントである地元の発行主体が強権をふるってもダメだし、都会の編集者やデザイナーが自分のやりたいことを追求しすぎてもうまくいかない。このバランス感覚が重要だ。「La Collina」を始めどこも皆、多少交通費がかさんだとしても、顔を突き合わせて話し合う機会をなるべく作るようにしているのが印象的だった。

COMMUNITY TRAVEL GUIDE『三陸人』(撮影:喜多村みか)
地元の見るべき名所ではなく、会っておきたい人にフォーカスする観光ガイドCOMMUNITY TRAVEL GUIDE(英治出版)というシリーズがある。これは、博報堂のクリエイティブチームが立ち上げたissue+designという団体が手がけている。制作主体はissue+designだが、そのつど異なる地域の人々と協働を行っており、これまでに『海士人』『福井人』『三陸人』『大野人』『銚子人』が刊行されている。
このCOMMUNITY TRAVEL GUIDEが面白いのは、地元の人との編集のプロセスを仕組み化している点である。例えば『大野人』の第一回目のワークショップでは、「魅力的な大野人と宝物を発掘する」というテーマで、さまざまなアイデアが地元・福井県大野市の参加者から出てきた。すると、そば打ちの達人、どんぐり作家、里芋堀りの救世主など100以上の”大野人”がリストアップされ、「大野の伝説」「とんちゃん文化」「川遊び」などの宝物が浮かび上がってきた。
こうした人と宝物というコンテンツの種をもとに、取材、撮影、執筆にチームが分けられる。そして第二回、三回とワークショップを重ねることでこれらの成果をフィードバックし、実際の記事に落とし込んでいくという。結果として「軽トラデートスポット7」「雪かき決まり手四十八手」というような、ちょっとやそっとでは思いつかない記事が生まれていく。
実は、ローカルをテーマにしたメディアは、ウェブ媒体を含めれば地方のみならず、首都圏でも近年たくさん生まれている。 LCCの登場や高速バスの低価格化などによって、移動が安くなって国内旅行が見直され始めているのと同時に、家賃の安さ、自然の豊かさなど様々な理由によって移住を希望する人々のニーズも高まっている。原発事故も後押ししただろう。定年退職の熟年層から、子育てを考える若年層まで世代も多様だ。このところ首都圏のメディアもローカルを新たな市場として見出し始めているように思う。
そんなとき、読者が欲しいのは単なる憧れを煽る地方の理想的な姿ではなく、移住や観光を具体的に進めるために役に立つ情報だ。しかし、東京のメディアのチームだけでは、現地の一次情報はなかなか手に入らない。たとえライターが毎回地方に出向いて取材を行い、記事を執筆するとしてもコストがかかりすぎるし、たとえ1日や2日行ったとしても地元の本当の姿は描けないだろう。
一方、地元の人たちだけで地域の細やかな魅力を引き出そうと思っても、農協が推す特産品や自治体が推す観光スポット、B級グルメなどメディア映えするもの以外で、自信を持って語れる宝物が果たしてどれくらい見つかるだろうか。
ここで重要なのが、上記のようなワークショップ、それからオン・ザ・ジョブ・トレーニングという機会を一連の編集フローの中に組み込むことだ。“よそ者”と“地元の人”が、ローカルな情報と、その“魅せ方”を競い合って議論しあうことで、読者が本当に欲しいコンテンツが明確になってくる。そして何より、そのプロセスで起きた悲喜こもごものドラマは、ともすると出来上がったものそのもののクオリティよりも、つくり手たちの記憶に深く刻まれる“宝物”になる。
フランソワ・トリュフォーが『アメリカの夜』という映画の中で、作品の裏側の撮影所の中で起きる人間ドラマを描いたけれど、大勢のスタッフや関係者が一つのものをつくり上げる協働の現場では、作品には現れないスタッフどうしのケンカや恋愛などの事件が日常茶飯事だ。だからこそ、互いに右往左往しながらメディアをつくる“プロセス”の記憶は、 “よそ者”と“地元の人”の絆を深くするし、そういう経験を共有しているからこそ、ましてやメディアが出来上がった時の喜びは計り知れないものになるだろう。
メディアは目的ではない、手段なのだ
少し話は変わるが、3.11の震災の日、僕は東京・巣鴨の自宅にいた。当時飼っていた20歳の老猫を抱えてクローゼットに隠れ、揺れが収まるのを待っていた。大きな衝撃の後に、ゆったりとしたゆりかごのような揺れが長く残って、それが心地よかったのか、膝に抱えていた猫は目をとろんとさせてまどろんでいた。
その日の夜、自宅近くの幹線道路は都心部から離れているのにもかかわらず、帰宅困難者で溢れており、コンビニに商品はほとんど残っていなかった。そんな異様な光景を目に焼き付けたくて、余震で頭上の電線が激しく揺れるのも恐れず、夜の街を何時間も歩いた。
翌日、自宅に回覧板が回ってきた。そこには「地震怖かったね、こんなときだからこそご近所づきあいを大事にしましょうね」 というような趣旨のことが書かれていた。面倒な近所付き合いも、こういうときこそ心強いと感じる。危機的な状況だからこそ、互いに励まし合うささやかなコミュニケーションツールとしての回覧板が、安否情報が飛び交うツイッターのような新興のSNSと同じくらい重要なメディアだと実感した瞬間だった。
本来メディアとは、顔の見える近しい人々と活発に交流したり、互いの生息を確認するための手段となって初めて価値が生まれるものだと思う。メディアは目的ではない。手段なのだ。地域雑誌の先駆けとして知られる『谷中・根津・千駄木』のメンバーの一人で作家の森まゆみさんは自身の著書『小さな雑誌で町づくり「谷根千」の冒険』(晶文社)でこう語る。
送り手と受け手に互換性があり、情報が双方向に行き来すること。私たちの雑誌は、まさにそのためのメディア (乗り物)であればよい。
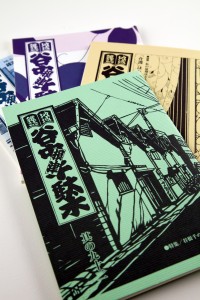
地域雑誌『谷中・根津・千駄木』(撮影:喜多村みか)
僕たちは、互いに励ましあい、慰め合い、認め合う機会を常日頃から欲している。寂しいときは、家族に電話を掛ける日もあるかもしれない。
ただ、ふだんの生活のなかでは、本当に親しい人や毎日顔を突き合せる人以外とコミュニケーションを取る手立てはない。経済活動によって日々商品を交換しあっているにもかかわらず、地方の一次産業の生産者と受け手が出会う機会も損なわれている。さらに、グローバリゼーションの波のなかで、大きなニュースに小さなニュースが飲み込まれてしまい、地元の本当の宝物は何か? を議論する機会も奪われている。
そんなとき、地方と都市の情報の不均衡を是正し、そこに住むこと、訪れることの“かけがえのなさ”を伝えるローカルメディアが活きてくる。地域の人と人をつなげ、他愛のないローカルな話題でひと盛り上がりしてまた家に帰る。まさに、井戸端会議や回覧板としてのローカルメディアだ。
そこでは、自分たちの遠い世界の、メジャーなメディアで紹介される“事件”としてお墨付きをもらった情報ではなく、イノシシの畑荒しや、地元で一番の不良が実家に戻ってきた話のほうが重要だ。それはメディアの権威を補強はしないが、目の前の数人の友人・知人の信頼を獲得することはできる。
そういう情報を載せるメディアが、全国各地に無数に生まれることを想像してみる。東京の高島平や、多摩ニュータウン、神戸の新興住宅地のように、高度成長期に生まれた団地で、ご近所さんとのつながりもなく建物と共に老いていく独居老人たちをつなぐメディアがあってもいいのではないか。あるいはUターン、Iターンで地方に移住した若者たちが、自分たちの遊ぶ場所や共感できる仲間を増やすために始めるメディアがあってもいい。
僕たちは、メディアが文字通りよそ者と地元の人をつなげる媒体になったり、自分たちが自分たちの言葉でローカルな話題を語り合う場(プラットフォーム)になりうることをもう一度確認すべきなのかもしれない。
(つづく)
執筆者紹介
- 1982年生まれ。合同会社千十一編集室 代表。アート/カルチャー書のプロデュース・編集、ウェブサイトや広報誌の編集のほか、各地の芸術祭やアートプロジェクトに編集者/ディレクターとして関わる。著書に『大人が作る秘密基地』(DU BOOKS)、『ローカルメディアのつくりかた』(学芸出版社)、編著に『ローカルメディアの仕事術』(学芸出版社)、『あたらしい「路上」のつくり方』(DU BOOKS)など。
千十一編集室:https://sen-to-ichi.com/
最近投稿された記事
- 2019.11.18ローカルメディアというフロンティアへ天気の次の話題を探して――「街の手帖 池上線」
- 2017.10.18ローカルメディアというフロンティアへ第7回 地域のクリエイティブはどこにある?
- 2017.05.09ローカルメディアというフロンティアへ第6回 京都ではじまるローカルメディア・ワークショップ
- 2016.12.26ローカルメディアというフロンティアへ第5回 紙やウェブに捉われない新しいメディアのかたち

