つい最近まで、自分で版元をやろうなどとはまったく思っていなかった。正直なところ、今も半信半疑だ。
そこで、この連載では、既にひとり、もしくは数人で小規模な出版社をされている方々のお話を聞きながら、そのお話を参考に私が版元をおこし、本を出版する過程をリポートしていこうと思っている。
――なぜこんなことになってしまったのか。
詳しくは後述するが、当初はフリーランスのライターとして、このところ増えているというひとりで出版社をおこした方々に取材したいと思っていた。しかし、今後、フリーランスの編集者としても仕事をしていく自分としては、出したい本の企画を抱え、版元探しをしながらそのような話を聞いているという状況に、
――自分は一体どの立場でこの話を聞いているのだろう?
という当たり前の疑問にすぐにぶち当たってしまった。
――これは自分で出版社をやってみるしかないのではないか?
次第に取材なのか身の上相談なのかわからない形でお話を聞くようになっていった。
この原稿を書いている2013年1月現在、まだ出したい本の中身も資金も準備段階にある。本当に本が出るのか、連載のゴールはどうなるのか、まったくわからない。まさか人生でもっとも大きな賭けに出る過程を世間に晒すとは思わなかった。
だから万が一、何かの理由で本を出すことが出来なくなったら、取材という以上に相談に乗っていただいた出版社の方々、すぐに焦り、怖じ気づく私の背中を押してくれた友人や先輩、そして何よりもまだこの世に存在すらしない版元に人生のもっとも大事な作品を託してくれた著者には、ただただ謝るしかない。……だが、いやだからこそ、そういうことはとにかくないよう気を引き締めて、この無謀な連載をスタートさせたいと思う。
とにかく出版社に入りたかった。
大学4年になり、突然出版社を受け始めた。
「編集者とかいってかっこいい仕事だと思ってんでしょ。どんなことやるのかわかってんの?」
母の辛辣な言葉を背中に浴びながら、慣れないスーツとヒールで繰り返し会社説明会に足を運んだ。就職氷河期真っ只中の1999年。東京にある出版社なら片っ端から履歴書を送ったが、面接官に会うことすらなく、「今後のご活躍をお祈りしております」という趣旨の手紙とともに履歴書は戻ってきた。
【趣味】の欄には「洗濯」と「散歩」。【志望理由】は、芸術学科映像専攻の卒業論文に選んだある映画の感想と、映画の制作過程がくどくど書かれ、その映画の手法を参考に本を作りたいという、チンプンカンプンな意志表明で埋め尽くされていた。
「映画の本を作りたい」といったわかりやすい目標はなく、単に「私」という人間をまるごと知ってほしいという22歳の若者の目も当てられない主張だった。ライターと編集の区別すらついていなかった。受かるはずがない。
その頃の私のお目出度さは相当なもので、返却された履歴書と不採用通知の入った、出版社の社名が印刷された封筒の宛名に、手書きで自分の名前が書かれていることだけでも少し誇らしい気持ちになった。やっぱり出版社の人は字がきれい。しげしげと封筒を眺めていた。
母の言うとおり、何もわかっていなかった。しかし、当時編集者はまだかろうじて「あこがれの職業」で、出版社は「あこがれの会社」だったのは確かだったと思う。ほんの10年ちょっと前までは。
人文系の書籍を発行する老舗版元が希望だったが、募集自体がごく稀にしかなかった。しかも私には経験も教養も(教養は今も)なかった。しかし、親から言われたわけでもないのに、何故か子供の頃から、早く自立して稼がなくてはという気持ちが強かった。今になって思えば、腰を据えてじっくり考えていたら……と思う。とにかく出版社を受けまくって、軒並み落ちた。
それでもようやく、進みたいジャンルとは違ったが、DVD情報誌の編プロに腰を落ち着けた。それからもう少し自分の好みの本を作ることができる出版社へ……とにかく前職の経験プラスαの経験、経験と、自分の経験したい“技術”と会社のニーズを擦り合わせながら、一瞬それが合致してもすぐに蜜月は終わり、の繰り返しで、編集プロダクションを2社、出版社を2社、転々とした。自分の転職のタイミングですぐ入社、となると、先述のとおり、行きたい会社は募集がなく、募集をしている出版社はヒットを狙える自己啓発本やビジネス書が中心の会社ばかりで希望に合わない……と、とにかくなかなか鞘に収まらない。
しかし、出版業界全体が、日本の不況のせいだけではない、業界の構造的な問題からくる苦境にも立たされていた。出版社の倒産も年々増加し、私もその渦中にいた。入ってすぐに会社の縮小や雑誌の休刊にも直面した。
「また辞めんの?」とか「出版社はもうやめておいたら」など、周りからは呆れ半分言われたし、自分でも思った。体力的にもきつい仕事で、大の苦手な細かい確認作業も多く、給料も安かった。決して憧れの職業なんかじゃないことはもうわかっていたが、まだ「これぞ」という気持ちの良い球を投げたことがないのがただ悔しくて辞められなかった。
その後、それまで雑誌編集部にばかり在籍していたので、単行本の編集経験を積みたいという想いから、5社目。某企業の出版部門の契約社員になった。出版社の不安定さを経験し、そこから逃れたいという気持ちもあったと思う。猛烈に忙しくなり、結局、出したかった本とは畑違いの、エンターテインメントのジャンルに限定した本づくりだったが、本という商品の細部を詰める楽しさを感じるようになっていた。それも良いかと思い始めていた。
刊行点数も増やすし、今なら昔は毛嫌いしていた自己啓発本もバンバン作るぞ。職人としての編集者に、それなりの達成感もあった。エンターテインメントの本作りで大半の生活時間を過ごし、仕事が少しでも早く終わると呑みに行く。それなりに順調に回転している気になっていた。
だが、たまに朝まで仕事してそのまま帰宅し、眠りに着く前に、身体は疲労に包まれながら頭だけものすごく冴えた状態で、言いようのない焦燥感に襲われた。経験を積みたいというところまでは良かった。でもそれはさすがに終わった気がする。でもどんどん時間が過ぎて年をとっていく。今はどうにかなっているが、この先どうしたいという希望がなくなっていた。
そして12年目の2011年3月。契約社員から正社員になるか、それとも辞めてまた転職するか。あと一年で決めなくてはならないと、選択を迫られた。もう今の場所にやり残したことはないと思った。では別な出版社にまた転職し、広いジャンルの本を編集するのか――? 転職にはさすがに疲れた。また、学生時代から密かに入社を希望していた、挑戦的に本を出し続けていたある版元が、大幅な社員の縮小に踏み切ったことを知り、衝撃を受けていた。
そのわずか3日後。東日本大震災が起きた。余震と放射能(とその情報)に怯え、初めて死を隣り合わせに感じた。思考停止の状態から突然、視界が開けた気がした。
中堅の版元の多くが、出版点数を増やして自転車操業に陥っている。ヒット本の二番煎じが溢れ、出版点数が増え続けることで、返本が増え、本が売れず、売れないからさらに出版点数が増え……もちろん、手堅く良書を出し続ける出版社はある。だが、台所は厳しい。結果、社員編集者は仕事に忙殺されるか、はたまた会社自体が危なくなって転職するか……読者のためでも著者のためでもない、ただただ会社も社員も倒れないようにするために回転し続けなくてはならないような気がした。この渦から飛び出したいと思った。
ひとまずフリーランスになろう。そして、お酒を控えよう……。しかし必ずしもヒット狙いではないジャンルの本を作りながら、生活していく方法なんかあるのか? このシンプルかつ永遠の難題にはどうやって取組んだらいいのか?
その頃、出版業界ではミシマ社や夏葉社といった、ひとりで出版社を立ち上げる人が目立ち始めていた。先の疑問に答えはないかもしれないけれど、そこには光が射しているように見えた。
今後のプランは全然見えない。ただ、既にある場所に自分の居場所を作ってもらうのではなく、自分で場所を作って本を出して暮らしている人たちに話を聞くうちに、自分自身のこの先のヒントを見つけたいと思った。
とにかく勇気ある先輩に会いにいくことに決めた。
編集グループ〈SURE〉の北沢街子さんと会う。
3月11日の地震から6日後、福島第一原発の事故から5日後の2011年3月17日、関西出張があった。この時期、外に出れば地下鉄もコンビニもデパートも節電で薄暗く、会社へ着くと、水を買い占めたという同僚の話に辟易した。だがスーパーへ行くとがらんとした棚に焦りを感じ、一人暮らしの自宅に戻ると頻繁な余震で目が覚めた。気づけばTwitterで地震と原発情報をチェックし、「地震予知」のデマに惑わされるまでになっていた。
そんな折に降って湧いた関西出張で、関西の明るい街中を歩いているだけで心の底からホッとした。目的地は大阪と京都の間に位置する枚方市。京都駅に着くと、夜には東京が計画停電になる可能性があるとのことで、京都で足止めを食らった。もう夕方。思わぬ京都泊が正直、ものすごく嬉しかった。東京からの避難者で宿はどこもいっぱいだったが、何とか空きを見つけた。
こうなったら本屋にでも行こう。ずっと気になっていた恵文社一乗寺店へ向かった。二両しかないチンチン電車の叡山電車に乗ると気持ちが沸き立ってきた。
全国一律、ベストセラーばかりが並ぶ新刊書店と違い、かなり稀少な本を扱いつつ、読者の好奇心を刺激するテーマに分けた棚作りが楽しかった。棚を見ていると幸せな気持ちになった。
そしてこのあと、会社を辞めるまでの1年間、何度か大阪出張があり、そのたびに恵文社一乗寺店、そして同じく左京区のガケ書房、それから三月書房などの京都の個性的な新刊書店に足繁く通うようになった。震災後、それまで当たり前だと思っていた東京中心の回転の早いモノ作りから距離を置いて世の中を眺めてみると、京都の、洗練されていて、かつ目を配れる範囲で成り立たたせている商売のやり方に、文化の成熟度と心地良さを感じていた。

そして2012年のあたま。恵文社一乗寺店で異彩を放つコーナーに目が止まった。「編集グループ〈SURE〉」という版元のコーナーだ。鶴見俊輔、山田稔、小沢信男といった錚々たる名前が並ぶが、表紙にはおそらく同じイラストレーターの手だろうか、可愛らしくユーモラスなイラストが描かれている。『小沢信男さん、あなたはどうやって食ってきましたか』、『北沢恒彦とは何者だったか?』『酒はなめるように飲め/酒はいかに飲まれたか』など、なんとなく身につまされるタイトル。しかし一般流通の本ではあまり見かけないような自由さ。数冊購入しようとレジに向かった。
ずっとSUREの棚を担当しているというベテラン店員の能邨(のむら)さん曰く、「どこにでも本を卸すということはしない」とのこと。一体どんな人がやっているのか訊ねたら、代表は北沢街子さんという女性だと教えてくれた。「とても40代に見えない素敵な方ですよ」とのこと。
帰りの新幹線でHPを覗いてみた。
「編集グループ〈SURE〉」は「街の律動をとらえる」(Scanning Urban Rhyme Editors)ことをめざして、京都から活動をはじめた集まりです。 楽しく、美しいと思えるものを手づくりすること、街を自分たちの足で歩くことから、この試みを育んでいきたいとわたしたちは思っています。
(「編集グループ〈SURE〉」HPより)
「街の声を聞く」という言葉に惹かれた。
新卒の時、履歴書に書きまくった稚拙な卒論のテーマは、ドキュメンタリー映画だった。大学時代、夜な夜な熱い議論が交わされる山形の映画祭で、ドメスティックバイオレンスや公害病や貧困などなど、その日上映された映画が扱う問題について、こんなに議論が白熱しているのにもかかわらず、東京に戻ってスクランブル交差点を歩く自分は、周りの歩行者同様、今晩のテレビのことなんかを考えている。とても豊かで突っ込んだ話題に興奮する一方、世間と距離が開いていくドキュメンタリー映画の世界に入っていく勇気がなかった。ヘタレなりに、大学卒業間際、この間を繋ぐ仕事ができないかと考えたのが、本を作りたいと思った最初だった。
本について、活動について丁寧に解説してあるHPによれば、創始者の北沢恒彦氏は、京都市役所で中小企業診断士しとして実際に商店主たちの声を聞く傍ら、雑誌「思想の科学」の編集・執筆に関わり、べ平連(ベトナムに平和を!市民連合)の運動にも参加。退職後、個人ジャーナル「SURE」の発刊をしたのが始まりだという。その後、恒彦氏の子である黒川創氏や北沢街子氏らが中心となり、出版活動を続けている。
SUREの取り扱い書店は恵文社一乗寺店他、京都を中心に一部書店にしか卸しておらず、主に郵便振込。郵便での取引が主体となると、一体どうやって読者を獲得しているのだろうか。
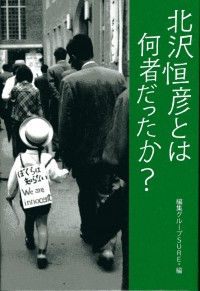 お店で直接購入することを名目に京都の事務所にお伺いしてみようと電話した。北沢街子さんらしき女性が出た。電話越しに少しくぐもった声。突然の訪問依頼に、「わざわざいらっしゃるんですか?」と少し驚いた様子だったが、OKしていただいた。
お店で直接購入することを名目に京都の事務所にお伺いしてみようと電話した。北沢街子さんらしき女性が出た。電話越しに少しくぐもった声。突然の訪問依頼に、「わざわざいらっしゃるんですか?」と少し驚いた様子だったが、OKしていただいた。
それからおよそ1ヶ月後の2月半ば。大阪出張の帰り、京阪電車で出町柳まで。節電のため寒く静かな電車内で、『北沢恒彦とは何者だったか?』を読む。恒彦氏は最期、自死という選択をするが、「どこかマンガ的な人」と、周囲はその人柄に明るい印象を持っているという。息子である黒川氏は、父の「書く」という行為について次のように綴る。
「原稿料を稼いで食えるような文章ではなかった。だが、彼には書くべきことがあった。(中略)原稿を書くたびに歯が一本抜けたようだ」
鼻の奥がツンとした。生きることは書くことだったのだろう。生ききった人だと感じた。
京都大学の前の小さくて古い長屋の一角。元は米屋だったらしく、看板はないが、表には商店の軒先がそのまま残っていた。古いが手入れの行き届いた佇まいから、何となくここかな、と思った。呼び鈴を押すと、引き戸から「あ、電話の……」と言いながら女性が顔を出した。この人が北沢街子さんだ。ほとんどノーメイクで、おかっぱ頭。くるりと後ろを向くと寝癖がチャーミングだった。中に入れていただくと、下駄箱には大量のスリッパと書籍の包。だがとてもよく整理されている。かつて米屋の店先があったことがわかる小上がりに通していただく。
「こんなところですみません」
笑顔がこぼれた。この日街子さんと話す中で、大人がマナーとして身につけた種類のものではない、見ているほうが心が晴れるような笑顔がとても印象的な人だった。図々しい訪問にもかかわらず、鶴見俊輔、山田稔といったSUREの主だった著者についておおよその知識しかない勉強不足が申し訳なく、縮こまっていたが、笑顔に救われ、途端に気持ちが緩んだ。石油ストーブのチリチリという微かな音だけがする静かな室内が、心地良く感じられた。
「父が切り貼りして作ったA3判のジャーナルを、30部くらいコピーして知り合いに配っていたのが最初で。『編集グループ』って名乗りながら、実際はひとりでやってたんです」
クスクスと楽しそうに笑いながら、街子さんはお父様について語る。恒彦氏は、普段は京都市役所に勤め、京都の街の中小企業診断士として商店街のお店に行き、町の中でのお店の在り方やつながりについて話していたという。
「父は仕事をエンジョイしてました」
晩年は京都精華大学の講師をしながら、個人ジャーナル「SURE」の発行を続けた。
小さなサークルから生まれた本
長机が部屋の中心にあり、ここで鶴見氏や山田氏も交えた勉強会を開いているという。
「京都は狭いので、夜遅くても帰れるから。鶴見さんたちともよく遅くまで話し込んでしまいます」
SUREの本は、この元米屋の「勉強会」から生まれる。入口の大量のスリッパは、来客の多さを物語っていた。
「本は決まったところにしか卸さないです。大量に仕入れて結局売れずに戻ってきて、本も傷むし。直接販売だと装丁も自由にできるから。部数はだいたい少ないものだと500部、多いものでも1500部くらいです」
「勉強会」という小さなサークルから生み出された本に詰まった“知”が、京都に住む文化に親しむ人たちに手渡しされていくような感覚だろうか。京都という土地ならではの成り立ちかただと感じた。
しかし、やはりヒットが持続を支える。125人の人々への追悼文を集めた鶴見俊輔氏の『悼詞』は6刷を重ねた。
「著者に鶴見さんたちのお名前があるから、うちのことを知ってもらえることも多いですね。新聞で取り上げられたり、テレビに出たときは、すごい反響がありました。『悼詞』のおかげもあって、なんとか活動をつづけています(笑)」
現在は、街子さんの兄である黒川創氏と黒川氏のパートナーの滝口夕美氏、そして街子さんの3人で話しながら企画を立てる。
『小沢信男さん、あなたはどうやって食ってきましたか』は、「新日本文学」の編集に携わり、小説や俳句、評論、ルポルタージュなど幅広い執筆活動を続ける、今年85歳になる“現役最長老級”作家、小沢信男氏の多彩な(しかしお金にならなそうな)活動を、どうやって食べてきたか、という生活面の視点から迫る対談集だ。小沢氏と異なる世代で共通の作業を続ける津野海太郎氏、黒川創氏が対談相手として参加する。こういった対談形式の本が多いのも、「勉強会」というスタイルがSUREの根幹にあるからかもしれない。

ユニークな表紙のイラストと装丁はほとんど街子さんが手掛けているという。イラストはだいたい本の内容から着想を得ているらしい。だが、岐阜県徳山村という、ダムで沈んだ村について記した本『ぼくの家には、むささびが棲んでいた―—徳山村の記録』(大牧冨士夫著)の表紙は、内容との関連性が見当たらなかったので訊ねると、
「大牧さんがバーッと机に資料を広げて話すようすが印象的で、それをそのまま装画にしたんです」
そう言いながら、前屈みになって手を広げ、大牧さんの話の様子を再現する街子さん。楽しんで絵を描いている様子が伝わってくる。街子さんはオーストラリアの美大卒。絵で食べていこうとは思わなかったのだろうか。
「そこまでの覚悟というか、重さがなくて、ただよってるんですね」
そう言ってまた笑った。
この取材時(2012年2月)、街子さんらは原発国民投票のための署名集めを手伝っていた。環境社会評論家の中尾ハジメ氏が、SUREのメンバーらに福島原発事故の実情を解説していく対話集『原子力の腹の中で』や、黒川創氏のベン・シャーン展での講演を収録した『福島の美術館で何が起こっていたのか』など、実態のわからない原発の問題を解明していこうとする書籍をその後も続々と発刊している。
「大阪よりもむしろ東京の方が署名が集まらないみたいだけど福島の原発事故のことはもうすぐ忘れられてしまうんですかね」
この日、街子さんはそうやるせなさそうに呟いた。
外に出ると、ちらほら粉雪が舞っていた。街子さんはお酒が好きで、何軒もハシゴで呑んだりしたこともあったらしい。私が最近はほとんど呑んでいないので落ち着いたらぜひ一緒に、と言うと、別れ際、
「いきなりストンと落ち着くときが来ますよ」
と、ニッコリ。力の入った背中をトン、と叩かれたような気がした。
(次回につづく)
執筆者紹介
- 里山社代表/編集・ライター。出版社勤務を経て、2012年10月、出版社「里山社」設立。2013年11月、田代一倫写真集『はまゆりの頃に 三陸、福島 2011〜2013年』、2014年7月『井田真木子著作撰集』、2015年3月『井田真木子著作撰集 第2集』、2016年3月『日常と不在を見つめて ドキュメンタリー映画作家 佐藤真の哲学』発売。フリーランス編集・ライターとしても活動中。
最近投稿された記事
- 2017.06.29本を出すまで第8回 「明るい」時代と山田太一ドラマ
- 2016.11.16本を出すまで番外編2 佐藤真の「不在」を見つめて
- 2016.04.29本を出すまで番外編1「失われた20年」と佐藤真
- 2015.09.04本を出すまで第7回 返品制度の壁と事業計画

