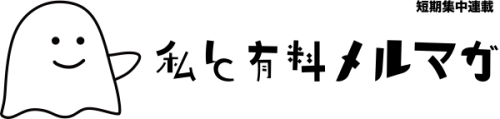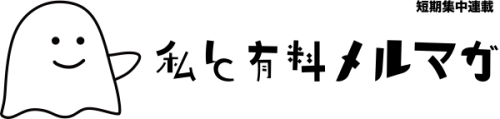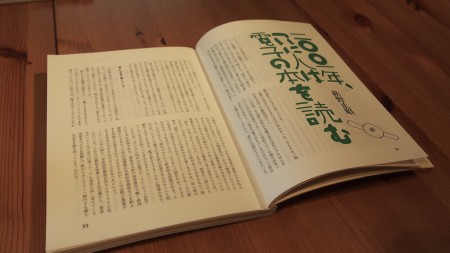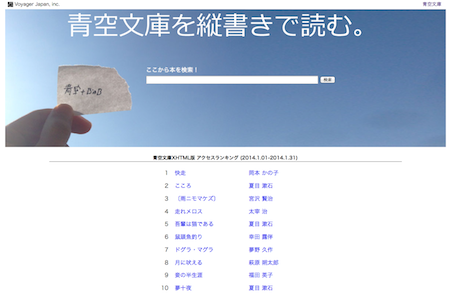東京都写真美術館で行われていた恵比寿映像祭で、2月22日に「電子書籍化の波紋-デジタルコンテンツとしての書籍」と題したシンポジウムが開催されました。これは当日の昼間に放映された、Google Books にまつわる騒動を題材としたドキュメンタリー映画「電子書籍化の波紋《グーグルと知的財産》」と連動したプログラムで、グローバル化やデジタル化の波が「知的財産」や「電子書籍」にどのような影響をもたらすかについて、出版社・弁護士・哲学者・政治家などさまざまな立場から論じた内容です。

登壇者は、写真右から福井健策氏(弁護士)、神谷浩司氏(日本経済新聞文化部記者・討論司会)、角川歴彦氏(株式会社KADOKAWA取締役会長)、エルヴェ・ゲマール氏(政治家/前フランス経済・財務・産業大臣)、エリック・サダン氏(哲学者/エッセイスト)、ドミニク・チェン氏(株式会社ディヴィデュアル共同創業者/ NPO法人コモンスフィア理事)です。在日フランス大使館とアンスティチュ・フランセ日本の共催で、フランス語と日本語の同時通訳が用意されていました。
“All rights reserved.” ではないことの意思表示
シンポジウムはまず、ドミニク・チェン氏によるコモンスフィア(旧クリエイティブ・コモンズ・ジャパン)の活動についての説明から始まりました。従来は、著作権が全て保持(All rights reserved.)された状態か、自由に利用できるパブリック・ドメインのどちらかしかなかったところに、その中間の概念を用意したのがクリエイティブ・コモンズ・ライセンスです。著作権者の意思によって、第三者が自由に使える範囲を「表示」「継承」「改変禁止」「非営利」の組み合わせによって示すことができます。クリエイティブ・コモンズ・ライセンス v2.1 日本版がリリースされたのが2004年3月なので、日本で活動を始めてちょうど10年ということになります。ライセンスは動画投稿サイトのYouTubeや、写真共有サイトのFlickrなどさまざまな場所で利用されており、活動の輪はどんどん広がっています。
また、日本独自の活動として、漫画家の赤松健氏によって提唱された「同人マーク」が紹介されました。これは、現在交渉中のTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)で米国が要求している「著作権侵害の非親告罪化」が実現してしまうと、同人活動が萎縮してしまうという危機感から対抗策として生み出されたものです。クリエイティブ・コモンズ・ライセンスは日本における二次創作の同人活動に対する意思表示としてはあまり使い勝手が良くないことから、「第三者が二次創作同人誌の頒布を同人誌即売会で行うこと」を著者があらかじめ許諾するという、日本独自のライセンスを別途用意したのです。赤松氏が「週刊少年マガジン」で連載している「UQ HOLDER!」にはタイトルロゴのすぐそばに表示されていますが、現時点ではまだ試験運用中です。
チェン氏は、角川歴彦氏の著書『グーグル、アップルに負けない著作権法』から、ドワンゴ会長の川上量生氏による「ネット時代に作ったコンテンツの寿命を延ばそうと思うなら、二次創作を認めてソーシャルで広がっていく仕組みを作らないといけない」という発言を紹介しました。新しい作品は、何もないところから一人の天才が生みだすわけではなく、過去の様々な作品にインスピレーションを受けて生まれるものだとチェン氏はいいます。また、ソーシャルメディアの普及によって、読者と著者がフラットな立場で会話できるようになったことで「読者が編集者的になってきているのではないか?」という指摘は、私自身も実感するところであり共感できました。
デジタル化の波が著者に与える不安
続いてエリック・サダン氏から、著者の立場からの意見が述べられました。サダン氏は2001年に、デジタル化やグローバル化によって発生するさまざまな問題について討議するシンポジウムに参加したそうです。そのころはみな熱に浮かされたようになっていて、未来について楽観的だったといいます。しかし、例えば個人のプライバシーに関わる問題や、インターネット上での一部の企業による寡占化、出版社や新聞社の弱体化など、当時からすでに予見されていた問題が現実のものになっていくにつれ、だんだん不安になっていったそうです。
タブレットが普及して重い本を持ち運ぶ必要はなくなり、使いやすくなったのは間違いないとサダン氏はいいます。しかし作家の一人として、「タブレットのバーチャル性」や、知的所有権を容易に侵害できること、紙の本のように集中して読むことができないことなどを、果たして歓迎してもいいのかと疑問を持っているそうです。「電子書籍」はすでに後戻り不可能な領域まで拡大していることは理解しているし、「新たな知覚のゲーム」や使い方が生まれているのも分かっているが、同時に批判的な観察をすることも必要だとサダン氏は説きます。
サダン氏の発言は哲学者だけあってかなり難解で、同時通訳の方もかなり苦労していたようです。発言の趣旨を正確に把握できたかどうか分からないのですが、「本を書く行為がいろんな人の喜びのためになるには、著作権=既得権を保持しなければならない」ということを強く訴えかけていたようです。「ネットではみんな無料になってしまう」という発言があったので、創作者にちゃんと対価が還元できないと「文化」が衰退してしまうという危機感を表明していたのだと思われます。
プラットフォーマーとの対決姿勢
角川歴彦氏からは、事業者としての立場からのプレゼンが行われました。KADOKAWAは出版社であると同時に、ゲーム、アニメ、映画も出している会社です。直営電子書店「BOOK☆WALKER」のアプリは121万ダウンロードされており、185社8万7000点(うちKADOKAWAの本は約2万点)の電子書籍を配信しています。日本は電子書店の激戦区ですが、紙の出版市場としても大国だし、ネットもアメリカに次いで2番目だといいます。角川氏はコンテンツを創作する立場として、このままだとアメリカにコンテンツの付加価値を奪われてしまうという強い危機感を持っているそうです。そこで、コンテンツレイヤーの力を結集し、プラットフォーマーに対抗しようと提案します。
角川氏は、地方の駅前商店街が、デジタル化によってどんどん衰退しているといいます。ゲームセンター、時計店、CD・レコード店、映画館、カメラ・写真店、本屋などなど、文化伝達の担い手が衰退してしまったと。ただ、アメリカに比べれば日本はまだ頑張ってる方だとも感じているそうです。日本の出版界は本屋を大事にしており、アメリカの出版社が本屋を守れなかった教訓を活かしていると。そして、リアルとデジタルの融合をはかっていけるという自信をのぞかせます。具体的な言及はなかったのですが、恐らく昨年末に話題になった「電子書籍販売推進コンソーシアム」の実証実験のことを指しているのだと思われます。
フランスにおける書店保護施策
エルヴェ・ゲマール氏は、フランスにおいて著作権とその擁護のために行われたさまざまな施策や法制化について紹介しました。フランスでは個人書店を保護する目的で、1981年に書籍の定価販売を義務付ける法律が制定されています。近年でも、書籍がデジタル化されていく中でどのような法律が必要が検討され、さまざまな試行錯誤が行われたそうです。
パブリック・ドメインの文化遺産については、電子図書館「Europeana」で無償提供していくことになりました。デジタル書籍の付加価値税(通常20%)は、紙の本と同じ税率(5%)にしました。また、販売価格は、Amazonなどの販売プラットフォームではなく出版社が決められるようにしました。出版社と作家の関係においては、紙の本の出版契約と同時に、電子出版契約を結ぶ形にしていくそうです。
問題は、著作権保護期間中で、新刊はもう流通しておらず、デジタル化もされていない「グレーゾーン」領域にある本です。フランスの著作権保護期間は著者の死後70年と長く、20世紀に書かれた作品の80%はいまだ保護下にあります。フランスでは、ドキュメンタリー映画「電子書籍化の波紋《グーグルと知的財産》」の中でも描かれていたように、Google Books プロジェクトはこの「グレーゾーン」の本をデジタル化することにより市場の支配を試みた、というように受け止められています。
結局、2012年1月に制定された法律で、「グレーゾーン」の本をデジタル化するのは、作家と出版社の共同会社の役割ということになったそうです。著作権保護期間中にも関わらず紙では流通していない本を、デジタル化によって読むことができるようにするプロジェクトを、アメリカの一企業に委ねるのをよしとしなかったということでしょう。ゲマール氏がプレゼンを「グローバル世界に怯えてはならない」と締めくくったのが印象的でした。
ナショナル・デジタル・アーカイブ構想への提言
福井健策氏からは、日本におけるデジタル・アーカイブ構想と法的課題についてのプレゼンが行われました。日本では2009年に127億円という予算が計上されたことでデジタル化が一気に進み、国立国会図書館デジタルコレクションとして228万点がデジタル化され47万点が公開されています。これは欧州の Europeana に刺激を受けているのと同時に、Google Books プロジェクトに対するある種の危機感が共有されたことに依るものだと福井氏はいいます。
しかし、博物館や図書館の最大の課題は、予算不足、人員不足、著作権処理ができないことだそうです。特に大きいのは権利処理の壁で、問題なのは著作権使用料ではなく、権利者を探して交渉する手間と時間だといいます。例えばNHKには78万番組がアーカイブとして保存されているものの、10年間権利処理をし続け、NHKオンデマンドで公開できたのが8500番組。このままのペースでは、権利処理だけで1000年かかってしまうという状況だそうです。
権利者を探しても見つからないという「孤児作品(オーファン・ワークス)」問題は、さまざまなところで顕在化しています。例えば国立国会図書館のデジタル化では、明治期に書かれた著書の71%に権利者が見つかっていません。比較的新しい放送台本ですら、50%しか権利者が見つからないという状態です。孤児作品を利活用するため裁定制度があるのですが、厳格に運用され過ぎていてあまり使われていないという現状もあります。
そこで福井氏は、全国のデジタルアーカイブのネットワーク化と統一ゲートウェイ(横断検索)化、各国デジタルアーカイブとの相互接続の促進、孤児著作物相互利用協定の締結、デジタル化ラボ・字幕化ラボの設置、公的アーカイブはオープンデータ化を原則とすること、基本的にパブリックライセンスを付与すること、デジタルアーキビストの育成と研修の充実化、孤児作品や絶版作品のデジタル活用促進といった提案を行い、プレゼンを締めくくりました。
サダン氏、角川氏、ゲマール氏は、Google Booksに代表されるアメリカ企業のグローバル活動を文化侵略や脅威として捉え、いかに対決していくかという観点での発言が中心でした。チェン氏、福井氏は少し立場が異なり、権利を既得権としてただ保護するのではなく、文化資産として活用することにより輝きを増す方向での提案を行っていた、ということになるでしょう。

パネルディスカッションでの論点
このように、同じ「電子書籍化の波紋」というテーマでも、かなり角度の異なるプレゼンだったため、その後のパネルディスカッションは「ディスカッション」というよりは、それぞれの意見を補強するような形で進められました。正直、まとめようがないので、箇条書きにしておきます。
- 本をスクリーンで読むことは、認識科学的にどのような影響があるのか。本を読むときはディープ・アテンション(深い注意)が必要になるが、スクリーンによる読書で文章への深い没入が可能なのか(サダン氏)
- 理想的な形は、物理的な本とデータの本をセットで販売することだと思う。ただ、日本の住宅事情では「本の重さで床が抜ける」という問題があるので、物理的フェティシズムを感じるような本だけ物理的な形で残しておくという選択肢になるのではないか(チェン氏)
- 自分は物理メディアとデジタルの両方を体験しているが、デジタルだけで育った世代にどんな影響があるのか。生身の体を持っている人間として、デジタルだけで育つのはよくないのではないか? という予感はある。デジタル・ディバイド(情報格差)という問題もある(チェン氏)
- 実際に自社で電子書店を経営してみてわかったことは、たくさんある。システム投資が大きく人員も多く配置しているので、まだ収益は上がっていないが、大きなビジネスチャンスを得つつあるという実感がある。KADOKAWAでは現在7%が電子書籍の売上。紙の書籍市場は13年間下がり続けており、紙の本を大事にしすぎるあまり出版社全体がやせ細っていくような状況は放置できない、積極的に取り組むべき(角川氏)
- フランスでは電子書籍市場の発展のために、税率を紙と同じにし、出版社に価格決定権があるようにした。この法律を施行したことで、Amazonのシェアは8割から5割に減少した。事実上の独占状態は市場として健全ではなく、Amazonは流通を独占している。だからこれは保護的な政策ではなく、同等の武器で戦わねばならないという公平性を確保するためのものだ(ゲマール氏)
- 「紙の旅行ガイドや料理本はなくなる」という予言がなされたことがあるが、まだ生き残っている。分野によって、デジタル化率は変わるのだろう。そのいっぽうで、デジタル化の先取りをすることで大きく収益を上げている企業もある。デジタルと紙は交じり合う。例えば、本を1冊から出版できるオンデマンド印刷。既存の出版社では出版してくれないような本が、世に送り出されるようになる。いい意味での多様化が生まれる。これほど幅広い著者がいる時代は、これまでなかっただろう(ゲマール氏)
- 一般的な新書は8万字だが、自分が先日「ミニッツブック」で出した本は2万字。本を書くことの敷居を下げることは、潜在的な作家を増やすこと。電子による新しい作家たちが次々と生まれている。紙のほうが表現しやすい場合もあれば、電子のほうがいい場合もある。例えば、料理のレシピコミュニティーサイト「クックパッド」には日本人が料理をする機会を増やす効果があり、結果的に紙の本の売上を増やしたのではないかと考えている。相乗効果やシナジーというのはあると思う(チェン氏)
- 「売り方」がだいぶわかってきた。紙と電子を同時に売ると、双方に良い効果がある。紙でベストセラーだった本は、電子でもベストセラーになる。リアル書店は坪数で在庫量が決まってしまうため、「グレーゾーン」の本が置かれない。そこにGoogleが介入するスキがあった。電子書店は、すでにリアル書店で置かれなくなってしまった本に、再び命を吹き込むことができる(角川氏)
- ボーンデジタルの出版物や大衆から発信されるコンテンツに対し、著作権法は冷淡なのではないかと考えている。いまの著作権法は知識人を守ろうとするもので、大衆が自ら発信していくことが考慮されていない(角川氏)
- 出版社に価格決定権があるというのは一般的には評判が悪いが、流通側に価格決定権があると、従来は4000社がそれぞれ決めていた価格を数社で決めてしまうことになる。プラットフォーマーはコンテンツ売上だけに依存したビジネスモデルではないので、流通側に価格決定権があると販売価格は確実に低下する。価格が下がっても素晴らしい作品が生み出され続けるのであれば、問題はないが……(福井氏)
- コピーの流通をコントロールするのが著作権(コピーライト)。流通経路が紙の書籍のように限定されているときには向いているモデルだが、デジタル化によってコピーの流通を止めることは難しくなっている。つまり、コピーを抑えて収益を上げるモデルが限界にきている。コピーコントロールを諦めて、流通は止められないという前提にたち、そこからどうやって収益を上げるかを議論していかねばならない(福井氏)
- デジタルでの読書データが収集されていることに不安を感じている。どの本をどのように読んだかという情報を、他の情報と交差されることで商業的な目的に利用されてしまうかもしれない(サダン氏)
- グローバル企業と対抗するには、まず税の回避問題と戦わねばならない。また、Amazonの責任者と話をすると驚くが、彼らにクリエイションに対する報酬という考え方はない。もう出ている本なのだから、なるべく安く消費者へ提供するという考えしかない。創作行為に対する報酬は重要だ(ゲマール氏)
- フランスの法律では、4つの書店に置いてなかったら絶版状態であると認定され、作家は出版社との出版契約を破棄できるようになっている。しかし、デジタルの場合は事実上絶版状態がないので、出版契約をデジタル化に合わせていかねばならない(ゲマール氏)
- 出版社を通していない作品の権利保護に関しては、例えば国会図書館のような公的機関に登録(納本)するようなシステムがいいのではないか(ゲマール氏)
会場からの質疑応答では、「出版することの敷居が下がることで、文化水準が下がるのでは?」という危惧に対し、チェン氏からは「正当な対価があれば、文化水準が下がることはない」という回答が、角川氏からは「トップレベルのものが低くなってくる危惧はあるが、同時に底辺が上がっていくだろう」という見解が述べられました。
学術書の出版環境が悪くなっていることに関し、角川氏が「それは電子書籍が生まれたからではない」と断言したこと、「アカデミックな本が刊行されなくなるのを放置してはならないから、出版事業者が学術書を存続させるために血の滲むような努力をしなければならない」という強い意志が述べられたことは非常に印象的でした。また、「出版の民主化が始まっている」という言葉が角川氏から発せられたことには、少し驚きました。出版社が、これまでと同じ役割を果たしていてはダメだという意識を強く持っているということなのでしょう。
また、福井氏とはシンポジウムの前後に、個人的に少し話をする機会があったのですが、ちょうど当日の朝に日本経済新聞から出ていた「(TPPで)日米を含む複数国は映画や音楽などの著作権を守る期間を権利者の死後70年に延ばす案を支持という記事に対する強い憤りを表明されていたことが、シンポジウムで語られていたことより印象的でした。結局、25日まで行われていたTPP交渉は大筋合意に至らなかったわけですが、ではこの報道は結局何だったのか。どこからの情報によって、このような報道がなされたのか。「電子書籍化の波紋」はアメリカのグローバル企業によって発生したわけですが、もっと大きな波紋がアメリカ政府によって引き起こされようとしていることも注視しておかねばならないでしょう。
■関連記事
・ドミニク・チェン 読むことは書くこと Reading is Writing 第10回「本の死とその蘇生」(DOTPLACE)
・リアル書店で電子書籍を売るということ
・グーグルはまだ電子図書館の夢を見ている
・グーグル・プロジェクトは失敗するだろう
・あらゆる知識にユニバーサル・アクセスを