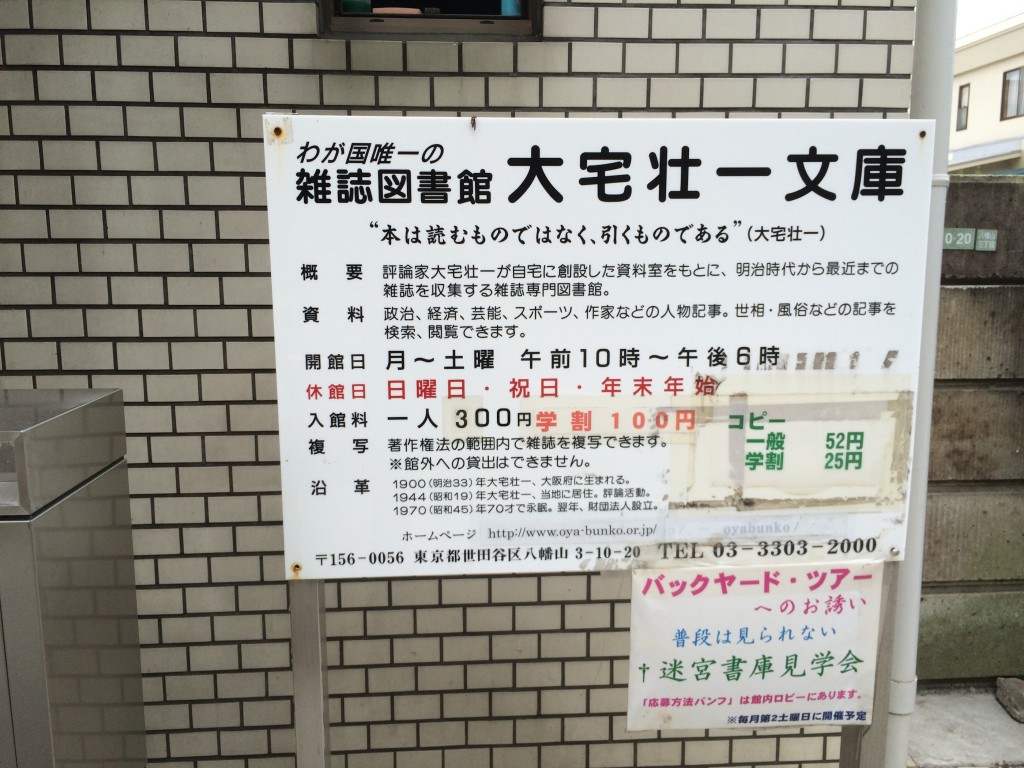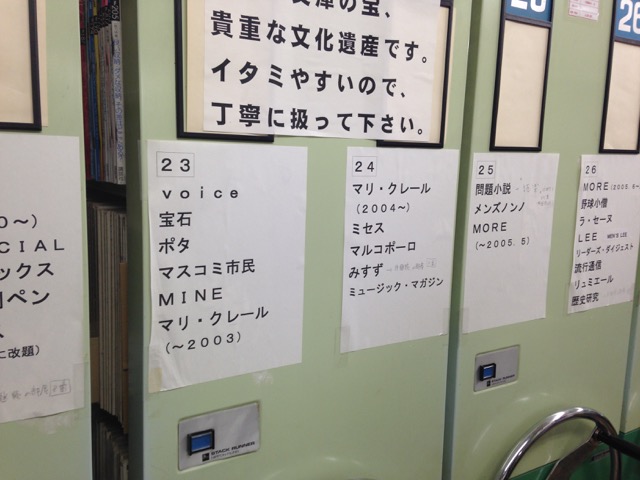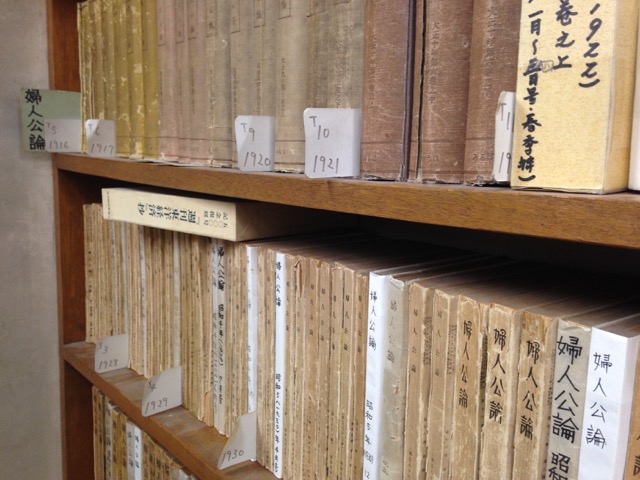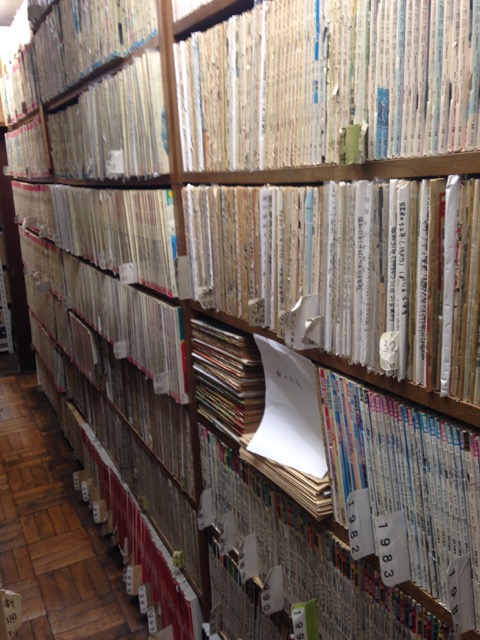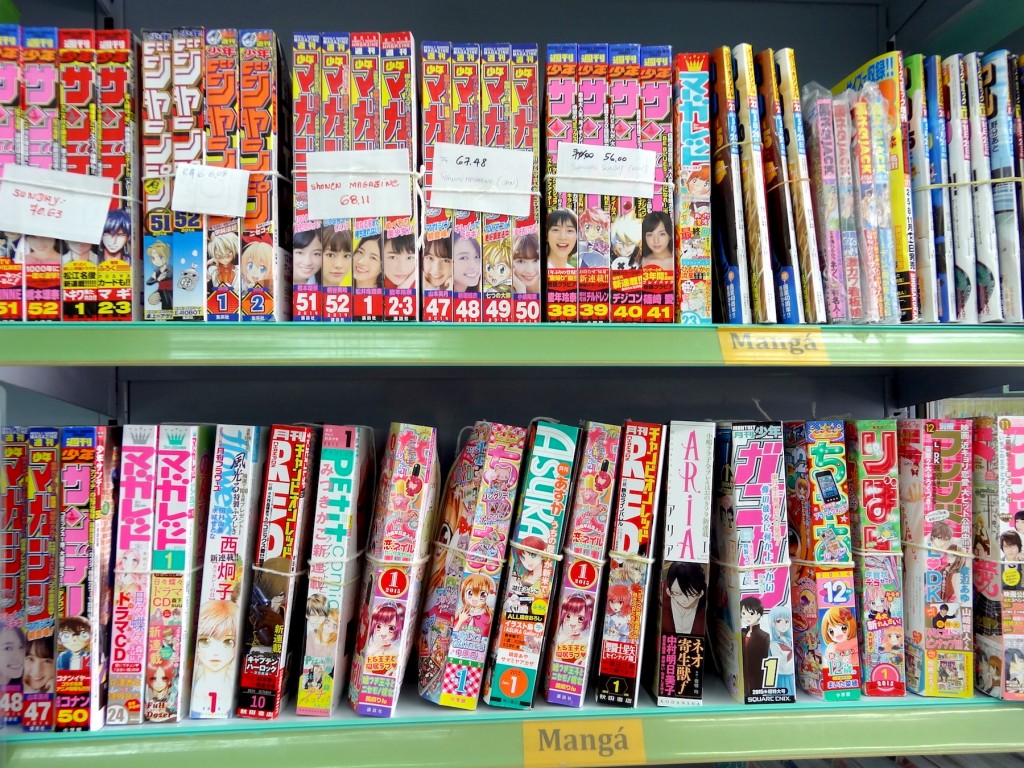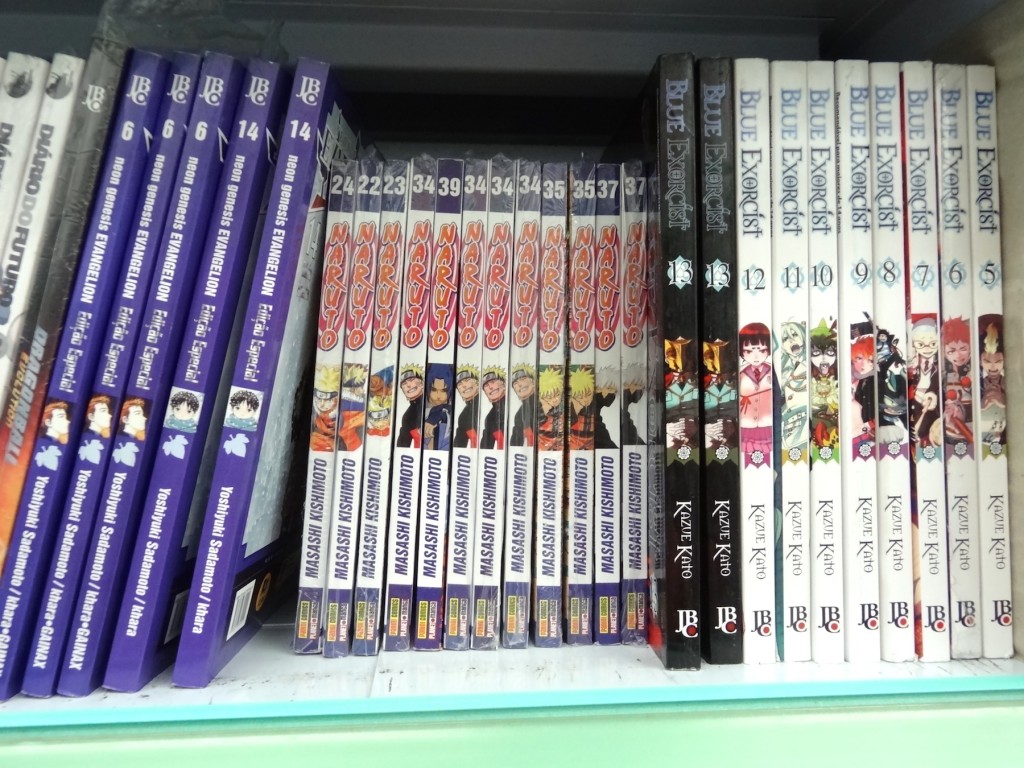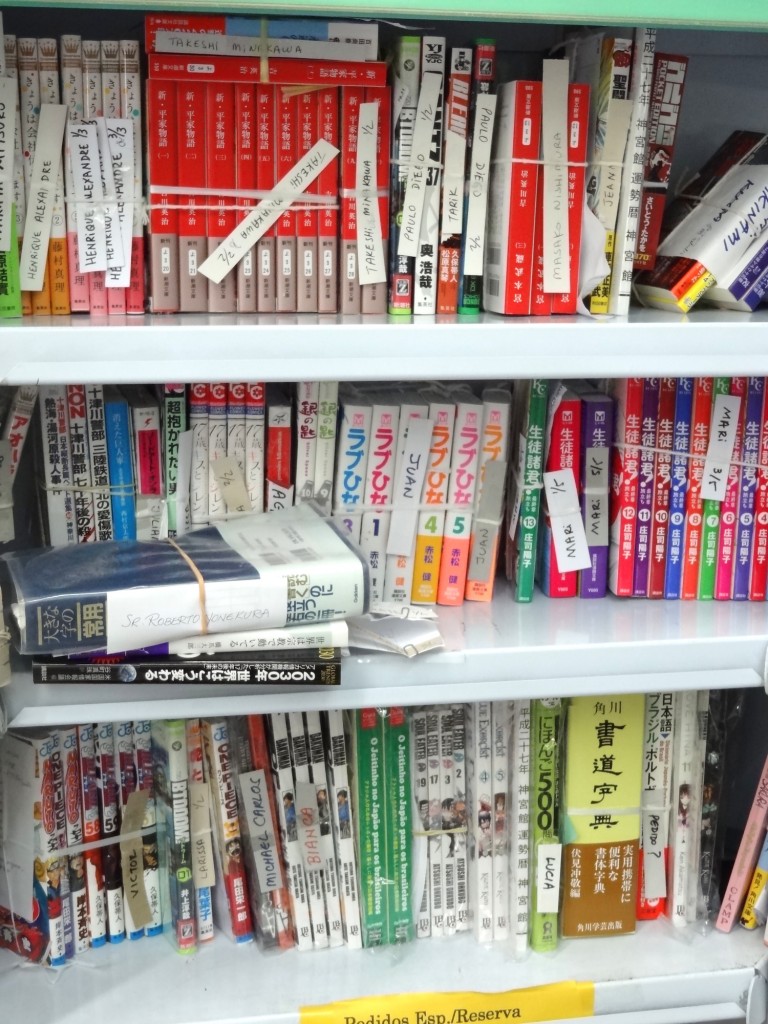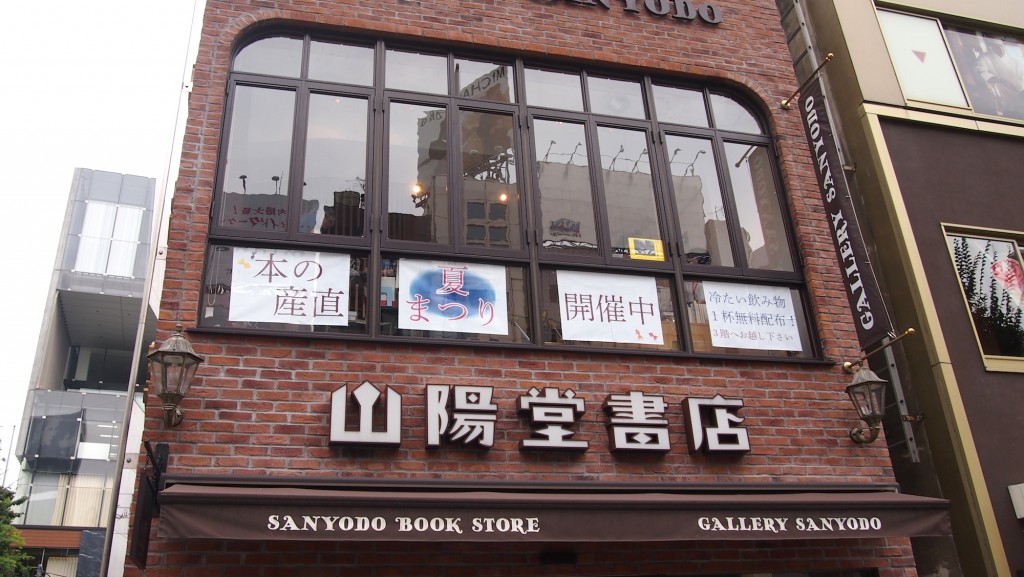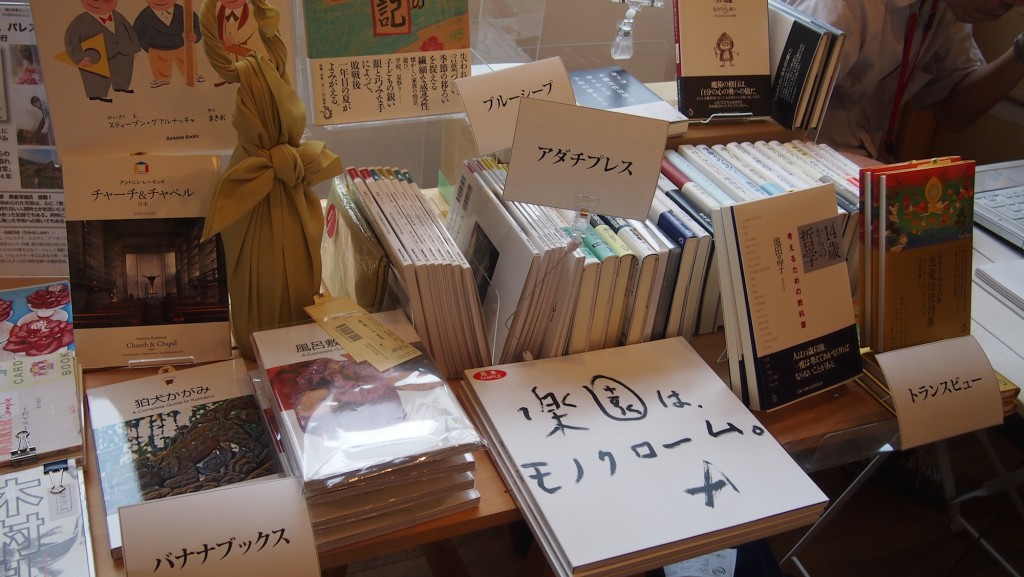京王線・八幡山駅で下車し、左手に都立松沢病院の鬱蒼とした木立を眺めながら大宅文庫(公益財団法人・大宅壮一文庫)へと向かう。この道を、いつも一人で、しかも、複雑な心理状態で歩いていた記憶がよみがえる――。
サラリーマン編集者をしていた20〜30代の頃だ。ある時は、予定していた取材先だけではページが埋まらず、締め切りが迫る中、急遽、ネタを探し直さねばならず焦っていた。またある時は、企画会議の直前だというのに手持ちのネタがなく、急ごしらえであろうが企画をひねり出さなくてはという不安に押しつぶされそうになっていた。そして資料を漁り終えると、一目散で編集部に戻らなければならない。街を眺める余裕すらなかった。何度も通った八幡山なのに、自分はこの街のことをほんとんど知らないことに気がついた。
大宅文庫に「行く人」と「行かない人」
実を言うと、今回、正式な取材の申し込みをする前、本誌「マガジン航」の編集・発行人である仲俣暁生さんとの打ち合わせのついでに、あらためて大宅文庫に足を運んでいた。というのも、前回の記事の最後で触れたとおり、仲俣さんは大宅文庫に行ったことがないというのだ。駆け出しの編集者の頃、情報誌やコンピューター雑誌の仕事が中心だった仲俣さんには、大宅文庫を特に必要とする機会がなく、そうこうしているうちに「グーグルの時代」が来てしまったのだという。
たしかに、筆者が知るフリーのライターや編集者の先輩の中にも、大宅文庫に行ったことがないという人が何人かいる。彼らのキャリアを見ると、自社に資料室を持つ大手出版社や新聞社から独立した人が多い。また、出版社でもテレビの制作会社でも、「資料探し」は下っ端の仕事。売れっ子の文筆家の中には、担当編集者や若手のライターに、 それを依頼する人もいる。大宅文庫はマスコミ関係者御用達というイメージが定着しているが、キャリアや立場、仕事内容の違いで、ずっと縁がなかったという人ももちろんいるのだ。
まずは仲俣さんに、大宅文庫の「底力」を、利用者として体感的に理解してもらわなくてはいけない。打ち合わせの席で、開口一番、そのことを伝えると、仲俣さんも同じことを考えており、小一時間ほどの打ち合わせの後、早速、大宅文庫へと向かうことになった。大宅文庫の窮状を、声高に訴えるだけの記事にはしたくない。使い勝手に多少の不満はあるが、時代の流れの中で淘汰されてもしかたがないとも思っていない。大宅文庫は、国立国会図書館や東京都立多摩図書館といった公立の雑誌アーカイブに勝るとも劣らない、「私設」ならではのサービスを提供している。それを知ってもらいたかった。
大宅文庫の館内は、お盆休みに入る前日だったせいか、それほど混んではいなかった。数日前、雑誌「TOmagazine」のオフィシャルサイト「TOweb」で知った大宅文庫のバックヤード・ツアーに参加したときも、土曜日の午前中だったせいか、マスコミ関係と思しき利用者はあまり見かけなかった(ちなみに、最新号の「TOmagazine」[6号]で批評家の大澤聡さんが、大宅文庫についての仔細なレポートを寄稿している。そちらもぜひ、ご一読いただきたい)。
今回の訪問は、取材前のロケハンと大宅文庫初体験となる仲俣さんの案内役ではあったが、以前から大宅文庫で調べたい記事があったので一石二鳥だった。調べたかったのは、小説家・後藤明生(1932~1999年)に関するものだ。
以前、本誌でも紹介していただいたが、筆者は後藤明生の長女で著作権継承者の松崎元子さんと「アーリーバード・ブックス」というレーベルを立ち上げ、セルフパブリッシングによる電子書籍での復刊を行っている。現在までに26作品をリリースし、今後もさらに作品数は増える予定だが、その一方で、後藤明生に関する評論などを集めた書籍を刊行したいと目論んでいた。そのための資料を探そうと思っていたのだ。
すでに「国立国会図書館サーチ」の検索は済ませており、そこで見つかった書籍や雑誌記事、大学の発行物に掲載された論文などは、おおむね入手していた。そのまま国会図書館にオンラインで申し込んでコピーを郵送してもらったものもあれば、近所の図書館の蔵書をコピーしたものもあり、古書価が安い書籍に関してはAmazon.co.jpのマーケットプレイスで購入していた。
しかし、雑誌の目次に記されたキーワードからしか記事が検索できない「国立国会図書館サーチ」では、ヒットしない記事も多い。目次だけでなく利用者が必要と思われるキーワードを独自にタグ付けしてデータベースを構築している大宅文庫であれば、さらに多くの記事が見つかるはずだ。
Web OYA-bunkoの威力
さっそく受付で入館料を払い、1階に設置されたコンピュータ端末「Web OYA-bunko」で検索すると……。やはり、あった。「中央公論」2014年11月号では、「谷崎潤一郎賞の50年 歴代受賞者に聞く 私の好きな谷崎賞受賞作品」という記事の中で、小説家の阿部和重さんが後藤の『吉野太夫』について記していた。また、評論家の坪内祐三さんが「群像」2012年12月号で、翻訳家の東海晃久さんが「新潮」2012年11号で、未完のまま長らく単行本化されたなった長編小説『この人を見よ』を書評していた。さらに、「週刊文春」2013年11月21号でライターの永江朗さんが取り上げてくれたアーリーバード・ブックスの記事、「新潮」2014年4月号に著作権継承者の松崎さんが寄稿した「後藤明生・電子書籍コレクション」に関する記事もヒットした。
最も驚いたのは、「ユリイカ」2001年3月号「特集・新しいカフカ」に掲載された文芸評論家・城殿智行さんの小論だ。当該誌をめくってみると、目次にも記事の見出しにも「後藤明生」の文字は見当たらない。しかし、記事を読んでみると、後藤作品におけるカフカの影響を論じたものであることがわかる。目次に記されたキーワードからしか記事が検索できないデータベースでは、絶対に見つからない原稿だ。
これほど多くの記事が見つかるとは、予想以上だった。隣席に陣取る仲俣さんに、他の利用者の迷惑にならないよう声をひそめながらも、少し興奮ぎみに「Web OYA-bunko」の素晴らしさを力説する。単純なキーワードだけで検索すると、ヒットする記事が多すぎて逆に不便なので、検索キーワードの選び方にもセンスが必要になるなど、ちょっとしたコツを伝授しながら、それぞれ検索に没頭した。
筆者が閲覧を申し込んだ雑誌は40冊。手元に届くまでの時間は20分だった。後日の取材でわかったことだが、閲覧が申し込まれた雑誌を書庫から取り出して利用者に届けるまで、「20冊で10分」を目標にしているという。そこから、雑誌のページを繰って、お目当の記事に目を通し、必要なものはコピーを申し込む。20冊35枚のコピーが手元に届くまでの時間は30分。この早さは、国立国会図書館を上回るのではなかろうか。
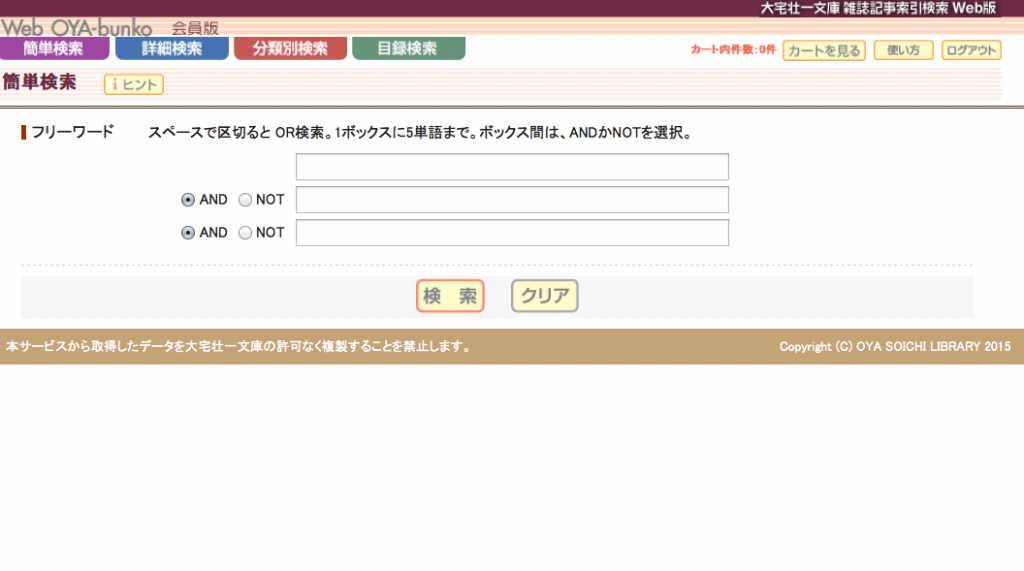
Web OYA-bunkoのログイン後の画面。複数の検索方法が可能。
Web OYA-bunkoの利用案内ページ http://www.oya-bunko.or.jp/web_oyabunko/tabid/73/Default.aspx
仲俣さんが「このデータベース、オンラインで家でも使えたら便利だよね」と言うので、待ってましたとばかりに「今年の4月から使えるようになったんですよ」と説明し、筆者自身もその場で「定額利用サービス」に申し込んだ。
2002年、これまで大宅文庫に行かなければ利用できなかった「Web OYA-bunko」が、大学や公立の図書館にも提供されるようになった。2013年には、賛助会費が年間1万円の個人会員も、オンラインで利用できるようになった。ただし、検索表示料金は1件につき10円。コピーの郵送サービスのほかにファクシミリによるオンライン複写サービスもあり、送信資料代は1枚268円、送信手数料は1件309円。営業日の16時までに申し込めば、当日中に送信してくれる。
がしかし、そこまで急ぐような用事は滅多にないし、それぞれの料金も高い(ただし、会員になれば、大宅文庫に行って資料を閲覧・コピーする際の割引がある)。そのため、地方在住者などからの要望もあり、今年4月からは個人会員にならなくても「Web OYA-bunko」が利用できる、さきに言及した「定額利用サービス」が始まった。年間検索料は5400円で、検索表示料金は0円。ファクシミリによるオンライン複写のサービスはつかないが、有料でコピーの郵送はしてくれる。しかも、3ヶ月間は無料のトライアル期間がつく。大宅文庫に足を運ばなくてもホームページから申し込みができるので、興味がある方は、ぜひ使い勝手を試していただきたい。
「国会図書館のデータベースではヒットしない資料がこれだけ見つかって、しかも月額にすれば450円かあ。近所の図書館にありそうな雑誌はそこでコピーすればいいんだから、これは便利だし、お得ですね」と仲俣さん。筆者の目論見は見事に成功した。
経営悪化の背景
こうした予備取材を経て、経営状態を含めた大宅文庫の実状を伺うべく、正式に取材を申し込んだ。取材に応じてくださったのは、バックヤード・ツアーの際にもお世話になった資料課の黒沢岳さんである。
ここで訂正が一つ。前編で〈平成26年度の貸借対照表を見ると、負債合計は38,540,950円……〉と記したが、これは平成26年度の事業計画の負債合計で、実質的な赤字は正味財産増減計算書に記された当期経常増減額の43,613,580円である。つまり、昨年度は事業計画の段階から赤字予算を組んでいたことになる。さらに平成27年度の事業計画でも24,904,202円の赤字が見込まれている。昨年度、借地だった敷地を購入したことが赤字の原因かと思いきや、平成25年度も約3600万円もの赤字を計上しており、それが原因とも考えにくい。大宅文庫が慢性的な赤字経営になっていることは間違いなさそうだが、その原因は何か? 今後どうやって経営を健全化していくのか?
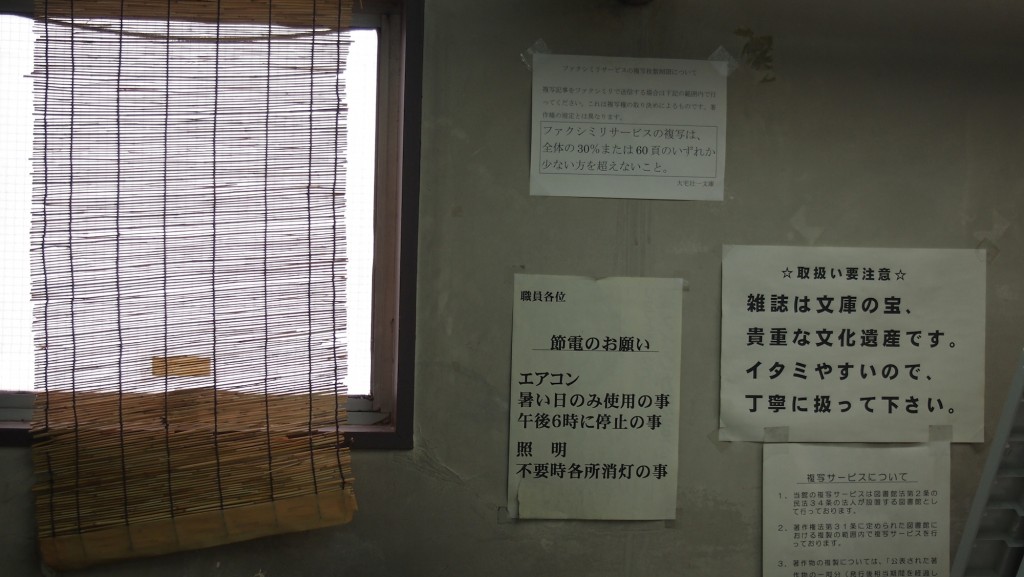
「雜誌は文庫の宝、貴重な文化遺産です。」との張り紙とともに節電も励行。
赤字のいちばんの原因は、やはり利用者の減少だった。ピーク時の2000年前後、1日の利用者は約100人で、多い日の閲覧は1万冊もあったが、現在は1日に50~60人、閲覧は2000冊、多い日でも3000~4000冊とのこと。さらに、年間契約の法人会員の減少が著しく、それが経営悪化の原因になっているという。法人会員の多くはマスコミ関連企業だが、出版社はまだしも、放送関連企業の継続契約が激減しているという。
この投稿の続きを読む »