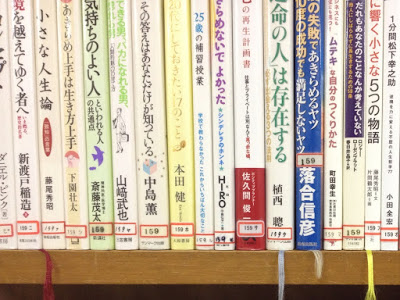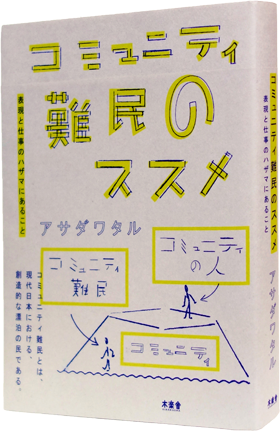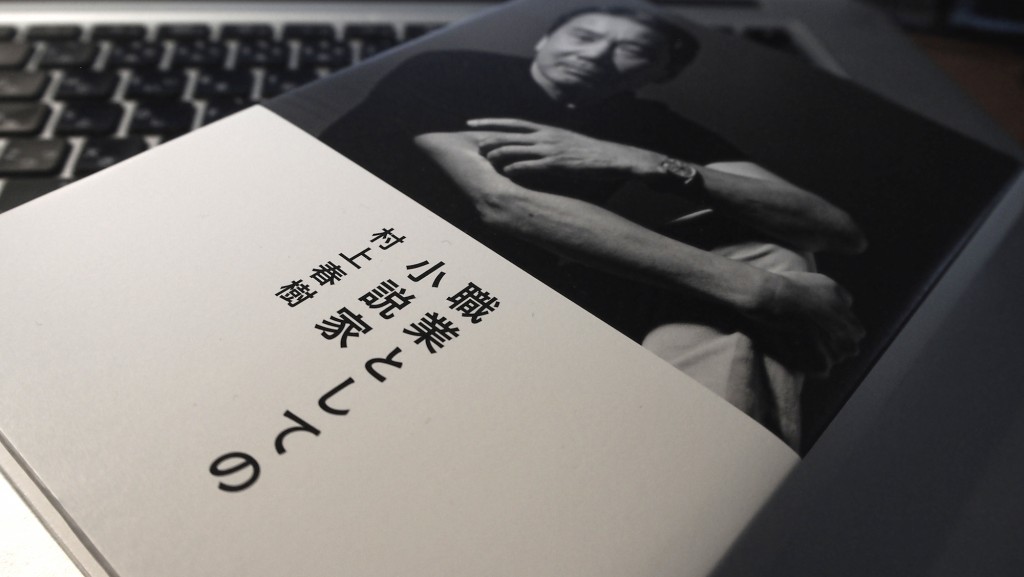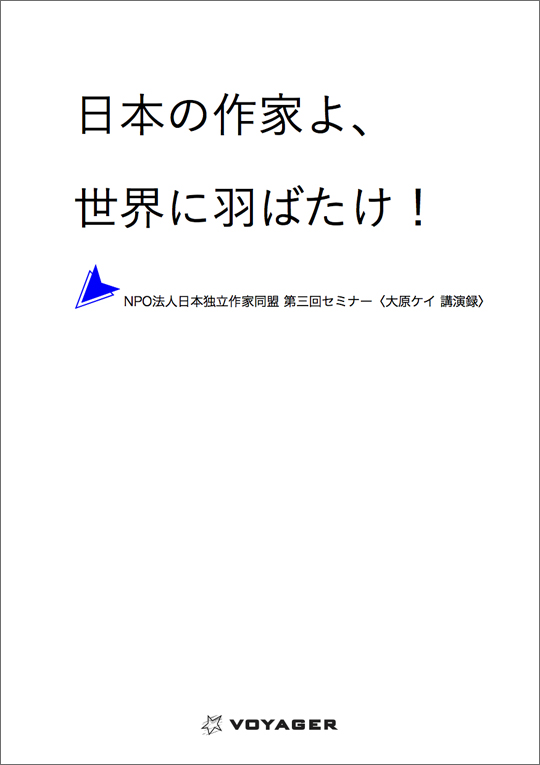これまでの経緯
こんにちは。この「マガジン航」で以前、電子書籍への再販制度導入について、書かせていただいたことがあります(リンク)。
その時は、再販導入を主張する鈴木藤男氏(NPO法人わたくし、つまりNobody副理事長)、落合早苗氏(hon.jp代表取締役)の主張を、主に経済学的な観点から、分析しました。
紙幅の関係で、「電書再販論」のもう一人の主張者である、高須次郎氏(日本出版者協議会会長、緑風出版代表)の所論については、「後編」に回すことにしたのですが、その「後編」を書きあぐねているうちに時間がたってしまいました。すみません。
今回、「後編」として、「電書再販論」について、さらに詳しく書かせていただきます。
そもそも「再販制度」とは?
はじめに、出版物の「再販制度」とは何かについて、ちょっと整理しておきます。
独占禁止法では、商品の生産者や供給者(この場合は出版社や取次)が販売者(この場合は書店)に対して一般消費者に対する(最終)販売価格を(拘束)強制することを禁じています(法第2条第9項)。
ところが新聞、雑誌、書籍などの商品(著作物)については、法第23条第4項によって対象外とされています。これが「再販制度」と呼ばれるものです。
ただし、「制度」と名前はついていますが、
「著作物はすべて出版社の決めた価格で売らなければ違法!」
という法律があるわけではありません。
あくまでも原則は、「生産者が最終販売価格を決める契約は違法」ですが、著作物に限り、この規定の対象外としますよ、としているにすぎません。いわばお目こぼしです。
このあたりを誤解して、本や雑誌が安売りされていると聞くと、即、
「再販制度に違反している!」
とまるで犯罪でも見つけたかのように脊髄反射する人がいますが、間違っています。本の安売りは犯罪ではありません。
当事者が合意すれば原則、どのような契約でも結ぶことができる。これは「契約自由の原則」あるいは「私的自治の原則」と呼ばれる近代私法の大原則の一つです。
つまり著作物については、
生産者が最終価格を決める契約(再販契約)を結んでもいいし、
結ばなくてもいい(最終価格を決めない契約=非再販契約を結んでもいい)
というのが正確な理解です。
さて、紙の書籍や雑誌については、このように出版社が決めた価格(定価)での販売が広く行われ、それは合法なわけですが、電子書籍は現在、対象外となっています。
つまり、電子書籍については、生産者が最終価格を決める契約は、他のほとんどの商品と同じように「違法」とされるのです(実は抜け道があるのですが、これについては後述します)。
これに対して、独禁法の第23条第4項を改正するなどして、電子書籍も第2条第9項の対象から除外し、「再販制度」の適用対象とするとする動きがあります。これが「電書再販論」です。
前編のおさらい
前回、筆者は、業界誌「出版ニュース」に掲載された、二つの「電書再販論」(鈴木藤男氏、落合早苗氏)を取り上げ、それぞれの問題点を指摘しました。
鈴木氏の主張は、煎じ詰めれば、次のような内容になります。
著作物は通常の商品と異なり、自由競争になじまない。そのため、再販制度が設けられた。電子書籍も紙の書籍と同様、著作物なのだから、同じ扱いにすべきだ。
それに対して筆者は、まず、前段について、著作物が本質的に他の商品と異なる、というのは言い過ぎではないかと示唆しました。
ついでにいうなら、木下修「書籍再販と流通寡占」(アルメディア)によると、著作物に再販制度が導入されたとき(1953年)に、このような「本質論」を出版界が主張した形跡はありません。
それどころか、同書には、「文化保護のために再販を導入した、というのは後付けでつけられた理屈ではなないか」と疑わせる証言が、複数紹介されています。
とはいえ、再販導入後数十年にもわたる日本の出版の発展に、再販制度が、少なくとも、ある程度の寄与を果たした可能性は、否定できないかもしれません。
ただし、1900年から1997年まで再販制度を実施していたイギリスでは、再販廃止後、書籍の刊行点数、出版社の売上、国民の書籍の購入額、新規参入の出版社数のいずれもが、成長を続けていることにも留意すべきです(この点は前回も紹介しました)。
さらに、百歩譲って、紙の出版物ではプラスの効果があったとしても、ただ「似ている」というだけで同じ仕組みを電子書籍にも適用すべきかどうかは、別問題です。
このような理由で、鈴木氏の「電書再販論」に、筆者はあまり説得力を感じなかった、ということを書きました。
次に落合早苗氏です。同氏の主張をまとめますと、次のようになります。
電子書籍の価格は競争が激しく、下落傾向にある。米国では価格競争のせいで大手書店チェーンが倒産した。行き過ぎた価格競争はアマゾン一人勝ちの状況を生む。書籍や電子書籍は売れればいいというものではない。「電子図書」という新しいジャンルを創設し、再販制度の適用の可否について議論すべき。
これに対して筆者は、米国で苦境に立っているのは、主に金太郎飴のような大手書店チェーンであって、中小書店は健闘しているという事実を指摘しました。
また、このときは書きませんでしたが、これら書店チェーンは、オンライン書店の隆盛と並行して衰退しているのは事実ですが、それが行き過ぎた価格競争のため、という証拠はありません。
リテールの中心が、リアルからオンラインへ移行しているのは、出版物だけでありません。一般消費財、アパレル、家電、食料品など、すべての商品で起きていることです。人々がリアル店舗でなく、オンラインで購入するのは、価格が安い、ということもありますが、便利、というのがいちばんの理由でしょう。
価格競争だけで「アマゾン一人勝ち」になっているかのような言い方は牽強付会ですし、「電子図書」という別のカテゴリーを設けると、なぜそこではアマゾン一人勝ちにならないのか(価格でなく利便性が「一人勝ち」の原因だとしたら、何も変わらないでしょう)、説得力ある議論が展開されているようには思えません。
そもそも現在、再販制度下にある紙の本は、アマゾンも定価で販売しておりますが、そのことが、アマゾンがオンライン書店ビジネスで優位に立つことを防いでいるでしょうか?
「出版物販売額の実態2014」(日販)によりますと、インターネットルートによる書籍の販売額は2013年の時点で約1600億円。このうちのかなりの部分が、アマゾンジャパンによるものと見られています。
CCCの書籍・雑誌の売上高が1130億円(2014年3月時点)、紀伊國屋書店の売上が約1070億円(2014年11月期)です。アマゾンが日本での出版物売上を公表していないので、確実なことは言えませんが、日本最大の書店はアマゾン、という説は、この数字を見る限り否定できないと考えられます。
アマゾンの独占的な台頭を防ぎたいのであれば、それを可能にしている、再販制度を含む現行の出版ビジネスのやり方がまずいのではないか? と考えるのが普通の思考法でしょう。逆に、「アマゾン一人勝ち」になっている現在の紙の本の出版慣行を電子書籍にも適用すれば「アマゾン一人勝ち」を抑えられる、と考えるのは、通常の論理では、ちょっと理解ができない超展開です。普通に考えて、紙書籍で起きたことが電子書籍でも再現されるだけではないでしょうか?
価格競争のある世界で何が起きているか
ところで、世の中のほとんどの商品では、価格競争があります。たとえば、先日、筆者は冷蔵庫を買い換えたのですが、パナソニック、日立、シャープ、ハイアールなどを比較して、結局、日立のものを買いました。同等の性能の製品の中で、割安だったからです。
価格競争があるために、冷蔵庫業界では「一人勝ち」が起きているでしょうか? 日経トレンディが引用しているデータによると、2013年時点の冷蔵庫国内シェアは、パナソニックがトップで約22.6%、シャープ約21.8%、日立アプライアンス約18.5%、三菱電機約12.6%……だそうです。
同じく激しい価格競争のあるビール業界では、周知のとおり十数年にわたってキリンビールが圧倒的なシェアを持っていましたが、1987年の「スーパードライ」の登場以降この構図が崩れ、アサヒビールが首位を奪還、その後、取ったり取り返したりのシーソーゲームが続いております。ロイターによりますと、2014年時点では、アサヒが38.2%でトップ、2位のキリンが33.2%、サントリーが15.4%のシェアを獲得したそうです。
要するに、(極めて常識的な話ですが)価格競争があっても、「一人勝ち」になっている業界と、なっていない業界があるわけです。そして、価格競争以外の原因で、長年続いた「一人勝ち」が崩れることもあります。
従って、論理的に考えれば、「価格競争をなくせば『一人勝ち』がなくなる」という結論は出せないはずです。
となれば、単に、「一人勝ち」が起きている、と指摘するだけでは、制度の導入を合理化する理屈としては、あまりも弱いとしか言いようがありません。
というわけで、鈴木氏、落合氏ともに、「紙の本が再販なのだから、電子書籍も再販に」となんとなく単純に類推しているに過ぎないのではないか、というのが筆者の印象でした。
価格決定と紙への影響
鈴木氏の本質論、落合氏の競争政策論に対し、高須次郎氏は、やや違ったアプローチで「電書再販論」を主張します(「出版ニュース」2014年1月上・中旬号)。
高須氏は、中小零細出版社は電子書籍をいつでも発行できる体制にあるが、慎重姿勢をとっているとし、その理由として、電子出版物に対する出版社の権利が確保されていないこと、そして電子書籍に再販制度が適用されていないことをあげています。
(このうち、前者に関しては、2014年4月に成立し、2015年1月に施行された改正著作権法で、いわゆる「電子出版権」が導入されたことで解消されたはずです)
そのうえで、次のように主張します。
- 「(電子書籍は非再販なので)出版社が価格決定権を持てず、電子配信業者による安売りが蔓延すれば紙の書籍の売れ行きに影響がでて、出版社の電子書籍発行への意欲は阻害される」。
- 「紙と電子の出版物を一体的に再販商品と認めさせ、あるいは価格拘束を可能とさせるための議論と運動が、 出版業界に求められているのではないか」
ここでは、「出版社が価格決定権を握ることが必要」という主張と、「安価な電子書籍が紙書籍の売上を阻害する」という主張の二つが提示されています。後者はいわゆるカニバリズム論(電子書籍が紙の書籍の売上を食い荒らす)ですが、こちらは後回しにして、まずは前者について見てみます。
一般論として、製造者が価格決定権を持つことが、売上を伸ばすことになるかどうかは、条件による、としかいえないはずです。
出版界は1997年をピークに、18年連続で売上が落ちています。だからこそ、システムの改革が求められているのですが、その「システム」には、再販制度も含まれています。
前項で述べたように、現在の制度がうまくいっているのであれば、それを電子書籍に適用すべき、というのも理解できるのですが、うまくいっていないことが明らかなのに、あえて援用しようとする意味がよくわかりません。
より一般化してみましょう。生産者の価格決定権について考える際、参考になりそうなエピソードがいくつか思い浮かびます。ここではその中で、「ダイエー・松下戦争」について取り上げてみましょう。
生産者が価格決定することはいいことなのか?
「ダイエー・松下戦争」、俗に「30年戦争」とも呼ばれるこの争いは、1964年、松下電器(現パナソニック)の製品を流通大手(当時)のダイエーが安売りしようとしたことから始まります。ダイエーが希望小売価格の2割引で販売しようとしたところ、松下電器が抗議、出荷を取りやめたことから始まり、30年にもわたってダイエーの店頭に松下の製品が並ばなかった、という事件です。
「流通革命」を掲げ、価格は消費者が決めるべき、と主張するダイエーに対して、松下電器側は、価格決定権はメーカー側にあると主張、ダイエーが松下を独禁法違反で提訴する騒ぎにもなりました。
ちなみに冒頭に説明したように、生産者が最終小売価格を小売店に強制することは独禁法違反ですが、「この価格で売ってほしい」という目安を提示するのは合法で、この価格を「希望小売価格」といい、こうした商習慣を「建値制」と呼びます。
この対立、今からみると、なかなか示唆に富んでいます。
パナソニックは、この一件で、一時は流通最大手だったダイエーという販路を失いました。しかし、だからといって、企業経営がこのことから直接的に、甚大な被害を受けたかというと、筆者の調べた限り、そういうことはなかったようです。
一方、ダイエーは、バブル崩壊後、阪神淡路大震災という不幸な出来事もきっかけとして、急速に経営不振に陥ります。しかし、メーカーとのこうした対立が、主要因ではありませんでした。過大投資と、「カテゴリーキラー」と呼ばれる、特定商品に特化した量販店の伸長、単に安ければいい、という価値観から実質的なお得感へと、消費者の嗜好が変化したことが理由として挙げられています。
つまり価格決定権のありかは、両社の経営にそれほどのインパクトを及ぼさなかったと考えられます。
少なくとも、高須氏の危惧するような、「生産者が価格決定権を失えば、果てしない安売り競争が始まり、生産者のビジネスが成り立たなくなる」ということには、なっていないことは明らかです。
定価(希望小売価格)こそが安売りを招く
その後、1990年頃から多くの家電メーカーは、希望小売価格の表示自体をやめてしまい、小売店に価格を任せる「オープン価格制」に移行しました。
直接のきっかけは、量販店の一般化で、希望小売価格と実際の販売価格の乖離が激しくなり、消費者に誤解を与えるとして、公正取引委員会が問題視したこと、もう一点は(驚くなかれ)希望小売価格の提示が、「安売り」を招く、という理由によるものです(小本恵照「オープン価格制の普及と取引制度の変化に関する経済分析」ニッセイ総合研究所、2006による)。
希望小売価格がある商品では、「希望小売価格から◯割引!」という形で、小売店が安売りしやすくなるからです。
大事なことなのでもう一度繰り返しますが、
メーカーが販売価格を提示すると安売りを招く
ということも理由の一つとして、家電等ではオープン価格制に移行したのです。
さらに付言するなら、建値制のもとでは希望小売価格を守る販売者に対して生産者からリベートを払う必要があり、このリベートが不明朗な取引関係を生み経営も圧迫する、ということも前掲資料で理由として挙げられています。
高須氏は別のところで、出版業界には不明朗な取引が多すぎると苦言を呈しています。
栗田出版販売の民事再生が意味するもの(リンク)
まず「現在の正味体系」を中心とした取引条件の問題点に踏み込むことなしに、取次店の再生はないのではないか。ご承知のように出版社が販売価格を決定できる再販制度を前提に、定価の何掛けという形で現行の正味体系はできている。この正味が今や1割以上の格差になっていることである。大手・老舗版元、医書などの正味は一般に限りなく高く、中小零細・新規版元は限りなく低いのだ。高い正味では7.5掛けなどはざらで8掛けなどというのもある。
次に、歩戻しと呼ばれるバックマージンである。新刊委託をはじめとして、長期委託、常備寄託などさまざまな名目での販売協力金であるが、中小零細、新規版元ほど多くのパーセンテージを強いられている。
また、販売代金の支払い条件である。中小零細、新規版元は、新刊は6カ月精算、原則翌月払いの注文品にも、納品額の3割が6カ月間支払い保留されるなどの注文品支払い保留が強いられる。一方、大手・老舗版元には、原則6カ月精算の新刊が翌月に全額ないし一定割合が支払われる内払い、条件払いが適用される。
「正味」とは出版用語で、仕入れ値のことです。出版社から取次会社に卸す金額を「入り正味(または版元出し正味)」、取次会社から書店に支払う金額を「出し正味」などといいます。
高須氏が指摘するとおり、出版流通にはさまざまな形でバックマージン(リベート)があり、取引条件にも格差があります。そして前掲資料を見ると、家電や化粧品、その他あまたの業界で、同様の問題があり、その問題の解決のために、建値制の撤廃、オープン価格制の導入が図られた、とあります。
電子書籍に再販制を適用すれば、高須氏のいう、こうした不明朗な取引が、そのまま電子書籍にも持ち込まれてしまう恐れがあるのではないでしょうか?
紙の出版流通での不明朗な取引をやめさせたいのであれば、まずは建値(定価)、つまり再販制度をやめるべきだと、高須氏は主張すべきではないでしょうか?
建値(定価)のデメリットについてさらに付け加えましょう。現在、再販制度のもとで、新刊本には定価が表示されており、全国どこに行っても同じ値段で売っています。
そしてブックオフ等の新古書店や古書店に行くと、定価の横に販売価格のシールが貼ってあり、ひと目で割引率がわかるようになっています。
しかしこの「定価(の表示)」がなくなれば、どうなるでしょうか?
新刊書店も新古書店も独自に価格をつけるようになり、新古書店のメリットは、非常にわかりにくくなります。
誰だって古い本よりは新しい本がいいに決まっています。新刊書店でも安売りが行われ、メリットがわかりにくくなれば、新古書店に足を運ぶ人は確実に減るでしょう。
ブックオフを台頭させたのは、再販制度なのです。
この投稿の続きを読む »