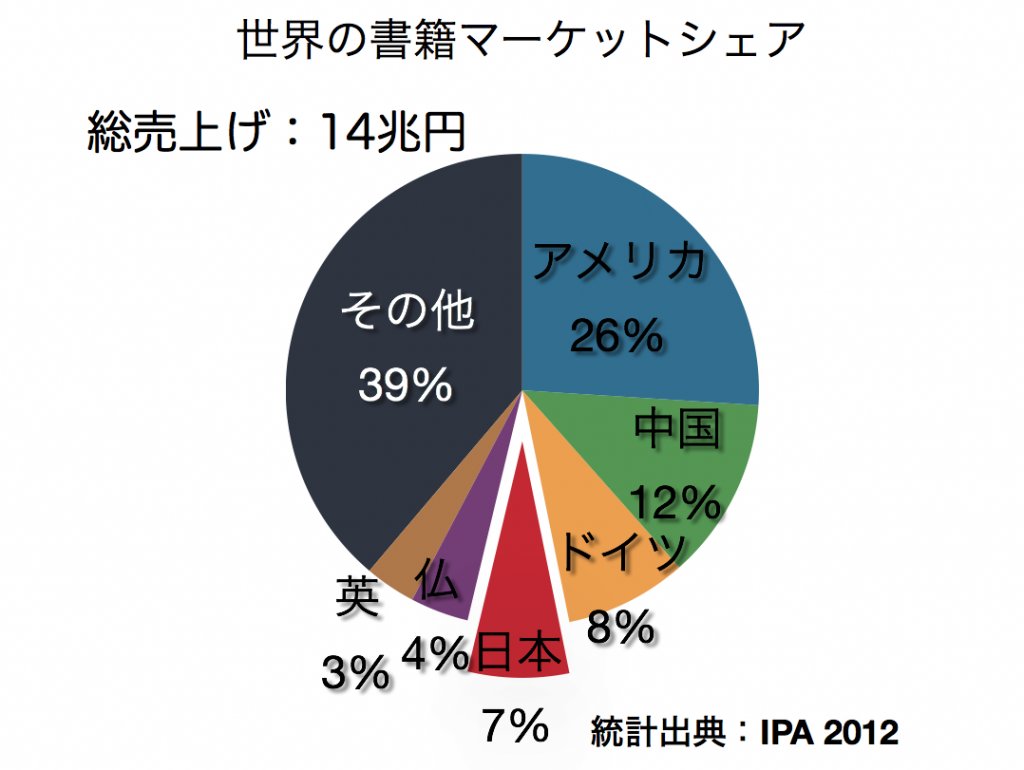雑誌「ダ・ヴィンチ」から「本をめぐる物語」を依頼された時、僕のよくない癖が出た。
依頼を逆手に取って、おそらくは先方の望んでいないであろう小説を書いてしまったのだ。前にも「卒業をめぐる物語」を依頼されて、いつまでたっても卒業しない「高校三十三年生」という落語を書いてしまったことがある。あれも「ダ・ヴィンチ」の仕事だった。なんか、すみません。
今回もその発想でやった。大手出版社が新刊小説を刊行しなくなる、という話を書いた。題して「新刊小説の滅亡」(ダ・ヴィンチ編集部編『本をめぐる物語〜小説よ、永遠に』に収録)。
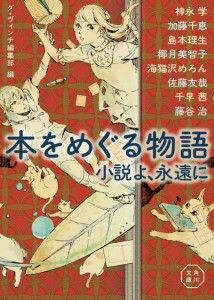 発想は悪ふざけみたいなものだけれど、そしてこれは、タイトルありきで中身を考えていったような小説ではあるけれど、書き進むにしたがって、どんどん自分が真面目に、というより、冗談で済まないことを書いているのに気がついた。
発想は悪ふざけみたいなものだけれど、そしてこれは、タイトルありきで中身を考えていったような小説ではあるけれど、書き進むにしたがって、どんどん自分が真面目に、というより、冗談で済まないことを書いているのに気がついた。
新刊小説の一斉刊行停止という、架空の事態に説得力を持たせるのに、努力する必要がなかったのだ。出版社が新刊小説を出さなくなる理由が、すらすらといくらでも出てくるのである。新刊小説というのは、出さなくても痛痒ないどころか、出して有害なのではないか。書き進めながら肌に粟を生じたといっても過言ではない。
日本の商業出版社は、もちろん、小説を売るだけで商売をしているわけではない。しかし小説を売っている出版社はどこも、口を揃えて「新刊が売れないんですよ」と嘆く。
今年はついに、図書館を仮想敵にするかのごとき言説や要請まで現れた。
読書家で図書館を使わない人はいない。そんなことは誰でも知っているのだから、図書館の新刊貸し出しが売上に響くと、出版社の社長が公言するのは、これはよほどの緊急事態と考えざるを得ないのだろう。
(この件に関して、詳しくはこのURLを参照してください。)
「石にかじりついてでも本は買わない」人たち
僕のところにやってきて、「藤谷さんの新刊、図書館で借りて読みました!」とか「すみません、貸し出しの順番が回ってこなくてまだ読んでないんです」などといってくる人も、たまにいる。著者であるこちらが売文稼業で食いつないでいることと、読者である自分が本を買わないことの間に、相関関係があるということにさえ気づかない読者が、とにかく存在するんだと思う。
しかしまあこれは僕がたまたま、そういう鈍感な人間に出会ってしまったというだけの話で、これをもって「今時の風潮」などと主張するつもりは毛頭ない。
けれども図書館という公共サーヴィスの役割ないし目的が、市民にタダで本を読ませることだと、ごく自然に捉えている人間がいるのは確かだ。本に出す金もないし(酒に出す金はある)、本を置く場所もないが(ワンルームマンションにひとつだけある本棚は、DVDとアニメのフィギュアで満杯だ)、読みたいは読みたい、だから読ませるのが政府なり地方自治体の務めだろうという「論理」なのかもしれない。
それは少なくとも我々売文の側から見れば、石にかじりついてでも本は買わない、といっているのも同然である。絶版本や資料といった、入手困難であったり、公共の知に供するための本に限らず、とにかく、何がなんでも、本は買わないのだ。駅前の本屋に山積みになっている本を、ふた駅先の図書館まで借りに行く。もし制度なり法律なりが変わって、図書館がある種の本を所蔵しないということになったら、そういう人たちは、単に読まなくなるだけである。どっちにしても、買わない。
そして、ここでいう「駅前の本屋に山積みの本」「ある種の本」とは、おおむね、新刊小説のことである。
ある種の人々が、なぜかたくなに新刊小説を買わないのか。そんなことを考えても、どうしようもないと僕は思う。僕がなぜアニメのフィギュアを買わないのかを考えたってしょうがないのと同じだ。僕にとってアニメのフィギュアは、意味がない。ある種の人々にとって、新刊小説の存在には、意味がない。それだけのことである。今に始まったことでもなければ、「嘆かわしい」ことでもない。
図書館が新刊を何冊も買い入れて貸し出す「複本」が問題なら、レンタル向けのDVDみたいに、紙や表紙を丈夫なものにして、図書館が買う本だけを一冊十万円にすればいい。そうするくらいの権利を、出版社は主張できるはずだし、そんなアイディアはとっくに出ているに違いない。それができないということは、何か法律の壁とか社会制度の規制があるのだろう。もしくはそういう提案をする勇気が、出版社側にないとか。いずれにしてもそうであればそれは、「新刊小説が売れない」という問題の本質ではない。
問題の本質は、「とにかく買わない消費者層」にはない。
買って手元に置いておこうか、どうしようか、見定めたい、という種類の人たちが、結局は買わない、ということ。これが本質である。(これとは別に、「買うも買わないも、新刊小説の存在を知らない」という人たちが存在することも、大きな問題だが、ここでは取り上げない)
新刊小説は、買わない方がいい?
小説のような嗜好性の高い商品について、なぜ買わないかを包括的に考えても無駄なように思われるかもしれない。僕はそうは考えない。それどころか、これこそ最重要課題だと考えている。ビジネスとしての出版にとどまらない、新刊小説の、ひいては現代文学の根本に関わることだ。
といっても、「興味は持っている消費者が新刊小説を買わないのはなぜか」という問題の「解答」が重要なわけではない。こんな問題に答えるのは簡単なことだ。
消費者にとって、新刊小説を買わないことには、メリットがあるからである。
新刊小説は、買わない方がいいからである。
なぜ買わない方がいいのか。どんなメリットがあるのか。それは「新刊小説の滅亡」に書いた。これほどヴィヴィッドで、喫緊の問題を、あからさまに書いたことは一度もない。時事的な、一過性のトピックスを扱うと、小説はすぐに古びてしまうが、これは現代文学の本質に関わることだと信じて書いた。
僕はつまらない、味もそっけもないことしか考えられない人間だ。東日本大震災は僕に、自分の足元を支えているのは「文学」や「愛」や「民主主義」などではなく、「地面」であることを認識させた。
それと同じように、出版不況や図書館問題、そして自分の小説の売れ行きが思わしくないという事実は、僕に文学の本質が「表現」や「認識」や「自己主張」にあるのではなく、「読む・読まれる」という営為の強度にあることを突きつけたのである。有体にいえば、一回読んだら置き場所に困るような文学など、買わない方がいい、ということだ。
新刊小説を売る仕事に関わっている人たち――著者に限らない。編集者も、出版営業者も、流通も、批評家も、そして読者も――は、いっぺん歩みを止めて、考えた方がいい。新刊小説が滅亡したら、自分はどうなるのかを。現代文学を取りまく状況は、それくらいのところまで来ている。
「滅亡してはいけない」と思うなら、「なぜ」という問いに答えなければならない。僕は、あの程度の小説を書いているくせに、これまでもこれからも、この「なぜ」に答えられるだけの小説でなければならない、と覚悟して書いている。
「滅亡してもいいのかもしれない」と思うなら、そんな人は、今すぐあっちに行ってくれ。
【イベントのお知らせ】
藤谷治さんが主宰する「文学の教室」の番外編が12月20日(日)に下北沢の「本屋B&B」にて開催されます。この作品のことも話題になると思いますので、ふるってご参加ください。
「フィクショネス文学の教室 in B&B〜年末番外編〜」
2015年12月20日(日)19:00~21:00(開場18:30)
会場:本屋B&B(世田谷区北沢2-12-4 第2マツヤビル2F)
入場料:1500円+drink
http://bookandbeer.com/event/20151220_ficciones/
出演:藤谷治(作家)、田中和生(文芸評論家)、瀧井朝世(ライター) 、仲俣暁生(編集者・文芸評論家。「マガジン航」編集発行人)