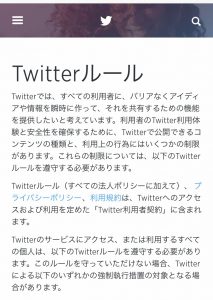印刷されたマンガから電子コミックへのシフトが確実に進む中で、注目されているのが「エージェント」という仕事だ。
エージェントという職業はこれまで日本の出版界にはほとんど定着していない。しかし、欧米の出版界では古くから「リテラリー・エージェント」という職業があるのだ。
「作家の代理人」とでも訳せばいいのか。作家に代わって出版社への売り込みや契約、二次使用権の管理、プロモーション、テレビ化や映画化などのメディアミックス、シリーズやキャラクターの長期的なセールス・プランニングなどを行う専門職のことである。
欧米ではリテラリー・エージェントが欠かせない存在に
前回も書いたように作家・クリエーターには売り込みやお金の管理、交渉事が苦手という人が多い。そこで、苦手な部分をそっくり専門家に任せてしまうのだ。税金のことなら税理士、法律なら弁護士、といったぐあいに出版関係の専門家が存在すると思ってもらえばいい。
リテラリー・エージェントは作家から委託を受けた業務をこなすことで、作家が受け取る原稿料や印税から一定割合の報酬を受け取る。かつては、印税や版権収入の10%が相場だったので、リテラリー・エージェントのことを「テンパーセンター」と呼んだこともあった。
今日のようにテレビ化・映画化が重要なプロモーションにつながり、版権収入にもなる時代では、エージェントの報酬の料率は複雑になっているが、どのエージェントと契約するのかが作家にとって成功の鍵になっていることは間違いない。
リテラリー・エージェントが登場する小説に、アメリカの女性推理作家ヘレン・マクロイの代表作『幽霊の2/3』がある。
あらすじはこうだ。過去にアルコール中毒で苦しんだが、いまはすっかり克服した人気作家のエイモス・コットル。しかし、別居していた妻が戻って来るという知らせを受けたエージェントは慌てる。妻の存在がエイモスのアルコール中毒を再発させ、小説が書けなくなるかもしれないからだ。そして、事件は出版社の社長の家で行われたパーティの中で起きる。泥酔した状態でパーティにやってきたエイモスが「幽霊の2/3」というゲームの最中に殺されてしまうのだ。
エージェントの仕事についてとりあえず知りたいという方にはぜひ読んでいただきたいミステリーだ。アメリカの出版界におけるエージェントのポジションも概ね理解してもらえる内容になっている。
日本ではなぜエージェントの仕事が目立たないのか
欧米では当たり前になっているこの職業が、日本ではこれまであまり注目されなかったのはなぜだろう。それは、出版社、とくに編集者がリテラリー・エージェントの仕事をほぼ引き受けていたという特殊な事情があるからだ。
二次使用権の管理、プロモーション、テレビ化や映画化などのメディアミックス、長期的なセールス・プランニングはみな、作家を抱えている出版社の仕事だ。さすがに売り込みと契約を代行することはないが、編集者の仕事とリテラリー・エージェントの仕事とはほぼ重なっている。
マンガの場合はもっと徹底している。第4回にも書いたように、新人を発掘し、デビューさせる段階でマンガ家と編集者はほとんど二人三脚状態になる。二次使用権の管理にしても、編集部や担当編集者の権限は強い。
私は、仕事関連でマンガ・カットの使用許諾を取る機会が多いが、担当編集者が締切までに捕まらずにカットを使うのを断念することは珍しくない。うっかり、マンガ家本人に連絡して許諾を受けたら、担当編集者から怒られた、という例もある。こういうことがあると、次にお願いするときに「NG」になることが多いので気を遣う。
TV番組や講演会へのマンガ家の出演依頼や、コメントの執筆依頼などがあっても、多くの場合は編集がいったんブロックして、そこから取捨選択する。
マンガ家にとっても、執筆以外の雑事から解放されるのはありがたいことだ。編集者がブロックしてくれるおかげで、雑音からシャットアウトされた状態で原稿に専念できる。出演料のギャラ交渉なども任せておけばいい。
これは素晴らしいシステムに見える。
しかし、マンガ雑誌の売れ行きに陰りが見え始めた頃から、出版社がエージェントも兼ねているという仕組みは少しずつ歪みを見せるようになった。
雑誌の売上が減ったために出版社は編集者の数を減らし、編集者は複数の作家を掛け持ちすることになり、エージェント部分に手がまわらなくなったのだ。さらに、出版社は社員編集者からフリー編集者などへの置き換えをはじめた。現在、編集プロダクションからの派遣編集者やフリー編集者はもちろん熱心にエージェント的な仕事もこなしているが、社員編集者に比べれば権限は限られている。そのために、どうしてもレスポンスに時間がかかるようになるのだ。
たとえば、映像化の話が持ち込まれたが、担当編集者のもとでペンディングになっているうちに時期を逸した、というような事例もあった。出版社は、権利関係の窓口を一本化させるために「ライツ事業部」など専門の窓口をつくったが、作家との直接のパイプにはなっていない。そのため、版権管理はするが版権ビジネスはできない、という不思議なシステムになっているのが実情だ。
一部の大手出版社では、事務の効率化を図って、申請書類の書式や使用料まできちんと規定して、手続き通りにすれば大丈夫、というところもある。ただ、その場合でも作家によって直接依頼しなければならないケースがある。困るのは、いったん申請してからでないと、どのマンガ家が直接交渉の対象なのかがわからない、ということだ。
こうしたシステム上のキシミによって、作者の利益を損なったり、不信感を与える事例が出てきたことが問題なのだ。最近増えているマンガ家と出版社の間のトラブルの原因は、当事者間の直接の原因とは別に、こうした不信感の蓄積があって、それがある事件が元になって爆発したというケースが少なくないと考えられる。
クリエーター・エージェンシー「コルク」
そんな日本の出版界で、エージェントの存在にスポットライトが当たるきっかけをつくったのが、2012年10月に設立されたクリエーター・エージェンシーの「コルク」だ。
コルクは、元講談社「週刊モーニング」編集部の佐渡島庸平と同「群像」編集部の三枝亮介が講談社を退社して立ち上げたエージェント会社だ(三枝は現在、コルクを退社して新たなエージェント会社「CTB」を設立し、伊坂幸太郎らの海外版権を扱う他、大日本印刷などが運営するハイブリッド書店「honto」のオフィシャルマガジン「honto+」の編集などを行っている)。
設立当初、コルクがエージェント契約をしたのは、マンガ家では小山宙哉、安野モヨコ、小説家では阿部和重、山崎ナオコーラ、文芸評論家の山城むつみらだった。
私は、設立後間もないコルクとその周辺を取材したが、興味を持ったのはスタート後にコルクにコンタクトをとってきた会社や個人のほとんどが、出版社や電子書店以外の「ネットとコンテンツの結びつきに新しい可能性を感じている人たち」ということだった。出版社の反応は、当の講談社にしても様子見という感じだったのだ。
出版社にしてみればエージェントの仕事は自社の編集者に任せておけばいいわけで、ある意味で余計な存在だ。電子書店にとっては、出版社が持っているコンテンツを配信することが主な業務なのだから、許諾の相手は出版社になる。おそらくその当時は講談社も、コルクの存在は自社出身の編集プロダクションくらいにしか認識していなかったのではないか、と思われるフシがある。
一方で、コンテンツビジネスを考えるIT系の起業家などにとって、エージェントの登場は待ちわびたものだった。
日本の古いシステムでは、映像コンテンツを使おうとすれば映画会社やテレビ会社の高いハードルがあり、マンガや小説を使おうとすれば出版社の高いハードルがあった。IT系の起業家の多くは、ビジネスや技術的なノウハウには長けていてもクリエイティブな方面にはネットワークがない。クリエイティブなアイディアや才能を求めようとしても、旧メディアの壁が阻んでくる。エージェントが生まれたことで、エージェントを通してクリエーターたちと結びつくことができれば、自社が持つ技術を使ってコンテンツに新たな展開を考えることもできるわけだ。
これはマンガ家にとっても新しい創造のチャンスに繋がる。
ましてや、出版不況で原稿料が低く抑えられ、単行本の発行部数も減ってくる中では、マンガ家は生き延びるために、出版社だけに頼るのではない道を模索せざるを得ない。電子化や映像化、商品化などの案件に関わるのが苦手なマンガ家にとって、エージェントは頼りになる味方だ。
こうしたニーズに応えるように、コルクのスタッフには編集経験者のほかに、プランナーやウェブ系のエンジニアなど幅広い人材が在籍している。
出版不況とデジタル化の波の中で、日本に従来のリテラリー・エージェントとは違う新しい姿が生まれつつあると考えてもいいだろう。
〈通訳〉であり〈代弁者〉
第4回で「編集者であると同時に出版エージェントの仕事にも極めて近い」と紹介したオンライン・コミック・マガジン「電脳マヴォ」編集部の小形克宏にもエージェントと編集のことを再びきいてみた。
実はこのときの記事について、小形からは「エージェント業務の部分で記事は大切な部分を漏らしている」という指摘を受けた。漏らしたというよりは、編集業務とエージェント業務の境界は今のところ曖昧で、編集者について書いた章に並べて記述することで、読者に混同されないかとおそれたのだ。
小形が考えるエージェントと編集者の違いはどこにあるのだろうか。
「編集者もエージェントも才能と資本の仲立ちをするという点では同じです。違っているのは、編集者は出版社という資本から給料をもらうのに対して、エージェントは作家という才能がもらう利益を作家と分け合うということです。世間的には編集者は作家の代弁者だと考えられているかもしれませんが、最終的には給料を払ってくれる出版社の代弁者にならざるを得ません。ところが、エージェントは報酬を作家と配分しますから、作家と同じ立場で出版社やウェブ配信元といったクライアントと交渉することになるのです」
――つまり、作家の味方ということですね?
「ただ、作家の代弁者だというだけではエージェントの仕事は成立しないのです。僕たちのクライアントはIT企業が多いのですが、彼らとマンガ家では話す言葉がまるで違う言語なんです。『締切』と言えば、彼らには守るべき『納期』ですけど、マンガ家にとっては原稿を仕上げる『目標』であって、必要なら変更がきくものです。言語の違う両者の間に立って、通訳としてクライアントに伝えるのも大事に仕事になります。その意味では〈通訳〉であり〈代弁者〉ですね」
小形の言う〈通訳〉であり〈代弁者〉という表現は非常にわかりやすい。欧米にあった作家の代理人という従来型のリテラリー・エージェントとも、従来の日本のように出版社がエージェントを兼ねるシステムとも違う、ウェブ時代のエージェントの姿を的確に表現している。ウェブ時代の日本のエージェントは作家の代理人・交渉人に留まらず、仕事全体に対してもより踏み込んだ立場になるはずだ。
ここで現在の「電脳マヴォ」のエージェント業務を整理しておきたい。
「エージェントの仕事はもちろんマンガ家と契約してマンガ家のために働くことです。その報酬としては、原稿料、配信料などマンガ家への支払いをいったんマヴォの口座に振り込んでもらって、そこから描き下ろしで30%、すでに発表された既発表作品で平均40%(10~60%)のコミッションを差し引いてマンガ家さんに渡すシステムです。いろいろ調べたんですが、これはかなり低いパーセンテージだと思います。出版社が自社で扱う作品を電子化する場合だと半分以上をコミッションにしてしまうこともあるようです。マヴォのエージェント業務の配分率や作家向け契約説明書はコーポレートサイトに公開しています。この種の情報を公開しているエージェントは僕たちだけだと思います」
その上で、〈通訳〉であり〈代弁者〉として働くわけだが、まったく土壌が違うクライアントとマンガ家の調整は容易ではない。先ほどの「締切」一つをとっても、クライアントにとっては納期が大切になるが、マンガ家にとっては納期を遅らせてでもよりよい作品を作り上げたいという思いがある。へたをすれば平行線になって、プロジェクトそのものが頓挫してしまう。エージェントの役目は極めて大きいものになる。
コスト面でも、クライアントは少しでもコストを下げようと考えるが、エージェントとしてはマンガ家の利益を第一に考えるのが当然の責務だ。
「そこで鍵になるのが著作権なんです。日本の著作権法は著作者人格権が規定されているので、描いた本人がダメだと言えば、第三者が出版したり、デジタル化することはできません。これまで、出版社や電子書店がマンガの単行本を出版したりデジタル配信する場合、作家が持っている著作権のうち、単行本の出版やネット配信に関する権利だけを『許諾』してもらう契約を結んでいました。
ところが、僕たちはエージェントとしてマンガ家の著作権のうち著作者人格権をのぞく財産権としての著作権の全部を、期間を限定して管理するために『譲渡』してもらう信託契約を結んでいます。だから、僕たちは著作権を持つ権利者として、クライアントにはこれまでより強い立場で話ができますし、なにかある毎になにもかもマンガ家に伺いを立てて、という必要がなくなる。もちろん、作者の意向に反したことは絶対にできませんが、より早い判断ができるわけです」
扱う作品の大半が新人マンガ家という「電脳マヴォ」の特殊性もあるかもしれないが、財産権としての著作権の信託という考え方は、これから出てくるであろうエージェントにとっては、ひとつの指針になる可能性がある。
最後に、これからエージェントとしてやっていこうとする人たちの適性についてもきいてみた。
「マンガの知識はもちろんですけど、コンピュータの知識、法律の知識が大切だと思っています。マヴォの場合、編集長の竹熊健太郎がおもにマンガ表現に関する部分をジャッジして、僕がおもにコンピュータや法律の部分を担当しているんです。もともと僕の資質がエージェント部分をやるようにできていたのかもしれません」
第4回にも、『ナナのリテラシー』の中で作者の鈴木みそが、「編集者は出版社を離れてエージェントとして別会社を設立し、完全にマンガ家側に立ってサポートしてはどうか」という提言をしたことを紹介したが、エージェントは、編集者よりもむしろマンガに興味があるIT技術者や法律を勉強した人たちに適性がある仕事になるのかもしれない。