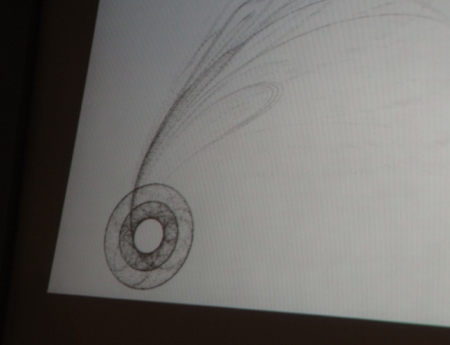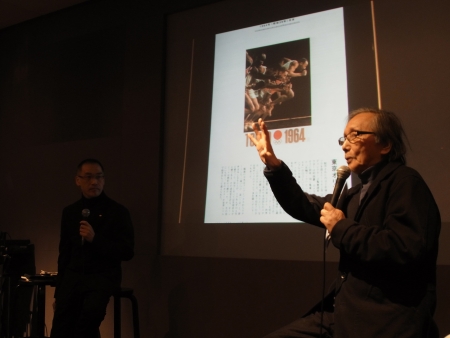どうやらアップルは意外に早く、次の一歩を踏み出した。つまり、iPadの拡販からApp Storeの収益拡大への重心の移行ということだ。1,000万台に達したiPadは世界の出版社に大きな期待を抱かせてきたが、10ヵ月足らずの「試用期間」を経てアップルが出してきたのは、iPad (iOS製品)をプラットフォームとして利用する場合の厳しい条件と見積だった。iPad(が汎用デバイスであること)を前提にE-Bookビジネスを構想してきたプロジェクトは、再検討を迫られる。今回の「事件」の影響と日本のE-Bookビジネスの対応について考えてみたい。
どうやらアップルは意外に早く、次の一歩を踏み出した。つまり、iPadの拡販からApp Storeの収益拡大への重心の移行ということだ。1,000万台に達したiPadは世界の出版社に大きな期待を抱かせてきたが、10ヵ月足らずの「試用期間」を経てアップルが出してきたのは、iPad (iOS製品)をプラットフォームとして利用する場合の厳しい条件と見積だった。iPad(が汎用デバイスであること)を前提にE-Bookビジネスを構想してきたプロジェクトは、再検討を迫られる。今回の「事件」の影響と日本のE-Bookビジネスの対応について考えてみたい。
読者、出版ビジネス、アップル…誰も得をしない
まず確認しておきたいが、アップルがアプリの仕様について一方的なガイドラインを押し付けるのは自由だ。米国やEUの司法当局が、独禁法上の違法性について調査する可能性は十分にあるが、ゲーム機ではこれまでソニーもプレステについて同様の措置をとっており、ユーザーはインターネットに接続するデバイスで、自由にWebにアクセスし、コンテンツやサービスを受ける権利があると考えたい人々と対決してきた。ネットに対してオープンにするかしないかは、基本的にはメーカーの判断だと思う。
 にもかかわらず、アップルのIAPガイドライン(の強制)は、圧倒的に優れた操作性とユーザー体験(UX)を実現する製品の機能を大幅に制約することにより、ユーザーを失望させ、さらにアップルの企業イメージ(敢えて言えば「知的道徳的ヘゲモニー」)を大いに損なうことは間違いないように思われる。それに、少なからぬ出版社がiPadに期待したのは、アマゾンKindleの閉鎖性に対して、アップルがより開放的で汎用的な環境を提供すると信じたからだった。Kindleも限界まで単純化したインタフェースで成功したが、もともと単能機であるために、その点が注目されることはなかった。他方でiPadは、Web上で最も優れたUIを持つ多能機であるために、期待も大きかったのである。
にもかかわらず、アップルのIAPガイドライン(の強制)は、圧倒的に優れた操作性とユーザー体験(UX)を実現する製品の機能を大幅に制約することにより、ユーザーを失望させ、さらにアップルの企業イメージ(敢えて言えば「知的道徳的ヘゲモニー」)を大いに損なうことは間違いないように思われる。それに、少なからぬ出版社がiPadに期待したのは、アマゾンKindleの閉鎖性に対して、アップルがより開放的で汎用的な環境を提供すると信じたからだった。Kindleも限界まで単純化したインタフェースで成功したが、もともと単能機であるために、その点が注目されることはなかった。他方でiPadは、Web上で最も優れたUIを持つ多能機であるために、期待も大きかったのである。
もちろん、アップルから見れば、クラウドビジネスにおけるデバイスは、あくまで「端末」であり、その多機能性はアップル・クラウドが提供するサービスの陰に過ぎない。その点でアップルとユーザーやビジネスパートナーの間には、あまりに大きな誤解が広がっていたと思われる。結果的に市場の失望は大きく、iPadへの「熱」に水をかけることになるのは避けられない。それはトータルなデザインでやや劣るAndroid機や、別の魅力を持ったPlayBookやPalmに機会を与えることになるだろう。
優れた技術はなぜ最後の勝利を得られないか
ITの世界では、技術的に最も優れたものは市場での勝者にならない、というジンクスがある。それはアップルも経験済みだが、イノベーションを実現した独自技術への過信が、マーケティングの軽視による失敗と結びつきやすいからだ。技術的優位を絶対的なものと考えると、マーケティングは強気(あるいは安直)になり、結果的にユーザー(消費者)を無視、軽視し、時には平気で挑発しさえする。技術的劣位を自覚した企業はその逆をやるから、着実にユーザーの信頼を獲得していくということだと思う。今回のアップルの場合、iPhone、iPadは優れたUIというだけでなく圧倒的な商業的成功をも実現した。そこでクラウド上のプラットフォームとして稼ぐモデルへの唐突な移行となったと理解するのが自然だろう。
しかし、これはまずい判断だ、とわれわれは考える。ユーザーやパートナーの失望は、アップルからすると「勘違い」「筋違い」「心得違い」なのかもしれないが、アップルのUIは一種の公共財となっており、オープンな環境でそれを使いたいと考えるユーザーの期待は、アップル以外に向かうことは止められない。
 次に、アップルは本というコンテンツが音楽やビデオとは決定的に異なることを忘れている。本は他のコンテンツより数も種類も多く、その構造性とともに豊富なコンテクストを持つ。作家-作品という関係はほんの一面にすぎないからだ。本は単独ではなく、他の本や人やテーマなどの明示的関係の中で存在している。そうしたコンテクストを掘り起こし、紐づけることなしに本のビジネスはありえない。消費者の知識、情報を前提に、決済プラットフォームとデバイスを用意すれば成功した音楽のようなわけにはいかない。
次に、アップルは本というコンテンツが音楽やビデオとは決定的に異なることを忘れている。本は他のコンテンツより数も種類も多く、その構造性とともに豊富なコンテクストを持つ。作家-作品という関係はほんの一面にすぎないからだ。本は単独ではなく、他の本や人やテーマなどの明示的関係の中で存在している。そうしたコンテクストを掘り起こし、紐づけることなしに本のビジネスはありえない。消費者の知識、情報を前提に、決済プラットフォームとデバイスを用意すれば成功した音楽のようなわけにはいかない。
本においてアマゾンが強いのはオンライン・マーケティングが優れているからだ。iPadが1,000万というユーザー規模に比べてE-Bookの販売が(出版界から見て)不振な理由の一つは、iBookstoreが本のマーケティングを知らない(あるいはとくにやっていない)ためであると断言できる。音楽と映像に関する限り、アップルは強いが、本において硬直した閉鎖環境を読者に押しつけても成功の見込はほとんどない。
アマゾンがKindleを優先せず、iPadを含む、可能なあらゆるデバイスにKindleアプリを載せているのは、それが本について最も有効なマーケティング手段であるからだ。アマゾンは他社アプリと競合することをまったく怖れていない。8割のシェアは、自社デバイスに依存しないことによって築かれているのである。その点でアマゾンは、オープンとクローズドを有効に使い分けていると思う。読書体験とは対話であり、対話の中から本が購入され、また生まれる。その対話を途絶させるものは満足な読書体験を実現しない。
この投稿の続きを読む »