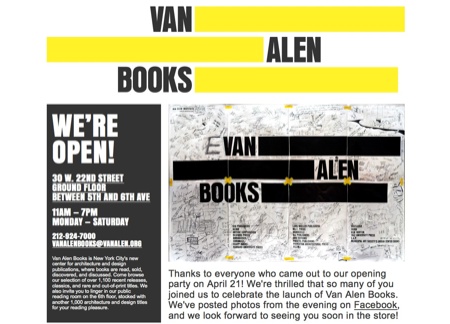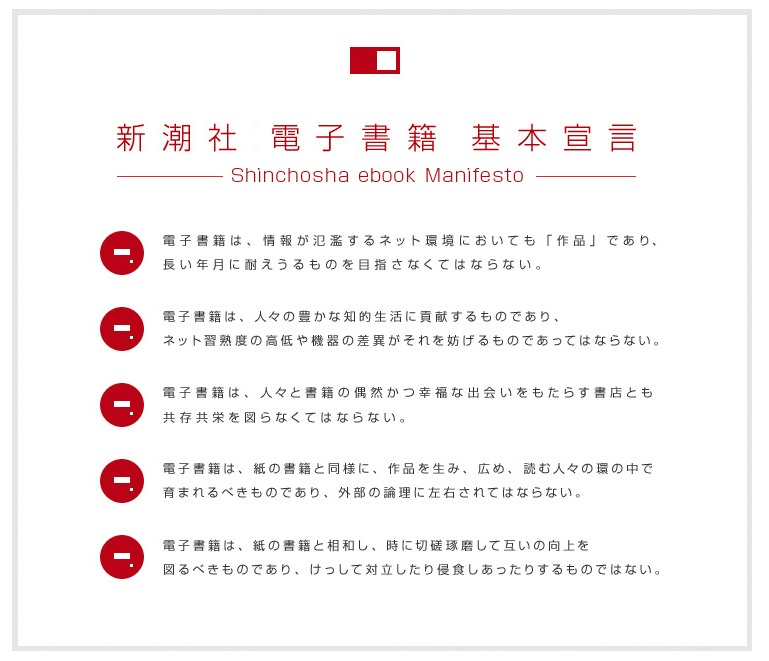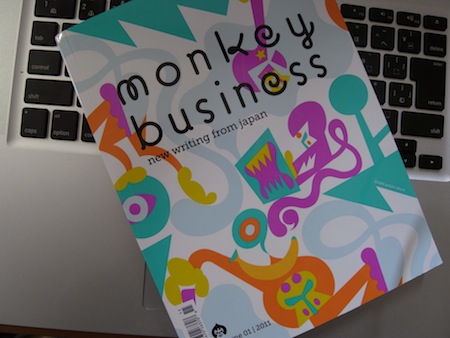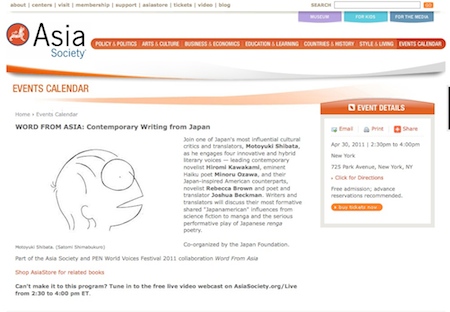アメリカの非営利団体インターネット・アーカイブ(Internet Archive)の創設者であるブリュースター・ケール氏が国立国会図書館の招聘で5月末に来日し、「あらゆる知識へのユニバーサルアクセス――誰もが自由に情報アクセスできることを目指して」という演題での講演と、国立国会図書館館長・長尾真氏、愛知大学教授の時実象一氏を交えた鼎談が行われました。
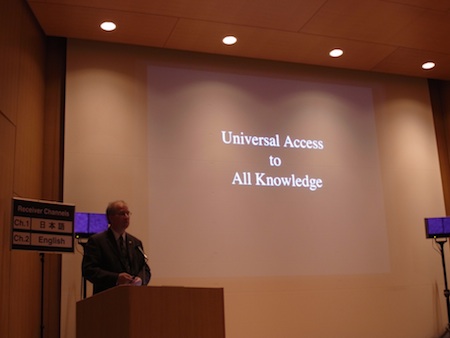
国立国会図書館で講演中のブリュースター・ケール氏。
すでにご存知の方も多いと思いますが、インターネット・アーカイブは書物から映像、音楽、コンピュータプログラム、ウェブサイトにいたるあらゆるコンテンツを集積し、無償公開しているインターネット上の巨大なアーカイブです。
ケール氏はMITを卒業後、並列コンピュータで知られたシンキング・マシーンズ社に参加。ここでWWW登場以前のインターネットで重用されたWAIS (Wide Area Information Server)という情報検索システムを開発します。ここからスピンアウトして創業したWAIS社を1995年にAOL(アメリカ・オンライン)に売却し、翌96年に非営利団体インターネット・アーカイブを設立。同時に営利企業として設立したアレクサ・インターネットではウェブのアクセス解析をするツールを開発し、こちらはやがてアマゾンに売却されました。
こうした来歴からも分かるとおり、ケール氏は筋金入りのコンピュータ・エンジニアですが、同時にライブラリアンとしての顔ももっています。アレクサというプログラム名は、古代エジプトのアレキサンドリアにあったとされる大図書館へのオマージュだといいます。かつてのアレキサンドリア図書館のように、インターネット上にデジタルな「図書館=アーカイブ」を創り上げることが、若い頃からのケール氏の夢でした。そしてその夢をかなえつつあるのが、インターネット・アーカイブの活動なのです。

独自に設計・開発された、Scribeと呼ばれる本のスキャン作業専用マシン。
インターネット・アーカイブには、現時点ですでに250万もの無料で読める電子書籍が保存・公開されており、1日に1000冊のペースで本のスキャニング作業が行われています。インターネット・アーカイブでは本だけでなく、映像や音楽、ウェブサイトなど、あらゆるメディアのコレクションを広げていますが、ことに「ウェイバック・マシン(Wayback Machine)」と呼ばれるWWWのアーカイブでは、1996年以後の世界中のウェブページが保存されており、URLを入力するだけでタイムマシンのように、当時のサイトを見ることができます(たとえば1996年の橋本内閣当時の首相官邸ホームページなど)。
ケール氏の講演ではインターネット・アーカイブの運営方法が具体的に紹介され、そこでの経験から得た数字をもとに、「あらゆる知識に、誰もがアクセスできる」アーカイブが決して遠い未来の夢ではないというプレゼンテーションがなされました。とくに強調していたのは、「あらゆる知識」をアーカイブするためのコストと時間は、多くの人が想像するほど天文学的なものではないということです。ケール氏によれば、それは「2億ドルから5億ドル(約160億円から400億円)」「5年以内」で可能だというのです。
この投稿の続きを読む »