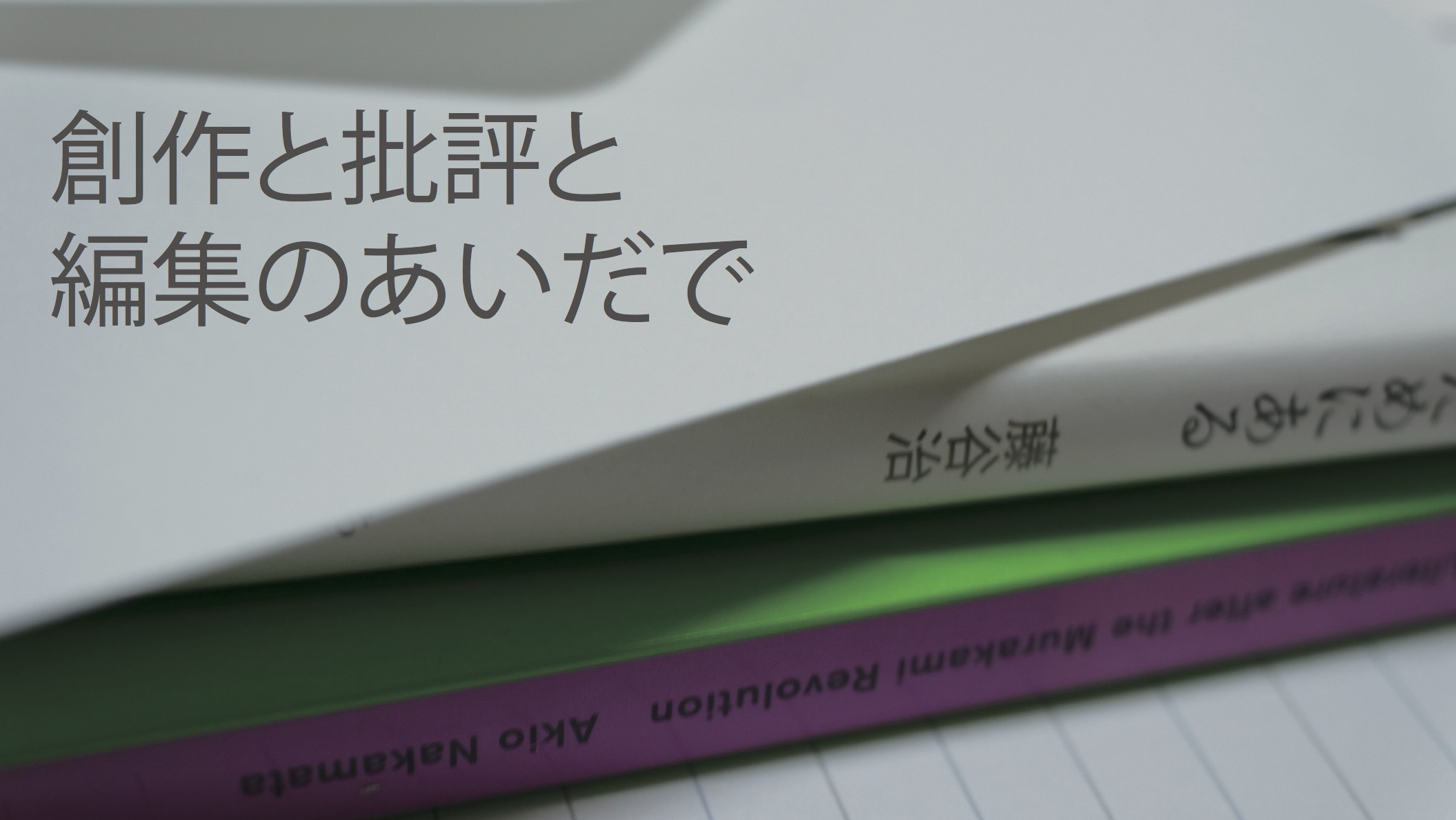先月から小説家の藤谷治さんとの往復書簡「創作と批評と編集のあいだで」を始めた。この連載をはじめた意図は第1信の「本の激変期のなかでどう生きるか」に書いたので繰り返さないが、同世代の信じられる小説家との言葉のやりとりに静かな興奮を覚えている。
私が「マガジン航」を始めたのは2009年の秋だった。この年の夏の東京国際ブックフェア/電子出版EXPOで当時ボイジャーの代表取締役社長だった萩野正昭さんと久しぶりにお会いし、意気投合したのがきっかけだった。たまたまこの時期は日本における何度目かの「電子書籍元年」(なぜかマスメディアは数年おきに集中的に「電子書籍」について過剰報道を繰り返してきた)に当たっており、本誌でもこの分野についての楽観的な見通しや期待を伝えることが多かった。
あれから十年弱の歳月を経て、「電子書籍」はある程度の定着をみた。とくにマンガ市場では電子化されたコンテンツがほぼ半分を占め、雑誌も紙からウェブ版への移行や同時配信、さらには「読み放題」へとシフトしつつある。最終的にどのあたりで安定するのかはわからないが、電子的なメディアを介しての出版は日本の社会に確実に定着している。
他方、昨年から東京国際ブックフェアが2年続けて休止(再開の目処もたっておらず、事実上廃止されたと考えられる)となったことが象徴するように、出版業界の混迷は深い。それは小田光雄さんがライフワークとして継続的に行っている、この業界の定点観測コラム「出版状況クロニクル」が伝えるとおりである。
しかしこうした「状況」は、出版社、取次、書店のいわゆる「業界三者」の視点から語られることが多く、紙の基盤だけでなく、ウェブをはじめとする多様なプラットフォーム上でもすでに活動を始めている他のステイクホルダー(たとえば小説家やライター、フリー編集者、デザイナー、校閲者、翻訳者など)の声はなかなか聞こえてこない。
私が藤谷さんとの公開往復書簡を始めた最大の動機は、こうした「業界三者」以外からみた出版界の現状を可視化し、議論の俎上に乗せたかったからだ。
モノローグが多すぎる
その際に「往復書簡」という形式を選んだのも理由がある。一つには、端的にこの形式への憧れがあった。〈往復書簡〉をキーワードにしてネット書店などで検索をしてみれば分かるとおり、錚々たる文学者や思想家によるこの形式による書物は、過去にやまほど刊行されている。
エラスムスとトマス・モア、ゲーテとカーライル、ベンヤミンとアドルノ、漱石と子規、川端と三島、はてはヒトラーとムソリーニ。最近ではポール・オースターとジョン・クッツェー、古井由吉と佐伯一麦による往復書簡が面白かった。そうした人たちに伍するつもりは(少なくとも私には)ないが、その真似事くらいはしてもよい年齢に、そろそろ自分たちの世代も達しているという自覚はあるつもりだ。
もちろん公刊された往復書簡のほとんどは、プライベートに交わされた書簡をのちに編纂し直したものだ。書簡は本来、特定の相手だけに向けられた書き物であり、他の者が読んで面白いものではない。ところが、そうしたごくプライベート性質をもつ書き物でも、何往復ものやり取りを経るうちに不思議なグルーヴが生まれる。それは一種の時代精神とでも呼べるもので、結果的にいくばくかの公共性さえもつようになる。煎じ詰めれば、往復書簡がしばしば公刊される理由はそこにある。
例えるなら、こういうことかもしれない。往復書簡はいわば〈言葉のキャッチボール〉である。キャッチボールはいかなる意味でも「試合(勝負)」ではないが、たんなる肩慣らしや練習でもない。ボールを投げ、受ける者同士がともに持続の意志をもたなければ、いつでも即座に打ち切ることができる。逆にいえば、一種の共犯関係がなければキャッチボールは持続不可能であり、その意味で創造的な行為でもありうる。なにより、キャッチボールは楽しい活動であり、いつまでも飽きずに続けることができてしまう。それは実際に一度でもキャッチボールをしたことがある者には自明のことだろう。
ところで、いまネット上で流通している言葉のほとんどが、モノローグであることに私はすっかりウンザリしている(こういう言い方のほうが、ずっと正直かもしれない)。もともと「マガジン航」は、それまでやっていた自分の個人ブログへの反動として生まれたという経緯がある(長らくその場を提供してくれた「はてなダイアリー」も来年春でサービスが終了となる)。
「はてな」での活動に一区切りをつけて私が「マガジン航」を始めたのは、ひとり語りをネットで書き連ねることに限界を感じ、より多くの人の多様な声を集めたかったからだ。その願いは十分に叶えられ、「マガジン航」にはこれまで100名を超える寄稿者を迎えることができた。あのまま個人ブログを続けていたら、私はこうした多彩な声や意見と出会うことはなかっただろう。
「マガジン航」を編集発行するなかで出会った仲間とは、NPO法人を立ち上げるまでに至った。イギリス在住のジャーナリスト、小林恭子さんが2013年のロンドン・ブックフェアを取材した記事で伝えてくれた「独立作家同盟」(Alliance of Independent Authors)という非営利団体の存在に刺激を受け、フリーライターの鷹野凌さんが日本でも同様の活動を、と声を挙げて誕生したのが日本独立作家同盟である。日本独立作家同盟の活動は「マガジン航」とも深い関係があり、私もこのNPO法人の理事を務めている。
創作も出版も「孤独な営み」ではない
日本独立作家同盟は現在、二つの大きな活動を行っている。その一つはHON.jpという電子出版に関するニュース配信を中心とするメディアの運営である。このHON.jpのサイトが本日(10月1日)にリニューアルされた。2004年に創刊されたhon.jp Day Watchの活動をNPO法人として継承したものだが、このたびHON.jp News Blogという名称で新たにスタートを切ることになった。
このリニューアルを記念して、今月16日に以下のイベントが予定されており、私もモデレーターとして参加する(登壇者は「ベルりんの壁」で知られるブックチューバーのベルさん、スマートニュースの松浦シゲキさん、オトバンクの久保田裕也さん、日本独立作家同盟の理事長・鷹野凌さん)。
「飛び出せ! グーテンベルグの銀河系 ~ 本と出版の未来はどこにある!? HON.jp News Blog 正式発進記念トークイベント」
https://www.aiajp.org/2018/09/honjp-launch.html
そしてもう一つ、日本独立作家同盟の活動の軸となっているのがNovelJamという合宿形式の創作出版イベントで、昨年2月に初回を、本年2月には第二回目を開催した。
NovelJamの第三回目は今年の11月23日〜25日に開催されることになり、参加者募集の〆切が10月5日に迫っている。今回は当日審査員の一人として、先にふれた往復書簡の相手である藤谷治さんにもご参加いただけることになった(他の当日審査員は作家でエッセイストの内藤みかさん、『出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本をすすめまくった1年間のこと』でも知られる書店員の花田菜々子さん、ゲーム作家の米光一成さん)。
私にとって「マガジン航」とは、本や出版の未来を考えるメディアであると同時に、フリーランスの編集者兼物書きである自分が、こうした仲間と共同でさまざまなプロジェクトを行っていくための土台でもある。
もちろん言論や創作は、最終的にはそれぞれの発言者や著者が一人で背負っていくべきものだ。しかし同時に、出版とは孤独な営みではなく、やはり一種の共同作業でもある。藤谷治さんとの往復書簡も、「作者」「編集者」「デザイナー」がトロイカで一つの作品を作り上げる創作合宿のNovelJamも、私のなかでは「マガジン航」というメディアを立ち上げた動機の一直線上にある。
出版の世界が激変しつつあるいま、孤独なモノローグだけではなく、さまざまなダイアローグ、つまり〈言葉のキャッチボール〉がもっともっと必要だと私は思う。これらの〈対話的〉な活動に関心をもち、参加していただけることを期待する。
執筆者紹介
- フリー編集者、文筆家。「シティロード」「ワイアード日本版(1994年創刊の第一期)」「季刊・本とコンピュータ」などの編集部を経て、2009年にボイジャーと「本と出版の未来」を取材し報告するウェブ雑誌「マガジン航」を創刊。2015年より編集発行人となる。著書『再起動せよと雑誌はいう』(京阪神エルマガジン社)、共編著『ブックビジネス2.0』(実業之日本社)、『編集進化論』(フィルムアート社)ほか。
最近投稿された記事
- 2023.10.22Editor's Note軽出版者宣言
- 2023.06.02往復書簡:創作と批評と編集のあいだで暗闇のなかの小さな希望
- 2023.04.06往復書簡:創作と批評と編集のあいだで魂のことをする
- 2022.09.24往復書簡:創作と批評と編集のあいだで様式によって動き出すものがある