村上春樹の4年ぶりの長編(新潮社によれば「7年ぶりの本格長編」)『騎士団長殺し』が2月24日に発売された。当日は各地の書店で深夜零時からの発売に向けたカウントダウンや読書会など、さまざまなイベントが行われた。
私も都内の大型書店で行われた深夜零時からのカウントダウン&即売イベントに参加した。発売日夕方にこの本をめぐってラジオの生放送で話をする仕事があり、その前に確実に手に入れたかったのだ。
「まだ大丈夫かな?」と不安に思いつつ、発売数日前にこの大型書店に向かって手に入れた整理券の番号は39。案外と若い数字に驚いた。当日の集合時間ちょうどに会場に着いたときも、すでに集まっていた人の数は思ったよりも少なく、殺到という感じではなかった。カウントダウンの瞬間までには長い行列ができたが、その一部は、当日の呼び込みで並んだ人たちだった。

書店によってはタワー上に積み上げたところもあったようだが、この書店ではオーソドックスな面陳だった。
一つしかない特設レジで、あらかじめカバーがかけられ、手提げのビニール袋に入れられた上下巻セットが淡々と売られていく様子は、さほどドラマチックなものではない。かつての「Windows 95」や、人気のゲームソフトが発売されたときと比べれば、きわめて静かな風景だった。
しかし、こうしたイベントがテレビや新聞などのメディアで報じられ、本の存在が多くの人に知られることの意味は大きい。ニュース映像や新聞記事が伝えるイメージは、この夜の実際の雰囲気とはかなり異なるものだったとしても、同じ本を求めて人が集まるということ自体が、いまの時代には新たな意味をもっている。
アマゾンで予約すればそれほど待たずに家に送られてくる本を、わざわざ夜中に本屋まで買いに出かけるのは、一番乗りで読みたいというファン心理だけが理由ではないはずだ。自分と同じ本を読んでいる、他の読者がどんな人たちなのかを知りたい。そんな動機も働いていたのではないか。

報道陣の姿が目立った『騎士団長殺し』発売日の都内大型書店。
こうした即売イベントは、メディアがその本の読者を取材する絶好のチャンスでもある。私が並んだ書店でもカウントダウンの前から取材陣が待ち構えており、購入したばかりのお客さんからコメントをとるのに余念がなかった。メディアの取材陣がとりまくことで、地味だった即売会場も、心なしか華やかな雰囲気になっていた。
「風物詩」となったティーザー広告
今回の『騎士団長殺し』は初版が上下巻が各50万部、さらに発売前に上巻20万部、下巻10万部の増刷が決まった。メディアは大げさにこれを「130万部」と報じたが、通読する読者は最大で60万人(図書館や個人間の貸借、中古本での売買を考慮にいれなければ)である。この本より売れている本は、現代小説に限ってもいくらでもある。必ずしも村上春樹のこの作品が、飛び抜けた大ヒット作というわけではない。
にもかかわらず、新刊が出るたびにメディアは村上春樹の新作を取り上げ、社会でも大きな話題となる。それは書店側が仕掛けるイベントだけが理由ではない。なによりも出版社の側が、この作家の本を売ることに積極的に取り組む姿勢を見せていることが大きい。

村上春樹『騎士団長殺し』公式サイト。ティーザー広告が発売後は公式サイトになった。
今回も、本が出版される数ヶ月前から、内容には一切触れずにタイトルだけを開示するいわゆる「ティーザー広告」という手法がとり入れられた。この戦略が大成功を収めたのは、2002年の『海辺のカフカ』(やはり新潮社)のときだ。折しもインターネットが一般に普及し、マスメディアに替わる有効な告知媒体となりつつある時期だった。これが功を奏したことで、以後、版元がどこであれ、村上春樹の新作に関しては、つねにこの方法が採られるようになったのだろう。
今回の『騎士団長殺し』でも「村上春樹 7年ぶりの本格長編 2017年2月刊行決定!」と謳った新潮社の特設サイトが早くから立ち上げられ、店頭ポスターとも連動した大々的なプロモーションで読者や書店の期待を高めていた。こうした情景は、村上春樹の新作が出るごとの「風物詩」となった感がある。
もちろんすべての新刊書に対して、これだけの手間とコストをかけたプロモーションができるわけではない。それなりの売上が見込める村上春樹のような人気作家だからこそ、ということなのかもしれない。
しかし本来は、その反対であってしかるべきではないか? さほどプロモーションをしなくても、ある程度売れることが確実な人気作家でさえ、これだけの努力をしないと本が売れないのだとしたら、そうでない作家や本は、さらにきめ細かい新刊情報を事前に書店や読者に流し、本の魅力を伝える努力が必要なはずだ。
書店員と読者を招いた新刊ラインナップ説明会

新刊ラインナップ説明会に登壇したロビン・スローン氏。このあとで本誌の長い取材に応じてくれた。
この前日、2月23日に行われた東京創元社の新刊ラインナップ説明会にも参加した。このような場は初めてだったが、『ペナンブラ氏の24時間書店』の著者ロビン・スローン氏(メディアの未来を予言した動画「EPIC2014」の作者の一人でもある)がちょうどこの時期に来日しており、同書の文庫化にあわせて登壇の予定があるという。ぜひスローン氏を取材したいとオファーしたところ、説明会への参加とインタビュー取材を許可していただけた。
この新刊ラインナップ説明会は、東京創元社が今年発売する本について、招待された書店人や読者に対してプレゼンテーションを行う場だ。入場時に配られた封筒には、今年刊行予定の書目とその概要が記された書類やチラシのほかに、「SECRET」とシールが貼られた小袋が入っていた。案内に従って開封すると、なかには文庫サイズの小冊子が。同社イチ推しの新刊の冒頭部分が読めるプロモーション用サンプルだった。

「SECRET」と書かれた小袋を開封すると小冊子が入っていた。
ラインナップを記した資料を見ると、久生十蘭の『魔都』が創元推理文庫から4月に復刊されるとあった。私の知るかぎり、社会思想社の現代教養文庫、朝日文庫に次いで三度目の文庫化となる。これはとてもうれしい。おそらく会場を埋めた他の書店人や読者も、自分の好きな作家や作品との出会いに、同じように胸をときめかせたことだろう。
配布された資料の情報はソーシャルメディア上でのシェアも許可されており、この説明会に参加するような書店人や読者が、ネット上でのインフルエンサーとしても期待されていることがわかる。
会場の廊下には関連する既刊書や特製グッズ、特製のガチャポンまでが運び込まれ、物販も行われていた。登壇する著名作家の姿も自然に会場に溶け込んでおり、書店や読者への感謝イベントのような風情も感じられ、取材であることを忘れるほど楽しかった。
こうした試みは一版元だけでやるだけでなく、同ジャンルの複数版元でやれば、なおのこと効果的だろう。すっかり既刊書の(下手をすれば「不良在庫」の)安売りイベントと化した東京国際ブックフェアは、今年の開催が中止になったと本日付けの「文化通信」が伝えている。その代わりに、このような「新刊案内」の場がもっと機能すべきではないか。エンターテインメント系の本だけでなく、人文書などでもぜひ、こうした場をつくってほしい。
新作が事前に読めるNet Galleyが日本でもサービス開始
本を売るための古典的な仕組みとして書評(ブックレビュー)がある。もちろん書評は「批評」の一種であり、ダイレクトな意味での販売促進の施策ではないが、現実には多くの書評家や作家に対し、書評を期待した献本が行われている。
最近では「プルーフ」と呼ばれる簡易製本の書評用冊子が刊行前につくられることも増えた。しかしこれは、あくまでも書評家など限られた人が対象であり、一般の読者――ウェブで熱心に本のレビューを書いているような人も含め――が本の刊行に先立って新作の内容を目にする機会はない。
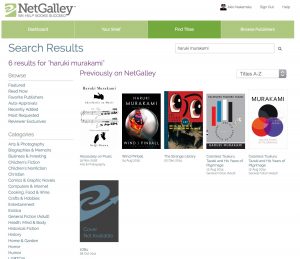
アメリカのNetGalleyでは過去に村上春樹の作品も。
ところで、アメリカにはNetGalley(galleyはゲラ、つまり校正紙)というサービスがあり、本をプロモーションしたい側の出版社と、事前にプルーフを読んでレビューしたい書評家(登録制)とをマッチングさせる仕組みになっている。このサイトでためしにHaruki Murakamiで検索すると、6点がヒットした。もちろん、現在はプルーフを読めないようになっているが、新刊のときはこのサービスをつかってプロモーションを行ったようだ。
NetGalleyには日本人もレビュアー登録ができるようなので、試しに入会していくつかの本をリクエストしてみた。しばらく待つと、リクエストした本は自分の「本棚」に登録され、DRM付きのPDFかKindleへの配信として読める。もちろん単なる「タダ読み」は許されず、感想やレビューなどのフィードバックを促される。そのフィードバックの品質や頻度によって、レビュアー自身も評価される仕組みのようだ。

アメリカ版Net Galleyのトップページ。登録したレビュアーは、ここに掲載されたなかから希望する新刊のゲラをリクエストできる。

リクエストした本のプルーフが読める状態になったところ。DRM付きのPDFまたはKindleで読める。
このNetGalleyが日本でも今春、サービスを開始する。2月10日に行われた印刷業界向け展示会「PAGE2017」のカンファレンス「デジタルメディア時代の出版ビジネス最前線」でも、出版デジタル機構の新名新社長が、この春からNet Galleyの事業を展開することを告げていた(なお、出版デジタル機構はメディアドゥの子会社となることが2月28日付で明らかになった)。
当日のプレゼン資料によると、現在はα版をテスト中とのこと。レビュアーとしては「プロフェッショナルリーダー」が想定されているが、その資格はプロの書評家など従来の書き手に限らず、図書館員や書店員、ウェブ上のインフルエンサー(影響力のある書き手)なども含まれるという。

プロモーション支援ソリューションNetGalley(ネットギャリー)の仕組みを伝える図(出版デジタル機構の公式ページより)。
このように本の情報や話題、意見のあつまる場はいま、多様化している。リアルイベントにしても書評やレビューにしても、これまでのように書店の店頭や印刷媒体のなかだけで閉じるのではなく、それをきっかけにネット上で話題が広がり、さらに多くの人々の目に触れるようになりつつある。
日本でのNetGalleyのサービス開始は、出版デジタル機構の公式サイトでもすでにアナウンスされている。会員(レビュアー)側の申し込みも始まっていたので、私もさっそく登録した。思いがけないほどスピーディに日本での展開が決まったのは、本の話題や評判がウェブで広まっていくことへの、出版社の側の大きな期待があってのことだろう。この仕組みが定着すれば、日本でも本の売り方が大きく変わっていくに違いない。
執筆者紹介
- フリー編集者、文筆家。「シティロード」「ワイアード日本版(1994年創刊の第一期)」「季刊・本とコンピュータ」などの編集部を経て、2009年にボイジャーと「本と出版の未来」を取材し報告するウェブ雑誌「マガジン航」を創刊。2015年より編集発行人となる。著書『再起動せよと雑誌はいう』(京阪神エルマガジン社)、共編著『ブックビジネス2.0』(実業之日本社)、『編集進化論』(フィルムアート社)ほか。
最近投稿された記事
- 2023.10.22Editor's Note軽出版者宣言
- 2023.06.02往復書簡:創作と批評と編集のあいだで暗闇のなかの小さな希望
- 2023.04.06往復書簡:創作と批評と編集のあいだで魂のことをする
- 2022.09.24往復書簡:創作と批評と編集のあいだで様式によって動き出すものがある

