海外に出かけたとき、ほぼ必ず訪れる場所の一つが書店だ。といっても、あらかじめ所在地を調べておいたことは……まあ、あるにはあるが、ほんの二三度。たいていは、そぞろ歩きの最中に出くわした書店にふらりと入る。足休めにカフェに寄ってエスプレッソをすする、というのにかなり近い感覚で。ぼくがかろうじて読める言語は(日本語のほかに)英語のみだが、書店にふらりと入るのは英語圏の旅先に限ったことではない。ようするに、書店が、書店という場=空間が、好きなのだ。もっとも、日本では――つまり、普段の生活では、書店に立ち寄ることはめっきり少なくなってしまったのだが。
脳裏に鮮明に焼きついている書店(とその時の気分)もある。例えば、乗り継ぎの関係で一晩だけ(午後3時くらいから翌早朝まで)滞在したアルゼンチン・ブエノスアイレスで、空腹を満たすべく適当なレストランを探している時に、ふいに出くわした古めかしい書店。そこのやたらと高い天井とその高い天井いっぱいに設えられた書棚にぎっしりと本が詰まった幽玄な光景には、どんな壮大な自然の景色に臨むのにもまさるとも劣らない感慨を覚えた。
それから、パリで国際列車に乗り込むこと約20時間、ようやくたどり着いたポルトガル・リスボンでの初日のこと。英語が予想以上に通じないこともあいまって一人旅の心細さを、ひいては人生の孤独を、しみじみと臓腑に染み渡らせていた散策中に、忽然と現れた、十坪ほどの小さな、もしかしたら潰れかけていたかもしれない書店。その埃っぽく傾いだ書棚にJunichiro Tanizakiという文字を背表紙に見つけた時は、(とくに谷崎のファンではないのに)無言の励ましを受けたような気がしたものだ。

もちろん、本というグッズそのものへの嗜好と興味もある。匂い、重み、触感。そして、デザイン。あの大きさと形と商品でもあるがゆえの制限との中で繰り広げられるグラフィックアートを鑑賞していると、ふつふつと心が沸き立つ。そういう意味では同様にレコード(vinyl)も大好きなのだが、こちらは海外の中古レコード店を訪ねたところで、日本の中古店と根本的に異なるわけではない。
そりゃ、日本では滅多に見かけないブツが信じられない安価で売られていたり、店番の女の子が中古レコード店ではあるまじき美貌とセクシーさをそなえていたり、といったことはあるにせよ、売られているのは基本的には同じグッズ――音楽ソフトは、同デザインのものが世界中に流通しているのだから。しかし、本は、刊行する国によって(言語によって、時には版によっても)、いちいちデザインが違う。目から鱗なデザインに出会うことも珍しくない。また、見慣れぬ言語が紙の上に整然と並んでいるのを目にするのも楽しい。ここに未知の世界があるのだと思うとなおさら楽しい。そうして、その言語が読めるかどうかに関係なく、つい買ってしまう。ホテル代とか食事代とかはかなりケチってるくせに、総じて日本の本よりも高価な本を買ってしまう。
もう一つ、海外の書店が好きな理由、しかも決定的なのがあるのだが、それはおいおい……というか、まあ、前口上はこのくらいにして――
BOOKS INC (サンフランシスコ)

北の低いところに刷毛でぞんざいに描いたような白い雲がいくつか浮かんでいるが、それを除けば、気が遠くなるほどに真っ青の空が広がっている。カリフォルニア州サンフランシスコ。ぼくは、ひさしぶりに――6年3か月ぶりに、アメリカの地を踏んでいる。海外にしても、じつに5年5か月ぶりだ。
その二日目、とはいえ到着したのは前日の宵の口なのだが、時差ぼけが甚だしい中、ゲイ・コミュニティで有名なカストロ・ストリート周辺をぶらついてみることにした。ダウンタウンの停留所でミュニメトロのF系統に乗りこみ、わざと一つ手前の停留所で降車し(だって、ぶらつくのが目的なのだから)、ロハスな雰囲気と品揃えの食料品店でキウイ・ジュースを買って、それを飲みながら……と、我ながら驚くほど早々に、今回の旅における最初の書店に出くわした。Books Incというのが店名なんだろう。それなりにお金のかかった、まあ、スクエアと言えなくもないファサード。そこそこ新しい――ここ10年くらいの間にオープンしたか、改装したかのどちらかだろう。いずれにせよ、個人経営の書店ではなく、大なり小なりチェーン店とみた。

となると、制服を着たりネクタイを締めた書店員が……いやいや、ここはアメリカ、入ってすぐのレジカウンターでは、くしゃくしゃのグレーの髪によれよれのグレーのTシャツ、という風体の五十男がその大柄な体を縮めるようにしてデスクトップ・パソコンに向かっている。書店員というよりは、大工の親方か舞台の大道具係といった風情である。
ぼくらに気づくと、見ようによっては強面の、しかつめらしい表情をさっと崩して「ハロー」。知性が光源となった間接照明のような笑顔だ。午前10時すぎ、という開店まもない時間ということもあってか、ぱっと店内を見渡した限りぼくらのほかに客の姿はない。店の広さは……(感覚で申し訳ないです)120〜150㎡くらいか。ものの一分も経たないうちに、エントランスから二十歩と歩を進めないうちに、ぼくの心は弾んでいる。たちまち、というか、思いがけず、というか、薮から棒に、フィクション≒文芸に包囲されているのだから。
目に飛び込んでくるのは、面出しになったジェームス・エルロイやトマス・ピンチョンの新作ハードカヴァー、ロベルト・ボラーニョやハルキ・ムラカミの数字がタイトルになった大冊、素敵なデザインのカフカやディッケンズのペーパーバック、ウィリアム・バロウズの書簡集……。さらに奥へ進んでいくと、グラフィック・ノヴェルや料理本や旅行ガイドブックや語学テキストなんかも(当然ながら)陳列されているのだが……なにはともあれ、この書店の……いや、しらばくれるのはやめよう……これまでの経験から言って、欧米における書店の、中核をなす(少なくとも、そう感じさせる)商品はフィクション、もう少し範囲を広げても、+ノンフィクション(とりわけ、伝記本やメモワール)、なのである。そのことをあっさりと思い出させてくれる、そして2014年秋の今もほとんど変わりがないということを示してくれる、書店にのっけから出くわしたのだった。
印象的だったのは、店全体のムードからは、いわゆる手作り感といったものはあまり感じられないのにもかかわらず、書棚のあちらこちらで、さまざまなタイトル(新刊か旧作かに関係なく……二三の例を挙げれば、Fishburne “Going to see the elephant”、Fitzgerald “Tender Is The Night、Delillo “Underworld” )が、手書きの“Staff Review”とともに面出しになっていること。それと、日本にはないので余計に目を引くのだが、セール品のコーナーがあること(前述のバロウズの書簡集は35ドルから12.98ドルに値下げになっていた)。さらに、まあ、これは間違いなく場所柄だろうが、LGBT関連の本がいやに目につくこと。“THE BIBLE OF GAY SEX”というタイトルと、卑猥さとスマートさが同居するデザインには思わず唸ってしまった。
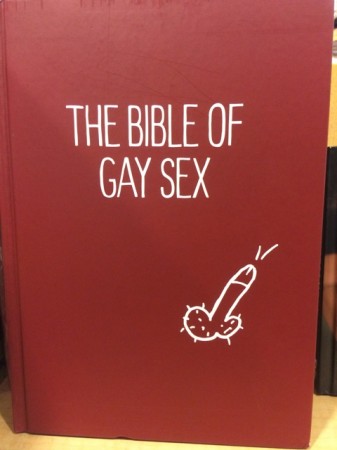
のっけから荷物を増やすのもどうかとは思ったけど……Harper Collins社の傘下レーベルHarper Perennial の創刊50周年を記念して、ポップな新装丁の廉価版(10ドル)で売られていた Malcolm Lowry “Under the Volcano”を購入した。あとでグーグル検索したところ、このBOOKS INCは、サンフランシスコ市内を中心に、ベイエリアに11店舗を展開するインディペンデント系の書店だった。ウェブサイトにはThe West’s Oldest Independent Bookseller とある。著者がやってくる無料イヴェントやブッククラブ(読書会)が毎日のように催されている。その全体タイトルは “The Experience You Can’t Download” ……まあ、そのとおり。
AARDVARK BOOKS(サンフランシスコ)

カストロ・ストリートと24thストリートをそぞろ歩いて(途中、油断すると転げ落ちそうなほどの急坂をのぼってくだり)ちょうどいい具合に空腹になり、ミニュメトロのJ系統に乗ってチャーチ・ストリートをマーケット・ストリートまで戻ってきたところで、二軒目の書店を見つけた。
Aardvark Books。スタンド看板には〈NEWS & OLD BOOKS〉とある。けっこう広い……250㎡はありそうだ。客の姿もちらほら……ざっと六人くらい。カート・ヴォネガットをどことなく髣髴させる、灰色の髪に灰色の顎髭の男――オーナーだろうか――が、アレン・ギンズバーグをどことなく髣髴させる、禿頭に黒縁眼鏡の男――常連客だろうか――と、レジカウンター越しにおしゃべりしている。
入口のドアに、書棚のあいだを渉猟したり平積みの本の上で丸くなる茶虎猫の写真がこれ見よがしに貼ってあるし、店の中央に彼/彼女の寝床とおぼしき空の段ボール箱が置かれているので、もしかするとこの茶虎猫こそがCEOで、ヴォネガット系の灰色男は雇われ店長なのかもしれない。キャットパーソンとしては、彼/彼女にぜひともお目にかかりたく(できることなら撫でさせてもらいたく)、店内を捜しまわったが、残念ながら謁見は叶わず……。
いやまあ、それはそうと、肝心の本。新刊は一割弱だろうか(とりわけ目立っていたのは、ハルキ・ムラカミの “Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage” とリチャード・ヘルの自叙伝)。あとは古本。絵本から学術書までオールジャンル。ざっと見ではあるが、建築系やアートブック、それにグラフィック・ノヴェルが充実しているようだ。
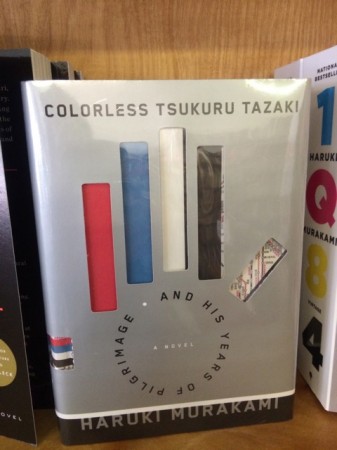
とはいえ、やはりここでも中心はフィクション/文芸……という気がするのは、ぼくの贔屓目なのだろうか。試しに、フィクションの棚をMまで辿ってHenry Millerに行き着いてみると……予想以上の、端から新刊本の書店に行く必要がないくらいな、品揃えだった。値段はだいたい7ドルから9ドル。定価の半分ってことだろうか。“Big Sur and the Oranges of Hieronymus Bosch” を手に取ってぱらぱらとめくっていると、襟を立てた白いシャツにロールアップしたブルージーンズという装いの小柄な黒髪女性がするすると傍らにやってきた。いやいや、傍らどころか、背表紙を辿るその人差し指がミラーのところで止まって “The Books in My Life” を抜き出すではないか。
おいおい。ジュノ・ディアズとかそれこそハルキ・ムラカミならあり得なくはないだろうが……ヘンリー・ミラーだよ? まじで?
立ち読みしてるふりして横目で観察した。おそらく南アジア系――インド?パキスタン?バングラデシュ? 推定年齢24歳。留学生? それともインド系アメリカ人の大学院生でカリフォルニア時代のヘンリー・ミラーについての修士論文を執筆中とか? 想像と興味は膨らみ、心臓がばくばくする。そうして、意を決したぼくは、さっそく “Excuse me? Do you like Henry Miller? ” と話しかけて、少しの立ち話の後で昼食に誘い、午後はいっしょにゴールデンゲート・パークへ行って、夢のように映画のように楽しい時間を……というのは嘘です。同行者が妻なのでね。しかも空腹のせいで、機嫌が傾きかけており――いやいや、妻がいっしょでもべつに良かったじゃん、変に意識しすぎ、とにかく話しかけるべきだった、ここはアメリカだぜ、と悔やんだのはその夜ベッドに入ってから。
PEGASUS BOOKS(バークレー)

ゲイのカップルで溢れたカフェでサラダ・ランチを食べ終えると、抗いがたい睡魔が襲ってきたので、ヘイト・アシュベリーへ移動するのはやめにして、ダウンタウンのホテルに戻り、階下から立ち上ってくる街の喧噪をBGMに一眠りした。
目覚めたのは午後4時前。予定を変更して、バークレーへ行くことに。BART(高速鉄道……まあ、東京メトロみたいなもの)に乗って、約30分。じつは今回の旅行中に合計6回このBARTに乗ることになるのだが、ぼくが観察したところ、紙の本の読書率は、最近の東京の電車内よりも明らかに高い(スマートフォン/SNS普及以前の東京よりは低いと思うが)、よってスマートフォンいじり率は低い。こんなのはぼくの体験と観察であって、データとしては無効なことはわかっているが、タブレットや電子ブックリーダーを使ってる人は驚くほどに少なかった。

蛇足ながら、東京(というか、日本の大都市圏)の電車内光景との大きな違いは、スーツ姿の勤め人がめっぽう少ないこと、受験/試験勉強中の高校生や中学生が皆無なこと、居眠りしている人も少ないこと、自転車を持ち込んでる人がやたらと多いこと(自転車のためのスペースがドアごとにある)、車内にしろフォームにしろ広告が極端に少ないこと、そのぶん路線図が大きくてわかりやすいこと、などなど。
Downtown Berkeley駅で降りると、カリフォルニア大学バークレー校の近隣ということもあってか、サンフランシスコのダウンタウンとは明らかに雰囲気が違う。道は広く、建物は低い。緑の葉っぱを茂らせた街路樹が歩道にちょうど良い木陰を作っている。いかにも観光客ってかんじの人々も見当たらない。目を合わせちゃいけない、と咄嗟に考えてしまうヤバいルックスの人にも遭遇しない。ユニクロやGAPなど多国籍企業の看板があからさまに視界に割り込んでくることもない。いいかんじだねバークレー、などと妻と言い合ってると、ほんとにいいかんじの書店に出くわした。

Pegasus Books。かなり広くて……300㎡ は軽くありそう。ここも Aardvark Booksと同じく、オールジャンルで新品も古本も扱っている。が、新品の占める割合が前者よりもずっと高い。ざっと半分くらいだろうか。音楽ソフト(CD、vinyl)や映像ソフト (DVD) の中古も扱っている。とりわけ、レコード(vinyl)が目につく(じつはこのあと、同じ大通りの反対側に Half Price Booksという全国チェーンの古本店を見つけるのだが、こちらでも音楽/映像ソフトは商われていて、とくにレコードの比率が高かった。アメリカでは、CD時代は終わりかけ、レコードさもなくばダウンロード、という時代に入っているのだろう)。
店の中央付近には、ガレージセールで入手したかのような古いソファとテーブルがおかれていて、そこで座り読みができるようになっている。案内の表示にしろ書棚にしろ、全体的に手作り感の強いお店で、レジカウンターの後ろにいるのもDIYな雰囲気をふんぷんと漂わせた二十代後半の女性。着古したチェックのシャツに色あせたジーンズ、まるでマリファナを嗜みながらルームメイトにカットしてもらったかのような、そしてシャンプーの後はいつだってタオルドライのみってかんじのブロンドのショートヘア。なんだか、アシッドフォーク系シンガーソングライターのようにさえ見えてくるけど……アメリカにやってきてまだ24時間弱、ぼくがへんに舞い上がってるだけ?

新刊コーナーを差し置いて店内でもっとも目を引くのは、“Staff Picks”(スタッフ選)という棚だ。エイミー・べンダー、リディア・デイヴィス、ジョージ・ソウンダースといった比較的最近の純文系作家から、ジェームス・クラウリー、マックス・ブルックス、アーシュラ・K・ル=グウィンといった新旧のジャンル小説家、果てはヴォネガット、ナボコフ、ドストエフスキー……さらに、光瀬龍『百億の昼と千億の夜』、黒澤明『蝦蟇の油―自伝のようなもの』の両英訳! もちろん、ぼくの知らない作家の知らない作品(おそらくは日本では未刊行のもの)もたくさんあるのだが、そのひとつひとつにスタッフのコメントが付いて陳列されている。この、ごった煮感にしびれる。何者にも阿ることのない、てんで空気を読まない、いや、これこそがアメリカの空気であるところの、「わたしはわたし、あなたはあなた」を集積した、ごった煮感に。
全体の品揃えにおけるフィクション/文芸の割合は……ざっと、三割五分くらいだろうけど、スタッフ選の書棚に限れば、八割強がフィクション/文芸。この店に限ったことではないのだが、日本のふつうの書店で幅を利かしてる(というか、売れているんでしょうけど)セールスメッセージがそのままタイトルになったような自己啓発本? 処世術と仕事術と精神論が合体したようなビジネス実用書? 日本株は五年で売れだの知られざるアメリカの闇だのといった軽めの(つまり、専門書ではない)経済本/歴史本/教養本? それから、幅を利かすほどじゃないけどけっこう目につく「散歩とコーヒーと読書」「楽しい古本屋巡り」的なエッセイ? の類いは、どういうわけか見当たらない。拙い英語力のせいで目がキャッチできないだけなのかもしれないが。
さまざまな分野と種類の本がミソもクソもいっしょにすさまじい回転率で大量に入り乱れる日本の書店のほうがはるかに豊かなのだ、と言うこともできるんだろうけど……そもそも豊かさって何? つーか、本って何? 何をもって本? まあ、いずれにせよ、いま挙げたような本がお好きで日頃から書店に通ってらっしゃる方は、アメリカのインディペンデント系書店にやって来てもつまらないかもしれません……念のため。
CITY LIGHTS BOOKSELLERS & PUBLISHERS
(サンフランシスコ)

翌日。午後の便でサンフランシスコを離れることになっていたので、最初からピンポイントで狙いを定めて、City Lights Booksellers & Publishersへ向かった。サンフランシスコを訪れるのは二度目だけど、前回――たしか1997年の夏――は大いなる事情と小さな怠惰によって来そびれていた、ピンポイントで狙いを定めて訪れるにふさわしい書店。ビート・ジェネレーション好きにとっては聖地のような書店。さらには、カウンター・カルチャー、ヒッピー、オルタナティヴ、インディペンデント、DIY――そんな単語に縁取られた、ムーヴメントなりアティチュードなりコンセプトなりを、敬愛する/実践する/拠り所とする人々の、総本山……なんていうのは、言いすぎか。
ともあれ、ぼくはいつになく襟を正し、背筋もしゃんと伸ばし、胸を高鳴らせて向かった。気負いすぎたのか、10時の開店より20分も前に着いてしまった。近隣を散歩。本日も快晴。青い空が目と心に染みる。陽射しは強いが風は涼しい。遠くに海が見える。ベイブリッジも見える。近くにはトランスアメリカピラミッドが聳える。

10時5分、聖地に戻ってくると、すでに巡礼者/客が何人か。ぼくとほとんど同時にお店に足を踏み入れたのは、初老、おそらく七十代のカップル。ビート・ジェネレーションの聖地に七十代の初老夫婦……てのが日本人の感覚、というか少なくとも、ロウブラウな辺地で育ったぼくの感覚では、いまいちしっくり来ないのだが、もしケルアックが生きてたら当年とって九十二歳だし、この書店を一躍有名にしたギンズバーグ『吠える』の刊行から今年で58年……つまり、七十代なんてぜんぜんふつうなわけだ。彼らの様子から、絶対に近所の人じゃない、おそらくベイエリアの人でもない、もしかするとアメリカ人ですらないかもしれない、明らかに観光客だ、というのがわかる――そして、数分後、彼らがドイツ語でしゃべってるのを小耳に挟むことになる。
書店員というより、なかば観光地化した老舗バーのバーテンダーといったかんじの、浅黒い肌の男が、心持ち冷ややかな微笑で、ぼくと初老のカップルが入店するのを迎える。そばに控える、同じように浅黒い肌の若い女性スタッフも、自分の職場にプライドを持ってる人に特有の、横柄さの入り混じった落ち着きと落ち着きの入り混じった排他性を、それとなく漂わせている。

じっさいに辿った順とは逆になるが、まずは地下。広さは75~100㎡ほどか。ミステリーやSFなどジャンル小説(一階でいくら探してもなかったブルース・チャトウィンはここにあった、紀行文学がジャンル分けされているとは)、映画や音楽関連、政治学や経済学関連(Green PoliticsやAnarchism なんて分類も)、文化人類学や形而上学……それから、意外なことに、児童書や料理本まで揃えてあった。
そして、一階は(広さはレジカウンターがあるぶん地下よりじゃっかん狭い)まるごとフィクション。入ってすぐのところに、シティライツの出版部門から刊行されている数々のタイトル。それから……これまでに訪ねた書店との、というより、英語圏の多くの書店との大きな違いは、細かな分類がされている、ということ。具体的には、英語圏文学でも、18世紀19世紀のものと、20世紀以降のものは別の棚だったし、海外文学/翻訳ものも、フランス、ドイツ、ロシア、ラテンアメリカ、中東、アジア……と国や地域によって分かれていた。
日本ではあまりアナウンスされることのない事実だと思うので、簡単に説明を差し挟むと、英米の書店ってけっこう大きな規模のところでも、棚は「国内文学、英語もの」か「海外文学、翻訳もの」かには分かれていない。たいがいは、オリジナルの言語がなんであろうとぜんぶごっちゃで、単に著者名のA to Zで並んでいる。例えば、村上春樹(Murakami)は、Mの欄、つまり、サマセット・モーム(Maugham)やコーマック・マッカーシー(McCarthy)の並びに、川端康成(Kawabata)はフランツ・カフカ(Kafka)やミラン・クンデラ(Kundera)の並びに陳列されている。
この細やかな分類は、文芸を専門とするシティライツとしての矜持なのか。あるいは、翻訳というプロセスをことのほか重視しているということなのか。僭越ながらぼくの意見をいわせてもらうと、ヘミングウェイもヘッセもボルヘスもウェルベックもウェルシュも三島もチェーホフもカルヴィーノもぜんぶごっちゃってのが最高にワンダフルなんだけれど。はじめて、そんな分類、というか、無分類を目の当たりにした時は、胸がすく思いがしたものだけど。
ちなみに、アジアのところに、ハルキ・ムラカミ、リュウ・ムラカミ、コウボウ・アベ、ヨウコ・タワダを見つけた……これだけだったのが(見落としてしまった可能性もなきにしもあらず)、残念。
地下と一階だけでもこの書店を訪れる甲斐はじゅうぶんにあると思う……しかし、シティライツの中枢というか売りは二階だ。ビート関連と詩集がぎっしり。ぎっしりとはいえ、地下や一階が人がすれ違うのも難儀なほどところ狭しと陳列されているのに対して、こちらは、書棚は壁際のみ、中央にはアンティークなテーブルや椅子も置いてあって、ゆったりとしたスペースになっている。立ち読み、座り読み、考え事、瞑想、詩作、どうぞご自由に、といった雰囲気。


ただし、階段を上がったところに“WARNING! Reading Books May Change Your Life”と印字されたポスターが貼ってある(好きだなあ、こういうユーモアのセンス)。ついでながら、店内には、ほかにも“Democracy Is Not A Spectator Sport”とか“BOOKS NOT BOMBS”といった標語がでかでかと貼ってある。ようするに、ただの書店ではない、ということ……だよね。


さて、ぼくはおのぼりさんよろしく(というか、じっさいそうだし)、“CITY A COMMUNITY CENTER FOR BOOKS AND FREE THINKERS ”とプリントされたオリジナルTシャツと、ケルアックの“Big Sur”を購入して店を出た。ちなみに、“Big Sur”は、“On The Road”に引けを取らない傑作だと、かねてから思っている。安直な物言いだけども……ぐっときちゃうのだ、中年期に入って傷つき疲弊したケルアックに。
THIRD PLACE BOOKS(シアトル)

ワシントン州シアトルへ。サンフランシスコの晴天からシアトルの曇天へ。シータック空港に、15年来の友人であるJが迎えにきてくれる。彼の出身地はニューヨーク、その後オハイオ、埼玉、京都、シカゴ、東京と(ざっと)経て、三年ほど前にワシントン大学の准教授のポストを得、シアトルに移ってきた。というわけで、シアトルでは彼の家に泊めてもらい、行動などもひとまず任せきりなのだが……その晩、彼がディナーに連れて行ってくれたのは、Third Place Booksという、なんとこれまたインディペンデント系書店の奥で(書店との仕切りなしに)営業する、ギリシャ料理レストランだった。
「なんと」と書いたのは、ぼくは彼に書店に行きたいなどとは一言も言ってなかったのだから。食事前、みんな――Jと彼の韓国人の奥さん(彼女もワシントン大学の准教授)、ぼくら夫婦――でビール(IPA)を飲みつつおしゃべりしてる時に、憚りがてら団らんから抜け出して店内をぶらついた。
広さは……いいかげんな数値に置き換えないとすると……典型的なコンビニエンスストア4店舗分くらい? バスケットボール・コートがすっぽり入るくらい? 新刊も古本もオールジャンル。新刊と古本の比率は4:6くらいか。古本の書棚をうろついていると、どこかの、しいて言うなら、小さな町の大きな図書館にいるような錯覚にとらわれる。妙に居心地がいい。ここが商業施設だということを失念してしまう。適当な本を抜き出して板張りの床に座り込んで読み耽りたくなる。
一角のちょっとしたスペースで、初老の男女が6人ほど椅子を車座にして座っていた。そのひとり、深緑のセーターを着た白髪の男性と、目が合って微笑み合ったのをいいことに(かつ、ちょうど休憩中のようだったし)、おじゃましてすみません、と断りつつ、二三質問してみた。以下、編集済みの――ぼくのたどたどしい英語や不格好な問い返しといった不純物を取り除いた後の――やりとり。
「何かの集まりなんですか?」
「ブッククラブだよ。プライヴェートなね」
「プライヴェート?」
「うん、告知はしてないんだ。月に一度ここに集まってる」
「どんな本を読んでいらっしゃるんです?」
「とくに明確な方針があるわけじゃないんだが……先月と今月はジェーン・オースティンを読んだよ。『高慢と偏見』と『説得』を」
「ジェーン・オースティン!? ジェーン・オースティン・ブッククラブっていう映画や本が――」
「いやいや、その本や映画とは関係ないよ……どっちも良かったけどね。その前は、カーソン・マッカラーズを読んでた」
「本はどうやってセレクトするんでしょう?」
「順番に提案するんだ。来月の分はわしが提案することになっている」
「なにを提案するおつもりなんですか?」
「(ほかのメンバーにちらりと目をやってから、ぼく以外には聞こえないように声を低めて)シャーウッド・アンダーソンだ。『ワインズバーグ・オハイオ』をもう一度じっくり読んでみたいんだよ」
「なるほど。ご親切にありがとうございます」
「どういたしまして」
営業時間中(ぼくが訪ねたのは平日の夜7時ごろ)の書店の片隅で、このような小規模の読書会が催されている……つまるところ、まちの書店でありつつ、コミュニティ・スペースとしても機能している、機能させている、ということだろう。あとでウェブサイトを閲覧してわかったことだが、じっさい、 “Public Commons” であることを前面に打ち出していて、シアトル市内にある二つの店舗(ぼくが訪ねたのは小さいほうだった)で、著者がやってくるイヴェントからライティング講座やこどもの読書会にまでいたる、年間1000本を越える無料イヴェントを催しているらしい。

25席ほどのカフェもあって、数人のいずれも一人客が、読書したりノートになにやら書きつけたりPCの画面を睨みつけていたり。その奥には、子どもの憩い場があって、ちょっとした玩具や絵本が置いてある(日米韓のアダルトな会話から弾き出されたJ夫妻の愛娘(三歳十一か月)はここに座って絵本を読みふけっていた)。そして、ぼくらがディナーを食べようとしているギリシャ料理のレストラン。さらに、地下にはけっこう広いパブがあって、地ビール(主にIPA)やパシフィック・ノースウェスト(ワシントン州とオレゴン州)産のワインが飲める。時間帯のせいもあってか、地下がいちばん賑わっていた。
全体的にゆるい。これまでの書店も(日本に比べれば)そうだったから(もっと言えば、書店に限らずなのだが)、今さら指摘するのもどうかと思うけど、ここはとりわけ、ゆるい。繰り返しになるが、商業施設だということを失念するくらいに。なのに、ちゃんと秩序がキープされている。素朴でありながら、なにげに洗練されてもいる。
東京に同じような書店/空間があったら、と想像してみた。おそらくはメディアに取り上げられて注目を浴びるだろう。「おしゃれスポット」的な扱いを受けるかもしれない。そうじゃなくとも、営業時間中に店内で、地元の老人たちがのどかな(あくまでも“一見”だけど)読書会を催すなんてことはきっと許されないだろう。客の年齢層もおのずと偏ってしまうだろう。少なくとも、三歳の子どもと七十八歳の老人と四十六歳の外国人観光客とが同じ空間でそれぞれの時を過ごす光景ってのはちょっと想像し難い。
シアトルという人口63万人(あくまでも市の人口だが)の中都市ゆえに、許される書店/空間なのか。しかし、日本の人口63万人の地方都市ならば、経営がなり行くだろうか。いかんともし難い、アメリカと日本の文化や風土の違い、それぞれの市民が有するコモンセンスの隔たりを含めて、いろいろと考えさせられる書店だった。
一つ、書き加えておきたいのは、朝の8時から営業しているということ(夜は10時まで)。旅を続けている間に徐々に実感していったことだが、アメリカは全体的に朝が早い。サンペドロやハリウッドのスターバックスは朝の4時半(当然、まだ真っ暗)から営業していた。
POWELL’S CITY OF BOOKS(ポートランド)

たまたま、最初の二日間のうちに立て続けに書店に出くわしたので、まるで書店探訪が目的の旅であるかのような印象をみなさんに与えているかもしれないけど、ぜんぜんそんなことはなく、かつ、本稿は旅行記ではないので、このあとの約一週間をすっ飛ばし……今、ぼくは今回の旅で二度目のオレゴン州ポートランドにいる。妻はすでに帰国し、彼女と入れ替わりで日本からやってきた男友達といっしょにいる。一度目はシアトルからアムトラックを使ったけど二度目は車を運転してやってきた……まあ、そんなことはどうでもいい……そぞろ歩き中に、大きな書店に出くわした。
Powell’s City 0f Books。大きい、というか、ポートランド市の規模(人口60万人弱、ウィキペディア英語版によれば都市圏人口は約230万人、ちなみに同じくウィキペディア英語版によれば、東京の都市圏人口は3500万人強)を考慮に入れれば、メガストアといってもいいかもしれない。
エントランスを入ってすぐのメインフロアは天井が高く、明るく、広々としている。新刊本がいかにも新刊本らしく「フィクション」「ノンフィクション」「バイオグラフィー」といった分野ごとに陳列されている。ベストセラー・ランキングの棚やいろいろな賞の受賞作品を揃えた棚も設置されている(気になったのは、カート・ヴォネガットの『スローターハウス5』がフィクション部門のベストセラー・ランキングで20位にランクインしていたこと。今ごろなぜに?)。

長いレジカウンターには、何台ものレジがあって、会計を待つ客の列ができている。まあ、言ってみれば、ふつうの大型書店ということなのだろうが……いや、しかし「ふつうの」と言い切ってしまうには、少なからず違和感がある。たとえば、前回のアメリカ旅行中にニューヨークやシカゴで立ち寄ったBarnes & Nobleや、パリのFNACや、頭の中で少々翻案する必要があるが新宿の紀伊國屋書店とは、どことなく、しかし確実に、ムードがちがう。
なんといえばいいのか、ようするに(何度もこれらの言葉を使うことにさすがに恥じらいを覚えるけれど)インディペンデントな、オルタナティヴな、空気が漂う。態度も方針も服装もインディレーベル在籍時のままに、世界的メガヒットを飛ばしてしまったグランジ・バンドのような……ってこんな比喩じゃなおさらわかりにくいか(すみません)。
これこそがヒッピー〜DIYの街・ポートランド的ってことなのかなあ……などとぼんやり考えながらキョロキョロしていると(自分ではキョロキョロしてるつもりなどなかったのだが)、三十代後半とおぼしき赤毛の女性に “Can I help you? ”と声をかけられた。どぎまぎしつつ――早い話、ぼく好みの美熟女だったわけで――「いいえ、大丈夫です、ありがとう」と答えると、彼女は上腕部に貼られた“NEED HELP?”という黄色いステッカーを指差し、両頬が浮き上がるほどににっこり笑って言い添えた、「なんでも訊いてくださいね」。
メインフロアを離れて、カテゴリー別になったフロアに足を踏み入れると、インディペンデント/オルタナティヴなムードはより濃厚になる。雑誌セクションの一角にはジン(zine)のためのスペースがある。フェミニズムやLGBT関連の雑誌も目につく。地元で発行された詩の雑誌なんかも置いてある。オンデマンド印刷機のEspresso Book Machineも設置されていて、道端に停車中の宅配便トラックのごとく、ほんのさっきまで動いてたような雰囲気がある(この時は動いていなかったが、過去に印刷・製本された本がすぐ後ろの棚に陳列されていた)。
そうして、ほんのり暗くなった書棚の森に足を踏み入れると、ふつうの大型書店との決定的な違いに遭遇する――古本も取り扱っているのだ。いや、古本も取り扱っている、というレヴェルではなくて、(あとで知ったところ、それこそがこの書店のストア・コンセプトなのだが)古本と新品とが同じ棚の中で同じ扱いで売られているのだ。例えば、チャールズ・ブコウスキーの “Women” ――新品は15.99、そのすぐ隣の中古品は10.95ドルって具合。


それにしても、圧巻の品揃え。店内はちょっとした迷路のような作りになっているのだけど、カテゴリーごとに標示が色分けされていて(まるで地下鉄の路線図のよう)、存外にわかりやすいし、時間が許すならあえて迷い込んでみるのも楽しいかもしれない。ほんとに迷って出てこられなくなったとしても(そんなやつはいないだろうけど)、ところどころにインフォーメーション・デスクがあるし、前述したように、“NEED A HELP”という黄色いステッカーを胸や腕につけたスタッフをそこらじゅうに見かける。店内案内図のようなものがないかなと思い、スタッフに尋ねてみたのだが、現在品切れ中で、次の入荷は来月とのこと。
簡単な食事のできる広々としたカフェもある。カフェの中の大きな黒板には、メニューではなく近々催されるイヴェントのスケジュールが記されている……と、書いているうちに思いついたが、このカフェも含めて書店全体としては中規模の美術館の雰囲気(フラッシュさえ炊かなければ写真も自由に撮れる欧米の美術館――ということになるけれど)に近いかもしれない。本のすべてを、手に取ってもいい、気に入れば買うこともできる、展示品と考えれば、妙にしっくりくる。

おみやげグッズというかオリジナルグッズもなかなかに充実していて、お店のロゴ入りトートバック、ステッカー、マグネット、マグカップ、グラス、水筒、傘、Tシャツ、パーカー、帽子、ハイソックス、ヴォネガットやマーク・トウェインのマグカップ、などなど。しかし、書店のロゴ入りハイソックスって……。
あとで知ったことだけど、オンラインでの販売にもずいぶんと力を入れていた。ぼくは日本に戻ってから、日本のアマゾンではブツ自体がバカ高く、アメリカのアマゾンではブツは安いけど送料がバカ高かった、Truman Capote “The Dogs Bark”の中古本を手頃な値段と手頃な送料で見つけて、購入した。10日ほどで手元に。郵便ポストの中に外国郵便を見つけた時って、いまだに心が弾みます。
SKYLIGHT BOOKS(ロサンゼルス)

さらにまた一週間飛ばして、旅の終点はロサンゼルス。しれっと書くと、余裕綽々で移動してるみたいだけども……地図が手元にある方は是非ご覧になってください。主に車を運転して移動した旅の後半をざっと記すと……シアトル〜アバディーン〜ポートランド〜(アムトラック車中泊)〜サクラメント〜ヴァレーホ〜ナパ&ソノマ〜バークレー〜モントレー〜ビッグサー〜サンペドロ〜ロサンゼルス。
そんなわけで三週間近くにおよぶアメリカ旅行が終りかけていた。最終日もすでに日が暮れつつあった。ぼくはハリウッドにいた。その日は昼過ぎにハリウッド近くのモーテルにチェックインし、地下鉄に乗ってLAのダウンタウンに出、現代美術館MOCAを見学し(いまいちだった)、光と影が錯綜するダウンタウンをぶらぶらし(いまいちだった)、アメリカ滞在中にすっかり好物になったサラダランチを食べ(いまいちだった)、ハリウッドに戻ってきて、観光客がうじゃうじゃしているスポーツバーのテラス席でバド・ライトを飲みながら、賑々しく中継されるアメフトの試合を無視しつつ、しこしこと旅日記をつけていた。車での移動をはじめ諸々の理由で書きそびれていた分を。
ロサンゼルスにやって来るのははじめてだった。にもかかわらずほとんど調べていなかった。何か月か前にロスを特集していた雑誌を買ってはあったのだが、忙しくて読み損ねていたし、その手の情報をおいそれと受け入れることへの羞恥やひねくれた反発が(買ったくせに)あったりもして旅の荷物には混ぜなかった。ベタなガイドブック(「地球の歩き方」と“Lonely Planet”)は一応(まあ、テクニカルな情報も必要なわけで)、持ってきていたけど、携帯してるのが鬱陶しくなってモーテルに置いてきた。翌朝日本へ帰る、という既決の事実が心に雨雲のごとく、いや、ビニールシートのごとく、覆い被さってきていた。何を隠そうぼくは、やっぱ日本がいちばんだよね〜、なんて逆立ちしても思えない人間なのだ。
そんなわけあるかよ? アメリカがいちばん、ではないにしても。そもそも、旅に出ている、この状態が、この浮遊感が、この落ち着きのなさが、たまらなく好きなのだ。このまま毎日車で移動しながらのモーテル暮らしでもかまわない(金さえあれば)と思ってしまう。まあ、半年もそんな状態が続けばさすがに辟易するのかもしれないが、3週間やそこらではむしろ心地よいだけだ。それが終わりかけていた。終りかけていて、憂鬱だった。
そんな時に、ふと思った。そうだ、本屋さんへ行こう。ロスでは――といっても、この半日のことだけど――一度も書店に出くわしていなかった。ハリウッドの繁華街は、いってみれば、新宿の歌舞伎町や原宿の竹下通りのようなもので、書店などありそうもない。ぼくのiPhoneは、Wi-Fi環境下でしか使えないことになっていたので、スポーツバーの、素行の悪さがNFLへの道を閉ざした元ランニングバックといった雰囲気の、店員に、フリーWi-Fiのパスワードを尋ねた。愛想は小数点以下だけど、わりに読みやすい字で紙ナプキンに書いてくれた。そうして、グーグルに「Bookstore Hollywood」と打ち込んだ。何軒か引っかかった中で、もっともアクセスしやすい書店(地下鉄で二駅、かつ駅から徒歩圏内)へ、向かった。

その書店Skylight Booksに到着した時には日は沈んでいた。午後から別行動を取っていた友人との待ち合わせ時間も迫っていた。だからゆっくり見てまわる余裕はなかった。しかしながら、インディペンデントな書店であることは一目瞭然だった。明らかにアメリカの書店は新しい時代――アマゾン以降の、そして電子書籍化以降の時代――に入ってるのだ、ということをまざまざと感じさせる書店だった。「レコードがクールなように紙の本ってクールだよね」「書店ってのはもはや本を売るだけの場所じゃないんだ」「未来って自分たちの手で作るものなのかもしれないよ」――そんな囁きがどこからともなく聞こえてきそうな書店だった。そしてなにより、書物に対するリスペクトと愛情を感じさせる素敵な書店だった。いわゆる「おしゃれ」なのではない。というか、そういう物差しは野暮きわまりない。ただ、静かに熱い、のだ。

店の様子は簡単に。二手に分かれていて、地下鉄の駅から来ると手前の店舗に、アートブックやグラフィック・ノヴェル、音楽関係、映画関係、ジン(zine)、雑誌、それに、ちょっとした文房具。奥側の店舗に、フィクションやノンフィクションや哲学本や料理本、その他。古本はなし、新品のみ。当然のごとく、スタッフ選があり、各種のイヴェントもあり。
ブコウスキーのプリントTシャツが売っていた。書店で本を買わずにTシャツのみ、というのも少々気が引けたし、おまけにブコウスキーというのもなんだか気恥ずかしかったのだけど……口の中に唾液がたまるほど欲しいのだからしょうがない、レジへ持っていった。
三十すぎとおぼしき、無精髭を生やした気だるそうな店員が、気だるそうな口調で、わざわざ訊くまでもないことだけどさといった口調で、話しかけてきた。
「ブコウスキーが好きなの?」
「うん、とても。ゆうべはサンペドロに泊まった」
「ふうん。お墓には行った?」
「うん、今朝ね」
「そうか。ビールは持っていった?」
「同じことを墓地の管理人のおじさんにも言われたよ、ビールは持ってきたかって、あいつはビールが好きだったろって」
「おっと。決まり文句ってわけか」
「きみもブコウスキーが好きなの?」
「ああ、もちろん」彼の灰色がかったグリーンの瞳がぱっと輝く。「グレートだよな、あいつ」
会計の間の、そんな、短く、どうということのない会話だったけれども、そのちょっとしたコミュニケーションが、日が傾くにつれて濃くなっていた、息苦しいほどに濃くなっていた憂鬱を、いくらか薄めてくれたのは確かだ。まあ、ちょうどいい薄さに。ちょうどいい……気取った物言いかもしれないけど、少しの憂鬱は必要なのだから。本を読むにせよ、何かを書くにせよ。つまり、生きていくために。


翌朝、ロサンゼルス国際空港への道すがら、フリーウェイに入る前の下道で、凄まじい渋滞に巻き込まれた。かなり余裕を持ってモーテルを出たはずなのに、レンタカーのフォードはほとんど数メートルずつしか進まず、いつしかきわどい時間になっていた。友人は焦り始める。ぼくは不謹慎なジョークを飛ばす。友人は笑わない。
フリーウェイに入ると渋滞は和らいだものの、しばらくはのろのろとした走行が続いた。いまだ燻っているぼくの気持ちをいみじくも表しているかのように。ロサンゼルスの、アメリカの、笑っちゃうほど巨大な風景が後方にゆっくりと流れていった。樹々、家々、車輛、ビルディング、ショッピングモール、広告板、倉庫、空き地、工事中の何か、その他の何やかや。空を仰げば、気が遠くなるほどの深い青が気が遠くなるほどの彼方へと広がっていた。目を瞑ってもその深い青はぼくの中に広がっていた。その深い青の中では、飛行機に間に合うかどうかなんて瑣末なことに過ぎなかった。
■関連記事
・いまなぜ本屋をはじめたいのか
・ワルシャワで、「家みたいな書店」と出会う
・ボーダーズはなぜダメになったのか?
執筆者紹介
- 小説家。著書『どうしてこんなところに』(双葉社)、『冬の旅』(河出書房新社)、『アレルヤ』(双葉文庫)ほか。
桜井鈴茂オフィシャルサイト
最近投稿された記事
- 2014.12.08レポートアメリカ西海岸ブックストア探訪記

