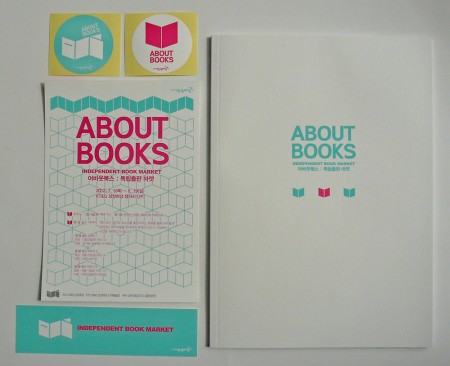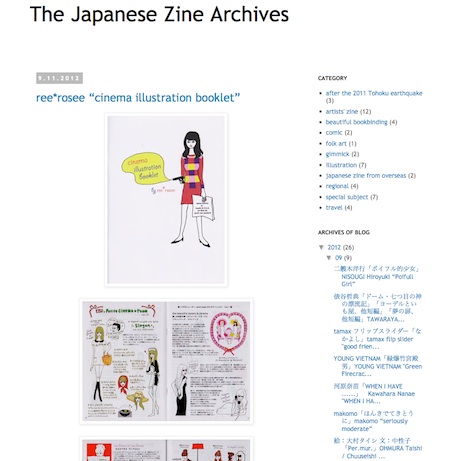「ニューヨーカー」誌のフィクション・エディターであるデボラ・トリースマンにインタビューをしたとき、彼女は「ニューヨーカー」誌に来るまえに「グランド・ストリート」誌という文芸季刊誌のマネジング・エディター(副編集長)を4年間やったと言っていた。(デボラのこのインタビューが収められた電子書籍『アメリカン・エディターズ〜アメリカの編集者たちが語る出版界の話』はここで購入できます)。

デボラ・トリースマンは『アメリカン・エディターズ』にも登場。
「グランド・ストリート」誌でデボラは編集はもちろん、広告取りから、ウェブサイトのことまで出来ると思えることは全部やったと語ってくれた。僕も自分の出していたアメリカの雑誌・洋書を読むひとのための雑誌「アメリカン・ブックジャム」を出しているとき、記事書き、編集、コピーライト、広告取り、ウェブなど何でもやった。
「アメリカン・ブックジャム」を編集していた場所が、僕の住んでいるニューヨークだったため、アメリカの雑誌の作り方に大きな影響を受けた。そして、ひとくちにジャーナリズムと言っても、新聞のジャーナリズムと雑誌のジャーナリズムは大きく違うということも知った。
アメリカの作家/脚本家で作家ジョーン・ディディオンの夫であったジョン・グレゴリー・ダンによると、雑誌ジャーナリズムでは最終的に「Why」が「Who」「What」「Where」「When」「How」よりも重要になってくるという。それも抽象的な「Why」ではなく具体的な「Why」に重きが置かれる。
このジョンの言葉を読んで「おー、なるほど」と興味を持った人に読んでもらいたいのが、『The Art of Making Magazines』(彼がこう語ったレクチャーもこの本に収められている)。
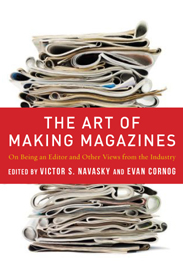
刊行はコロンビア大学出版部。
この本はもともとコロンビア大学ジャーナリズム科でマガジンの勉強を集中的におこなう学生や大学院生に向けてのレクチャー・シリーズをまとめたもので、そのレクチャラーのラインアップが凄い。
「エル」誌の編集長ロバータ・マイヤーズ、「ワシントン・ポスト」紙のコラムニスト、マイケル・ケリー、「ニューヨーカー」誌のファクトチェッカー、ピーター・キャンビー、「ヴァニティ・フェア」誌のデザイン・ディレクター、クリス・ディクソン、言わずと知れた有名編集者ティナ・ブラウン、「コンディナスト・トラベラー」誌のクリエーティブ・ディレクター、ピーター・カプラン、「ハーパーズ・マガジン」誌の発行人、ジョン・マッカーサー、名門出版社クノッフの編集長ロバート・ゴットリーブなどだ。
このラインアップに登場する編集者、デザイン・ディレクター、コラムニスト、クリエーティブ・ディレクターたちはその職につくまでに当然そのほか「ニューヨーク・タイムズ」紙、「GQ」誌、「エスクァイア」誌、「アトランティック・マンスリー」誌、「ローリング・ストーン誌」、「イン・スタイル」誌、「ミラベラ」誌、サイモン・アンド・シュースター社、「ニューヨーク・マガジン」誌などに在籍した経歴があるので、レクチャー本文の冒頭に添えられている彼らの紹介文を読むだけで、マガジン好きの人なら脈拍数が上がること請け合いだ。
どのレクチャーも面白いが、普通の記事では絶対にお目にかかれないものを2、3紹介しよう。
え〜と、と言ってもほとんどの内容が普通の雑誌や新聞に載ることがないものなので選ぶのに困るが、まあ、僕にとって特に興味深かったものを紹介する。どれが興味深いはもちろん人によって違うとは思うけれど。
雑誌と書籍ではことなる編集者の役割
まずは、ロバート・ゴットリーブのレクチャー。彼はウィリアム・ショーンの跡を継いで「ニューヨーカー」誌の編集長を務めたが、出版社クノッフやサイモン・アンド・シュースターで編集長を務めトニ・モリスン、ジョン・チーヴァーなどの編集者でもあった。つまり、本と雑誌の両方の世界で編集長の経験がある。その経験から雑誌の編集者と書籍編集者の違いを語っている。
ロバートによると本の編集者は著者を守る立場にあるという。著者の仕事を理解し、同じ波長で接することが重要だという。本の編集では著者との信頼関係が必要となってくる。彼はトニ・モリスンとのやりとりを挙げている。彼の元でトニ・モリスンが短い小説「Sula」を書き上げたあと、彼はトニ・モリスンにこう言った。「これはソネットのようなとてもいい作品だ。もう一度同じような作品を書く必要はない。次は自分を自由に開け放って、もっと大きな作品に取り組んだらどうだろう。やるだけやって、失敗でもいいじゃないか。やってみよう」
ロバートはトニ・モリスンが自分でも分かっていたことを言ったまでで、編集者として彼女がやりたいと思っていることをやってもらうきっかけになる必要があったと言う。そして彼女が書いた作品が「Song of Solomon」だった。この長編作品はトニ・モリソンの評価を確定させる作品となった。
一方、「ニューヨーカー」誌の編集長として雑誌の世界も知っている彼は、雑誌の編集長の役割をこう語る。
「雑誌では編集長が神的な存在です。編集長はライターを守る必要はありません」。つまり雑誌では立場が逆となり、書き手が編集長の希望に応えなければならないのだ。全ての原稿は一度編集長の元に送られ、編集長が目を通し担当の編集者に渡される。「ニューヨーカー」誌の場合はそこからファクトチェッカーに回るのだが、ロバートは名物プルーフリーダーのエレノア・グールドのことを語っている。エレノアのファクトチェックを受けたスーザン・ソンタグが初めは「何故、彼女はこんな直しをするか理解できない」と言っていたが、そのうちに「ちょっと待って、この女性は天才だわ。並外れて優秀だわ。私が書いたもの全部を彼女にエディットして貰いたい」と言うようになったことや、エレノアとジョン・アップダイクとの戦いを語っていて、とても面白い。
もうひとつは「ヴァニティ・フェア」誌のデザイン・ディレクターのクリス・ディクソンのレクチャー。彼は「ニューヨーク・マガジン」誌のアート・ディレクターも務めた経験があり、「ニューヨーク・タイムズ・マガジン」誌でエディトリアル・デザイナーとしても働いている。
雑誌作りはアート側の人間と文字側の人間が関わる。このふたつの分野にまたがる優れた才能を持つ人は稀で、普通はどちらかひとつの側からの観点で雑誌作りを進めていくことになる。自身を振り返れば、僕はまったく文字側の人間でアートの部分はまったくデザイナーに任せてきた。僕たち文字側の意見からすると雑誌は記事で読ませるもので、ビジュアルの大切さは理解していると思っているが、それでも記事の内容のほうが重要だと感じている。
今回クリスのレクチャーを読んで、アート側の人がいかに余白を大切と感じているか、タイプフェイスを熟知し記事とタイプフェイスを合わせることの大切さ、フォントの大きさなどについての見解をもっているかを知り、いまさらながらであるが、ためになった。
「文字側の人間がデザインの美的センスに敏感になるためにはどうしたらいいか」という質問に、クリスは「ヴァニティ・フェア」誌や「ワイアード」誌などよいデザインが試みられている雑誌を多く見ることだとしている。
そして、もうひとつを挙げるとすれば、「ハーパーズ・マガジン」誌の発行人ジョン・マッカーサーのレクチャーだろう。
1996年、「ハーパーズ・マガジン」誌は製薬会社ファイザー社に好意的ではない記事を載せた。このためファイザー社は予定していた10万ドルの広告をキャンセルした。ファイザー社のこの記事は、もしファイザー社がその後4年間広告を載せ、それに製薬会社協会の広告も取ったとしたら、40万ドルから100万ドルの損害となる。1本の記事で40万ドルから100万ドルがぶっとんだのだ。
これは「ハーパーズ・マガジン」誌にとって大きな痛手である。ジョンは当時の上手くいかなかったファイザー社との電話でのやりとりを語っている。その一方で、社会にとっての表現の自由の大切さも語っている。大上段から正義を振りかざすのではないが、それでもやはり、国が健全であるためには表現の自由は欠かせないという。いまその自由の限界は広告主とメディアの関係に大きく左右されているという。
ビル・クリントンが大統領だった当時、クリントンの政策ストラテジストだったディック・モーリスは「もし自分の考えを大統領に伝えたければ、ニューヨーク・タイムズ紙、ワシントン・ポスト紙のop-ed欄か、ハーパーズ・マガジン誌、ニューヨーカー誌、ニュー・パブリック誌、アトランティック・マンスリー誌などの記事に自分の意見を載せればいい」と語っている。
そうした信頼できるという評価を得るメディアになるためには、発行人のそれなりの決意が必要なのだと分かるレクチャーだ。
その他にも、雑誌には(文章表現のチェックなどを担当する)コピーエディターが必要だと語るバーバラ・ウォルラフ、自分のあこがれた女性雑誌「エル」の編集長にいかにしてなったかを語ったロバータ・マイヤーズ、雑誌作りの極意を語ったティナ・ブラウン、多くの有名編集者や作家たちとの関係を語ったピーター・カプランなどどれも見逃せないものばかりだ。
これぞアメリカン・マガジン・ジャンキーたちに贈る1冊と言えるだろう。面白かった〜。
■関連記事
・ソウルの「独立雑誌」事情[前編]
・本のジャム・セッションは電子書籍でも続く