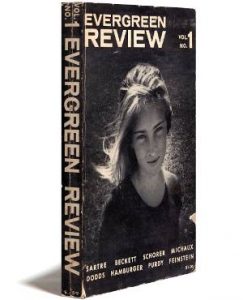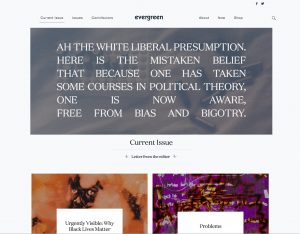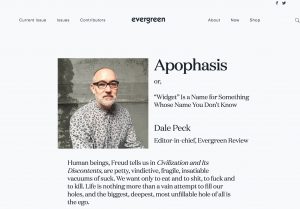ネット投稿小説プラットフォームを運営する各社に現状や今後に向けての課題について聞き、ネット投稿小説の現在と未来を解き明かしていく本連載の2回目。前回につづきエブリスタ代表取締役社長の芹川太郎氏のインタビューをお送りする。
創作を誘発する仕組み

エブリスタ代表取締役社長の芹川太郎氏。
――重視する指標としては読者数となりますか?
芹川:そうですね。数字という観点からは重要ですね。
――発掘や新ジャンル開拓という意味でアワードが重要であるということはわかりました。創作そのものを誘発する仕組みとしてはいかがでしょうか?
芹川:やはりアワードがわかりやすい取り組みだと思います。募集要項で、「こういう作品を求めています」と呼びかけることで、創作を促しているわけですね。基本的には書きたいものを書いてください、というのがエブリスタの基本的なスタンスですが、「デビューしたい」という方に向けては、世の中あるいは出版界ではこういう作品がいま求められている、ということをわかりやすく案内している部分はあると思うんです。
たとえば、「少年ジャンプ+」の原作賞がありますが、「全体を通しての小説としての完成度」ではなく、「連載漫画として1話、2話、と毎週順番に読者が読んだ時の各話の面白さ」を重視していると明言して募集しています。

「少年ジャンプ+」とタッグを組んだ漫画原作賞。
あとは教育という観点からは、石田衣良さんによる「作家養成プログラム」や、エブリスタのスタッフによる講評を得られる短編賞「三行から参加できる 超・妄想コンテスト」も好評です。
――アワードといえば金銭的なインセンティブというのがこれまで一般的だったかと思いますが、エブリスタの場合はそうではないわけですね。
芹川:もちろん商品券などを用意する場合もあるのですが、皆さんそれを目的に書く、ということはあまりないと思います。仮に賞金額を大きくしても、その分投稿が増える、ということは実績を振り返ってもありません。世の中の文学賞などは多額の賞金を用意していますから、それに見劣りしないようにはしたいと思いますが、いずれにしても金額ではないと思います。
――アワードがマッチングの精度をあげ、またトップ作品のクオリティを上げているということもよくわかりました。一方で、「場」としてのエブリスタ全体を見た場合に、全体の質を担保するためにはどのようなことをされているのでしょうか。
芹川:まず投稿される作品の総数が大事だと思います。ある割合で優れた作品が生まれてくると考えた際には、「数が質を担保する」側面はあります。作家のレベルアップに貢献するという観点からは、作品が読まれてフィードバックを受ける機会をいかに設けるかかなと。読者にコメントや評価をもらうというプラットフォームとしてはおそらくいちばん重要な機能があり、それに追加してプロにフィードバックをもらう機会を増やすということですね。
たとえば、「1万字小説を書いて『yom yom』編集長に読んでもらおう!コンテスト」を開催し、大変好評でした。大賞作品は新潮社の小説誌「yom yom」の紙版最終号(2017年冬号。次号から電子版に移行)に掲載されるというものですが、賞のタイトルからもわかるように、プロに読んでもらうこと、というのが大きなインセンティブになっているんです。

「1万字小説を書いて『yom yom』編集長に読んでもらおう!コンテスト」の受賞作。
――私のような商売をしていると、プロの編集者に書いたものを読んでもらうというのはある種の「痛み」も伴う作業なのですが、エブリスタに投稿されている方からすればそれは「喜び」になるわけですね。
芹川:マンガと違って、読むのに時間がかかる小説は、編集部持ち込みで読んでもらうことがほぼ不可能です。プロに読んでもらう機会がない方がほとんどですし、実際にちょっとした指摘によって自分の作品が「よくなる」実感が得られるという面も大きいと思います。それは投稿作家さんにお話を伺っても、私も感じるところですね。賞にはエントリーして、いいところまでは行くのだけれども、なかなかその上に行けない、という人にとっては、スキルアップのための非常に貴重な機会ともなっているのです。エブリスタのような投稿サイトの場合、短いエピソードを投稿した際の読者数やコメントの動きで「面白くなった」という手応えが直ぐに得られますので。
――たしかに従来の小説賞ですと、よほど上まで行かない限り「○次選考通過」といったところまでしかフィードバックが得られませんからね。
芹川:そうなんです。あとはエブリスタ内では「サークル機能」のような作家と読者、ユーザー同士のコミュニケーションを図る仕組みは充実していますが、作家同士のコミュニケーションをもっと生み出せないかと考えています。お互い学び合うところ、励まし合うところがあると思うんですよね。またリアルな場として、地方での文学フリマには出展し、オフ会も開催しています。
――そういったお話を伺うと、ますます小説投稿プラットフォームというよりも、SNSのようなコミュニティという位置づけが正しいように思えました。
芹川:そうですね。機能を提供すれば勝手に盛り上がるというものではないと思っています。書くほう、読むほうとも相当エネルギーを求められるサービスですから、そこに対してモチベーションを維持してもらうための我々の努力というのもかなり大切なものだと捉えています。カスタマーサービスも、モバゲー時代からの蓄積がありますが、「傾聴」は徹底しています。
――サイト内でジャンルをどう分けるか、というのもウェブ投稿小説サイトではかなり重要なポイントであると思います。ジャンルの切り方でランキングの様相や、そのカテゴリの盛り上がり方が変わってきますが、エブリスタさんの場合はいかがでしょうか?
芹川:そこは永遠の課題ですね(笑)。いまだに満足をしていませんし、すべての人が納得する分け方というのはおそらくないのだと思います。「小説家になろう」さんも最近変更されましたが、おそらく考えに考え抜いてあのような形になったのだと思います。私たちは取り扱いジャンルやユーザー層がさらに広いので、難易度が高いです。
エブリスタが考える投稿小説の未来
――投稿小説サイトはますます競争が激しい時代に入りました。そのようななかで、エブリスタをどのように位置づけていますか?
芹川:主要プレイヤーの一つにはなることが出来ているかなと思います。ただジャンル別に見るとライトノベルでは、「小説家になろう」さんには勝てていません。小説全体で見たときのラノベの重要度からすれば、エブリスタがそのカテゴリでできることは考えなければいけません。
――「小説家になろう」の場合は、商業活動を禁止していますね。そこで差別化という方向はありませんか?
芹川:それは我々もほぼ同じだと思います。出版社の販促活動としての連載は規約で原則として制限させて頂いています。一部存在しているものは、個別にお話をして決めているものですね。例としては集英社さんのJ-BOOKSの枠といったものはあります。
ただ、私たちもあまりそういった掲載を積極的にオススメしているわけではありません。あくまでエブリスタはコミュニティであり、作家の顔が見えにくい作品は読まれにくい傾向があるからです。ただ本を読みたいのであれば、アマゾンでもいい。それでもエブリスタでなぜ読むかといえば、作家との距離が圧倒的に近いからなんです。「読者がたくさんいるから、良質な作品を置けば読まれるだろう」、ということでもないんです。すでにデビューしている作家の作品であっても、作家さんがエブリスタの中で読者とのコミュニケーションを頑張っていると、だんだんとファンが増えてたくさん読まれるようになります。

作家と読者がサイト内でコミュニケーションできる仕組みも。
他のコンテンツサービスのように、我々が人気作を用意し掲載すればたくさん読まれるわけではないというところが難しいところです。
――KADOKAWAが「カクヨム」を始めるなど、出版社自らこの分野にも乗り出しました。
芹川:作家さんに作品を投稿してもらう、というのは何らかのインセンティブを用意すれば実は難しいことではないと思います。難しいのは読者さんを集め、サイト内で作家と読者を繋げることです。読まれるからこそ、投稿するし、書き続けられるのです。エブリスタの場合は、幸いモバゲーから、そしてドコモユーザーの誘導がありましたから、一定の規模の読者を獲得しています。これを出版社やスタートアップ企業が一から実現できるかというとそれなりにハードルは高いはずです。
――作品と読者とのマッチングの精度という面では差別化できませんか?
芹川:まだ十分に実現できていない部分もあるのですが、技術によってニーズのマッチングは追求していきたいところですね。今後、人工知能や機械学習によってレコメンドの精度を上げていくということも、やっていきたいと思います。読者からみたときの「発見」、我々から見たときの「発掘」を技術によってどう効率化するのかという話でもあります。データはもちろん取っているのですが、いまは人がその分析と反映をおこなっています。その部分をある程度自動化できれば、違う拡がりが出てくるはずです。
――同種のサービスというところから離れて、従来の文芸・ラノベと、ウェブ投稿小説は、どう異なると捉えておられますか?
芹川:いわゆる「携帯小説」の時代は異質なものであったと思います。人によっては「携帯小説は小説ではない」と評価するくらい異なっていたわけです。しかし現在では、従来の文芸やラノベも含めて、ウェブの中で生まれ、読まれるようになっています。昨年の出版界のベストセラートップ10の中になかに入った新人は、「小説家になろう」さん出身の『君の膵臓をたべたい』の著者、住野よるさんだけです。昨年の文芸で注目の新人を生みだしたのが唯一ネットだったということを考えると、もうその垣根はなくなっていると思います。芥川賞や直木賞をネット発の人が獲るのも、時間の問題のはずです。
一方で、エブリスタの中でも短編では純文学に近い作品をずっと投稿している人たちが一定数います。「三行から参加できる 超・妄想コンテスト」は隔週で行っているのですが、集まってくる作品のクオリティはタイトルからの印象に反してとても高いのです。毎回500〜700作品が集まってきて、文体もしっかりしたよく練られたものが集まってきます。「妄想コンテスト」の受賞作を中心にテーマ別に編み直した短編集は、現在「5分シリーズ」と名前を変えて河出書房新社さんから発売中です。
先ほどの「フィードバックがインセンティブである」という話にも通じますが、この賞は私たちが一つ一つ読んで講評をつけています。おそらく、これまではそういった「良質だけど短い」新人の作品を受止める場所はあまりなかったはずで、ネット上にそれを用意したことで、新たな才能が集まってくるということなのだと思います。
――本来、芥川賞は「短編」を対象とした新人賞なのに、書籍化するために原稿用紙換算で200枚書かないと受賞できなかったりします。文芸の短編のみを対象とした、ネット上の新人賞の仕組みがもっとあってもいいかもしれません。
芹川:新人発掘の場としては最も一般的な存在になっているというイメージは持っています。読者が最も多い場となっているか、というのはまだ未知数ではありますが。これは消費できるコンテンツの種類と数が増えていくなかで「小説」というものが、ウェブ小説によって劇的にその存在感を拡大するかというと、ちょっとわからない部分もあるからです。
とはいえ、作家目線で考えたときには、いわゆる文学新人賞に応募するとか、一方でパソコンに眠らせたままにしておく、という人はどんどん減っていくはずです。そこに僕は可能性を感じています。これまでがそうであったように、これからもウェブ投稿小説を巡る環境は変化するはずで、出版社さんや編集さんとの向き合い方も変わってくるでしょう。エブリスタとしてもそういった変化に柔軟に対応してきたいと考えています。
* * *
エブリスタはその出自やユーザー層、競合との差別化から、ネット投稿小説プラットフォームの中でも、特定の色がない「一般化」の道を探り続けてきた。作品のプロモーションや二次展開にも積極的に関与する姿勢は、従来の出版社の手法にも近いものがあるが、プラットフォーム上の各種データを元に、よりロジカルに方向性を探っていった。その結果、時代の変遷と共に、エブリスタにおけるヒットコンテンツも変化していった様子が、今回の芹川氏のインタビューから伺えたのは興味深いところだ。
その一方で、このエブリスタと非常に対照的な、ライトノベルに特化した方針で運営されているのが、「小説家になろう」だ。次回は、このサイトを運営するヒナプロジェクトを取り上げる予定である。