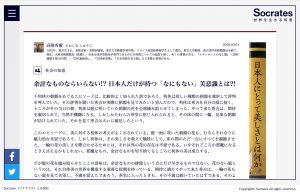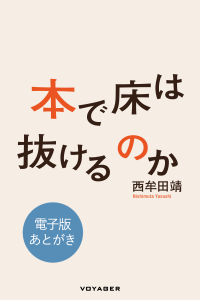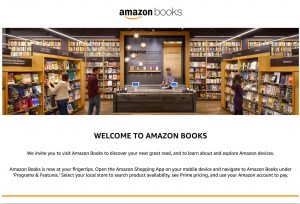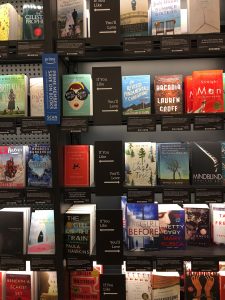イメージ通りではなかった電子コミック時代
第1回の「出揃った電子コミックのプレイヤーたち」から連載をスタートしてまもなく一年が経つ。第1回では、コンテンツホルダーでもある出版社が本格的に電子コミックに舵を切ったことでいよいよ本格的な電子コミック時代が来る、ということを書いた。
たしかに電子コミック市場は右肩上がりを続けている。逆に紙の出版物は部数、金額ともに縮小に歯止めがかかっていない。予想通りといえばその通りなのだが、現状は思い描いていた電子コミック時代とは少し違っている。
肝心の「電子コミック」の未来像がよく見えてこないのだ。原因は三つある。
一つ目は、配信の中心になっているのが無料コミックアプリだということだ。無料コミックアプリはコミックを売るのではなく、コミックでお客を集めて、コミック以外の広告やスタンプを売るビジネスと考えたほうがいい。コミックはおまけみたいなものだ。配信元は内容の良し悪しよりも、いかに広告収入を挙げることができるのかを考えているし、無料でおまけを読み始めたユーザーにとっては、コンテンツは無料で享受できるのが当たり前になってきている。これでは、コンテンツビジネスとは呼べない。
二つ目は、出版社の電子コミック戦略がいまひとつわからないことだ。豊富なコンテンツを武器に市場拡大に乗り出すのかと思いきや、雑誌がマンガの中心だった時代と同じように、ウェブの新連載に注力して、せっかくの財産を埋もれさせている。もちろんウェブ連載からもヒット作は出ているが、過去のストックをうまく使えば、その何十倍もの収益が期待できるはずなのだ。この状況は、技術的には圧倒的に優位にありながら、その技術の活かし方がわからないまま、アメリカのベンチャー企業やアジアの新興国に後れを取ってしまった、日本の家電メーカーの末路とどこか似ている。
三つ目は、収益化は紙で、という考え方が当然のように語られていることだ。電子は無料で配信して、紙化したものが売れることでようやくリクープできるというわけだが、結果として、本来ならば紙の属性から自由なはずの電子コミックの文法が、紙の属性に縛られたままになっている。韓国で生まれたスマホ向けの新しいマンガ「ウェブトゥーン」も日本にやってきたとたん、紙で出版することを考慮してコマを縦に並べただけのものが多くなった。韓国のようにウェブで完結できていないのだ。
つまり、「紙から電子」という看板は立派だが、マーケティングも表現も紙のまま、という不思議な状態がこの一年の間、続いていたのだ。
読者が求めるのは電子? 紙?
もう一つ気になっているのは、読者の反応だ。
教えている大学で学生を対象にしたアンケートを行ったり、レポートに「紙のマンガは消えるのか?」というテーマを出すと、学生のほぼ全員が「紙のマンガはなくならない」「紙のマンガのほうが好き」という反応を見せる。韓国からの留学生でさえも「ウェブトゥーンよりも日本の紙のマンガが好き」という答えだ。これまでマンガ市場縮小の理由として言われてきた「若者のマンガ離れ」は、現実とは違うのではないか。
学生にアンケートをして、もう一つ面白い反応があった。それは先ほどの韓国からの留学生だ。「自分にとってウェブトゥーンは暇つぶしで、ゆっくり読むなら紙のマンガ」というのだ。1話目からビューを稼がなくてはならず、1話あたり5分程度で読まれることを想定しているウェブトゥーンでは、複雑な物語設定が難しく、スケールの大きな伏線の多い作品は成立しにくい、ということらしい。両者が別物だということを留学生に教えられたようなものだ。
いずれにしても、「紙のマンガ表現が若者は古臭いものになってしまった→だから、紙のマンガの魅力が失われた→そのためにマンガ市場が縮小した→紙のマンガは滅びて、スマホで読む電子コミックの時代になる」という論法は間違っている。それだけではない。この連載でも書いたように、スマホが電子通信デバイスの最終形態であるという保証はどこにもないのだ。新しいデバイスが登場したとき、スマホで読む電子コミックそのものが過去のものになる危うさを秘めている。これで、電子コミック時代到来と言えるのか。
紙と電子の売り方の違いとは
電子コミックを含めたマンガの未来を作るための方法は、老舗の出版社や大手ITベンチャー系の配信会社が気がついていないだけで、必ずあるはずだ。小規模の出版社や配信会社の中には違う動きがあるのではないか。
今回は、電子小説、電子コミックを手がけるユニークな電子書籍製作会社と、ひとり雑誌社として独創的なマンガ雑誌を作り続けている個人を取材して、コンテンツ作りに関わる人の本音を探ってみた。
はじめに紹介するのは株式会社リ・ポジションの柳瀬勝也社長だ。リ・ポジションは、出版社と契約して電子書籍の製作受注を行うほか、「夢中文庫」のレーベルでBL、TLと呼ばれる女性向け連載小説の電子出版事業を自社展開する会社だ。「夢中文庫」のタイトル数は約450点。最近になって、女性向け恋愛コミックやエッセイコミックの製作配信もスタートさせている。配信は無料でなく有料である。

「夢中文庫」のトップページ。
本社は東京の木場にあるが、電子書籍の製作は、福島県にある子会社リポジション郡山が行っており、こちらのほうが主力部隊になっている。
「郡山のスタッフは女性が中心。我々の仕事は別に東京でなくてもいいのです。地方のほうが家賃も安いし、いい人材が選べるのも魅力です」と語る柳瀬。実は、電子コミック関連の会社を取材していつも疑問に思っていたのが、ほとんどの会社が東京都心の真新しいビルにオフィスを構えていることだった。IT化でもっと地方が活用できるはずなのに、IT系企業がそれをなぜ実践できないのか、と感じていたのだ。このことだけで、リ・ポジションには好感が持てる。
柳瀬が電子書籍編集の仕事をはじめたのは2012年。はじめは製作受注の仕事だけだったが、スタッフが育ってきたことや編集を外注できる先も増えたことから自社の電子出版にも踏み切ったという。
そんな柳瀬に電子コミックの現状はどう見えているのだろうか。
柳瀬 僕自身は「コロコロコミック」に始まって、ずっと紙で読んできていますから、紙への思い入れは強いんです。試験的に「夢中文庫」のオンデマンド出版もにも取り組んでいます。ただ、そもそも紙と電子では売り方が違うんです。そこを理解されてない人が多いのではないでしょうか。
——具体的にどこが違いますか。
柳瀬 僕らにとってはタイトル数を増やすことがまず必要です。タイトルが増えると、たとえば電子書店で半額キャンペーンをやったときに旧作の売り上げがドーンと増えて収益につながります。そういう収益モデルなんです。これまでの紙の出版だと、とにかく毎月毎月休まず新刊を出していかないと利益が出ませんよね。出版社は新刊を出す代わりにどんどん旧作を絶版にしていく。コンテンツが資産という考えが希薄なんです。僕らは、すぐに売れるかどうかは別にして、コンテンツのストックを積み上げていくわけです。
もう一つはボリュームですね。1巻や1話のページ数は紙より少なくていいんです。僕らの場合、基本は書きおろし作品です。単行本で書き下ろす作家さんの負荷を下げる意味でもページは多すぎないほうがいい。巻数もそれほど増やさないようにして、10巻くらいで完結させてます。紙だと、それなりの厚みが必要ですし、巻数は長いほどいいことになりますよね。電子だと完結記念のキャンペーンを打つタイミングも大切なので、そこそこの巻数のほうがいいわけです。
また作家さんたちに言っているのは「ツイッターやフェイスブックでわざわざ宣伝しなくてもいい」ということです。電子の場合、作家さんが自分のまわりに拡散したってそれほど売れるわけではないんです。電子書店でキャンペーンを展開して、そのバナーが目立つ位置に来るように工夫するほうがはるかに効率的です。紙の本の場合、サイン会やって、講演会やって、手売りしていく部分が大切だと考えられていますね。そのせいなのか、出版社の人が作家さんのフォロワー数を気にすると聞きますけど、ちょっと努力の方向が違うような気がします。
柳瀬が言っているのは、これまでの出版が扱ってきたのはコンテンツを詰めた出版物というモノであり、電子が扱うのはコンテンツそのもの、という実に単純なことだ。ところが、単純な区別ができないまま「紙から電子へ」と大騒ぎしているのが電子コミックの現状なのだ。紙は紙、電子は電子と区別した上で、それぞれの現在と未来を語らないことには、問題点も解決方法も見えてこない。
優良なコンテンツのストックこそ財産
柳瀬の言う「コンテンツのストック」という点で圧倒的優位に立っているのは既存の出版社だ。紙の出版がピンチと言われているが、出版社の編集者たちは意外に落ち着いている。企業体としての出版社にはまだ余裕があるからだ。それは、コンテンツという資産を持っていることからくる余裕だ。
さらに、新しい資産を生み出すノウハウを持っているのも出版社だ。出版社の資産でも、不動産は切り売りしていくといずれゼロになる。しかし、コンテンツは仮に全部売ってしまっても、新しく作り出すことができる。会社ごとコンテンツが売られても、新しいコンテンツを生み出すノウハウを持った編集者は新しい経営者にとっても金の卵を生むガチョウになりうる。
そこまでわかっていながら、売り方の部分で旧態から抜けられず、正しい手法に気が付いていないというのなら問題だ。
さらに、コンテンツを扱うという立場から、柳瀬は無料マンガアプリがひっぱる電子コミックのあり方にも疑問を投げかける。
柳瀬 僕は無料配信ではなく有料配信にこだわっています。作家さんが苦労して作り上げたものをこっちの都合で無料配信するのはいけないと思うんです。それに、広告収入や著作権ビジネスで収益を上げることを考えるよりも、作品を買ってもらうほうが確実だし、収益も上げやすいはずです。ビジネスとしての面白みもあります。僕はこの仕事を始める前に芸能系のブックキング仲介の仕事をしていて、大手のプロダクションとも仕事をしてかなりの儲けがありましたけど、やめました。右から左に動かすだけでお金になっても、面白みがないからです。
投稿作品などを集めて低コストでつくったものを、タダで配ってそこに貼りつけた広告で稼ぐというのは、タレントを右から左に動かして儲けるようなものです。効率的なのかもしれないけど面白くない。
——有料ということになると、読者を満足させる必要が出ますね。無料の暇つぶしとは違ってきます。
読者の満足は、むしろ当たり前ですよね。僕らは、いいコンテンツをたくさんストックしたいのです。それがビジネスにつながるのですから。編集者の存在は欠かせませんし、当然、作家さんへのギャラについても考えています。紙のように初刷部数にあわせた印税がない、というのは電子の一番のネックです。うちの場合は、保証印税みたいな形でお支払いすることもやっています。食べていける作家さんの裾野も広がっているし、作家を目指す人にとっても電子書籍はチャンスが大きい。今は、僕らのように小さい会社でも存在感を示せる面白い時期なんだと思います。
紙の出版社も電子書籍関係者も、ビジネスのあり方をよく理解しないまま、大きなパイを求めて動き始めて、行くべき方向を見失っている。一方で、リ・ポジションのような小さな会社は、自分たちの会社の収益モデルを堅実に考えている、小さいところほど収益モデルを見誤った時のリスクが大きいからだ。柳瀬の発言に私は未来の電子コミックの未来に光明が見えるように感じた。
電子コミック時代に生き残る小さな雑誌
では、紙の出版に目を向けてみよう。
「紙は終わりだ」と言われ続ける中で、「ひとり出版社」と呼ばれるような小規模な版元の元気がいい。立春の2月4日に世田谷区桜新町で小さな出版社による「ポトラ」というブックフェアが開催され、わたしも足を運んでみたが、大規模なブックフェアにはないような熱気で、何よりも展示されている一冊一冊の本の存在感に驚かされた。思わず手に取りたくなり、買って帰りたくなるのだ。「紙は終わりだ」というのはどこの国の話かと思うほどだ。
マンガの世界にも長年地道な活動を続けているひとり出版社がいくつもある。山上たつひこや宮谷一彦ら1970年代に活躍したマンガ家の作品の単行本化に取り組んでいるフリースタイル、三条友美や中川ホメオパシーらカルトなマンガ家の単行本化に取り組むおおかみ書房、今回取材した総合マンガ雑誌「キッチュ」もその一つだ。発行人兼編集人の呉ジンカンは台湾出身。日本に留学して京都精華大学に学び、現在は京都嵯峨美術大学で教壇に立つという経歴の持ち主。日本、中国、韓国、台湾在住者を対象として京都から新人マンガ家のデビューを支援する「京都国際漫画賞」の審査員を務めるほか、日台のマンガ交流にも積極的に関わっている。
そんな呉が2009年から年1冊ペースで刊行しているのが「キッチュ」だ。いままでの執筆陣はベテランの山田章博やひさうちみちお、斎藤なずな、さそうあきらから、ムライ、モサパサ、スケラッコら若手まで幅広い。題字は、時代劇マンガの巨匠・平田弘史が揮毫している。小説やコラム、評論にも力を入れていて、特集では『ガロ』や台湾マンガも取り上げている。また、7号からはワイズ出版創刊第一号として、同社を通して書店流通にも載せた(2018年春にはワイズ出版第二号を発売する予定)。めざしているのは創作と娯楽の狭間。

「キッチュ」創刊第二号。
それにしても、印刷や流通にコストのかかる紙の雑誌を個人で出し続けるこだわりはどこからきているのだろうか?
呉 僕自身は電子が嫌だとは思いませんし、紙へのこだわりが強いわけでもありません。掲載しているマンガは「キッチュ」のポータルサイトで画像入りで紹介したりしています。こだわりはないのですけど、あえて言えば、人と会ったときに「こういうことをやってます」と自己紹介がわりに出すのに便利、ということがあるかもしれません。電子だとサイトにアクセスしてもらわないといけませんが、紙の雑誌なら手渡すことができます。原稿をお願いするときも、形のあるものを見てもらえるので説明が早いし、マンガ家さんにとっては紙のほうがモチベーションが上がる、という利点もあります。多様性があるという意味ではいろんなコンテンツが一冊にまとまっているのもいいですね。電子だといろいろ入っていても読むのはそれぞれバラバラですよね。
やはり、紙の特性は「形のあるモノ」ということなのだ。先に紹介したように、アンケートを取った学生たちに紙のマンガが好きな理由を聞くと、「形があって置いておける」という答えが大半を占める。
「やがて紙の本はレガシーなものになって、装丁や紙に凝った高価なものだけが残る」という人もいる。わたしも一時期はそう考えていたことがあったが、考えが変わった。読者が紙の本に求めているのは、骨董品やコレクションとしての価値ではない。中身があって形があることに意味がある。つまり紙であることが価値なのだ。雑多さが求められる雑誌はなおさらだろう。
呉の言うのも柳瀬と同じことだ。紙と電子では違う。どちらがエライのでもなく、どちらもいいところがあり、足りないところもある。
呉 台湾は、日本のマンガが早くから入ってきて、人気もとても高いのですけど、マーケットが狭いので、台湾のマンガ家の中でマンガだけで食べている人はほとんどいません。その点、日本には紙のマンガの大きな市場があって、そこに電子まで登場した。うらやましい、というか、そんな日本にいられるのがたのしい。
呉が言うとおり、われわれが考えるべきは、紙をいかにして電子に移行させるかではなく、それぞれの持つ特性を知りながら、それぞれの特性の中でマンガというコンテンツをより面白い方向に育てるか、ということなのだ。創作と娯楽の狭間でもがきながら……。