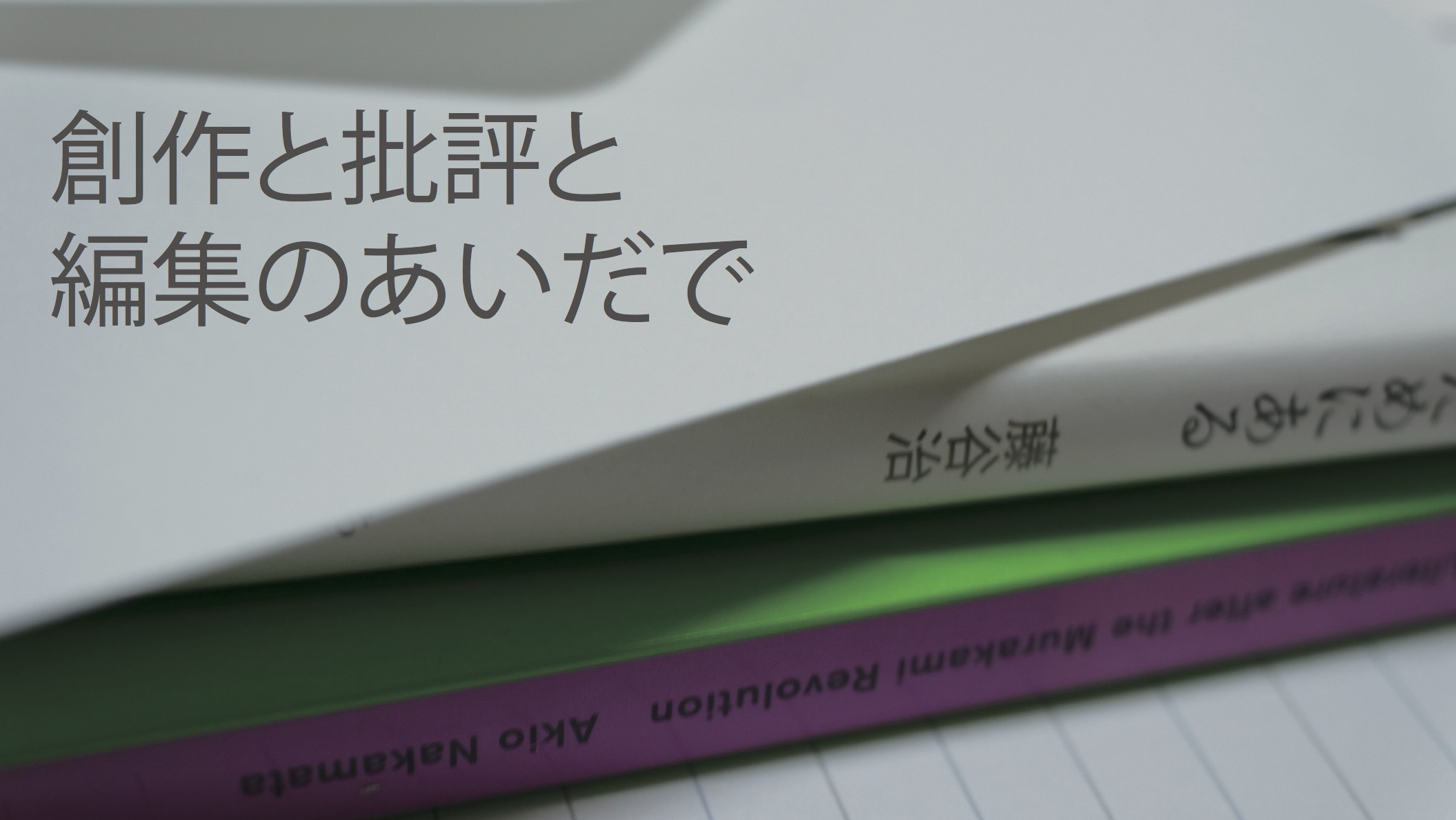第5信(仲俣暁生から藤谷治へ)
藤谷治様
先日はある文芸誌の新人賞パーティーで、久しぶりにお目にかかれて楽しかったです。ふだんああいう場に出向くことは少ないのですが、「小説家」や「文芸評論家」が抽象的な存在ではなく、姿かたちのある具体的な存在、つまり生きている人間なのだと確認できるのはよいことだなと、文学関係の集まりに行くたびに思います。
しかし文芸や文壇をめぐる話題は、このところすっかり気が滅入るものばかりなので、もう一つの話題、そしてこの往復書簡で僕が藤谷さんと一緒に考えたいと思っている話題である〈編集〉のほうに、少し流れを変えさせてください。
* * *
先の返信で藤谷さんは、僕のことを「編集者」と思ったことはなく、「文芸批評家」だと思っていたと書いてくれました。それに対して僕は、自分が文芸に向き合うときは「文芸批評家」ではなく、「文芸評論家」でありたいと書きました。藤谷さんはさらに応えて、自分も「作家」ではなく「小説家」と呼ばれたいと書いてくれた。これはとても面白いやりとりでした。
編集の話に行く前に、なぜ自分が「批評家」と呼ばれたくないのか、ということから説明します。
これまで自分が文学について書いたものに批評性がないとは思わないのですが、僕は小説を〈批評〉という鋭い刃で裁断するより、〈評論〉という古めかしい作法で向き合いたい気持ちが強いのです。もちろん小説を論じることを通じて現代という時代について語りたいことはあり、そうした書き物の場合には〈同時代批評〉とでも言えるのでしょうが、個々の作品に愚直に向き合うとき、それは〈批評〉である前に、まず〈評論〉であるべきだろうと思うのです。
あいにく僕たちは、あたかも批評が小説より優勢であるように思え、批評家が小説家より格好よいとさえ思えた時代に青年時代を過ごしました。切れ味の鋭い批評の文章に思わず快哉を叫んだことも一度ならずありますが、その結果として、いくら批評が読まれても、それが対象としている実作は読まれない、という本末転倒なことさえ起きたように思います。すぐれた批評は往々にして論じる対象を超えてしまいますが、その弊害も大きかったのではないでしょうか。
僕が自分を「批評家」というよりは「評論家」と規定したいのは、実作家よりも一段低いところから作品を読み解きたい、ということの宣言でもあるのですが、はたから見ればどうでもいい、たんなる言葉の好みの問題かもしれません。
しかしここで、優れた「批評家」(この場合は「評論家」ではなく)は、同時に優れた「編集者」でもあった事実を思い出さないわけにはいきません。過去において多くの批評家や思想家は、自身が寄って立つためのメディア――多くの場合は雑誌――を主宰し編集してきました。
鶴見俊輔の「思想の科学」、吉本隆明の「試行」、柄谷行人の「季刊思潮」や「批評空間」、東浩紀の「思想地図」や「ゲンロン」などがすぐに思い浮かびますが、いまちょうど読んでいる長谷川郁夫の『編集者・漱石』(新潮社)という本には、夏目漱石と正岡子規、そして雑誌「ホトトギス」をめぐるこんなくだりがあり、目を見開かされました。
漱石が最初に書いた散文作品といえる文章は、渡英中の明治34年(1901年)4月にロンドンから親友・正岡子規に宛てて書いた三通の長い手紙をまとめた「倫敦消息」です。同年5月の「ホトトギス」第4巻8号に掲載されたこの文章が成立する過程について、長谷川郁夫はこう書いています。
私なりの理解でいえば、漱石の最初の創作は、子規と虚子、そして漱石、きわめて私的な、三人の編集感覚のトライアングル――読む人(ここでは子規)、書く人、作る人――のなかで成立したのである。
友人の柳原極堂が松山で創刊した「ホトトギス」という小さな俳句雑誌を主導しつづけた正岡子規こそ、すぐれた実作家であると同時に「編集者」であり「批評家」でもあった人物です。その子規に宛てて書いた私的な手紙が、東京に拠点を移した「ホトトギス」の編集を子規から任された高浜虚子の手によって公的な誌面に掲載され、それが漱石の散文作家としての最初の「作品」になったと長谷川氏は言うのです。
この浩瀚な評伝のなかで、長谷川氏は編集(者)が果たす触媒的な機能についてたびたび語っているのですが、夏目漱石という「作家(小説家)」の誕生の瞬間を語るこのくだりで、その秘訣を「読む人、書く人、作る人」の編集感覚のトライアングルにあった、としているのが僕にはとても興味深く感じられます。
僕は文芸作品の誕生に立ち会ったことはなく、雑誌の編集長をした経験にも乏しいのですが、「マガジン航」というこの小さなメディアを、これまでなんとか9年間続けてきました。「ホトトギス」のようなリトルマガジンにさえ遥かに及ばないミニメディアですが、それでも「読む人、書く人、作る人」のトライアングル、つまり各々が役割を演じ、ときには交替しながら、一つのテキストが「作品」となっていく課程の醍醐味をなんどか味わいました(ウェブの場合、物としての姿形を「作る人」が不在なのは残念ですが)。
もちろん、そうした感覚はすべての編集者、そして編集者とともに「作品」を作り出したことのある作家たちが少なからず経験してきたことのはずです。
でもここでまた、冒頭の気の重い話題に戻らなければなりません。いまは本や雑誌が売れない時代です。そんな時代に、はじめから売れないことがわかっている本や雑誌を「作る」とき、そのモチベーションはどこに置いたらよいのか。商業出版社のなかにも、経済的な環境の悪化に抗いつつ、長谷川氏がいささかロマンチックに描いた「トライアングル」の運動を生み出すために奮闘している編集者がいることは想像できます。
でも、と僕は思うのです。「批評家」と自称するかどうかはともかく、いまは少しでも時代を動かす「運動体」をつくりたいなら、自身でメディアを立ち上げ、それを回していくことが必要なのではないか。ここ数年、勤めていた出版社から独立して「ひとり出版社」を立ち上げる仲間が増えており、雑誌にかぎらず、そうした出版社もまた「メディア」なのだと僕は思います。
そうした営みのなかでこそ、新しい文学なり、同時代に対する正確な批評が生まれるのではないか。あるいは紙の本や雑誌でなくてもいい。ウェブでも電子雑誌でもいいけれど、大切なのはとにかく、一人きりでやらないことです(「ひとり出版社」も実際は多くの人との共同作業のもとで本を出しています)。
ネット上にあふれる「ひとり語り」の言葉は、その根幹に長谷川氏のいうような「トライアングル」の基底を欠いているからこそ、どこまでも上滑りするだけで、人の心を深いところで撃つことができない。そう思えてなりません。
この往復書簡は「ダイアログ」にすぎず、理想的なトライアングルには一つ要素が足りないのですが、もしかしたらこの文章を読んでくれている数少ない読者が、その役を果たしてくれるのかもしれません。僕は小説の「編集」はできませんが、こうやって「小説家」である藤谷さんと公開の場で往復書簡を交わすことで、読者を交えた小さなトライアングルを回しているつもりなのです。
編集についてはもっと書きたいことがあるのですが、これでもかなり長い手紙になってしまいました。いささか中途半端ではありますが、いったんここでキーを打つ手を止めることにします。