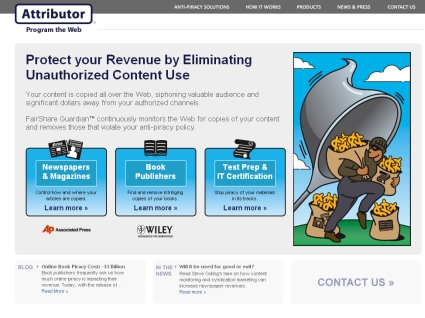1. ユーザーが何を読んでるか監視できる?
・Google Books: Yes ウェブサイト上で閲覧した特定の本やページを記録する。
・Amazon Kindle: Yes 記録する情報の正確なパラメータは不明だが、読んだ本やページを含む。
・B&N Nook: 不明
・Sony Reader: No 機器上のコンテンツに関する情報を記録しない。
・FBReader: No ユーザーから情報を収集することはない。
2. 機器は提携する電子書籍ストアから購入した本しか互換性がない?
・Google Books: N/A Google Booksは閲覧機器ではないが、DRM保護されてないPDFやEPUB形式のパブリックドメインの本をダウンロードできる。それを除けば、Googleのウェブインタフェースを通じてオンラインで読まなくてはならない。
・Amazon Kindle: Yes AmazonのプロプライエタリなAZW、そしてDRM保護されてないTXT、MOBI、PRC形式のファイルがKindleと直接互換性がある。新型のKindleはネイティブなPDFサポートがある。
・B&N Nook: No 自分のところ以外のソースから取得したEPUBやPUBといった一般的な電子書籍フォーマットをサポートしている。しかし、それらの形式はNookの多くの機能をサポートしていない。AZWはサポートしていない。
・Sony Reader: No DRM保護されてないフォーマットに加え、EPUB(Adobe)、PDF(Adobe)、BBeB(PRS)を含む複数のDRM保護された形式をサポートする。AZWはサポートしていない。
・FBReader: No EPUB、FB2、MOBI、PRC、OEBなどのオープンでDRM保護されない幅広い形式をサポートする。PDFやAZWはサポートしていない。
3. 書籍の検索履歴を記録できる?
・Google Books: Yes すべての検索データをIPアドレスとともに記録。ログインしていれば検索記録はユーザのGoogleアカウントと関連付けもする。ログインしてなければ検索記録とユーザアカウントと関連付けない。
・Amazon Kindle: Yes 機器上で閲覧、検索した製品情報を記録し、Amazonアカウントと関連付ける。書籍内を検索するにはクレジットカード情報が登録されたアカウントにログインする必要がある。
・B&N Nook: Yes Nook上の検索が記録されるかプライバシーポリシーが不明確だが、通常B&Nはウェブサイト上での検索や閲覧ページの情報を記録している。ログインしていればユーザアカウントと書籍検索を関連付けるかB&Nは明らかにしていない。
・Sony Reader: Yes プライバシーポリシーが不明確だが、消費者がReader Storeを利用したら、ソニーはIPアドレスやメッセージ情報を記録し、データをReader Storeアカウントに関連付け可能(閲覧にはログイン必須)。
・FBReader: No 書籍検索に関するデータを収集しない。
4. 書籍の購入履歴を記録できる?
・Google Books: Yes 書籍の購入履歴はすべてGoogleアカウントに関連付けられる。
・Amazon Kindle: Yes Amazonは利用者の購買履歴を収集する。
・B&N Nook: Yes B&N の電子書籍ストアからの購入に関するプライバシーポリシーが不明確。B&Nは、利用者がメンバー向けロイヤリティプログラムに登録していれば、購入履歴と関連付けると言っているが、購入履歴がB&Nのオンラインアカウントと関連付けられるかどうかについては何も言ってない。B&N は機器上で読んだ本を記録しない。
・Sony Reader: Yes プライバシーポリシーが不明確だが、本を買うのにログインしなければならず、またソニーはライセンスを理由に利用者に識別クッキーを割り当てるので、ソニーはReader Storeから購入を記録していると思われる。ソニーは他から取得した本を機器上で読む場合には記録しない。
・FBReader: No 書籍購入に関するデータを収集しない。
5. アグリゲートされない形態で収集された情報を誰と共有できる?
・Google Books: 法執行機関、訴訟当事者、Google自身の製品。
・Amazon Kindle: 法執行機関、訴訟当事者、Amazon自身の製品。
・B&N Nook: B&Nの電子書籍ストアを通じて収集した情報に関して:法執行機関、訴訟当事者、B&N自身の製品。
・Sony Reader: Reader Storeを通じて収集した情報に関して:法執行機関、訴訟当事者、ソニー自身の製品、Reader StoreのパートナーであるBorders。
・FBReader: No 何の情報も収集しない。
6. 消費者の同意なしにその企業以外と情報を共有できる?
・Google Books: No 利用者はGoogle以外と個人情報が共有されるのをオプトインしなければならない。
・Amazon Kindle: Yes 利用者は特定の宣伝、マーケティング用途に関してのみ情報の利用をオプトアウトできる。
・B&N Nook: Yes 利用者は特定の宣伝、マーケティング用途に関し、またサードパーティによる情報の解析利用に関してのみ情報の利用をオプトアウトできる。
・Sony Reader:Yes Reader Storeを通じて収集した情報に関して:利用者は特定の宣伝、マーケティング用途に関してのみ(オプトアウトかオプトインの原則に従い)情報の共有を拒否できる。Reader Storeを運営するBordersとの追加的な情報共有をオプトアウトするには、Bordersに直接コンタクトを取らないといけない。
・FBReader: No 何の情報も収集しない。
7. 消費者がその情報にアクセス、修正、削除するメカニズムを欠いている?
・Google Books: No 消費者は書籍の題名を削除したり、アカウントとの関連付けをなくすことができるが、それを読む権利を失う可能性がある。利用者は検索履歴を削除できる。
・Amazon: Kindle ある程度 顧客はアカウントプロファイルにアクセスして情報を更新できるが、Amazonは修正する前の記録を保持する可能性がある。検索や購入の履歴にアクセスしたり削除する権利はない。
・B&N: Nook ある程度 利用者はいつでもアカウントプロフィールにある情報にアクセス、修正、変更できる。検索や購入の履歴にアクセスしたり削除する権利はない。
・Sony Reader ある程度 Reader Storeを通じて収集した情報に関して:利用者は特定の個人情報の更新要求を送信でき、妥当な時間でそれが実行される。検索や購入の履歴にアクセスしたり削除する権利はない。
・FBReader: No 何の情報も収集しない。
(日本語訳:yomoyomo)