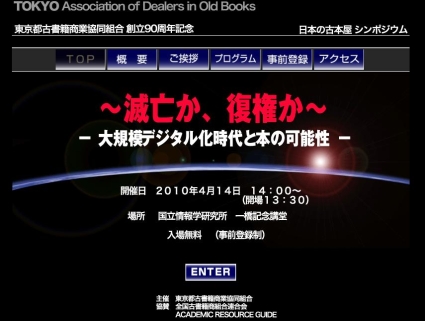落書きのためのスペースは教科書の欄外余白だった。本文ごとに、つまりどのページにも、左右そして上下に、ここに落書きをしなさいと、僕を誘ってやまない余白があった。上下の余白は横長のスペース、そして左右のスペースは縦長であり、幅は狭いけれども縦につながり横に広がり、四方をぐるっと取り囲んでもいる余白は、まさに落書きのためのものだった。表紙と裏表紙のそれぞれ内側は、腕の見せどころの入魂のタブローのための、特別なスペースだった。
そして落書きのための時間は、授業中がもっとも好ましかった。それ以外の時間にどこへ落書きしようとも、なぜかあまり面白くなかった、という体感が記憶の底にかすかにある。授業中の生徒がなにをしているのか、教壇の先生からはよく見えた。前の席の女性の背中に隠れて、教科書の余白に落書きに余念がないという至福の時間に、「おい、カタオカ、なにしてるんだ」と、先生の声が終止符を打っていた。
教科書一冊全ページの余白に連続漫画を、授業中の時間を使って描き上げたのは、一九五三年のことだった。手塚治虫の漫画を古書店でかたっぱしから手にいれ、夢中で読んでいたことのなかから、僕の余白漫画は生まれてきた。手塚の何年か前、『不思議な国のプッチャー』という、最初のアプローチがあるのだが。教科書まるごと一冊の余白に描いた漫画は、その余白をすべて切り取り、一冊のノートに順番に貼りつけた。いまの僕の日常語で言うなら、本にまとめた、ということだ。縦のつながりと横のつながりが交互する、いま思えば斬新な表現形態の傑作だった。タイトルは『おい、カタオカ』とした。
この投稿の続きを読む »