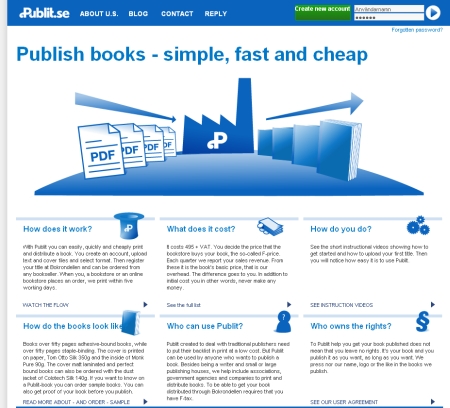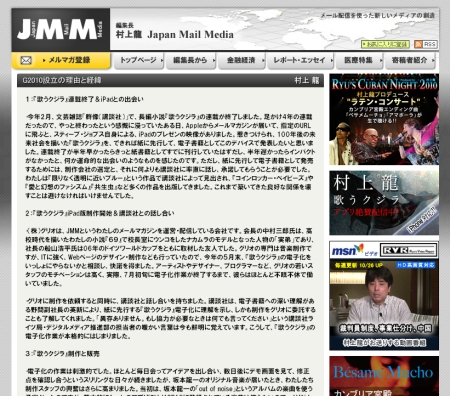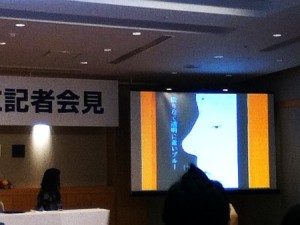それでも、いざそう考えてふり返って見ると、森、アドルノ、藤田といった人たちの批判もふくめて、急激な成長がみずからの終りを準備し、この黄金時代はいずれ崩れるしかないんじゃないかという予感が、一九五〇年前後から、けっこう多くの人のうちに生じはじめていたらしいことがわかってくる。
たとえば「いまの大学生は本を読まない」と、よく大人たちが嘆いていますよね。いちおう、もっともな嘆きといっていい。私も二〇〇一年に、ある小さな大学でおしえはじめて、あまりにも学生たちが本を読んでいないことを知って愕然としました。
それで最初の年、授業で五十人ほどの学生にアンケートをとってみた。さすがに一年に一冊も読まないという者はいなかったが、ひと月に五冊読むという学生もきわめてすくなかつた。たいていは月に一冊か二冊ていど。しかもライトノベルとか、そういうのが多い。他大学の教師たちの話をきいても、東大や早大のような有名校もふくめて、ていどの差はあれ、学生の多くがまともに本を読んでいないというのは事実なんじゃないかな。
ただ、事実なんだけれども、学生が本を読まなくなったと嘆く大人たちは、教師とか親とか勤め先の上司とか、おもに四十代後半、五十代から上の人たちですよね。そしてどうやらかれらには、私はちがう、われわれの世代はもっと沢山の本を真剣に読んでいたぞ、というかつての読書体験への自負心みたいなものがあり、それを基準にいまの大学生を批判しているらしい。でも、これ本当なのかな。本を読まない学生もですが、むしろ私はそちらのほうにちょっとひっかかるものを感じるんです。
じぶんのことを考えても、たしかにいまの大学生にくらべれば、かつての若者や学生はよく本を読んでいたと思う。でもね、そう自分で思い込んでいる大人連中にしたところで、じつは若いころ、「いまの若者は本を読まない」と、上の世代からさんざんバカにされたり嫌みをいわれたりしていたにちがいないんです。みなさん、そのことをすっかり忘れているんじゃないか。
私は忘れていません。たとえば、かつて中村草田男という高名な俳人がいた。一九〇一年、明治四十四年生まれ。松山の人。松山高等学校から東京帝大ドイツ文学科。だから、モロ旧制高校時代の人ですね。大正教養主義の流れにまっすぐ立っていた人――。
この中村草田男が一九六五年に「学生と読書」という随筆を書いている。私が大学をでた二年後です。ところどころ飛ばして読んでみます。
現代の生徒および学生──小学生から大学生にいたる各年齢層──が、戦前の時代に比較すれば、共通してほとんどといっていいくらいに、当面の課題範囲以外の読書に自発的につとめることが無くなりつつある。(略)電車内に席を占めている小学生は、ただその間の時間つぶしのためだけにはなはだニヒリスティックな無表情さで漫画本の頁を繰っている。(略)大学生は、これも同様に電車内での空白時間の大部分をチュウインガムを噛むことによってまぎらわせている。その時間内の彼らの頭脳中には意識の流れというような思惟の流れは存在していないのである。完全に空白な時間なのである。
ちょっとおどろくでしょう。いまとおなじなんです。この「学生と読書」を書いたとき、草田男は成蹊大学の先生だった。で、いまの大学教師が「最近の学生は本を読まなくなった」というのとおなじことを、半世紀まえに、おなじ口調でいっていた。
なぜ、かれらは本を読まなくなったのか、原因は三つある、と草田男先生はおっしゃいます。この三つの原因もいまとおなじ――。
(原因1)占領下の国字国語改革――それによって大学生の「日本語に対する関心と知識」が低下し、いまや「彼らの読書力そのものの貧弱は形容を絶したものがある」
(原因2)進学地獄――幼稚園入園のための予備校まで出現し、「日本の若いジェネレーションは少年青年時代を通じて」「徒に幅広くなった進学のための解説的知識を機械的に受けとることだけに追い立てられつづけて」「それ以外の範囲の一般読書のための余暇と余裕を持つことを許されていない」
(原因3)視聴覚文化の氾濫――「テレビ・映画の前に身を置いてさえいれば、割り切れた明瞭きわまる『形象』がつぎつぎに後を追って登場してきて、画面的説明を最後まで遂行してくれる」のに慣れて、「割り切れていない無形の、しかし生きたる有機体的なミクロコスモスの中へ突入すべく、われわれの方から全力をあげて一種の格闘をいどんでいかなければならない」「読書という営み」に、ついていけなくなってしまった。
とうてい五十年以上もまえの発言とは思えない。
一番目の日本語能力と読書力の低下。いまはさらに惨憺たる状態になっています。でも基本的にはおなじ。おかげで日本語ブームがくりかえし起こり、漢字検定などというわけのわからんものがはやる。
二番目の進学地獄、受験戦争についても同様。おなじ現象がもっと息苦しく脅迫的なものになっただけ。
三番目の視聴覚文化の氾濫。テレビや映画が持つ力はいちじるしく低下したが、かわりにインターネットや携帯電話に代表される生活環境そのもののデジタル化、オーディオ・ヴィジュアル化が一気にすすんだ。じぶんのまわりに途切れ目なく押し寄せてくる強烈な「形象」によって、こちらから「全力をあげて一種の格闘をいどんで」いく気力や能力がいまにも失われそうになっている。おなじだと思います。
ちがうのは、草田男先生の時代は高度経済成長が開始されてまもない時期だったということですね。若者をターゲットとする商品化社会はまだ完成にはほど遠く、サービス産業も素朴で幼稚な段階にあった。そのぶん、いまよりものんびりした面があった。とはいえ、当時の大人が新しく登場した若い世代、とくに「本を読まない大学生」に対していだく不安は、かなりのものだったろうと思います。とつぜん、空っぽ頭の、わけのわからん連中がでてきたぞ、という印象があったにちがいない。
では、一九六五年という時期に中村草田男は一体だれを批判していたのか。ズバリといってしまえば、この私なんです。
この文章を当時、私は読んでいません。でも、もし読んだとすれば、ここで批判されている「現代の生徒や学生」とはオレのことだときっと思ったでしょうね。なるほど若い私はかなりの量の本を読んでいた。それは事実ですが、私の読書にはもう、年長の人びとの読書をささえてきた精神の集中力、モラル・バックボーン、草田男先生のいうような「格闘」の要素はめだって乏しくなっていた。その自覚はありました。それに、そのころ私は吉祥寺の成蹊大学のすぐそばに下宿していましたからね。中央線か井の頭線の車中で実際に草田男先生とすれちがっていた可能性だってなきにしもあらずなんです。
中村草田男の批判からわかるのは、「最近の学生は本を読まない」という大人たちの嘆きが、いまとおなじ内容、おなじ強度で、すでに六〇年代の日本にも存在していたということです。しかも六〇年代だけ、草田男先生だけのことではない。おなじ嘆きが、戦後、読書のスタイルや環境が変わるたびに繰りかえし表明されていた。
ここで草田男を嘆かせている「はなはだニヒリスティックな無表情さで漫画本の頁を繰っている」小学生たちは数年後に大学生になります。電車のなかでマンガ週刊誌に読みふける大学生、つまり団塊世代の登場です。かれらより十歳ほど年長にすぎない私ですら、最初にその現場を目撃したときは度肝をぬかれた。しかも電車だけじゃないんです。喫茶店でデートしている男女が、向かいあって、ただ黙々とマンガを読んでいる。おまえら、なんのためにデートしてるんだよ、と見ていてイライラしました。
そして、つぎの変化の時がその十数年後、一九八〇年代です。いまとおなじく、あの当時も、出版界周辺では「活字文化があぶない!」という危機意識が急につよくなっていた。ただし統計で見ると、このころ本の売れ行きがとくに急激に落ちたわけではない。その逆です。年間発行点数も総発行部数も実売金額も、むしろ安定して増えつづけていた。それなのに、あの時期、なぜあんなに声高に「活字の危機」が叫ばれていたのか……。
よくわからないんですが、たとえば、それまではまあまあよく売れていた堅めの本がしだいに売りにくくなった。どうやら、この手の本の主要な購買層だった大学生や若い人たちの関心が、べつの方向へシフトしはじめているらしい。私が身をおいていた広い意味での人文書の世界に、そういう実感がじわじわと生じていたのは事実です。若い連中がかたい本を敬遠し、集中力ぬきで読める、肩のこらない、やわらかい本にしか関心を示さなくなった。当時はやりの四文字語でいえば、「重厚長大」から「軽薄短小」への変化です。
そういえば「雑高書低」ということばもあったな。七〇年代の終りから八〇年代はじめにかけて、年間の売上げ高で戦後はじめて雑誌が書籍を抜き去る。出版産業の中心が書籍から雑誌へと足早に移ってゆく。そのはじまり――。
しかもこのころになると、雑誌自体がすでに総合雑誌や文芸雑誌のような伝統的な活字中心の「読む雑誌」ではなく、七〇年代のマガジンハウスの突進にひっぱられて、いまあるような「見る雑誌」、大量の広告がはいったカラーの大型ビジュアル誌に変貌していましたからね。こうしたビジュアル誌のターゲットは、いうまでもなく若者、学生、若い女性たちです。読むかわりに見る。団塊世代のマンガへの熱中にはじまる若者の「活字ばなれ」(これも当時の流行語)が、この先もますます進んでいくのではないか。「活字文化があぶない!」という出版人の悲鳴には、ひとつにはそういう予感がふくまれていたんだと思います。
それやこれや、ようするに若者が大人によって「本を読まない」と批判されるのは、なにもいまにかぎったことじゃないんです。学生についていえば、いつの時代でも、その時々の大学生や高校生は、それ以前の世代にくらべると覿面に本を読まなくなったと感じられていた。
しかも戦後だけの傾向でもない。最近たまたま知った例でいえば、すでに昭和十年、一九三五年に、英文学者の平田禿木が「趣味としての読書」というエッセイで「今日の若い人達の間に如何にして趣味としての読書が閑却されてゐるか」について縷々語っています。中村草田男のいう「戦前の時代」の学生たち、むさくるしい寮の一室で内外の古典や新しい海外思想に懸命に食いついていたはずの教養主義全盛期の旧制高校生たちでさえ、じつは大人からはそう見られていたんです。この文章はいまは「青空文庫」で読めます。青空文庫、すなわち日本で最初のオンライン電子公共図書館。私は iPhone から接続して読んだ。なんだか皮肉な気がしないでもない。
こう見てくると、二十世紀という「本の黄金時代」が、同時に、豊富化ゆえの読書習慣の衰退へのおそれが絶えない時代でもあったということがわかるんじゃないですか。勢いにのって階段を上ってゆくと、上るはしから足もとで階段が崩れてゆく。そういうイメージ――。
いまの若い連中が本を読まないのは事実です。でもかれらは、なにもかれらだけで本を読まないんじゃない。かれらを批判する大人といっしょに本を読まなくなっているんです。大人たちが「本を読まない」と嘆く若者もまもなく大人になり、あとにつづく若者たちの活字ばなれを嘆きはじめる。こうして「まえの時代にくらべて本を読まない人たち」の層が順々にかさなってゆき、ふと気がつくと、若者だけでなく社会を構成する人間が全体として本を読まなくなっていた。だから「狼が来た」なんですよ。「狼が来たぞ!」という空しい叫びを何度も繰りかえすうちに、とうとう白い牙をむきだした本物の狼が出現してしまった。
その牙が私たちの目に最初にはっきり見えたのが、日本でいえば一九九七年に、こんどこそ本物の出版危機がはじまったときです。とつぜん本の売れ行きが落ち、二十一世紀になったいまも、その低落のいきおいが止めどなくつづいている。本の力が黄金時代の水準をとりもどすことは、世界的に見ても、もう不可能と考えるしかないだろう。そして奇しくも、といっていいと思いますが、その本と読書のどんづまり状況に電子化がピタリと重なってきた。そういうことじゃないかと思うんです。
※本稿は国書刊行会から今月刊行される、津野海太郎氏の新著『電子本をバカにするなかれ』のために書き下ろされた文章「書物史の第三の革命~電子本が勝って紙の本が負けるのか?」の抜粋です。