はじめに
今村明恒「火山の話」(『週刊ミルクティー*』第3巻第29号所収)を紹介・掲載してもらうべく、「マガジン航」あてにメールを出したところ、さっそく編集人の仲俣さんから「なるべく、当事者の言葉で語っていただくことにしている」「たんなる情報の掲載は極力しない」という返事がもどってきた。「単発のコンテンツの紹介はしずらい」、「サイトを拝見するかぎり、全体像がよくわからない」ともある。
ひとつひとつ反論したい衝動にかられる。見当ちがいの依頼に見えるかもしれないが、考えがあってのことなんですよとも言い返したい。……が同時に、「全体像がよくわからない」という感想は率直な意見だろうとも思い直す。サイトを訪れた多くの人たちが同意見なのかもしれない。作っている作品や内容には自信がある。にもかかわらずページのカウンタや販売成績が伸び悩んでいる原因は、作り手のひとりよがりの可能性が高い。作ることに集中しすぎて、結果、読者をおきざりのまま単独暴走していなかったか。制作に追われて、周囲を見まわしたりかえりみる余裕のなかったことも事実。
サイトの「ページ一覧」に並んでいる、これまで編集してきたすべてのタイトルこそがメッセージであり、全体像そのものであるという言いかたもできる。あるいは、そう簡単に「わかったつもり」になられてもうれしくないという思いもある。
メール末尾には「『週刊ミルクティー』の活動について何かお書きになったものなどがあるようでしたら拝見します」ともある。しいてあげるならば、スタート時に記した「T-Timeマガジン『週刊ミルクティー*』創刊」というページがある。以来、まとまったものはとくに書いてない。今回お題をいただいたのは、これまでを振り返ってみるいいきっかけなのかもしれない。そう思い直して、苦手な自己言及をしてみることにする。
T-Timeマガジン『週刊ミルクティー*』とは
個人で発行している電子本雑誌です。2008年7月に創刊して、現在通算130号ほどになります。青空文庫にて公開(もしくは公開前)のパブリックドメイン作品を、T-Time をもちいて復刻出版しています。毎週土曜の発行で一冊200円(税込。初期の作品のみ210円)、月末最終号は無料。特色として、(1) JIS X 0213 の ttz 形式を採用していること、(2) 旧字旧かなのオリジナルと現代表記におきかえたテキストを同時収録していること、の二点があげられます。
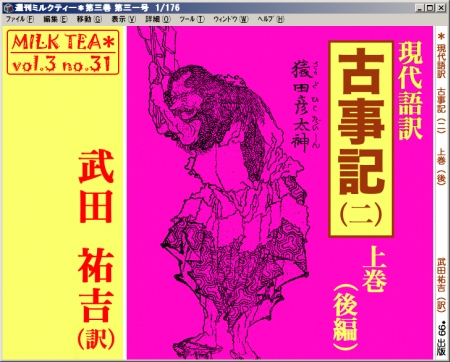
週刊ミルクティー*31号。通常号は200円だが、これは月末号なので無料で読める。
周知のように青空文庫では、長らく校正待ちのまま未公開の作品が少なくありません。たとえば、坪井正五郎「コロボックル風俗考」のような旧字旧かな・変体がなの作品も長いあいだ校正待ちの状態でした。著者没後50年を経たパブリックドメイン作品にはよくあることで、入力・校正は、底本に現代表記版を選択するほうがはかどります。結果、メジャーな作家の登録が進むいっぽうで、作業難易度の高い古い本が敬遠され、その傾向はジャンルのかたより(作品の多くが近代文学であること)にも現われています。
一工作員としてそうした青空文庫の弱みを感じていたころ、喜田貞吉『六十年の回顧』「個人雑誌の発行」という文章をたまたま目にしました。喜田貞吉は徳島県出身の歴史学・考古学者で、大正から昭和初期に東北地方を研究フィールドとしていた時期があります。山形や新庄や庄内にも訪れており、蝦夷や城柵跡・遺物・渡来民族などに関する論考があります。東北出身ではないため、ひいき目を持たない冷めた観察が期待できる。同じく、九州や四国といった周辺地域への広い視野も持っている。そういうわけで喜田に注目しています。
南北朝正閏問題の結果として、休職となった後の自分の生活は、実に気楽なるものであった。(略)わずかばかりの時間を教壇に立つ以外は全く自由で、実地について各地の古墳墓や、その他の遺物・遺蹟を、盛んに見てまわるようになったのもこれからだ。(略)実は自分は同人諸氏とともに、明治三十二年以来雑誌『歴史地理』を経営している。それで身体が閑になった大正元年以来は、ことに盛んに同誌の誌面を塞ぎ、それでも間に合わずしてしばしば他の諸雑誌にも御厄介になったものだった。しかしそれでは同人雑誌なるはずの『歴史地理』が、喜田個人の機関雑誌ででもあるかのごとき世評もあって、熱心に編輯その他のことに尽力せらるる同人諸氏に対して、まことに申訳がない。(略)ついに個人雑誌として、『民族と歴史』を発行することにしたのである。
君〔内田銀蔵〕は余が無遠慮にも、未熟の学説を常に雑誌上に公にするのをもって、余のために取らずとなし、「喜田さん、雑誌上の発表もあながち悪いとは申しませんが、なるべく推敲を重ねて、権威ある著書としてお出しになってはいかがです」と。これに対して余は常に、君の好意を謝しながらも、なおこれに従うの意志がなかった。「私に研究的態度を継続する元気の存する間は、私の学説は日進月歩で、逐次に訂正増補を加えて行かねばならぬ。なまじ著書の形をもって発表して、ためにみずから欺き、後進を誤るのは私の忍びないところです。それにはどうしても、漸次改訂を加うるの便宜多き、雑誌上の発表がよいと思います」と。
引用はともに『喜田貞吉著作集 第一四巻』(平凡社、1982.11)より。
これを読んだのが2008年5月。これが直接のきっかけとなって、“パブリックドメインの個人雑誌発行”というアイデアが生まれることになります。喜田貞吉もまた「小さなメディアの必要」を感じて個人雑誌を発行した、インデペンデント・パブリッシャーの一人であったわけです。
今村明恒「火山の話」について
「青空文庫にはジャンルのかたよりがある」と書きました。これは、NDC 分類「分野別リスト」設置活動をとおして痛感しました(青空文庫 分野別リストを参照。aozora blog: ジャンル別は便利!)。「インターネットの電子図書館」を標榜しておきながらバラエティに厚みがない。おどろくほど児童向けの本が少ないこともわかってしまった。
そこで個人雑誌『週刊ミルクティー*』の柱の一つとして児童向け図書、とりわけ古典と科学書をあつかうことにしました。和田万吉「竹取物語」、浜田青陵『博物館』、石川千代松「生物の歴史」、折口信夫「歌の話」、池田亀鑑『堤中納言物語』、山本一清「星と空の話」……そして最新が今村明恒「火山の話」です。これらの底本は、昭和初期に出版社アルスが「日本児童文庫」というシリーズで刊行したものと、戦後に至文堂が「物語日本文学」として刊行したシリーズです。
執筆陣の顔ぶれに驚かれることと思います。みな、その分野の巨人です。読むと手をぬいていないことが伝わってきます。推するに彼らは、その分野の研究を深めようとすれば自分一人の力ではおのずと限界のあることに気がついていたはずです。入門書を用意して、興味を持つ人たちを数多く育成することの意味を強く感じていたんだろうと思います。
さて、児童図書にかぎらず、また、ジャンルに関わらず日本語のパブリックドメイン作品を復刻するにあたって突きあたる課題が、オリジナルと現代表記の壁です。外字の問題と、時代経過による表記差異の問題。青空文庫だけでなく、国会図書館の近代デジタルライブラリーでも Google や大学図書館などのスキャン・プロジェクトでもおそらく同様のはずです。
研究目的であればオリジナル底本忠実主義の一本にしぼることも可能。けれども、青空文庫やプロジェクト・グーテンベルクは、発足当初から朗読・点訳・翻訳など機械的な二次利用も念頭においてあります。そのときに外字やコーディングの選択以上に課題となるのは、おそらく旧字旧かなの処理です。外字に言及する批評家は多いし、スキャン・プロジェクトも耳目を集めやすい。それらは文字集合を広げることとOCR精度の向上で解決できる部分が大きい。
ところが、旧字旧かなの処理となると誰も口を開きません。復刻最大の悩みだからなのかもしれません。国内の電子出版がいっこうにふるわない理由の一つも、そこにあるんじゃないでしょうか。本を読みたい人のすべてが、旧字旧かなに精通するわけではありません。『週刊ミルクティー*』では、この解決策を二者択一に求めないことにしました。それがオリジナルと現代表記の同時収録です。
(1) オリジナル版(旧字旧かな)
霧島火山群は東西五里に亙り二つの活火口と多くの死火山とを有してゐる。その二つの活火口とは矛の峯(高さ千七百米)の西腹にある御鉢と、その一里ほど西にある新燃鉢とである。霧島火山はこの二つの活火口で交互に活動するのが習慣のように見えるが、最近までは御鉢が活動してゐた。但し享保元年(西暦千七百十六年)に於ける新燃鉢の噴火は、霧島噴火史上に於て最も激しく、隨つて最高の損害記録を與へたものであつた。
(2) 現代表記版
霧島火山群は東西五里にわたり二つの活火口と多くの死火山とを有している。その二つの活火口とは矛の峰(高さ一七〇〇メートル)の西腹にある御鉢と、その一里ほど西にある新燃鉢とである。霧島火山はこの二つの活火口で交互に活動するのが習慣のように見えるが、最近までは御鉢が活動していた。ただし享保元年(一七一六)における新燃鉢の噴火は、霧島噴火史上においてもっとも激しく、したがって最高の損害記録をあたえたものであった。(略)
比較のため、ルビは削除しました。
この問題に気がつかせてくれたのは、青空工作員の一人、大久保ゆうくん率いる京都大学電子テクスト研究会による現代表記版の制作活動でした。彼らは「現代表記にあらためる際の作業指針」を用意し、作品ファイルの末尾に、「彼奴→あいつ 彼方→あっち 貴方・貴女→あなた 或→ある 或は→あるいは 如何→いか 不可ない→いけない 一層→いっそう 一杯→いっぱい 否→いや 愈々→いよいよ 中→うち ……」というような置き換えのすべてを延々とメモしていったのです!(モーリス・ルブラン『奇巌城』テキスト奥付より)
一見して、絶対にマネしたくないなあと(^^;)思ったものでした。自分にはそれほどの根気はないなあと。ところがそれを見ていて、ふと“置換リストをひとつだけ用意すれば、旧字旧かなテキストのすべてを自動変換できるんじゃないか”と思いつきました。その一覧リストを置換辞書として設定し、機械的にテキストを単純置き換えするわけです。それが新字新かな辞書「シンちゃん」のプロジェクトとなりました。『週刊ミルクティー*』の現代表記版は、二代目「シン弐くん」に活躍してもらっています。
※その他は以下を参照。
*99「The Small Issue(スモール・イシュー)」
変換用辞書セット2009年版
変換用辞書セット2010年版
オリジナルに手を加えて改めるのもいい。置き換えリストを用意することもいい。だからといって、オリジナルテキストが不要とは思えない。むしろ、誰もが比較できるように積極的に公開しているほうが望ましい。オリジナルとの比較が担保されているならば、そのぶん大胆な改変も可能になるんじゃないかと。本来ならば、底本のテキストに手を加えるのは御法度のはずですが、紙の本と異なり、差分の比較が容易だからこそできることもあると思うのです。
記述内容の老朽化について
ジャンルの問題、表記の問題について先に述べました。ここで、どうしても未解決の課題が残ります。記述内容そのものの老朽化です。考古学・天文学・生物学・物理学・地学……新規の発掘サンプルの出現や観測精度の向上などによって、いままで定説だったものや理論や仮説は、つねに内容を更新され続けます。
科学だけでなく、文学やアートでも価値観の変化や差別認識への反省から、表現の再検討を要求されることもあります。また、時代によって市町村名も所属する組織名も、県境や国境も変化し続けます。出版から長い時間を経過し、当の著作者もすでに亡くなって久しいパブリックドメイン作品と現代との乖離は、どうしたら埋めることができるのか。
「私の学説は日進月歩で、逐次に訂正増補を加えて行かねばならぬ」「それにはどうしても、漸次改訂を加うるの便宜多き、雑誌上の発表がよい」……そう、先に引用した喜田貞吉のことばです。彼は、記述内容の老朽化という問題に対して、雑誌・逐次刊行物の発行という手段を選択しました。自分の発行したものの内容を、常に点検し訂正し続ける……これは、かつてチャールズ・パースやカール・ポパーが提唱したマチガイ主義(Fallibilism)と同じ考え方です。さらにいえば、Wikipedia や Project Gutenberg へと引き継がれている思想そのものです。

『週刊ミルクティー*』では、関連するWikipediaの項目を収録した付録を同時配布。
『週刊ミルクティー*』の運営サイト「*99(アスタリスク99)」がレンタルウィキ(@wiki)をベースにしているのも、Wikipedia 各項目を付録に転用しているのも、あたりまえといえばあたりまえというほどの帰結かもしれません。調べてわからなかった言葉や地名・人名、誤植や誤入力の疑いのある点や疑問点を「難字、求めよ」「むしとりホイホイ」として掲載しているのも、あるいは編者注や奥付に気になったことをメモしているのも、マチガイ主義の実践です。
時宜的《タイムリー》な作品の提供について
青空文庫の入力・校正の二段体制は、ややもするとおちいりがちなボランティアの質の低下を防ぐ、見事な方法です。内外に評価を得ているのも、その作業を継続しているからだと思います。その反面、入力と校正がつながらないと、長らくお蔵入りになることは先に述べました。したがって、時節にあわせた作品の公開も同様に困難、不得手です。
リクエストを積極的に受け付ける余地も、かならずしも広いとはいえません。掲示板「こもれび」にリクエストを書き込むと、「自分でやれば?」という冷たいレスを頂くことになります。活動の多くも個人個人ごとに完結している。いい意味でも悪い意味でも、浮世離れしている印象が青空文庫にはあります。
本来ならば、ウェブの強みは即効性です。しかし、それが青空文庫に望めないなら……青空非公認の裏 Wiki *99 および『週刊ミルクティー*』では、そういう取りこぼしの部分に積極的に関わりたいという方針でいます。平城遷都1300年祭には「蝦夷論」「道鏡皇胤論」、鎌倉大イチョウ倒壊には「右大臣実朝」、大河『龍馬伝』には「清河八郎」、宮崎県口蹄疫発生には「シシ踊り」、はやぶさ帰還には「星と空の話」、そして iPad 発売・電子書籍元年には『光をかかぐる人々』というぐあいです。白鳥庫吉「倭女王卑弥呼考」はリクエスト対応です。考古学の海進・海退をしばしば話題にするのも、もちろん地球温暖化に対するわたくし流のレスポンス。
表現したものと、それが生み出された時代は、一見無縁のように見えてもお互いに影響・干渉しあわずにはいません。作り手の意図におさまりきらないこともある。熱狂をあおることなく、世の中の日々のできごとを他人事として素通りすることなく……。図書館や自宅にひきこもりながらも、そんな社会との関わりあい方・記憶の刻み方を試みています。
徳永 直『光をかかぐる人々』について
『週刊ミルクティー*』創刊以来、もっともページのカウンタ数が伸びたのが徳永 直『光をかかぐる人々』(河出書房、1943.11)でした。6000をこえる数字は、現在もって不動のベストワン。これは工作員の uakira さんが、個人サイト「徳永直『光をかかぐる人々』入力中」にてテキストおよび底本画像を公開している作品です。
uakira さんとは青空のメーリングリストを通じて面識あったことと、日本活版印刷術の立ち上がりの興味あるドキュメントでしたから、さっそく校正を名乗り出て、かつ『週刊ミルクティー*』にも掲載しました。ちまたで小林多喜二『蟹工船』のリバイバルが話題になっていたころと記憶しています。
その後、uakira さんは続編(雑誌『世界文化』連載分)の入力と公開も始めます。前編はどちらかというと幕末の黒船襲来前史のようで、なかなか核心に至らない。むしろ続編のほうが、東南アジアや上海周辺が登場する近代印刷史になっています。本と出版の未来を考えるならば、もってこいのテキストだと思います。
「当事者の言葉で語る」ことについて
評論家やジャーナリスト、作家や研究者ならば当事者の言葉で語ることはもっともです。でもぼくは『週刊ミルクティー*』という雑誌をつくるにあたって、自己主張の場にしないことを心がけています。あくまでも黒子役の編集者、もしくは喫茶店のマスターやウェイターでありたいと思うからです。
著者はみな物故していますから、本人が主体的に語ることはもはや不可能。彼らの声を聞き取ろうとすれば、少なくともそのあいだは静かに自分の口を閉ざしたい。図書館や書店で、あるいは喫茶店で自己主張されるのは、ちょっと困りものですしね。
雑誌の創刊にあたって、販売の方法をポシブル堂の田辺さんに相談に乗ってもらったことがあります。その際、現在使用している販売サイトを紹介してもらいました。その田辺さんが昨年、「iPad ほしい!」と大声でつぶやいていました。電子出版の同業ですから当然です。ぼくも欲しい。だけれども……です。極端に聞こえるかもしれませんが、使えるお金も時間も、読める本も作り出す電子本も有限です。無限に手に入れ続けることはできない。ハードディスクがクラッシュしたり、突然体調をくずしたりした時ほど、いま、自分がほんとうにやりたいことがはっきり見えることがあります。
「ぼくにとって問題なのは、iPad を買う買わないじゃなく、いま、誰の、どの本を復刻するかですね」とコメントした記憶があります。iPad や ePub 形式には今後をおおいに期待します。けれど、今現在のプアなパソコン環境のぼくにとってベターな選択は T-Time です。
ところで『ず・ぼん』16号(ポット出版、2011.1)によると、2008年統計で全国の公共図書館数は 3164 館あります。学校や大学の図書室を含めればもっとあるでしょう。仮に、そのうちの一割から毎週購入してもらえると、ひと月の生活費・制作費がじゅうぶんにまかなえます。図書館がパブリックドメイン作品を購入して無償閲覧・貸し出ししてくれるならば、ネット以外の利用者も便が得られます。もちろん、DRM などというやぼったいものは使っておりません。
一人の復刻出版で年産できる量には限界があります。利用者に興味を持ってもらえるジャンルをそろえるには、同業者が100人ぐらいになってほしいなあと願っているところです。
■関連記事
・新年にパブリック・ドメインについて考える
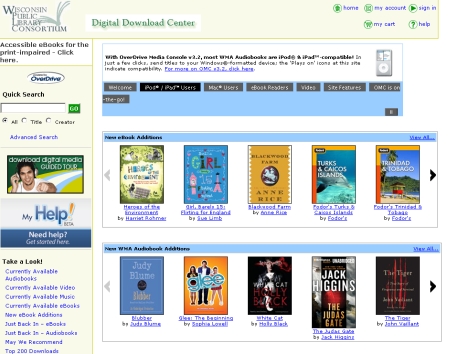
 国内の公共図書館では、
国内の公共図書館では、
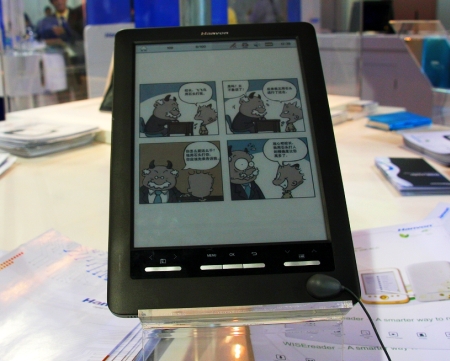

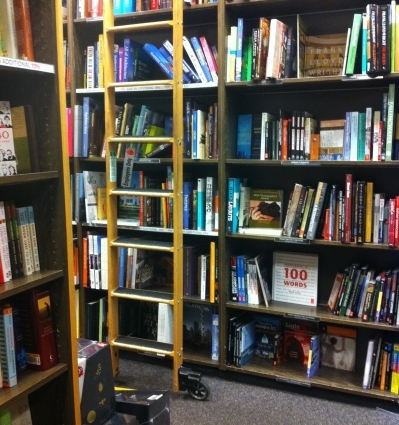
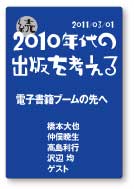 つづいて翌週の3月1日(火)には、阿佐ヶ谷ロフトAで
つづいて翌週の3月1日(火)には、阿佐ヶ谷ロフトAで
