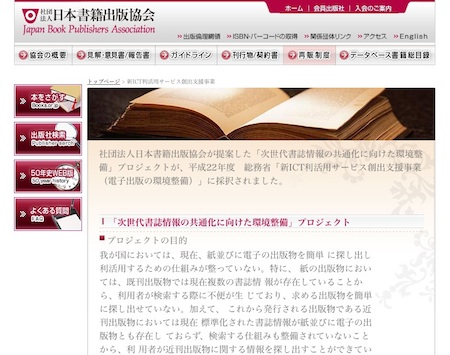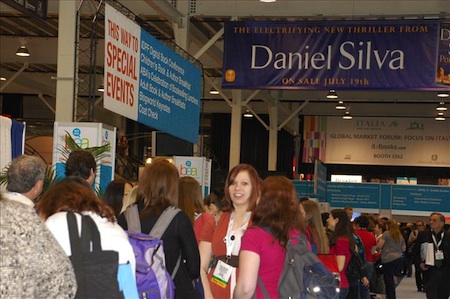未来なんてわからない
「本の未来はどうなるのか?」ということを2011年に問われたら、その質問の意味は、「本は電子書籍になるのか? 紙の本は電子書籍に取って代わられるのか?」だと考えていいと思う。
もちろん、「出版不況で人はどんどん本離れてる」とか、「ウェブで情報や知識は足りるんだから本なんか必要ないんじゃないか」とか、「本は残るかもしれないけど出版社は要らないでしょ、インターネットでだれでも発信できるんだから」とかいう質問も考えられるけど、ね。
で、紙の本は残るのか、電子書籍に置き換わるのか? といった未来予想についてボクは「わからない」としか答えられないんだ。ホントにわからないし、積極的に「わからない」という態度を維持するのがいいとも思っている。
未来は「わからない」んだけど、でも今起こっていることは全部「正しい」(勝間和代さんの本のタイトルのパクリですけど)とも思っていて、このふたつは両方とも自分にとって大切なポイントなんだ。
たとえば携帯電話。携帯電話は、電話をどこでも持ち歩けて、一人一台なものにしたんだよね。これは、やっぱり必然なんじゃないだろうか? 言い換えれば「正しい」。いくら技術的に、持ち歩ける無線の電話が可能になっても、人がそれを求めなければこれだけ普及したりしない。
一人一台が不必要なら、相変わらず電話は家族(みたいな複数の人間のあつまり)に一台だったと思う。人がそれを求めて、一人一人が持つようになったんだから「正しい」(というか、やっぱり必然かな?)としか言いようがない。
これに立ち向かって、「携帯は家族を解体してしまうので間違っている」といって「携帯禁止法」をつくろうとしてみても、現実は変えられないでしょ。立ち向かいたいんだったら、携帯がなくて、多くの人がマネしたくなるような、携帯に替わるモデルを生み出さなきゃ無理だ。
それでもいろいろ変化は起きている
では、本のありようのさまざまなモデルを考える上で、見ておくべき今起こっていることはなんだろう。
まずはじめに、情報がモノからはなれてデジタル(0と1でいいんだよね)に置き換わったということ。次に、その0と1を使ったりコントロールしたりして人間に、デジタルへの置き換えとアナログへの置き戻しをしてくれるコンピュータが発達して、ついにだれもが持てるものにまで費用を下げたこと(パーソナル化、ですね)。「そして、0と1という特性を利用して、それを線を使って届けあうインターネットというシステムを生み出したこと。
これが僕らの周りに起こっていることだ。コンピュータやネットは「多くの人に利用されている」というカタチで支持されているし、支持されたから多くの人が利用できるほどにその費用を下げることができた。
デジタルはとっても便利。0と1によって、音でも映像でも、もちろん文字でも表現できるようになった。おかげで、ボクはiPhoneやiPadやPCで動画を他の人に送り届けることができるし、映画を何本も持ち運べる(もちろん、届けられるってことと、届けて欲しがっている人がいるのか?ってのは別の問題です)。馬車の時代に自動車が生み出されたように、絵筆しかない時代に写真が生み出されたように、もうこの便利さからは後戻りできないと思っている。
馬車の最高スピードの何倍ものスピードが出せる自動車は事故を大きなものにし、多くもしたんだろう。でも、ボクらはそこから後戻りできなかった。どうやって交通事故を減らすか、という方向に進んだし、多分それは間違えていない道だった。
文字情報が0と1に置き換えられる便利さからは、もう後戻りできない。画面の読み辛さとか、装置の重たさを解消して行く方向で、今ある0と1の良くない点を減らして行くってことが、多分正解なんだ。それから、馬や馬車が完全になくならずに残っているように、紙の本がゼロになってすべてが電子書籍になることもない。
ならば、できるだけ電子書籍を運転してみて、そのいいところも弱点も早く気がつきたい。だから、電子書籍に前向きになる出版社でありたいと思っているのです。ボク自身は、かなりの紙フェチなんだけどね。いまだに電子書籍で読み終えた文字物は1冊だけだし、毎晩読むのは紙の本。
でも、こんな想定すら間違っているかもしれないよね。そんなときは、極力素直に、ゴメンナサイと言ってすまそうと思っている。実は未来の問題を語るときにイチバン大切なのは、間違ってたらゴメンナサイというってことなんだ。
間違ってたらゴメンナサイを封印してしまうと、東電みたいに、どう見ても想定を間違えたにも関わらず、「想定外だった」って言いワケばかりをでっち上げて、ゴマカさなきゃならなくなる。それってつらいでしょ。
この投稿の続きを読む »