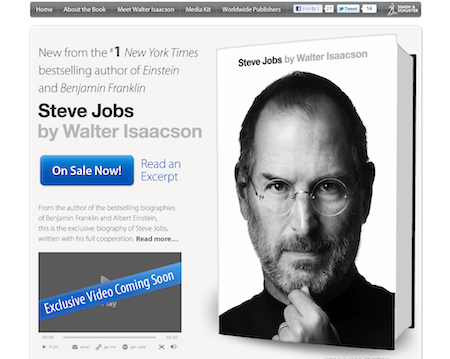楽天がkobo買収というニュースにはさすがに驚いた。驚いた後で、「なるほど、こりゃすごい良い買い物をしましたな」と感心するとともに、まだ電子書籍のガジェットがどうのこうのという日本での取り上げられ方に脱力。なんとか気を取り直してこのコラム書いてます。

koboは220万点の品揃えで「世界最大の電子書籍ストア」と豪語。
日本ではアマゾンが和書を売るオンライン書店としてだけでなく、日用品ならなんでも扱う外資系のオンラインリテーラーとして頑張っているから知名度も高いせいか、まだキンドルのサービスが始まってもいないうちから、黒船が、と話題になることも多いのはわかる。
しかし、本国アメリカではアマゾンがEブックもEコマースもすべてを牛耳っているわけではないので、機会あるごとにバーンズ&ノーブルのNOOK(ヌック)やソニーのReader、グーグルのeBookstoreやkoboもそれぞれの強みを活かしながらそれなりのプレーヤーになっていることを伝えてきたつもりなのだが、アマゾン以外はとんと印象に残らないらしい。
アメリカでは複数の電子書籍ストアが共存
しつこいようだが、もう一度説明するとこうなる。バーンズ&ノーブルは全米に数百あるリアル書店という強みを活かして、早くからアマゾンに対抗すべく、オンライン書店にもEブックにも取り組んできた。それを怠った業界第2位のボーダーズは倒産してしまったわけだが、バーンズ&ノーブルはしばらくは大丈夫だろうと見ている。実際、アマゾンよりも「本屋」であるがゆえの品揃え、クォリティー、サービスで上回る点も多い。
グーグルが「ブック検索」(のちのGoogle Books)を発表した時は蜂の巣をつついたような大騒ぎだったのに、その後すっかり忘れられているようだが、eBookstoreも端末の要らないEブックサービスとして力を付けている。本屋としてのリテール力はないので、インディペンデント系の書店と組むという賢い戦略を展開している。
ソニーのReaderも、単に本を読むためのガジェットという位置づけを超えて、デジタル化された書類を読むデバイスとしてアメリカでは地道にユーザーを獲得している。
そして話題のkoboなのだが、これもただのカナダの電子書籍屋と言ってしまうと、語弊がある。確かにあそこのリーダー端末は、Eインクのもタブレットもダサイ。でもそれは技術が追いついていないというよりも、最初からシンプルで最小限の機能だけつけて、値段を抑えるというビジョンがあってのものだ。100ドルを切るEインクのリーダーを最初に出したのはkoboだった。ソフトは独自のものは使わず、EPUBやアンドロイドOSを採用、いじりたい人がいじれるようになっている。
ソーシャルリーディングの機能が他より優れている、っていうのも大して重要じゃない。そんな小手先の技術はすぐに追いつけるし、ソーシャルリーディングの機能でkoboを選んでもらえるほど差別化はできないでしょ。
ボーダーズがつぶれちゃったから焦って買収してもらえるところを探していた、という話も聞かないし、ボーダーズとの提携だって、自社のリーダーがなくて焦ったボーダーズからアプローチしてきた話だったからね。
koboの強みはグローバルな版権と決済システム
だから私が今回の楽天による買収がすごい、目の付けどころがいい、と思ったのは電子書籍の端末とはあまり関係がない。koboが他と一線を画すのは、Eブックの版権をグローバルに獲得していることだ。
これがなぜすごいのか、少し説明しよう。例えば、日本でキンドルを入手した人なら経験があるだろうが、アマゾンのサイトに行って、欲しい本を見つけても、いざダウンロードしようとしたら「日本でのお取り扱いはできません」と言われてガッカリしたことはないだろうか。これはアマゾンがキンドルの版権を扱うときに、アメリカを中心にテリトリーごとにマーケットを作ってきたからだ。
その点、koboは最初から英語以外のヨーロッパ言語や、さらにアジアの言語でも表記ができるように、フォーマットが「緩い」。EPUBベースなので、日本語の縦書き表示もいずれできるようになるだろう。もちろん、グローバルスタンダード、つまり世界のどこでも使えるものは、それぞれの地域に細かく対応できないというマイナスはある。でもそのぶん、フレキシブルに対応できるという利点がある。
アマゾンも世界進出を目論んではいるのだが、マーケットを分けてその国ごとにキンドル版を用意してきた。キンドルストアごとに分断されている。だから日本で同じキンドルを使っているのに買えないタイトルが出てきたりする。
それに対してkoboは、カナダの会社だからだということもあるが、自国のマーケットで流通させるコンテンツを集めるときも世界権か全英語圏権であることを重視した。そうすることによって、koboの端末で、あるいはパソコン上で、北米、ヨーロッパ、オーストラリアのどこにいても同じ本が買えるのだ。とくにヨーロッパの人は、母国語が英語でなくても英語の本ぐらいはサクサクと読めるので、自国でアマゾンや他の電子書籍サービスが遅れていても、日本ほどフラストレーションはない。そしてすでに中国市場も狙って拠点を作っているようだ。
こういうマーケット戦略のおかげでkoboがもっている強みは、同じ本を通貨単位の違う国で売ってきた決済システムだと思う。ユーロでもカナダドルでも同じものを売って処理できるシステムとノウハウをもっているわけだ。
それを楽天が買ったということは、そのノウハウを搭載した端末で、世界中でモノが売れる道筋を作ったということではないのか? 国内でアマゾンと電子書籍で競争するためだけに236億円を投じたとは思えない。これは世界でアマゾンと闘うための投資だと考えると、これ以上適した端末はないのではないだろうか。世界のどこにいてもkoboがあれば、世界中の本が読める。世界中のモノが買えるようになるのだとしたら…。
そんなわけで、萎む一方の日本国内の書籍市場のために楽天がこんな買い物をしたのではないと思える。
アマゾンが出版社を差し置いて電子書籍の価格決定権を握ろうとしているのは許せないとか、楽天が社内で英語習得を奨励しているのを見てムダなことだと笑っていたり、Rabooがショボいとバカにしていた人たちに言いたい。電子書籍で成功するであろうプレーヤーは、すでに日本語の本を売ってどうこうという狭くて小さい世界を超えたビジョンを持って未来のリテールを見据えている。
■関連記事
・ボーダーズはなぜダメになったのか?
・バーンズ&ノーブルが身売りという誤報にビックリ(「本とマンハッタン―Books and the City)
・巨大電子書籍サイトがやってくる前に