グーグル社が、過去の本も現在の本もひっくるめて、人類がつくりだしたすべての本を網羅的に電子化し、かれらの全文検索サービスの対象にするという「グーグル・ブックス」計画をスタートさせたのが 2005年。これに対してアメリカの作家ギルドや出版社団体が「あきらかな著作権侵害だ」と集団訴訟をおこし、いろいろあったすえに一応の和解にたどりついた――。
この件について私が知っていたのはそのあたりまでです。その後、とくに最近は大地震と大津波、福島原発の崩壊と、すさまじいできごとがつづき、日本のジャーナリズム同様、そとの世界で起きていることがらに関心をもつ余裕をすっかりなくしていた。そんなとき仲俣暁生氏から一通のメールがとどいた。「ニューヨーク・タイムズ」と「ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス」の電子版にロバート・ダーントンの新しい文章がのっている。それを読んで感想をのべよ、というメールでした。
ダーントン氏は高名な書物史家でハーヴァード大学図書館の館長。私は以前、本誌に「グーグル・プロジェクトは失敗するだろう」という文章を寄せて、氏の「グーグル・ブックス」批判を共感的に紹介したことがある。その責任をとれというのかな。
で、とにかく読んでみたのですが、案の定、なかなか頭にはいってこない。英文が苦手という理由もあるが、それよりもやはり、いま東北や関東諸地域で生じている事態があまりにも強烈すぎるせいでしょう。ただ、注意して見ると、この大破壊のうちにも、われわれの本や読書の未来を深いところで変えてゆきそうなできごとが、いくつか見いだせる。そこで、まずそちらについての感想をすこし述べ、それとの関連でダーントン氏の文章に触れるというかたちに勝手に変えさせてもらうことにした。その点をご了承ください。
巨大製紙工場の崩壊と紙の未来
まずこの1ヶ月間、本や読書がらみで印象にのこったできごとを二つだけあげておきます。第一は地震と津波による巨大製紙工場の崩壊。そして第二に Wikiサイト「saveMLAK」の活動――。
前者については、すでに古田アダム有氏によるくわしい報告(「震災の後に印刷屋が考えたこと」)が本誌にのっているので、具体的なことはそちらにおまかせするとして、私は古い人間ですから、過去に、敗戦後(1940年代後半)とオイル・ショック時(70年代前半)の二度の紙飢饉(大規模な紙不足状態)を経験しています。その経験によって「私は二つの確信をえた」と、以前、「紙が消えたらどうしよう」という文章(1998年。『読書欲・編集欲』所収)で書いたことがある。「もし紙がなくなれば、いや完全になくならなくとも、かりに紙の生産量が半分になっただけでも、いまある私たちの社会や文化は致命的な打撃をうけることになるだろう」という確信が一つ。それともう一つ。
紙は永遠ではないし、つねに安定供給されるわけでもない。戦争であれオイル・ショックであれ、なんらかの原因があれば、この社会からあっさりすがたを消してしまう。日本にかぎっても、わずか半世紀で二度も消えた。このさき、おなじことが繰りかえされないという保証はどこにもないのである。
実感的にいえば、一度目の紙飢饉は小学一年生の私が中学にはいるころまで、つまり五、六年はつづいたような気がする。二度目は一年かそれ以上。小さな出版社の編集者として、さんざんな目にあわされた記憶がいまもまだなまなましく残っています。では三度目は? この段階で考えていたのは、予想される中国(人口13億)とインド(人口9億)の経済急成長と、それがひきおこすであろう木材資源の枯渇です。その過程で大小の紙飢饉を繰りかえしながら、紙にたよる文明は、徐々に、そのすがたをかえていかざるをえないのではないだろうか。
しかしそのときは、私が生きているあいだに、こんな事態が実際に生じるなどとは想像もしていなかった。個人的にいえば、そのことのショックですね。いまはじまったばかりの紙飢饉は、おそらく二度目のレベル(紙が実体的に消えたというよりも市場操作の産物だったらしい)をこえて、いっそう深まっていくでしょう。ただし、どう考えても敗戦直後の数年間のような悲惨さのレベル(教科書どころかノートも画用紙もない実体としての紙のほぼ完全な消滅)にまではいたらない。今回の飢饉も何年かたてばかならず終息する。しかし、より大きなレベルでの「紙の文明」の危機はこれによっていっそう深まってゆくだろう。それはたしかなんじゃないですか。
いや紙飢饉や紙不足にかぎらず、今回の経験によって、ついにというか、ようやくというか、私の世代の人間が敗戦時の危機や戦後の体験について、「ゆたかな時代にそだった人には理解できないだろうが」と特権的に語る(語らざるをえなかった)時期が終わったのだと思う。そして、それは同時に、いまの若い人びとが老人たちの干渉ぬきで、敗戦時や戦後の、すでに歴史となった経験をみずから再発見してゆく機会を手にしたことを意味する。なにしろ古田アダム有氏が紹介してくれた日本製紙釜石工場の被災写真は、米軍の空爆によって徹底的に破壊された日本の光景とそっくり同じなんですから。もはや年とった人間がえらそうな顔をする余地はない。
図書館を救え
そのことを痛感させられたのが、もう一つの、さきにあげた「saveMLAK」の活動です。つい最近になって、ようやく私はこの「博物館・美術館、図書館、文書館、公民館(MLAK)の被災・救援情報サイト」の存在を知った。

博物館・美術館、図書館、文書館、公民館(MLAK)の被災・救援情報サイト。
きっかけになったのは、たぶん読んだ方も多いでしょうが、朝日新聞の 4月4日号(朝刊)に掲載された、仙台市在住の作家、佐伯一麦氏の訪問記事です。なかに記者が佐伯氏の車に同乗して若林区の小学校に設置された避難所をたずねる場面がある。地震と津波で廃墟と化した名取市から、となりの同様に大きな被害をうけた若林区に「工藤さん」という佐伯氏の友人一家が避難してきていたんですね。
「ここが今の家です」。工藤さんは毛布を6畳ばかり敷き、家族6人で生活していた。片隅に『唐詩選』がある。佐伯さんは言った。「国破れて山河あり、か」
この記事にせっしたとき、ちょうど私は必要があって小津安二郎の戦場日記(田中真澄編『全日記小津安二郎』所収)を読んでいました。中国北部に召集された小津は戦地でも、出版されたばかりの谷崎源氏とか志賀直哉の『暗夜行路』とか、けっこう沢山の本を読んでいたらしい。そのこととのつながりで、おなじ本好きのひとりとして、戦場であれ避難所であれ、やはり人間は読みたい本を読むのだな、と切実な印象をうけた。
小津安二郎の場合は、それらの本を家族や友人から送ってもらうとか、兵隊仲間から借りるとか、行軍の途中に大きな街の本屋で買うとか、さまざまなやり方で入手していたようです。だったら工藤さんの場合は? はたして名取市の自宅から『唐詩選』(岩波文庫?)を持ちだすだけの余裕があったのだろうか。おそらく書店はだめ。被災後、図書館で借りたという可能性もないではないが、でも、こんな状況で近くの公立図書館が無事にひらいていたかどうか。そう思ってインターネットでしらべるうちに、国立国会図書館のサイトからリンクをたどって、この「saveMLAK」というサイトに行きあたった。
はいってみておどろきました。北海道から神奈川県まで、東日本全域の博物館・美術館(Museum)、図書館(Library)、文書館(Archive)、公民館(Kominkan?)の被災状態が、館種別・県別に、簡潔な表形式(職員・利用者の被害、施設の被害、蔵書・収蔵品、展示の被害、その他の被害、運営情報、救援状況など)で示されている。おかげで、3月17日現在、名取市図書館では職員は全員無事、ただし「損壊がひどく、再開のめどは立たない」という現状がすぐわかった。では仙台市若林図書館は? 人的被害なし。書籍落下。それでも、しばらく閉鎖したのち、4月8日に玄関まえの仮設カウンターで限定的にではあるが業務を再開したらしい。
ということは、4月4日の段階では、工藤さんはまだどちらの図書館でも本を借りられなかったことになる。とすればやはり、あの地震や津波のさいに逃げる工藤さんがたまたまつかんだのが、あの『唐詩選』だったということになるのだろう。
この「saveMLAK」というのは、おそらくボランティアのサイトなのでしょうが、それにしても、いったいどういう人たちがこれほど充実したデータベースを、しかも、これほど素早く立ち上げたのかしらん。答えは「SaveMLAKについて」のページで見つかりました。「ACADENMIC RESOURCE GUIDE」編集長の岡本真氏が「現状では、最終的な管理責任者」役をつとめ、スタートは 4月はじめ。ただし、それ以前に活動を開始していた「savelibrary」「savemuseum」「savearchives」という三つのサイトを「集約したもの」で、岡本署名以外の「情報の大部分は、多数の有志によって更新されています」とのこと。
博物館や美術館はさておき、危機に瀕した図書館の救援なんて、従来のこの国では、たぶんだれも思いつかないですよ。そんな反射神経は私たちの世代の日本人にはない。
私がじぶんの無力を「痛感させられた」というのはその点です。政治イデオロギーや最新の舶来思想や宗教宗派のカセにとらわれず、かといって個人生活や小さな社交圏にとじこもるというのでもなく、これだけの大きな活動(以前であれば国会図書館や図書館協会に一方的にゆだねてしまっていたにちがいないような)を即座に、なおかつ自発的に組織してしまう。そして、その活動をささえるための Wikiに代表される新しいネットワーク技術をつかいこなす能力を軽々と身につけている。だから自発性と技術力ですね。その二点にかんするかぎり、われわれ先行世代は完全に追い抜かれてしまったなあ。
グーグルとは逆にグーグルへ
要約していってしまうと、私はこの間、おもにこの製紙工場の破壊と「SaveMLAK」の活動という二つのことがらから、おおよそつぎのような感想をもった。「おもに」というのは、避難所にとどいた絵本に熱中する子どもたちのすがたとか、身ぢかな編集者たちが伝えてくれる東京有明の書籍用紙倉庫群の惨状とか、とりわけ携帯電話の不通や充電システムの破綻(電子本はどうなるのかね)とか、本や読書に直接・間接にかかわるできごとがほかにもいろいろあったからです。その感想をざっと整理しておきます。
- 人間はこれからも「印刷した紙を綴じたもの」としての本がもたらす特殊な安心感を必要としつづけるだろう。(工藤さんの『唐詩選』)
- しかし、その「物質としての本」をささえる紙は、いつもかならず安定供給されつづけるわけではない。需要の極大化がすすむにつれて紙の危機はいっそう深まる。(製紙工場崩壊)
- 「紙の本」に限界があるように、「電子の本」にも固有の限界がある。たえざる電源確保の必要もその一つ。二つの本に喧嘩させるよりも、二つ本の共存への道を積極的にさぐったほうがいい。(携帯電話の不通)
- いまの現在の公共図書館のしくみは戦後の廃墟の上につくられた。しかし近年、そのしくみがどうもうまく機能しなくなっている。もしかしたら、このたびの廃墟から 21世紀の新しい図書館像が生まれてくるかもしれない。(SaveMLAK)
そうしたことをとりとめなく考えながら、最初にもどっていうと、私は仲俣さんにおしえられてロバート・ダーントンの「グーグル・ブックス」批判を読んだわけです。
それで知ったのですが、この3月22日、ブルックリン連邦裁判所のデニー・チン判事が、グーグルと、著作権侵害という理由でかれらを訴えた作家ギルド・出版社団体が共同で作成した修正和解案(グーグルはかれらが所有する電子本データベースへのアクセス権を売り、その上がりをグーグルが37%、作家や出版社が63%の割合で分配する)を、「これではグーグル側が有利になりすぎて公正さを欠く」という理由でしりぞけてしまったらしい。この判決を、ダーントン氏は「われわれが共有する文化資産を特定の一社に独占的に利用させないようにする公共財という考え方の勝利だ」と高く評価しています。
ほかにも、オーファン・ブック(著作権者不明の孤児本)のあつかいや、著作権者の側が異議を申し立てないかぎりグーグルによる電子化を承認したとみなすという強引なやり口への批判とか、いろいろありますが、それらはダーントン氏がすでになんどか論じていることです。私の場合、こんど読んでつよく印象にのこったのは、『ニューヨーク・タイムズ』への寄稿の「グーグルのものよりいい電子図書館」というタイトルが明確に示すように、かれがビジネスではなく公共性の観点から、これまでよりも一歩踏み込んだ電子図書館のプログラムを提示していることでした。
とはいえ私たちは〈世界中のすべての本をだれもが利用できるようにする〉というグーグルの夢を捨て去るべきではない。そうでなく私たちは、それらの電子本を読者にタダで提供する電子公共図書館を建設すべきなのだ。いかにも前途には法的、経済的、技術的、政治的な多くの問題が立ちはだかっているだろう。しかし解決は可能である。(「グーグルのものよりいい電子図書館」)
ダーントンがここで「グーグルのものよりいい」というのは、データの独占やパイのぶんどり合戦といったグーグル式のビジネス・モデルとは別のしかたで実現される「グーグルの夢」という意味です。じっさい、過去20年間に、アメリカでは大学図書館などの研究図書館がコレクションの部分的な電子化をすませているし、「ナレッジ・コモンズ」や「インターネット・アーカイブ」などの大規模プロジェクトも自力で数百万点の本を電子化しおえた。アメリカにかぎらず、フランスやオランダやオーストラリアやフィンランドやノールウェイでも、また、その範囲をダーントンがよく知らない世界にまでひろげれば、中国や韓国、それにかなりのおくれをとってはいるが日本でも、おなじ『グーグルの夢の全世界電子公共図書館」にむけての作業がはじまろうとしている。
したがって、とダーントンはいいます。
電子公共図書館という目標にグーグル自身が積極的に加わることもありうる。同社はすでに1500万点の本をスキャンした。そのうちの200万点は著作権切れの公共資産《パブリック・ドメイン》だから、それらをコレクションの基盤として図書館の手にゆだねることもできる。こうした気前のよさによって会社が失うものはないもない。むしろその善行によって大いに称賛されるのではないか。
グーグルは科学技術の魔法やあけすけな大胆さによって、われわれの図書館がもつ知的資産、いまはどんより淀んだまま書棚に並んでいる書物群を、どうすれば変貌させられるかをおしえてくれた。しかしそれでも、 21世紀のさまざまな挑戦に直面して読者たちがもとめるものを提供できるのは電子公共図書館しかないのだ。だれもが、いつでも、どこからでもタダで利用できる知的資源の広大なコレクションだけにそれができる。(同)
「グーグルが失敗した6つの理由」というもう一つの文章(『ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス』所載)によれば、このときダーントン氏が具体的なお手本(ビジネス・モデルに対抗するもう一つのモデル)として思い浮かべていたのは、オランダのハーグを拠点とする「ユーロピアーナ」という汎ヨーロッパ的な電子図書館計画だったようです。ヨーロッパの 27の国や地域のセンターからはいってくるデータ(本や画像やレコードやビデオ)を標準化し、それらをシームレスの一つのネットワークに変換して、だれもがじぶんのパソコンや携帯電話に無料でダウンロードできるようにする。つまり、グーグルのようにコレクションを独占的に蓄積するかわりに、複数の独立した集合体のメタレベルの集合体としての役割を担うにとどめるというわけですね。
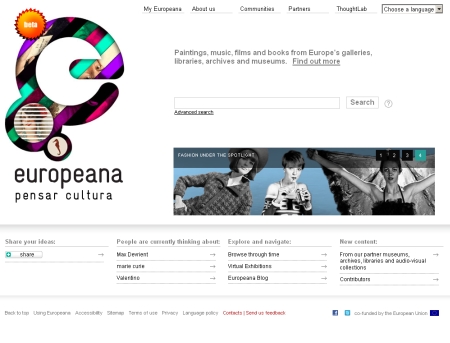
ダーントンがみずからいうように、もちろん「前途には法的、経済的、技術的、政治的な多くの問題が立ちはだかっている」にちがいない。しかし、近代図書館が長い時間をかけて獲得した「だれでも、どこでも、いつでも」の無料原則を欠いては、公共図書館も研究図書館も図書館ではないものになってしまう。だとすれば、これはたんなる夢想や大風呂敷ではない。いまこそ、新しい電子公共図書館実現のための智慧をしぼるべきときだ、とダーントンは考えているのでしょう。
私はかれの意見に賛成です。ではそのことと、こんどの大地震、大津波、原発破壊とのあいだに、どんな関係があるのか。おそらく、いずれなんらかの関係が生じてくるだろうとは思いますが、この数日、いそいで書いた文章で軽々に結論をだすわけにはゆかない。いまは、この震災によってヒビ割れる以前の世界では夢想にしか見えなかったものが、震災後の世界では実現可能なプログラムに変質している。そうなることをのぞむとつぶやくにとどめます。
■関連記事
・グーグル・プロジェクトは失敗するだろう
・Robert Darnton “A Digital Library Better Than Google’s” (The New York Times)
・Robert Darnton “Six Reasons Google Books Failed” (NYR Blog, The New York Review of Books)
・大震災 仙台の作家・佐伯一麦さんに聞く(asahi.com)
執筆者紹介
最近投稿された記事
- 2013.07.09コラム無料貸本屋でどこがわるい?
- 2011.04.18コラム揺れる東京でダーントンのグーグル批判を読む
- 2010.11.26書物史の第三の革命5 本の電子化はいつはじまったか?
- 2010.10.30書物史の第三の革命4 若者が本を読まなくなった

