公正取引委員会競争政策研究センター(CPRC)は11月15日、「電子書籍市場の動向について」の公開セミナーを行いました。内容は、「電子書籍市場の現状」などに関する共同研究報告書の紹介と、経済学的な論点提起、米国及び欧州におけるアップルの独占禁止法(カルテル)事例、プラットフォーム事業についての経済学的検証などです。現時点における電子書籍市場の状況を正しく把握するとともに、今後を考える上でも有意義なセミナーでしたのでレポートさせて頂きます。なお、講演資料は公正取引委員会のウェブサイトで公開されています。
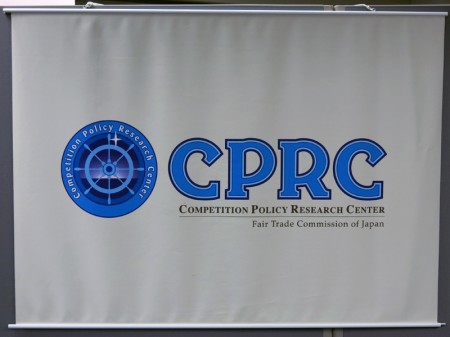
「電子書籍市場の動向について」の事業者アンケート結果
セミナーはまず、東京大学大学院経済学研究科教授でCPRC主任研究官の大橋弘氏から、共同研究報告書「電子書籍市場の動向について」の事業者アンケート結果が説明されました。アンケートは、出版社30社、電子取次5社、電子書店4社に対し、昨年11月から今年の2月にかけて行われたものです。
出版社に対する「平成23年度における紙と電子の売上比率」という質問では、電子が1%未満という回答が13社と最も多かったのですが、10%超も2社あるという興味深い結果が出ていました。Kindleストアが日本へ上陸する前の、「新たなプラットフォーム向け電子書籍市場」がまだ112億円(インプレスR&D)と推計されていたころの話ですから、680億円と予測(インプレスR&D)されている本年度では、もっと電子の比率が高くなっているものと思われます。
その「電子書籍」に対し、大半の出版社・電子取次・電子書店は「紙の書籍とほとんど同様で、置き換え可能なもの」という位置付けであると認識しているようです。
また、「紙の書籍の販売価格に対し、電子書籍の希望小売価格はどのくらいが妥当か?」という質問には、「八掛け(20%オフ)」という回答が多数でした。電子化に新たな作業が必要であったり、印税率が紙より高いなど、印刷・製本という物理コストを除いたとしても、制作費が紙とそれほど変わらないということに起因するようです。
出版社の「著作権者から電子化の許諾を得る際の懸念」は、著作者の所在などが分からなくなっていることや、著作者の紙へのこだわり、著作者が直接電子書店との取引を検討していることなどに回答が多く集まりました。
経済学から見た「電子書籍」の特徴と論点提起
次に大橋氏は「私見ですが」と前置きした上で、経済学から見た「電子書籍」の特徴について説明をしました。以下のような、三つの特徴があるそうです。
1. インターネットの役割
「電子書籍」を読むには、「端末」と「コンテンツ」が必要である。さらに、端末とコンテンツを繋ぐインターネット上の「プラットフォーム(仲介者)」が存在する。例えば、ゲーム機とゲームソフト、ビデオデッキとビデオテープと同じように、「電子書籍」が普及するためには端末の普及と豊富なコンテンツ提供の両方が必要となる。ここには相乗効果がある。
2. ネットワーク効果
インターネット上で取引されるコンテンツは、輸送コストが低く、在庫リスクもないことから、「ネットワーク効果(利用者が増えるほど利便性が高まる)」が強く働く。その結果、市場占有率が0か100かに偏る傾向が現れるため、黎明期には過度な競争を生み、成熟期には独占企業による市場支配力(ロックイン)を高める可能性がある一方、プラットフォームの栄枯盛衰が激しいという特徴もある。
3. コンテンツ生産とその特性
「電子書籍」は、紙の本と合わせて出版されているケースが多い。したがって、「電子書籍」の販売が紙の本の販売へ与える影響を考えざるを得ない。その影響が代替的(トータルの販売額は変わらない)なのか、補完的(トータルの販売額は増える)なのか。現状では、代替的だと考えている出版社が多い。また、コンテンツを生産する著作者と、出荷可能な形にする出版社との、権利関係も複雑である。そして、例えば著作者が直接市場へ流通させられるといった、紙の本とは異なる流通構造を持っている。

東京大学大学院経済学研究科教授・CPRC主任研究官 大橋弘氏
これらの特徴を踏まえた上で、大橋氏は以下の三つの論点を提起しました。
1.ホールセールモデルかエージェンシーモデルか
ホールセール(卸売)モデルとエージェンシー(委託販売)モデルの違いは、価格決定権がストアにあるか出版社にあるか。ストアが端末を販売している場合、それが専用端末なのか汎用端末なのかで効果が異なるため、どちらのモデルが良いかは一概に言えない。
また、ネットワーク効果の視点からは、黎明期には普及を促すために端末やコンテンツを安売りして市場拡大を図る場合がある。また、コンテンツ生産の視点からは、紙との代替程度や、コンテンツ提供や販促に伴う交渉力の違いも加味する必要がある。
2.最恵国待遇(MFN)・最恵顧客待遇条項(MFC)
家電量販店によく見られる「当店より安い店があったら、その価格にマッチングします」という条件は、競争を促進する効果があるように見える。ところがこれは、顧客を使って価格変動のモニタリングをしていることになるわけで、むしろカルテルを強固なものにする可能性もある。
3.大規模化に伴う競争上の論点
ネットワーク効果が強く働くことで、プラットフォームが大規模化し市場を独占する可能性がある。それは、小売の交渉力増大や、契約の規格化を招くので、競争上の問題になり得る。また、インターネットは効率的な販売を可能にするとともに、価格比較を機械的に行うことで常に最低価格をオファーできるようになった。その他にも、これまで多くのプレイヤーに分断されてきた電子書籍関連サービスが、小売の大規模化によってワンストップ化する可能性もある。
大橋氏によれば、今後、電子書籍市場が黎明期を脱するにつれて、競争上の問題はますます重要になってくるため、さまざまなビジネスモデルが競争に与える影響を、いろいろな観点から継続的に評価していくことが必要とのことでした。
電子書籍市場と独占禁止法
続いて、京都女子大学法学部教授で元CPRC客員研究員の泉克幸氏から、米国と欧州におけるアップルと出版社の共謀事例と、日本への示唆についての説明がありました。

京都女子大学法学部教授・元CPRC客員研究員 泉克幸氏
アップル及び出版社5社に対する米司法省の民事訴訟
アメリカ司法省の訴状によると、出版社大手5社(アシェット、ハーパーコリンズ、マクミラン、ペンギン、サイモン&シュスター)は、アマゾンによる9.99ドルという電子書籍の低価格販売によって、ハードカバーの売上浸食や価格破壊、小売業者への卸価格低減化、小売業者の出版業参入を恐れていたそうです。アップルは当時、iPadの発売を控えており、9.99ドルという低価格販売とそれに伴う低いマージンでの競争を望んでいませんでした。
そこでアップルと出版社は、2008年9月頃から話し合いを重ね、契約形態をこれまでのホールセールモデルからエージェンシーモデルへ変更し、価格決定権を出版社側に移すことで、小売価格の引き上げと販売競争の制限を図りました。
このエージェンシーモデル契約では、出版社はアップルに1冊30%の販売手数料を保証しています。また、MFC(最恵顧客待遇条項)の保証と、価格帯(Pricing Tier)の設定をすることで、電子書籍の平均小売価格は約10%上昇しました。
この共謀がシャーマン法(カルテル禁止法)第1条違反に該当するとして、2012年4月、司法省は民事訴訟を連邦地裁に提起します。小売価格競争と小売イノベーション競争を阻害するものだというのです。しかし、反トラスト手続・制裁法(司法省が和解を承認する)に基づく同意判決で、被告出版社とはすべて和解が成立し、アップルだけが今なお係争中という状況です。
同意判決の内容は、電子書籍販売に関するアップルとの契約終了、小売価格設定制限とMFC契約の終了、2年間の値引き制限禁止、MFC条項を含む販売契約締結禁止、カルテル禁止、競争上センシティブな情報伝達(事業計画、過去・現在・将来の卸売・小売価格、小売業者との契約条件など)の禁止、反トラスト・コンプライアンス責任者の指名とコンプライアンス検査で、裁判所が延長を認めない限り判決は登録日から5年後に失効するという時限制限になっています。
EUのアップルおよび大手出版社に対する欧州委員会の確約決定
EUでの事例も、被告出版社はアメリカの場合と実質的に同じです。こちらの場合は、「欧州委員会が表明した競争上の懸念を解消します」というコミットメント(確約)をすれば、競争法違反の有無を認定されることはないそうです。確約の内容は、アップルとの代理店契約終了、アップル以外の小売店との小売価格設定制限やMFC条項を含む契約の終了、2年間の値引き制限禁止、MFC条項を含む契約を5年間禁止と、アメリカでの事例とよく似ています。
欧米の事例が日本に示唆するもの
どちらも、小売店の力が強くなったことに危機感を覚えた出版社がカルテルを行ったというもので、日本でも同じようなことが起こり得ます。出版社間だけではなく、出版社と電子書店との共同行為にも注視すべきと泉氏は指摘します。なお、日本の独占禁止法は競争関係にあるものの間で成立するもので、はたして「垂直」的な関係の場合は不当行為にあたるのか? という議論もあるそうです。
アメリカの同意判決やEUの確約決定は、正式な判決や排除命令に比べ透明性や公正性・厳格さの点では劣るものの、実効性のある問題解決や柔軟な問題解消処置の構築が可能となるというメリットがあるそうで、日本で今後、MFC条項を含む契約が結ばれた場合に、それが競争に与える影響を正しく見極める必要があるとのことです。
なお、アメリカ司法省は、紙の書籍市場と電子書籍市場とでは、さまざまな要素が異なるものだと認定しています。日本の出版社・電子取次・電子書店の多くが「紙の書籍とほとんど同様で、置き換え可能なもの」と位置付けているというアンケート結果がありましたが、アメリカの当局は「電子は紙を代替する」のではなく「電子は紙を補完する」ものとして捉えているのです。これは、紙と電子の本を同時発売した方が売上が伸びるといったデータからも明らかなことでしょう。日本の出版社・電子取次・電子書店は、意識を変えていく必要があるように思います。
プラットフォームビジネスとしての電子書籍
次に、株式会社富士通総研経済研究所上席主任研究員の浜屋敏氏から、プラットフォームビジネスとしての電子書籍についての解説が行われました。

株式会社富士通総研経済研究所上席主任研究員 浜屋敏氏
価値創造プロセスの違い
従来の物流における「バリューチェーン」や「バリューシステム」の場合、最終ユーザーへのアクセスは、最下流のプレイヤー(小売業者)に依存しています。そこでの情報の流れや価値創造の流れは、基本的に一方向となります。
ところが電子商取引の場合、プラットフォームが「エコシステム」を形成します。また、初音ミク現象に代表されるn次創作や、ケータイ小説のようにユーザーが価値創造活動に加わることができます。さらには、どのように本を読んでいるといったPoint of Use(利用状況)のデータを含めた、すべての情報がプラットフォームに蓄積されます。つまり、プラットフォームが双方的な「価値共創」の場になる、と浜屋氏はいいます。
浜屋氏も、「電子書籍は紙の本の代替と考えるより、新しい商品と考えた方がいい」と提言していました。しかし同時に、紙の本を扱っている事業者には、そのようには考えづらいであろうと理解を示していました。
プラットフォーム独自の戦略テーマ
プラットフォームビジネスでは、こうしたエコシステムのマネジメントが重要なポイントになってきます。プラットフォーム事業者が、補完製品の参加やイノベーションを促すと、エコシステムの機能や規模・価値が向上します。すると、プラットフォームを利用するユーザーが増えます。補完プレイヤーがさらに多様な製品を投入したり、より多くの補完プレイヤーがエコシステムへ積極的に参加するようになります。
例えば、販売手数料を無料にしてコンテンツを増やそうとする事業者もありますが、コンテンツの品質をプラットフォーマーがどう管理するか?というところが課題になってくると浜屋氏は指摘します。無料にすれば参入障壁が下がる分プレイヤーは増えるものの、品質の低下も免れないということでしょう。
エコシステムの構造の違い
アップル、グーグル、アマゾンといったプラットフォーマーに共通しているのは「垂直統合システム」だという点です。垂直統合であれば、一部の事業が赤字でも他で補うことができます(例えばコンテンツ販売が赤字でも端末販売で補える、など)。かつて、マイクロソフトがOSにウェブブラウザをバンドルしたことが独占禁止法上問題だとされたことがあります。いずれこれらの垂直統合的なプラットフォームでも同じような問題が出てくるかもしれない、と浜屋氏は指摘します。
のちに大橋氏から、水平分離と垂直統合に関する補足として、技術革新が次々起き、それらに強い関心をもつ初期ユーザー(アーリー・アダプター)のみが利用している段階では水平分離の方が望ましいが、技術にあまり詳しくない大多数の人(レイト・マジョリティ)が利用する普及期には、むしろ垂直統合の方がいいのかもしれない、という意見が述べられました。ただし、それが電子書籍においても望まれる方向性なのか、正しいことなのかどうかは、大橋氏にも分からないそうです。
ひとり勝ち(Winner Take All)のメカニズム
浜屋氏によると、電子書籍ビジネスは、寡占状態になりやすいメカニズムになっているそうです。その例として、マルチホーミング(二つ以上のプラットフォームを利用)のコストとメリットが挙げられました。例えば一人のユーザーが複数の電子書店を利用すると、フォーマットの違いというコストが生まれます。それに対し、第三者がマルチホーミングコストを下げる、新たなサービスを提供する可能性もあるというわけです。
プラットフォームビジネスは「ひとり勝ち(Winner Take All)」になりやすい反面、簡単にひっくり返ってしまうといいます。フィーチャーフォンからスマートフォンへの移行のときと同じように、スマートフォンの優位があっという間にひっくり返ってしまう可能性だってあるのでしょう。質疑応答で公正取引委員会委員長の杉本和行氏が「競争環境を確保するには、当局は何をすればいいでしょうか?」という質問をした際も、浜屋氏は「規制をするよりイノベーションを促進するほうが重要」という見解でした。
たとえ競争環境を確保するためとはいえ、当局の介入は影響力が大き過ぎます。仮に日本の電子書籍市場がいずれかのプラットフォーマーによる寡占状態になったとしても、ユーザーにとって不利益(例えば値上げをするとか)がなければ、そのままの状態でも構わない、という考え方もできそうです。絶対安泰な企業というのはあり得ないわけで、独占・寡占状態にあぐらをかいた瞬間に、足元をすくう他のプレイヤーが登場するということなのでしょう。
いずれにしても、日本の電子書籍市場はまだこれからという段階です。多くのプラットフォームが参入し、群雄割拠の状態になっています。恐らく今後、競争に敗れて舞台から去っていくプレイヤーが続出し、寡占化が進んでいくことでしょう。競争に勝ち残っていくためには、「出版社の都合」や「電子書店の都合」ではなく、「ユーザーの利益」を最優先することが肝要だと私は考えます。そして、恐らく最も大きなカギを握るのは、現時点ではほとんどのプラットフォーマーが採用している「DRM(デジタル著作権管理)」の有無ではないかと想像しています。
■関連記事
・「電子書籍元年」の先に進むための原則
・ウェブの力を借りて「本」はもっと面白くなる
・大手出版5社はEブック談合してたのか?
・カニバリズムは神話だった
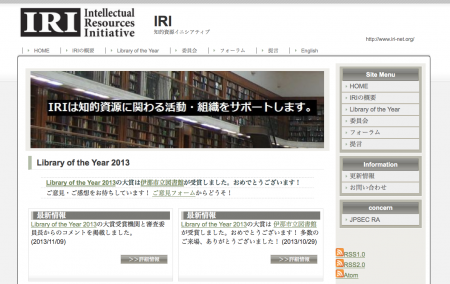


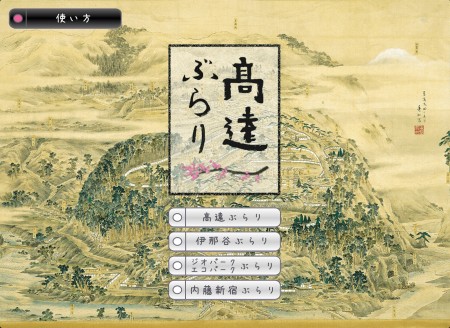
 オライリー・メディアが手がけた(電子)書籍の邦訳をボイジャーが手がけた
オライリー・メディアが手がけた(電子)書籍の邦訳をボイジャーが手がけた
