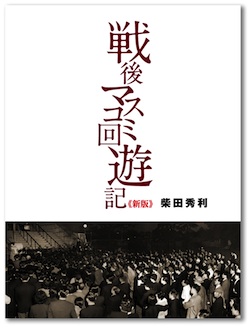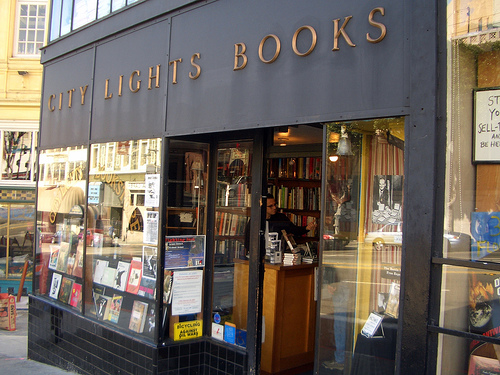〜ノンフィクション作家・佐野眞一さん、柴田秀利を語る
※これは2002年の東京国際ブックフェアにおけるノンフィクション作家・佐野眞一さんの講演を編集し、再録したものです。
テレビとはなんだったのか

有楽町で街頭テレビに見入る群衆。
昭和28年12月東京有楽町での街頭テレビに見いる群衆の光景です。右端に 『聖衣』という映画の看板が見えています。この映画はハリウッドがテレビの出現に対抗して導入したワイド画面シネマスコープの最初の作品でした。群衆はしかし、背をむけて食い入るように豆粒のようなテレビ見ているのです。とても皮肉なワンショットといえるでしょう。
こちらは日比谷公園です。「TOKYO MOTO……」の看板が見える。今日本でもっとも規模の大きいショーとなった『モーターショー』は、 1954(昭和29)年に日比谷公園でおこなわれていた。同時期に、これもまたその後に巨大なメディアを形成するテレビも産声を上げていた。公園内にある日比谷公会堂の階段にテレビが置かれ、群衆の目はその小さなボックスに注がれている。

1954(昭和29)年 日比谷公園
私はこの街頭テレビの写真を見るのは初めてです。もちろん街頭テレビは知っています。昭和29年といえば小学校へあがるかあがらないか、つまり物心がついた年で、いまこの写真を見ると、鳥打ち帽をかぶったオッさんとか、われわれの周りにはああいうオジさんたちがいっぱいいたナ、懐かしい日本人がいるナ、僕らのオジさんたちだなア、という気持ちを大変強くもちます。
私たちは、このような群衆の中の一人であったのです。
テレビとは何だったのか、どのようにしてテレビは私たちの前に現れてきたのか……?
柴田秀利著『戦後マスコミ回遊記』を電子出版する大きなきっかけは、このような問いの中から生まれてきました。きっかけを与えたのは街頭テレビの写真でした。これらの写真はすべて柴田秀利さんの遺品からひきだしてきたものです。

1953(昭和28)年 静岡公会堂前
柴田秀利さんと私は、実はとても深く知り合った関係でした。中央公論から出版した文庫『戦後マスコミ回遊記』の解説は私が書きました。そして私は、正力松太郎という人間を、1994年に文藝春秋から『巨怪伝』としてまとめました。大変ぶあつい本です。そのときに、大変重要なキーマン、それが柴田秀利さん、という人だったのです。
たぶん、現存のジャーナリストの中で生前の柴田秀利さんにあったのは私一人だとおもいます。たとえば、渡辺恒雄のことを書いた魚住昭氏の『メディアと権力』という本がありますけれど、そこにも柴田秀利らしき人が書かれています。私もそれを読みました、しかし、生前の柴田秀利さんにお会いになっていないから、非常にゆがんだ人間として描かれていると私はおもいます。
私は生前の柴田さんにお会いして、驚くべき話を山ほど聞きました。芝浦にあった柴田秀利さんの個人事務所で初めてお会いしたとき、ただならぬ人格というものを感じました。以来、柴田さんのところへ通って、信じられないようないろいろな話をうかがいました。テレビとはどういうふうに導入されてきたか……テレビの出現というのは一大イベントだったわけです。その裏には非常に秘められた歴史があるわけです。
私は『巨怪伝』に「正力松太郎と影武者たちの一世紀」の副題をつけました。われわれは、いまだに、良くも悪くも、正力がつくったメディアの権力の中にいます。正力という人はその後初代の原子力大臣となります。原子力開発を押しすすめます。しかしこの裏に、実は立て役者として柴田秀利がいたんです。われわれの生活では、原発でつくった電気を使っているわけです、その電力を使ってテレビを見、サッカー中継などを見て一喜一憂し又翌日新聞でその試合の模様を確認する、という行動の中にわれわれがまだいるわけです。つまり正力松太郎および、その本当の立て役者であるところの柴田秀利という人物が仕掛けたメディアの構造の渦中に、いまだわれわれがいるということです。
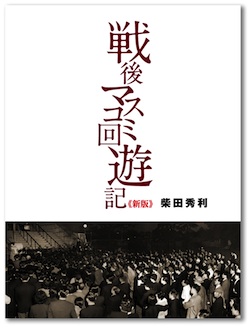
全巻をまとめ新版の電子書籍として再刊。
『戦後マスコミ回遊記』はすごい本です。大物中の超大物、例えば吉田茂、あるいは最近人気の白洲正子さんのご亭主、外務官僚だった白洲次郎さんなんかは、ほとんど通行人扱いで書いてあります。そういう錚々たる人物が登場するドラマなんです。白洲次郎とも親交があった、あるいは北大路魯山人とも親交があった、そういう関係をさらりと自然に書いている。占領軍はこの柴田秀利に目をつけます。非常に武器になる……この男はできる、やれる、とおもった。アメリカ人というのは非常にフランクな面を持っています。つまりこいつはいけるとおもったらどんどんやらせるという姿勢です。
柴田秀利は、この時代、まだ30を越えるか越えないかの非常に若い年齢です。その若さで、テレビの幕開け、原子力時代の平和利用といった相当な量の仕事をこなした人でした。
私は13の時に宮本常一の『忘れられた日本人』を読んで感動したという話を何回もしたことがあります。私が13の時というと安保闘争、昭和35年、1960年でした。世の中物情騒然としている、政治の季節。それからもう一方では、同時に高度経済成長の時代が始まっている、家電製品がどんどん入ってくる、テレビがはいってくる、電気冷蔵庫、洗濯機が入ってくる、つまり政治と経済が一緒にやってきた季節だったわけです。世の中泡立つような時代だった。
そうした時代に背を向けて四国の山奥でたった一人で盲目の博労の話を聞き取っているオヤジがいる。あるいは対馬の海っぺりにいて、開拓漁民といいますが、一つの漁村を開いたじいさんの話に耳を傾けているオヤジがいる……この姿に私は感動しました。非常に孤独な背中、その姿に感動したんだとおもいます。
宮本常一は柴田秀利とは真反対にあった人だともいえます。つまり私は、宮本常一に感動し、そしてまた真反対の柴田秀利にも感動します。本が売れなくなってきている時代とはいうものの、私は、本というものはまだまだ、それだけ大きなキャパシティーをもつものだということを訴えたいわけです。この幅の広さが読書の大きな醍醐味ではないか、ということが言いたいのです。そしてこの醍醐味を広げていく動きの存在無くして本の未来も無いだろうということです。その意味では電子出版もまた一つの動きとして力を蓄えていって欲しいと期待しています。
電子出版でなにができるか
私は電子出版について専門家じゃないから、その機能についてよく分からないことも多いですけれど、例えば百万言をついやすよりも、ここにある風景、日劇前の街頭テレビの人、人、有楽座というあの文字、シミキンというあの文字、そこから喚起されるものは僕らの世代にとっては莫大なものがあります。 そうだシミズキンイチというのがいたな、という非常な喚起力、こういうものを一瞬にして引っ張り出し、見る者、読む者に訴えかける力が、電子出版というものの中には秘められているのではないか、とまず私はおもいました。
ここでちょっと本の中味について紹介させていただきます。
『戦後マスコミ回遊記』第三部の「テレビ時代の夜明け」を開くと、目次の中から「アメリカ方式525本」という章があります。テレビには大きく3つの方式があります、アメリカ方式とヨーロッパ方式そして、主にかつてのソ連を初めとする社会主義諸国が採っていたSECAMという方式です。日本がアメリカ方式に決まる背景には、戦後から冷戦にいたる政治状況が深くかかわっていたわけです。

残された記念アルバムの写真を本文に組み込む。
こんなことが書かれています。「私のところに、三人の客人の行動記録を写し、記念に贈呈した、立派なアルバムの二冊だけが残っている。金張りの西陣で表紙を飾った、見事な贈り物の複製である…………この時起ち上がったホールスウセンの通訳として写っているのが、後に国連大使となった加瀬俊一氏である……」。「一同がアッと驚いたことは、壁一面に張りめぐらされた、全日本をカバーするネット・ワーク計画と、多重通信機能が誰にも分かるように図解された、目を見張る革新的計画案が、ズラッと並べられていたことだった……」

本文と写真による対話。

左の写真を拡大したところ。
これらの写真を丹念に見ていき、本文に一つ一つ組み込んでいく、そのことによって、いままでの本にいくつかの発展型が生まれ、本文と写真による対話が生まれていきます。
ここにいます弁護士のホールスウセン、それにホールステッドという技術者……みんな大変な大物をアメリカは送り込んできたわけです。何ということもない研究発表のような光景ですけれど、よく見ると明確な極東の地図がおかれていて、日本を含んで朝鮮半島をカバーする反共通信網の青写真が描かれているとうかがうことができるわけです。アメリカが意図する入念に準備された計画ということだったのです。
ある取材で、かつて日本の領土だった樺太の資料がないか、北海道中を探しました。小樽に小樽高商、小樽商科大学というのがありますが、ここの地下倉庫に3日間こもって探しましたがありませんでした。
ところが、りんごの産地で……ニッカウヰスキーでも有名な余市というところの市川文庫というところに膨大な豊原(とよはら)の写真が見つかりました。シスカという一番北端の町、トナカイの群れ、少数民族が閉じ込められた森、すべてを全部写している記録がありました。新発見だとおもいます。 たとえば、これを電子出版化するということになれば、これぞ知られざる樺太、日本領有時代の樺太はこうだったんだ、これぞ新しいんだとという、目に物見せるという仕事なるとおもうのです。
一番大事なのは、一次情報です。そこに人がいて、その人の目で撮った写真は時として本を抜きます。本は最強のビークル(入れ物)だと私はおもいますけれど、人が撮った写真というものは、本にアタッチメントする価値を十分にもつものではないでしょうか。
宮本常一は10万点の写真を残しています。ネット配信もはじまったと聞いています。高度経済成長を迎えようとしていた日本の光景を丹念に、くまなく歩いた過程で写された写真、膨大な情報、膨大な記録、国家的事業にも匹敵する仕事だったとおもいます。これを活用することによって、われわれはどういう事ができるか。
宮本常一は日本の島という島、村という村を、全部歩きました。距離にして地球を4周した男です。行かなかったところはありません。膨大な写真を撮っています。高度成長前の日本が見事に定着されています。例えば日本列島の白地図に宮本常一の足跡を赤インクで記していくと、日本列島が真っ赤になるという有名な話があります。宮本常一の撮った1920年代の写真、1930 年代の写真、1940年代の写真を使って日本の白地図をCTスキャンするように見ていくことができるなら、日本列島の中から何が失われたか、そのありかがわかるわけです。それが一つ。
それからもう一つの電子出版の可能性は、宮本常一が写した写真を見ることによって、あっ、この人見たことある、これはあのオジさんだっ、といった場面、関連が必ずでてくるはずです、それをインターネットで返してあげる。そうすると、新しい形の本が生まれる可能性もあるとおもうのです。たとえば、この章だけ欲しい、あるいはここをもっと読みたいというとき、そこを進化させていくような、自分だけの本、自分が知りたいだけの本というものをオンデマンドにやることができるとおもいます。それが新しいかたちの出版と読者との関係をつくっていくことになるでしょう。まったく新しい関係が端緒をつくりだすという気がします。
新しいモバイル、新しいビークルをつくる
本は20世紀最強のビークルだと私はおもいます。モバイルだし、簡便だし、情報量はたくさんある……しかし、一つの歴史的な変遷の中で、大量生産、大量消費のシステム自体がが崩れていこうとしています。本だけではなく、すべてがです、それは歴史的な流れなのです。残念だとおもってもしかたない。であるなら、我々の知恵で新しいモバイル、新しいビーグルをつくっていくほかはないです。
いろいろなツールが生まれていくことになるでしょう、まさにその中の一つに電子出版の動きもあるのです。ですからいま柴田秀利が電子出版として紹介されていることに、ちょっとした驚きと感慨を感じずにはいられません。柴田さんという人は、それに値する長い視野をいまでも伸ばし続けている人なのでしょう。

講演中の佐野眞一さん。
私は、はじめて柴田秀利と会ったとき、この人は総てを知っているすごい人だとかんじました。私流にいえばアドレナリンが出た。この人は本当の秘話を知っている、一読売の内部のことだけではなく、日本のメディアの全体の底流をなす一番重要なことをこの人は語ってくれたなと私はおもったのです。何回か事務所で話しをお聞きするうちに、本当にそんなんことがあったのかという、驚天動地の連続だった。それで、しばらく柴田さんの事務所へ通いましたが、「佐野くん、ぼくはゴルフ大会があるのでアメリカへ行く」ということで、聞き取りはしばらく中断したのです。
ところが、フロリダでゴルフ中に柴田さんは亡くなってしまった。その報を聞いたときは、あー、あれも聞いておけばよかった、これも聞いておけばよかったと、私はおもいましたけれど、生前柴田さんが誰にもいわなかった話をずいぶん私にしてくれたことを誇りにおもい、柴田さんが書き残してくれたもの、そして、奥様の柴田泰子さんがつくられた遺稿集などで補足もさせていただき、不十分ではあるが、私は『巨怪伝』というかたちでいいものが書けたとおもっています。あれから10年くらいの歳月が流れていますが、新しいメディアの誕生を得て、十数年前に僕が通った田町の事務所をここでこういうかたちで見るとは、おもいもよらなかった……なにかこう、非常に感慨深いものをかんじています。
政策研究大学院というところがあります。歴史学者として大変有名な御厨貴さん、伊藤隆さん、近現代史の専門家です……これらの方たちが中心になって、オーラルヒストリー研究会というのをやられています。日本人は一般的に伝記を残さない、記録を残さない民族だと言われていますが、必ずしもそうだとは言い切れないのですけれど、ここで記録を残す運動をしていこうということで、中曽根康弘から話を聞き取って評伝をつくる、あるいは渡辺恒雄から、後藤田正治から話を聞いて記録として残すという仕事を行っています。
昨年でしたか、このオーラルヒストリー研究会の御厨さんから、私は呼ばれました。聞きたいことがあると言われたのです。その中の若手のグループから、あなたの聞き取り技術を聞きたい、特に戦後マスコミの化けモノ中の化けモノ、正力松太郎を私が扱っているということで、どうしてこういうことが構築できたのかというのが、主題でした。
私は、柴田秀利のことを話して、柴田秀利とお会いできたことが、そして彼の残した『戦後マスコミ回遊記』を読むことが、私の正力取材の最大の源泉であったと話したのです。結局は千載一遇というか、その機会を逃すと、やはり永遠に歴史は闇から闇へと葬られてしまうのです。
宮本常一はこう言っています。「記憶に残ったものしか記録に残らない」と。至言中の至言だとおもいます。
振り返ればわれわれは、グーテンベルク以来継承して活字を発達させてきたわけですけれど、いろいろなメディアの開発をへて、こういう鮮明な画像を簡単に得るまでになりました。しかも自分の好きなように出版できるのです。いわばこれは単に読者になるだけじゃない、参加ができるのです。つまり自分の好きなように、この写真をもっと拡大する、この人物は誰だというこちらのアクセスが可能な状態になる。この人物のことがそのときには分からなかったとしても、いつか分かりうる伝達スタイルがきっとできるとおもいます。つまりベーシックな原型があって、それにどんどん付加がつのっていく。
付加をつのらせていくのは、やっぱり人間です。つまり人の素養であったり、堆積であったりなのです。個々の人の知識なのです、あるいは経験なのです。みんなが試されている、この中からなにを読みとるか、つまり読者としても試されているということを私は電子出版にたいしてつよく感じました。
読者であり作者である、作者であり読者である……私たちはこういう存在です。こういう相互に行き来する存在にますます私たちは入ってきている時代に生きています。
私はここで柴田秀利の『戦後マスコミ回遊記』を電子本としてあらためてみました。いろいろなことが頭を巡りました。私が書いた正力松太郎『巨怪伝』のことはもちろんです、あのときお会いした柴田さんのおもいで、そしてここに納められた幾多の写真から触発される私が生きた戦後の情景、そのとき時代は確実に動いていた、テレビ導入にかかわった柴田秀利もそこに激しく活躍していたのです。あの汲めどもつきせぬ問題意識というものは、このテキストのはしばしからからきっと感じられるはずです。たくさんのものがまだまだこの本、そしてこの電子出版には埋もれているんだということを、あらためて申し上げたいと私はおもいます。
※柴田秀利『戦後マスコミ回遊記』の電子書籍はボイジャーの「理想書店」で購入できます。