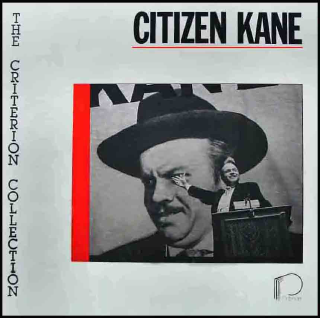12月3日は国連で宣言された「国際障害者デー」となっています。日本でも、障害者の福祉と社会活動について意識を深めるため、この日から一週間が「障害者週間」となっています。これにちなみ、今回は普段とは少し異なった視点での本の紹介です。
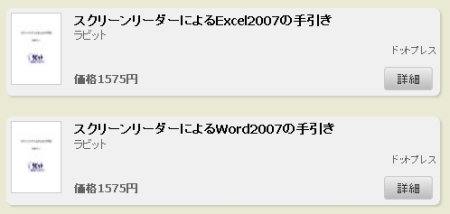
ラビット社が発行する、視覚障害者向けのWordとExcelのテキスト。
これらはラビットという会社の本です。ラビット社は、IT技術を活用した視覚障碍者・もうろう者のかたの総合的な支援サポートをおこなっています。その一つに、視覚障碍者がパソコンを利用するためのテキスト本を出版するという活動もあります。
今回の2冊は、オフィス系ソフトの代表ともいえるWordとExcelについて、音声読み上げとキーボード操作によって作業をこなす方法を解説したテキスト本です。これらの本が作られた目的は2つ、視覚障碍者が自身で操作を学ぶためという他に、視覚障碍者へのサポートをおこなっている教育者、ボランティアにとってもサポート方法を学び実践していくための指針となる、という意味もあります。
タイトルの「スクリーンリーダー」という言葉、ご存知でしょうか? 視覚障碍者がパソコンを使う方法の一つに、画面に表示されている内容を音声変換し読み上げさせる、というものがあります。この音声読み上げを行うソフトが「スクリーンリーダー」です。代表的なものに高知システム開発の「PC-Talker」があります。
この投稿の続きを読む »