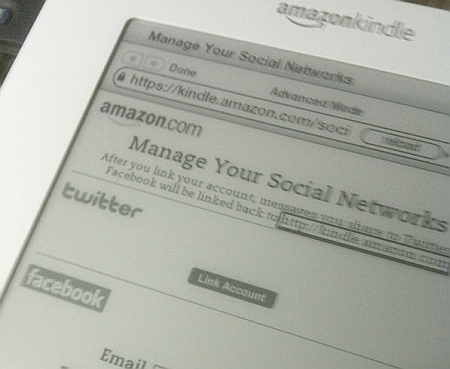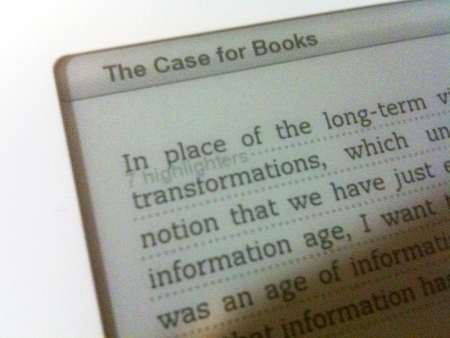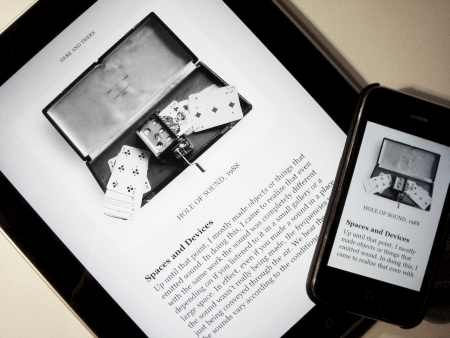いま、というのは二十一世紀の最初の十年がたった現在という意味ですが、そのいま、私たちにしたしい本と読書の世界が大きく変わろうとしている。
そのことを前提としてみとめた上で、この変化を「本の電子化やインターネット化に乗りおくれるな、急げ急げ」というようなあわただしい観点からではなく、五千年をこえる歴史をもつ書物史の大きな流れのなかで、できるだけ気長に考えてみたい。
いいかえれば、いまはせいぜい五年か十年の目盛りで考えていることを、百年、さらには千年の目盛りによって考えてみること。そうすれば、いまの変化が一体どれほどの深さや広がりをもつものなのかがわかってくる。いまはまだ完全にはわからなくとも、あるていどの見当はつくだろう。それがここで私がやりたいと思っていることなんです。
でも、これだけでは抽象的すぎて、ちょっとわかりにくいかもしれません。もうすこし具体的にのべておきましょう。
まず「百年の目盛り」ですが、これは、ついこのあいだ過ぎ去ったばかりの百年、つまり二十世紀とのつながりで現在の変化を考えてみようという意味です。意味というより提案かな。そのさい、ぜひとも頭に入れておいてほしいことがひとつある。二十一世紀生まれのいまの少年少女をのぞけば、私たちのほとんどは二十世紀に本とのつきあいをはじめた。ところが、その二十世紀というやつが、じつはただの百年じゃなく、書物史や出版史の視点から見ると、たいへん特殊な百年だったということなんです。
簡単にいえば、長い歴史をもつ本の力がかつてない頂点にたっした時代、つまり「本の黄金時代」です。それこそが私たちが生身で体験したあの二十世紀という時代だった。
頂点というのは、たんに「かつてなかった」というだけではなく、おそらくこの先もないであろう繁栄の頂点ということ。ここまでいそいで駆けのぼってしまえば、あとはもう峠のさきの坂道を下るしかない、いわばどんづまりとしての頂点。いまのこの変化には、そういう特殊な時代の終りという一面がある。いや、どうやらあるらしいぞということが、ようやく私たちにもわかってきた。それが「百年の目盛りで考える」ということの意味です。
では「千年の目盛りによって」とは、どういう意味なのか。
ようするに、いま私たちがそのさなかにいる変化を、紀元前三〇〇〇年ごろ、メソポタミア南端の都市国家シュメールで人類最初の本が生まれてからの長い時間のうちにおいてみよう、ということですね。そうすれば、いまのこの変化、つまり紙と印刷の本から電子の本へと向かう動きが、じつは「書物史の第三の革命」ともいうべき、もうひとまわり大きな変化の一部をなしていることがわかるにちがいない。なにも私が勝手にそう主張しているわけじゃないですよ。私のような歴史のシロウトにかぎらず、ロジェ・シャルチエやロバート・ダーントンといった人びとに代表されるプロの書物史家たちの多くも、徐々に、そんなふうに考えるようになっているらしい。
「第三」というからには、「第一」「第二」の革命があります。それまで延々と口頭でつたえられてきたことがらを、ついさっき誕生したばかりの文字によって記録するようになった。シュメールの場合でいえば粘土板に楔形《くさびがた》文字でということになりますが、それが「書物史の第一の革命」です。そして長い手写本の時代をへて、印刷技術の登場によって同一の文書をいちどに大量コピーできるようになったのが「第二の革命」――。

E.L.アイゼンステイン『印刷革命』
これらの変化を「革命」と呼ぶのは、やはり多くの書物史家たちが好んでこの語をつかっているからなんですね。たとえばエリザベス・アイゼンステイン。彼女は十五世紀なかばのグーテンベルクによる活版印刷術の発明を「印刷革命」とよんだ。同名の主著の翻訳がみすず書房からでています。
でも、どう思います? こうしたアイゼンステイン流の理解のしかたは、私にかぎらず、私たちのような東アジアの人間の目には、あまりにも西欧中心の歴史観に片よりすぎているように見えてしまうんじゃないかな。当然ですよね。もしグーテンベルクの発明だけが「革命」なのだとしたら、それ以前の中国や韓国における金属活字の発明とか、さらにそのまえに中国から東アジア全域にひろがった木版印刷術は、あれはいったい何だったんだということになってしまう。
私の考えははちがいます。むしろ木版や活版の発明をふくめて複数の土地に生じた複製化への試みが何重にも折りかさなり、それがやがて本の歴史に未曾有の大変動をもたらしたというふうに考えておきたい。くりかえし打ち寄せるゆるやかな「波動」であって、一回こっきりの「革命」ではない。だから本当は「革命」の語はつかいたくないのですが、でも「第三の波」といってしまうと、これまた以前どこかで聞いたことがあるような気がするし……。まあいいか、当面、ここは「革命」で妥協しておくことにしましょう。
ともあれ、書記革命(第一)と印刷革命(第二)というかつての二つの革命に匹敵する巨大な変化が、いま、われわれの本の世界にじわじわと到来しつつある。中心にあるのは、いうまでもなく紙と印刷の本から電子の本へと向かおうとする動き。その動きを「第三の革命」として書物史の内側に位置づけようとする意見が、おもに欧米の書物史家たちのあいだで広く共有されるようになってきた。
いや、そんなふうにいうと、
――書物史家ってなにさ。なぜいちいちそんな連中に気をつかうんだい?
と怪訝に思う人がいるかもしれませんね。
念のために、ざっと説明しておくと、二十世紀中葉、一九五〇年代後半から六〇年代にかけて、書誌学や美学や文学研究から歴史学や人類学や経済学にいたる多様なジャンルの研究者たちが、すでにある「科学史」や「芸術史」などとならぶ独立の学問領域として「書物史」というものを確立しようとする運動を同時多発的に開始した。書物史、英語では history of books、フランス語だと histoire du livre です。ひとまず、その流れに立つ学者、研究者たちというふうに考えておいてください。
まえにあげた『書物の秩序』のロジェ・シャルチエ、『猫の大虐殺』のロバート・ダーントン、『印刷革命』のエリザベス・アイゼンステインのほかにも、『書物の出現』のリュシアン・フェーブルとアンリ=ジャン・マルタンを筆頭に、『民衆本の世界』のロベール・マンドルーとか、いろいろな人がいます。広く考えれば、『物語の歌い手』のアルバート・ロードや『声の文化と文字の文化』のウォルター・オングや『グーテンベルクの銀河系』のマーシャル・マクルーハンも、そこにふくめていいかもしれない。あと『プラトン序説』のエリック・ハヴロックや『想像の共同体』のベネディクト・アンダーソンなども……。
本の歴史にも、巻物《スクロール》(巻子本)から綴じ本《コデックス》(冊子本)への転換とか、産業革命にはじまる紙や印刷の大量生産化とか、さまざまな節目があったんです。そのうちから、さきにのべた「口承から書記へ」の動きと「写本から印刷本へ」の動きの二つを、もっとも本質的で決定的な変化としてくっきりと浮かび上がらせた。浮かび上がらせることに成功した。いまは常識化しているが、じつはそれこそが二十世紀後半の書物史運動のもたらした最大の成果だったんじゃないか。私はそう考えています。
そして、それらと同レベルの、あるいはそれ以上かもしれない大きな変化が、いまわれわれの本の世界に生じつつある。長いあいだ、紙の本、物質としての本の歴史に専門的にかかわってきた人たちにとって、それを認めるのはなかなか容易なことじゃないですよ。それがわかるだけに、私はかれらの判断(たとえばダーントンは腹をくくって本の電子化に一歩踏み込み、その決断にシャルチエはやや批判的らしい)に、そのまよいや揺れもふくめていささか共感するところがあるんです。
――いまは五年か十年の目盛りで考えていることを、百年、千年の目盛りによって考えてみよう。
そう私は最初にいいましたが、それはおおよそこんな意味です。私たちが「いまの変化」というとき、その「いま」の厚さが、往々にして、あまりにも薄っぺらすぎる。幅もせまい。それが気にかかる。じゃあ、その厚さや幅をもうすこし大きくとってみたらどうなるか、どんな世界が見えてくるだろう、ということですね。うまくいくかどうかは別にして、とにかく、そんなあたりからはじめてみたいと思っています。
※本稿は国書刊行会から今秋に刊行される予定の、津野海太郎氏の新著のために書き下ろされた文章「書物史の第三の革命~電子本が勝って紙の本が負けるのか?」の抜粋です。これから月に1~2回のペースで1章ずつ公開していく予定です。