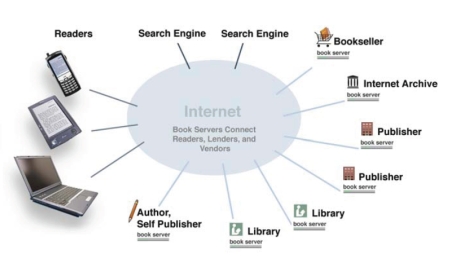アメリカ人が出版関連の利権で訴訟を起こしたり、ボイコットしたりしているのは死闘のバトルをやっているんじゃなくて、お互いに納得のいく着地点を探してプロレスごっこしてるだけ、なーんてことを以前に書いたので、なんだかオオカミ少年になりつつある気もしないではないが、またしても電子書籍をめぐってバトルが始まった。
今度はエージェントが大手出版社が抱える大物作家のEブック専門出版社を作り、アマゾンと専属契約を交わしてしまった、というニュース。報復措置として出版社側は、そのエージェントが担当する新人や新しい企画のボイコットをはじめた、というものだ。
電子化されるのは綺羅星のような名作ばかり
さて、このバトルで赤コーナーに立つのは、ICMやウィリアム・モリスと並ぶ大御所のアンドリュー・ワイリー・エージェンシー。クライアントの作家を思いつくまま挙げてみると、フィリップ・ロス、ソール・ベロウ、ノーマン・メイラー、サルマン・ラシュディー、マーティン・エイミス、オルハン・パムクなどなど、まさに綺羅星のような、そうそうたる顔ぶれだ。(リストを見ると大江健三郎や村上龍がはいっているが、これは日本のサカイ・エージェンシーと提携しているので、著作の一部を預かっているため)
このアンドリュー・ワイリー、業界では「ジャッカル」とか「ダース・ベーダー」とかあだ名される辣腕エージェント。つまり著者にとっては強ーい味方だが、出版社から搾り取れるだけ搾り取る、アグレッシブなやり方で有名な、いや、悪名高き御仁。でも、やっぱりいい作家とってるもんね。無視するわけにもいかない。
ワイリー卿(と呼ぶとしっくりくる。下のリンク先のインタビューの写真を参照)、つい最近まで電子書籍に関しては我関せずといったそぶりで、母校のハーバード大学の卒業生ロングインタビューでもキンドルについて訊かれて、「まだ売上げ全体の4%にしかならんものに、96%の時間を費やしてあれこれ言ってもしょうがない」ってなことを(しゃーしゃーと)答えていた。しかも「いちばん大衆的でくだらないベストセラーから電子化されるだろうね。ジェームズ・パターソンなんかEブックで十分じゃないの? 誰もそんなの書斎に飾っときたくないだろうし」なんて暴言まで吐いてるのだ。

オデッセイ社のウェブサイトはシンプルで、求める作品の電子書籍がすぐに購入できる。
ワイリーのクライアントである作家の電子書籍版権は、アンタッチャブルというか、出版社側は紙の本を出すときにもちろんEブック版権も付けてくれ、と申し出るのだが、それはダメです、渡せません、と言われてなす術がなかっただけで、Eブック版を放っておいたわけではない。だが、ワイリー卿ときたら、本当に自分のところでEブック専門出版社を作って、しかもその販売をする権利を、2年間の期限付きでアマゾンだけに譲渡という暴挙に出た。「オデッセイ」と名付けられたその出版社、名前にふさわしく今後数々の至難が待ち受けているんだろうなぁ。
この投稿の続きを読む »