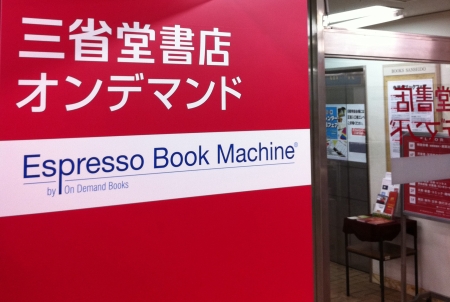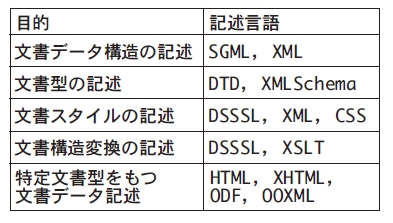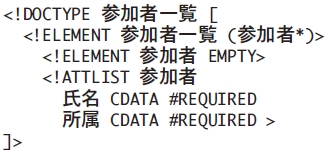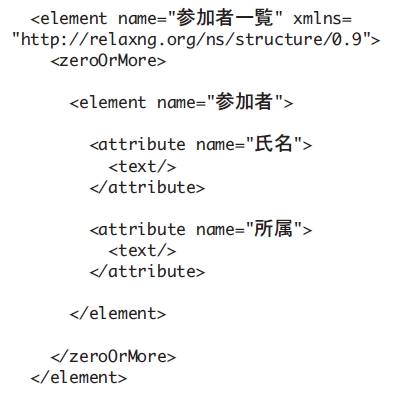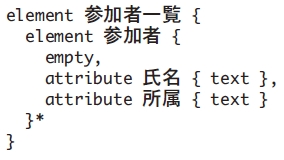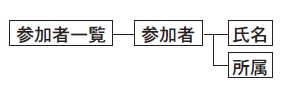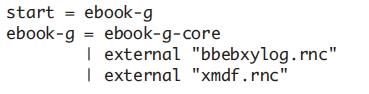以下は、『図書新聞』2010年7月24日号(第2975号)に掲載された拙稿です。同号は「2010年上半期読書アンケート」にあわせるかたちで、「電子書籍」特集の体裁も採っています。この記事のほかには、目玉企画として、前田塁・永江朗・藤沢周・円城塔の4氏による座談会「「電子書籍元年」、何を考えるべきか」が掲載されました。ご関心がおありの方は、ぜひ図書新聞編集部に問い合わせるか、図書館などでバックナンバーにあたっていただければと思います。
さて、今回、当該記事を本サイトに転載していただくにあたって、縦書きを横書きに変更し、改行数を増やし、小見出しを貼付しました。内容面での改筆は行なっておりません。基本的に初出のままです(ただし、校正前データを利用)。そのためもあって、ネットにアップするテキストとしてはいささか違和のある文体になったように思います。すなわち、紙に印刷されたテキストをそのままネットに移植したときにしばしば生じる違和感。それをはからずも体現する結果となりました。
同一コンテンツがメディアを取替えることで表層的印象までをも変えてしまう。書き手はこういったインターフェイス間の差異を意識しながら文章を書くでしょう。そうした多メディア環境という条件に由来する表現上の変化についても、あらためて別の機会に考えていければと思います。
《作者‐読者》の直接接続という夢想
杉山平助という批評家が、1930年代前半に、批評の社会性についてくりかえし分析している。その際、徹底して商業主義的な立場をとっている。背景には、小林秀雄らの〝自律した批評〟への目配りがあったはずだ(拙稿「大宅壮一と小林秀雄」[叢書アレテイア10『歴史における「理論」と「現実」』(御茶の水書房)所収]参照)。どれほど批評の地位が向上しようと、出版資本の一環にすぎないことを忘れるな、というわけだろう。
一例に、論説「批評の敗北」(『読売新聞』1931年10月17―23日)を見てみよう。杉山の分析はシンプルだ。いわく、批評家とは商品価値を測定する「鑑定人」である、と。商業が未発達の時代・領域の「消費者」は自らの鑑識眼を信頼し消費する。ところが、商品化が進展するにつれ、それは困難となる。なにより物量として選択肢が増大するからだ。その負担を代行すべく、「職業的批評家」が出現することになる。かかる一般論から、杉山は議論を説きおこす。そして、この構図を文芸業界に適用していく。
文芸批評家は、読者(=消費者)に文学作品(=商品)の解説を提供する。と同時に、読者を代表して作者(=生産者)に要望を伝達する。かくして、《作者‐批評家‐読者》の三者関係が形成される。ところが、実際には出版社も介在する。杉山はそれを「仲買人」になぞらえた。この四者関係で考えている(書店や取次など物流に関する存在は勘定に入れていない)。論説の中心議題は、出版社と批評家の関係である。両者は「第一義的要素ではない」。作者と読者のあいだに後発した存在だ。前者は作品の「交換価格」を決定する。後者は「質的優劣」を決定する。
ただし、両者の機能は相互侵犯的である。出版社は優劣の識別能力をもつからこそ、価格決定ができる。プライシングにおいて「批評」性を発揮する。他方、批評家は作品の優劣に言及することで、価値をも示すことになる。結果的に、市場価格の変動に影響をおよぼす。両者は機能的に近似する。ゆえに、対立関係におかれる。結論からいえば、批評家はこの対立に「敗北」する。批評もまた出版社をとおして商品とならざるをえないからだ。出版社は自身の利益に反する批評を排除できる。自身が批評家でありながら、杉山はこうした身も蓋もない見取図を導き出してしまう。
しかし、杉山は「批評の敗北」を「勝利」に反転する経路を末尾に指し出す。「発端」に戻れ、というのだ。すなわち、「作者と読者の直接的関係の恢復」。出版社と批評家が消失する光景を「最高の理想」とする。アクロバティックなこの論理展開は、紙幅の都合もあり説明されない。一ヶ月前に発表された「商品としての文学」(『東京朝日新聞』1931年9月19、20日)でも同じ議論を展開していた。こう結ばれる。作者と読者が「より合理的な新しい社会機関を通じて結びあはされる時代」が到来せねばならない、と(やはり詳細はなし)。
杉山以降も、多くの論者が《作者‐読者》の直接接続を夢想した。だが、具体策の提出にいたることはなかった。なぜか。理念を実現するテクノロジーが存在しなかったからだ。直販の一般化は不可能事だった(同人誌など限定空間における事例はある)。
電子書籍は出版社を消滅させるか?
さて、2010年代の現在はどうか。私たちは「理想」を実現しうる環境をすでに手にしている。杉山が漠然と表現した「新しい社会機関」がいよいよ出来する。インターネットの普及や電子書籍端末の登場によって。それらは出版社不在の取引を技術的に可能にするだろう。出版社だけではない。取次や書店もスキップされうる。作者と読者が直取引を行なう。その光景はもはや現実だ。諸機関は商品流通の複雑性を縮減すべく誕生した。ところが、複雑性は新たな技術により解消されてしまう。であれば、書き手は実入りの良いセルフパブリッシングを選択する(場合もある)だろう。金銭以前に、執筆自由度の高さや実験的表現の可能性も魅力的に映る。
さっそく、いくつかの試みが観察される。
例えば、小説家の瀬名秀明や桜坂洋らによる電子書籍『AiR [エア]』。Vol.1の配信が2010年6月17日に開始された。小説や評論、エッセイなど九つの書き下ろしを収録した雑誌スタイルだ。これを紹介する記事は、見出しに当人たちの思惑をこう記した。「出版社〝中抜き〟が目的ではない」と(ITmedia News 6月23日付記事)。実際、当該書籍の公式サイト冒頭部には次のようにある。「なにかを否定するためではなく、新しい可能性を肯定するためにこんなことをやっています」。当人の意図がどうあれ、直販は出版社の「否定」と見えてしまう。業界もこうした動向に過敏になる。そのため、事前の弁明が必要となる。
私個人は、技術的進展が出版社の消滅に帰結すると思わない。技術的に可能なことと、人びとが望むこととは、別の問題だからである。変容しながら残存し続けるだろう。「出版」という形態を前提するかぎり、責任問題や校閲、プロモーションなどをどう処理するのかという問題も残る。とすると、出版社と新技術との最適な接合形態もいずれ見えてくるにちがいない。
しかしながら、ここではあえて杉山の未来図に付きあってみたい。思考実験として、出版社消滅を仮定する。すべての書き手がデジタルデータによる直接サービスへと移行。この条件で考えてみよう。転換期において、多様な展開をシミュレートしておくことは無駄ではない。
出版社は企画・原稿を出版物へと飛躍させる窓口の役割を担ってきた。逆にいえば、そこでふるいにかけるわけである。その投機的営為において出版社は「批評」性を発揮した。ところが、現在の技術革新はこのゲートキーパーの撤退をうながす。望めば誰もが出版できる状況へ。金銭面での参入障壁(刊行コスト)の低減もそれを後押しする。
となると、従来ならば到底存在しえなかった有象無象の出版物が大量発生する。出版大洪水のごとき状況と帰すのか、それとも不可視の死蔵コンテンツの山と化すのかは、ここでは問わない。ともかく、そのただなかで、読者は自身の眼で取捨/発掘し消費することを求められる。これは、杉山のいう「発端」回帰を意味する。出版社に担保されていた「批評」が再び読者に戻される。「批評」を「信用」に置換えてもよい。読者は出版社のネームブランドを選択基準に入れる(場合がある)。だが、その基準も直取引の条件下では確保できない。
出版社「中抜き」にともなう負担が個々の読者に集中する。それは非経済的である(だから、技術と願望は別だと述べた)。何らかの代替装置が必要となる。作者と読者だけで構成される出版空間では、例えば先行読者による評価が重視されるだろう。アマゾンのカスタマーレビューに付された「おすすめ度」の星の数が典型的だ。クラウド的に立ちあがる集合的な批評行為と見ることもできる。読者による読者のための口コミ的な批評。だが、そうした「星の数」の平均値が「信用」ならないことを私たちは知っている。ときに、ステルスマーケティングに使われることも。
にもかかわらず、読者はそれに頼るほかない。読者はメディアパフォーマンスに幻惑され続ける。これが先の仮想条件から導出される風景だ。はたして「理想」的だろうか。だからといって、直販を止めろといっているわけではない。
「問いの構え」の変換を
長年私たちは、新たな出版流通モデルを模索してきた。「どのように改良すべきか」をめぐる議論の蓄積がある。ところが、キンドルやiPadを契機とした、ここ一年ほどの議論はタイプが異なる。多くは「未来はこうなる」型の言説に偏っていた。素朴な技術決定論による未来予想図が氾濫する。私たち自身が「何をしたいのか」「どうすべきなのか」といった問いのモメントはすっぽりと抜け落ちている。このあたりで、いちど電子書籍をめぐる議論の体勢を組替えるべきではないか。
「技術が進むことで、○○ができるようになる」型の論理だけでは片手落ちだ。「○○をしたいから、関連技術を進める」型の議論も必要となる。場面によっては、これが反動的な提言となりうることは十分承知している。だが、こと電子書籍論に関しては、あまりに前者に傾斜しているように見えるのだ。「○○をしたい」の部分は歴史的に規定される。とするならば、あらためて歴史的参照項の掘りおこしを進めなければならない。いかなる経緯で現行の出版流通体制が構築されたのか。それに対してどのような論議がなされてきたのか。
現在進行する出版環境の地殻変動は、杉山の活躍した1930年前後を連想させる。20年代半ばの出版大衆化状況の到来を経て、現在まで継続するビジネスモデルの基盤が急速に整備された時期だった。杉山が前述の問題にこだわったのは、かかる構造変動の渦中においてである。杉山にかぎらない。当時のジャーナリズムでは出版論が小さなブームをむかえていた。メディア論の萌芽といってよい議論が出揃っている。まさに、メディア=中間項、すなわち出版社や批評家が検討の対象となったのだ。そして、ただちに議論は現実の出版動向にフィードバックされた。
杉山は、「敗北」から出発する。その意味を強調した。別の機会には、それが自身の「評論の絶えざるテーマ」であるとさえ述べた(「文芸時評」『新潮』1934年2月号)。出版市場と批評家(という自身の〝職業〟)の関係の最適化を追求したのである。いま出版にたずさわるあらゆる立場の人間に必要なのは、そうした問いの構えである。
(初出:「図書新聞」2010年7月24日号[第2975号])