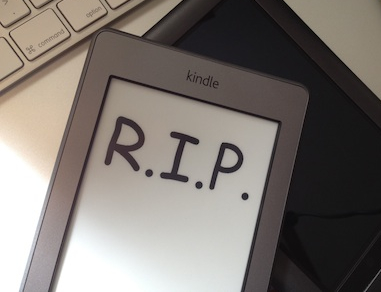1990年代からイタリアで日本漫画の翻訳家として仕事をはじめ、途中で米国ロサンゼルスのベンチャー企業でウェブの草創期に遭遇したり、ロンドンでコミュニケーション・デザインの修士号を取ったりして、その後に来日した。この過程で漫画の世界が完全にアナログからデジタルへと進化していく環境を観察してきた。けっこう面白い時代に生まれたなぁ、とわくわくしながら進化の波に乗って楽しくサーフィンしている気分だ。
電子出版はもはや松本零士のSF作品に出てきそうな遠い未来のものではなく、現在、毎日、実際に私たちの人生を変えつつある、絶対的な存在だと実感している。地球が一方向にだけ回るように、世界は「前」へしか進まないから、本が電子書籍に移行するかどうかはもはや問題ではなく、「いつ」移行するかが問題なのだ。
しかし、漫画には美術的な要素があるから、文字だけの書籍に比べると変化のプロセスは遅くなるだろう。そこで今回はまず、イタリアの電子書籍の全般的な状況について報告してみたい。
イタリアにもアマゾンとキンドル・ストアが登場
この記事の依頼が来たとき、イタリアの現在の電子書籍情報をもっと詳しく調べるちょうどいいタイミングだなと思いつつ、「でもまあ、イタリアではまだ早いだろうな」と、発育の遅い子供を心配する親のように、電子書籍の歩みの遅さを温かく見守るつもりでいた。でもそれは過小評価だったみたいだ。
イタリアという、ちょっと出来の悪い子供でも、思っていたよりデジタルの成長は早い。それは2010年11月末にようやくできたAmazon.itの影響も大きいだろう。もちろん他にネット通販の本屋さんも多少はあったが、どうして今までイタリアにAmazonがなかったか、不思議に思う人がいるかもしれない。あくまで推測に過ぎないが、イタリアでは郵便や宅急便の料金が高く、地方によって広帯域(ブロードバンド)へのアクセスの格差もある。
こうした物流上の問題にくわえ、官僚的な問題もあると思われる。イタリアでは起業のハードルが高く、ややこしい色々な許可を得たりすることが必要だ。イタリアに比べれば、日本は比較的に起業のコストが低くて簡単なのだ。

Amazon.itにもキンドル・ストアが登場。
Amazon.itには最初はキンドル・ストアがなく、Amazon.comからキンドル本体や英語の電子書籍を購入することしかできなかった。そして2011年12月1日、ようやくイタリアのキンドル・ストアがオープンした。Amazon.itではイタリア語の本だけでなく、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語など、多国語の本が並列で売られているのが特徴だ。

イタリア語以外の電子書籍も同じサイト内で買える。
イタリア出版協会のデータによると、e-bookの出版点数は1601(2010年1月)から6950(同年12月)までに増えている。現在Amazon.itのkindleストアには、イタリア語の出版物が1万9623点、(英語を中心とする)外国語の出版物は106万3328点が発売中だ。もう「出来の悪い子供」とは言い難い成長っぷりである。もちろん「発売中」 は「売り上げ」とは違う。でもiPhoneやアンドロイド系のスマートフォン、そしてiPadや他のタブレットの人気が増えれば増えるほど、e-bookの売り上げも増えるだろう。
ちなみにヨーロッパの電子書籍の市場規模のトップはアメリカと世界一を競う英国で、ドイツとフランスが続き、4位のイタリアはスペインより少し上である。[The Global eBook Market: Current Conditions & Future Projections By Ruediger Wischenbart, : O’Reilly Media http://shop.oreilly.com/product/0636920022954.doによる]
本の未来を考える国際会議「ifBookThen」が開催
去年から毎年2月にミラノでifBookThenという国際電子出版コンファレンスが開催され、ワークショップなども行われていて、出版業界の関係者からメディアまでに注目されている。
ifBookThenは「出版の未来についてのコンファレンス」で、去年に行われた際の内容は読書経験、デジタル文化の保存、米国とヨーロッパのマーケット状況、などがテーマだった。今年のワークショップは米国と英国の作家とエージェントと出版社の関係の変化や、それに対する自費出版の影響(Mike Shatzkin とDavid Miller)、米国の進化中の電子書籍マーケットに対する出版社の対応(ペンギン・グループの本のオンラインコミュニティ、Book CountryのMolly Barton)、出版の契約の変化(David Miller)などが話題となる。
他のスピーカーは40kの編集長Giuseppe Granieri、The Bookseller の副編集長 Philip Jones (Futurebookの彼のblog)、Nielsen Bookの社長 Jonathan Nowell、ReadmillのCEO Henrik Berggren、BookriffのCEO Rochelle Graysonなど、世界中の出版関係者が集う(スピーカー一覧はこちら)。こうした動きをみると、イタリアの出版社もかなり積極的に電子書籍の出版に挑んでいる模様。ちょっと心配だった子供も、元気あふれる青年に成長していきそうだ。
こうした流れがある以上、イタリアの漫画も遅かれ早かれ完全デジタル化するだろうが、そう簡単には行かない気がする。日本でもそうだが、漫画の愛読者には電子版より紙の本を求める理由がいくつもある。漫画という媒体は文字だけでなく絵も含まれ、コマ割りや見開きの表現なども作品の重要な一部、いわゆる漫画の「視覚的言語」の重要な要素なのだ。また、「モノ」として漫画を集めるコレクターも多い。
次回は日本の漫画の国際化などについて報告したい。
■関連記事
・2011 ロンドン・ブックフェア報告
・ヨーテボリ・ブックフェアへのブックバス
・北欧から見たヨーロッパ電子書籍事情