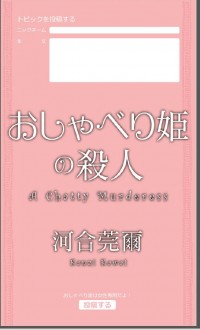私たちは『AiR(エア)』という電子書籍を刊行しています。これは、文芸や学芸、さらには漫画や現代美術、デジタルメディアや企業家など、いろんな分野の書き手と、デザイナー、校閲などつくり手が横断的に集まって、作品集をつくるプロジェクトです。マネタイズについてはシンプルで、基本的にページ単位で売上を分配しています。
電子書籍「AiR エア」公式サイト http://electricbook.co.jp/
1作目の刊行は2010年。そうiPadの発売の年でした。iOS向けアプリとして製作したこの号では、瀬名秀明さんが100枚規模の力の入った中編『魔法』を執筆。慶應大学SDM研究科教授の前野隆司さんが文理融合領域の論考を、また『All You Need Is Kill』の桜坂洋さんが『デビルマン』を新たに小説化するなど、出版社でも実現できないような企画を個人集団でやった(ちゃんとダイナミックプロダクションに許諾をいただいてやったんです。現在はライセンス期間の終了にともない公開を終えています)。

ありがたいことに、こうした私たちの試みに多くの人が興味を持ってくださり、紙でいうとほぼ1万部近い成績をあげました。また個人集団のこの企画が、他の商業作品を措いて、Apple、iPadのテレビCMの映像にも使われるという意外な展開もありました。
ちなみに故スティーブ・ジョブズさん本人が、いくつかの候補の中から「This one」と選んでくれたそうです。
「おもしろい」を求めて続刊を決定
もっとも当時の成績は、あの時期だからこそ獲得できたもの。商業作家である我々としても、最初からそれは狙いでもあり、本来『AiR(エア)』はこの1冊で終わる予定でした。率直にいうと「勝ち逃げ」を狙っていました。しかし実際に電子書籍をやってみると、正直、利益以上に「おもしろかった」。
紙というのはリスクが大きい。紙の本の原価率はだいたい30%から40%くらいになる(企画によっては原価率よりも採算分岐が重視されますが)。残りを各プレーヤーが分け合うわけで、紙の書籍はもともと薄利多売の商売です。そうすると1500円の本であればだいたい450円は原価であり、これを5000部刷ると本の製作原価「だけ」で200万円以上かかってしまうことになる。
もろもろの経費を考えると1000万円に迫ったり越えたりするプロジェクトになるわけで、そう考えると紙の書籍の企画決定にさまざまなハードルがあることは、今のような時代では仕方のないことかもしれません。
ただ、その傾向が行き過ぎて「今って企画の採用基準が類書や著者の過去の実績ばかりで、“おもしろいかどうか”をまず問うことが少なくなってきたね」という声もいろんなところで聞くようになりました。
もちろんプロである以上、そうしたハードルがあることは仕方のないことなのですが、中間はないのか。数字ばかりではなく、とりあえず「おもしろい」と思ったことを実現できるような場はないのか。そうした領域を目指して、覚悟さえすれば、自分たちで本をつくることができる電子書籍は、やってみるととてもおもしろいメディアでした。
そこで2号で吉田戦車さん(『ニュー吉田自転車』)、3号で福井晴敏さん(『「あしたはどっちだ?」って言っていられるうちが花なのよ党宣言』)、カラスヤサトシさん(『愛について語ってみよう』)ら、新たな書き手を迎えつつ、このプロジェクトは書き手の「おもしろいことをやる」という熱意によって今も続いています。
結構、出版社の編集者も応援してくれて、作家を紹介してくれたり、講談社BOX編集部にいたっては、この個人集団誌とコラボレーションして電子雑誌『BOX-AiR』を刊行。「電子でデビュー、紙の単行本化、そしてアニメ化」という試みを今も続けています。余談ですがこの『BOX-AiR』では、新人賞選考会の模様を公式ニコ生で中継し、毎回1万人以上の人が見てくれる人気番組になっています。
取次をKDPに一本化することに
1号当時以来、電子書籍のサービスも大きく広がりました。さまざまな電子書店も誕生しています。そこで私たちは、電子書籍取次と契約し、取次を委託。ひとつのコンテンツを多数のチャンネルで販売してもらうという、いわゆるマルチ販売をはじめてみました。こうした実験を実践するのも、この電子書籍の役割かなと考えていたためです。
もうひとつ。多数の書店でコンテンツを展開し、50、100と細かい売上を積み重ねる方法は、2000年代、特に中盤から後半に拡大して行ったケータイコミックの分野では、有効なモデルでした。電子書籍でもまた、有効かもしれないと考えていたこともあります。
ですが、この度発売した4号で、取次販売を円満に終了。今後は逆に販売チャンネルを1本化することにしました。エアの4号。その名も『AiR 4 KDP』(エア フォー ケーディーピー)です。
なぜ1本化するのか。経済学者ミルトン・フリードマンが「選択の自由」を訴えたのは1980年代でしたが、選択肢が多いことはすべての局面において「善」なのか。少なくとも電子書籍の現状では最善とはいえないかもしれない。
ケータイコミックにおいて「マルチ販売」モデルが機能したのは、あの分野ではすでにケータイという画面が行き渡っていて、ユーザーはもし読みたいコンテンツがあれば、あとは「買うか、買わないか」の決断をするだけですんだからでした。
しかし現状の電子書籍では、インターフェイスが多様にある。もし私たちの電子書籍に興味を持ってくれた人がいたとして、その人がまっさらの状態であった場合、ユーザーは「なにで読むか」⇒「どこで読むか」という選択肢に直面することになります。そして自分も経験があることですが、多くの場合、この「なにで」「どこで」での選択肢の中で迷宮に陥り、堂々巡りを演じることになるでしょう。
であるならば。もし読みたいと思ってくださったなら「これで読んで」「ここで読んで」と、RPGで言うところの1本道ルートを提示したほうがいい。そのほうが市場と読者の開拓につながるだろう。
さまざまな電子書籍小売り業が出てきてほしい
実はこれは僕の知見ではなく、Kindle書籍情報サイト「きんどるどうでしょう(きんどう)」を運営するzonさんが指摘していることでした。
「きんどう」さんでは毎日Kindle書籍の情報を公開し、中規模の書店に匹敵する数の書籍を売っていらっしゃいます。収入はAmazonから入る数%のアフィリエイトとなります。「なんだ、アフィリエイトか」と思われる人もいるかもしれません。ですが、上で指摘した通り、出版とはもともと薄利多売のビジネスです。
紙の本を売って20%の収益あげるのも魅力的ですが、電子書籍であれば物理流通のコストとリスクを負わなくてすむわけで、zonさんのビジネスは、事実上の「電子書籍小売り業」となる。こうしたモデルが成立するようであれば、電子の世界はとてもエキサイティングになると感じます。
たとえば昔、神楽坂にミステリを専門とする書店がありましたが、こうした形で、たとえば面白いゾンビ小説を専門とするサイトなど、さまざまな電子書籍小売り業が出てくる世の中になると面白くなるのではないでしょうか。
こうしたビジネスの先駆者であるzonさんは「なるべくユーザーがどこで読んだらいいのか迷わなくてすむようにしてあげたほうがいい。選択肢は買うか、買わないかのひとつだけが望ましい」と、『AiR 4 KDP』の巻頭特集「電子書籍で食うなら、売る力を身に付けろ」でおっしゃっていました。
なるほどさすがに現場ならではの意見だ、と僕も思います。実は人間は選択肢が多いほど迷うし、後から自分の選択を後悔する率も高くなる生き物。このことはマーケティングの世界でも、行動心理学でも指摘されています。ちなみに将棋の羽生善治名人も、同じことを著書『大局観』(角川oneテーマ21, 2011)で語っていらっしゃいます。
ケータイのようには、まだ画面が普及していない電子書籍。この分野は、まだまだユーザーを開拓していかなければならない。そして市場もユーザーとともに育っていかなければならない。
こうした状況では、自分たちのような少数タイトルのコンテンツ運用者が、取次を経由してマルチ販売を行うことは「継続的に行う手法ではなかったかな」と感じます。
「つくった人間が売るのが一番いい」
もちろん、「多数のコンテンツを公開し、そこから広く薄く運用益をあげる」というプレイヤー、たとえば大手出版社のような場合は、取次を経由することは大きな意味があるでしょう。あるいは少数でも非常に強力なタイトルを持つプレイヤーにも有効でしょう。
実はこうしたプレイヤーにとって重要なのは、取次の持つ「保険機能」だといわれます。新たに登場するこも多い電子書籍書店ですが、であれば当然、つぶれるところも出てくる。そうすると販売代金を「取りっぱぐれる」こともあるわけですが、取次を経由していると、そこは保証されます。そしてこれは、よく考えると紙と同じモデルです。
モノと情報があふれる現代で、供給力、サプライパワーよりも販売力が重視されるようになってひさしい。こうした流れで顕在化してきた潮流が「つくった人間が売るのが一番いい」でした。
よくも悪くも、もっとも顕著な例が、自分たちでつくって自分たちで売る業態、製造小売業(SPA)のユニクロですが、実は若者向け衣料では他にもSPAの躍進が目立ちます。またセブンイレブンのプライベートブランド商品の開発にも、僕などは「つくった人間が売る」の流れを感じます。
このことはコンテンツ産業でもよく言われます。実際問題、たとえば販売専門の担当者であれば、抱える案件はたくさんある。中でも特にヒットタイトルにどうしてもリソースは割かれるでしょう。
そうすると一番熱心にモノを売るのはやっぱりつくった人々。だからこそ現代の編集者は企画を立てる際に「どう売るか」まで含めて考えるようになっているわけです。
そんなに化石みたいな人は今では滅多にいませんが「売る方策は特にないが、その分、いいものをつくるように心を込めて赤を入れます」などという編集者がもしいたら、正直、著者にとってはちょっと迷惑なことでしょう。
こうした時代、私たちも自分で熱心に売っていく必要がある。状況に応じて商品説明の文面を変えたり、価格割引のキャンペーンを行うこともしなければならない。こうしたオペレーションは、取次を通してしまうとどうしてもラグが出てきます。先方も熱心に取り組んでくれるのですが、どうしても自由度が下がります。
であれば自分で売って行きたい。アメリカ映画では、売れない作家が車に自分の本を積んで、地方の本屋さんを回って営業している様子が出てきますが、今回はむしろ販路を絞って、丁寧に売って行きたいと思っています。
「本を出すための最小ユニット」がつくる電子雑誌
毎回、テンションの高い原稿が集まる「AiR(エア)」ですが、4作目では初参加の河合莞爾さんは中編小説をご執筆。「もし女性殺人犯が小町みたいな掲示板で相談していたら」というブラックユーモアあふれる作品で、編集係の僕は100枚あるのに一気に読んでしました。河合さんは本当にリーダビリティの高い文章をお書きになります。かつて校閲の人に面と向かって「この人文章ヘタねえ」と言われた悪文家の僕からすると、本当にうらやましい。
吉田戦車さんは「吉田旅客車」でエッセイの名手ぶりを発揮。「ひとり旅のようなタッチで家族旅行を書く」という手法は「吉田さんでないとできないな」と感じます。
カラスヤサトシさんは「男らしさとはなにか」という、心にジーンとくる漫画をお描きになっていました。カレー沢薫さんは「最近仕事の都合でチンコのことばかり考えている。」という衝撃的なエッセイを発表していますが、口惜しいほど下ネタとの距離感の使い方が上手です。

慶應大学SDM研究学科教授の前野隆司さんは「幸せとか何か/悟りとはなにか」を執筆。これはよくある「文系的な概念を科学で読み解きました」といった内容ではなく、哲学、宗教、文学、そしてご自身の「受動意識仮説」を踏まえて、文理融合領域から幸福と悟りを分析したもの。校閲の西村さんが「原稿をつい読んでしまって校閲にならないので、一度、普通に読み終えました」というほどの、おもしろい論考になっています(校閲は、普通に読んでしまうと、文脈で誤植など脳内補正してしまうのでNGなんです)。
ちなみに僕自身は「せっかく電子書籍なんだから、読んだ人から“あいつ頭がおかしいんじゃないか”と思われるものをやろう」と思っていました。
よく「それは著者の自慰にすぎない」などと言う人がいますが、そういう人は本当に「自慰小説」というものを読んだことがあるのか。「日本よこれがオナニー小説だ」というものを書いています。他の著者はまだこのことを知りませんが、バレたら引かれるのではないかと心配しています。
パッケージや本文については、いつもながら豪腕デザイナーのナカノケンさんが、腕を振るってくれました。この試みは、書き手、編集係、アートディレクター、校閲が集まった「本を出すための最小ユニット」という感じもします。
漫画雑誌『モーニング』の創刊編集長として知られる栗原良幸さんが、かつてデジタルメディアについて「紙以上の熱気を込めてつくらないといけない」とおっしゃっていました。確かにそうかもしれない。冷たいデバイスで読まれるテキスト。しかしこれが最短距離で書き手と読者をつなぐ。「そこで伝わる熱」という、ある意味矛盾した可能性があるならば、この世界もおもしろくなると思っています。ぜひまたこの結果について、ご報告させてください。
■関連記事
・同人雑誌「月刊群雛 (GunSu)」の作り方
・わが「キンドル作家」デビュー実践記
・自費出版本をAmazonで69冊売ってみた
・トルタルのつくりかた