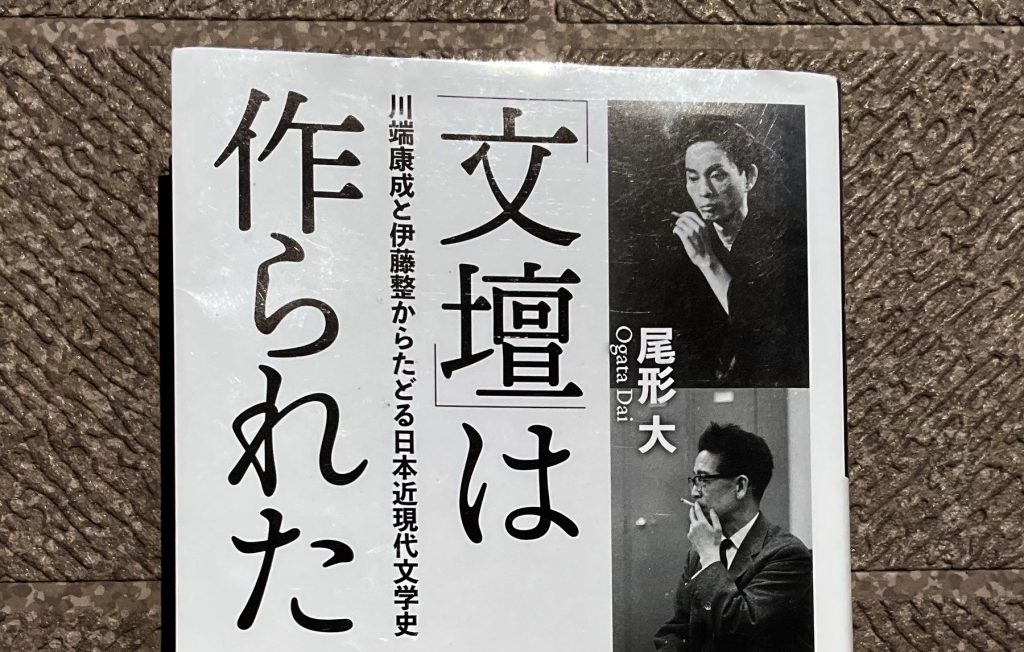※このエントリは、某媒体に依頼された尾形大『「文壇」は作られた――川端康成と伊藤整からたどる日本近代文学史』(文学通信)の書評だが、内容が否定的なので没になってしまった。編集方針は自由なので依頼主に恨みがましい気持ちはないが、お蔵入りにするのももったいないのでここに公開する。前提として、この本の著者や編集者に対する敵意は一切ない。また、ここで指摘した弊を私自身の著作が免れているかどうか定かでないことも告白せねばならない。ただ、(勿論これも私見でしかないが)最近の日本近代文学系の著作物は端的にいって面白くないのではないか、言い換えれば、一般読者にリーチする工夫のないまま成果が必要なために一般向けに出版されているのではないかという疑念がある。
断っておけば、すべての本が一般読者に向けて書かれねばならないと思っているわけではない。専門家数人だけが読むだろう本があっていいし、そういう本を書きたいという願いがあってもいい。むしろそこにこそ学術出版の意義がある気さえする。その上で、「なぜ読者はこれを読まねばならないのか?」の問いかけは、近代文学の研究者が自分の書くものに対していま一度自問してみていいと思っているのだが、どうだろうか。
* * *
最初に書きにくいことを書いてしまえば、本書に関して、根本的に失敗しているのではないかという疑いを拭うことができなかった。以下、活発な議論の種になることを願ってその想うところを率直に記したい。
本書は、川端康成と伊藤整、一方はノーベル文学賞をいただいた国民的作家と他方はいまや忘れられつつある小説家兼文芸評論家の仕事を同時に振り返りながら、そこで立ち現れた「文壇」の実際を年代順に読み解いていく一種の啓蒙書である。伊藤整は昭和初頭に活躍したモダニズム小説の名手としてよりも、何巻にもわたる『日本文壇史』の著者、文壇史・文学史の紡ぎ手として記憶されているかもしれない。近所のブックオフを訪ね、講談社文芸文庫となった全二四巻のうちの何巻かの『日本文壇史』を発見することは容易でも、その小説となると心もとない。が、そんな文学史家にも、自身がそこに投げ込まれたところの客体視しえない文壇的現実との格闘があった。川端との連絡や比較のなかでそれを掘り起こしていく。
本書の方法を支える根本的アイディアは、第一章に引かれるクローチェの言葉、「あらゆる歴史的判断の根底に存在する実践的欲求は、あらゆる歴史に「現代史」としての性格を与える」に要約される。時代や場所を俯瞰して構築される歴史は、しかし、その俯瞰の着眼点や角度それ自体が当の歴史家がいまもっている利害関心に縛られている。自らの立場として提出した「新心理主義」が、同時に伝統にも列するかのように見せるため、逍遥や四迷といった先行する文学者たちの仕事を旧「心理小説」として伊藤が括ったように。『日本文壇史』の印象が強ければ強いほど戦略的に躍動する評論家の姿が鮮やかに浮かび上がってくるだろう、そういう目当てが的外れだとは思わないし、また、かなり似たような問題意識をもつ近刊、木村政樹『革命的知識人の群像』(青土社)と並べてみれば、近代文学研究の領域でいまなぜ共通のアプローチがつづくのかという「現代史」的課題が見えてきて興味深い。
個人的には、川端の代作として伊藤が執筆した『小説の研究』が実は当時伊藤が翻訳したスコット・ジェイムズのThe Making of Literatureの完全な引き写しでしかなかったと喝破する第八章が最も刺激的だった。
そのような美点を認めた上でなお不満が残るのは、そもそもなぜこの本を読まねばならないのか、一般読者にとって動機が不明だからだ。序に相当する部分では、いきなり各章の要約からはじまる不穏のなか、第一章でその予感の的中を見る。文壇構築のメカニズムを扱う書でありながら、「今日もはや文壇は存在しない」ことがさらりと確認される。今日存在しないものをどうしてわざわざ知らねばならないのか。キャリアの最初期、伊藤は詩集『雪明りの路』によって頭角を現したが、詩壇と(小説中心の)文壇とを同一視していいのだろうか。言い換えれば、文壇メカニズムの歴史は論壇などもふくめたメディア的共同体に関する一般理論と連絡して初めてその意義を獲得するのではないか。
また、各章のつながりが体系的深まりを感じさせないのも歯がゆい。たとえば、伊藤が訳した『チャタレイ夫人の恋人』が猥褻文書の疑いで摘発・押収された、通称「チャタレイ事件」を論じる第一一章では、当事者の立場から公判を記録した『裁判』での伊藤のメディア戦略や事件を念頭に創作されただろう川端『舞姫』論などに示唆を受け取るものの、やや尻切れトンボのまま「こうして戦後の文壇は再建の道を歩みはじめる」と小括され、日本近代文学館設立事情を論じる第一二章へと突入してしまう。各章で得た知見が、以降の章とどのように連続し、どのように切れているかについて、本書はなにも教えてくれない。物語的文学史を相対化する以上、必然的な構造だったのかもしれないが、ここまでエピソード的だと豆知識の愉しさに留まって一書を読了したときの満足感は遠い。
あとがきによれば、編集者の「伊藤整を広場に出すにはどうしたらいいか」の問いかけのもと、「研究論文と読み物の中間を狙」ったという。いくら読み物だからって参考文献表くらいつけてもいいのでは、と思ったりもするが、とまれ結果的にその中間性は帯に短し襷に長しという中途半端さとして印象づけられた。いうまでもなく私見である。著者は勿論のこと、読者諸賢の反論を待ちたい。どうだろうか?
尾形大『「文壇」は作られた――川端康成と伊藤整からたどる日本近代文学史』
文学通信刊
ISBN978-4-909658-74-6 C0095
四六判・並製・256頁
定価:本体2,000円(税別)
執筆者紹介
- 1987年、東京都生まれ。在野研究者。専門は有島武郎。En-Sophやパブーなど、ネットを中心に日本近代文学の関連の文章を発表している。著書『小林多喜二と埴谷雄高』(ブイツーソリューション、2013)、『これからのエリック・ホッファーのために――在野研究者の生と心得』(東京書籍)、『貧しい出版者――政治と文学と紙の屑』(フィルムアート社)。Twitterアカウントは@arishima_takeo。
最近投稿された記事
- 2022.06.01書評帯に短し襷に長し?――尾形大『「文壇」は作られた』書評
- 2021.02.12コラム『文學界』編集部に贈る言葉
- 2021.02.06コラム削除から考える文芸時評の倫理
- 2019.04.26コラム献本の倫理